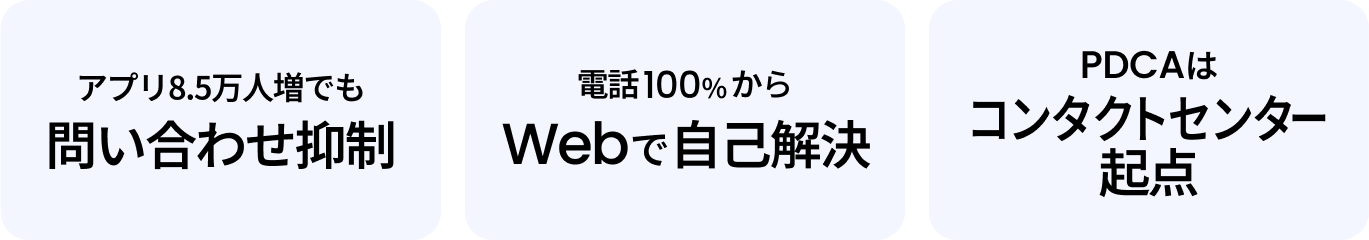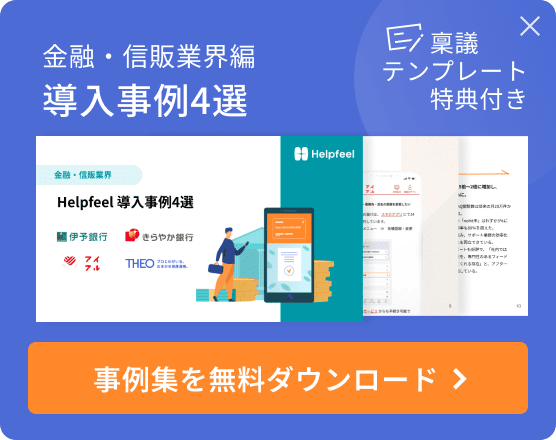アプリユーザー数の成長に比例して、問い合わせ数も増えていた
── はじめに、皆さまの業務内容を教えてください。

営業統括部 営業推進室長 青木 隆浩様
青木様 営業統括部では、インターネットバンキングやアプリなど非対面チャネルの成長、および営業推進におけるデータ利活用を担っています。
近年注力しているのは、アプリ利用者の拡大です。2024年度末には、ほくほくフィナンシャルグループの北海道銀行と北陸銀行のアプリ利用者が合計100万ユーザーを突破しました。
勝見様 私は部内のダイレクトバンキングセンターで、非対面チャネルの各サービスにおけるバックヤード業務を担うとともに、個人向けのコールセンターのマネジメントをしています。コールセンターは社内にあり、8名の正職員が個人のお客様からの電話問い合わせを担当しています。
西東様 私は、個人向けキャッシュレスサービスと、ホームページ運用を担当しています。Helpfeel導入後はFAQの運用にも携わるようになりました。
── Helpfeel導入前、お客様対応においてどのような課題がありましたか。
青木様 コールセンターへの問い合わせ数が増えていることに課題感がありました。当行が運営する「どうぎんアプリ」だけでも55万を超える利用者がおり、急増するユーザー数に比例して、問い合わせも多くなっていたのです。
勝見様 アプリの機能やサービスも拡充していたため、お客様自身が「何がわからなくて困っているのか」が明確ではないケースも増えていました。どうしていいのか見当がつかず“とりあえず電話せざるを得なかった”という問い合わせが少なくなく、お客様の疑問を紐解くところから始めていました。問い合わせチャネルは100%電話でしたので、1件あたりの対応時間も相応にかかっており、特に週明けや給料日などは一時的に電話がつながらない状態になってしまうこともありました。
青木様 FAQにある内容の問い合わせも多く、お客様に情報が届いていない実感もありました。当時は商品ページごとにFAQが分散していたため、探している情報の記事があるページに辿り着けないと不明点を解決できなかったのです。にもかかわらず、当時はFAQの改善活動もできていませんでした。
── 課題を解決するために、どのような検討をしましたか。Helpfeelを導入するまでの経緯を教えてください。
青木様 お客様が不明点を自己解決できるようにしたいと考えていた時期に、ほくほくフィナンシャルグループ全体でホームページ刷新の話が浮上したため、あわせてFAQもリニューアルすることにしました。
ほくほくフィナンシャルグループの北海道銀行と北陸銀行でFAQシステムを揃えたいと考え、両行で検討を進めました。最終的にHelpfeelに決めた点は3つあり、①お客様目線で考えた際に利便性の高いFAQだった点、②FAQ構築のサポート体制が充実していた点、③運用のサポートがある点、です。
Helpfeelはシンプルなデザインで、どのようなお客様でも迷わず操作できそうだと感じました。意図予測検索によって、さまざまな言葉で検索しても適切な情報がヒットすることにも惹かれましたね。
また、既存のFAQにある約400の記事をHelpfeelにどう移すべきかが悩ましい点でしたが、移行段階からサポートいただけることに安心感を覚えました。また当時はFAQの運用のノウハウや体制がなかったため、「導入しただけで満足してしまい、そのまま風化してしまうのではないか」という懸念もありました。そのためカスタマーサクセスの継続的な支援は欠かせないと考え、導入を決定したのです。
“残高照会”が検索されていた。データで気づいた、「お客様の思考に沿ったFAQ運用」の重要性
── Helpfeelの運用において、どのようなことを意識していますか。
青木様 導入しただけで満足せず、ブラッシュアップし続けることを意識しています。そのために、Helpfeel導入を機に運用体制を構築しました。記事の企画や制作を西東が担うとともに、お客様対応の現場の声をFAQに反映したいと考え、コールセンターをマネジメントする勝見も関与しています。
勝見様 導入当初から、コールセンター全体でFAQ運用に携わっています。以前のFAQから記事を移行する際は、お客様がお困りになるポイントを熟知しているオペレーターの知恵を総動員して記事を改善しました。
── KPIとして設定している数字はありますか。
青木様 FAQへのアクセス数やnohit(ノーヒット:ユーザーがキーワード検索をした際、検索結果に表示される記事が一つもないこと)率、離脱率に着目しています。
特に重視しているのは、nohit率です。お客様が不明点を解決できていない状態を早急になくすよう、課題が見つかるたびに優先対応しています。
── Helpfeelのカスタマーサクセスへのご感想もお聞かせください。
青木様 毎月の定例会によって、改善のPDCAサイクルを回せるのがありがたいです。当初意識していた「導入して終わりにしない」ことがクリアできています。
西東様 定例会でデータ分析結果を見ることで、改善点が明確にできています。お客様のニーズに沿ったFAQにするために、カスタマーサクセスはなくてはならない存在です。
 営業統括部 ダイレクトバンキングセンター 主任 勝見 真介様
営業統括部 ダイレクトバンキングセンター 主任 勝見 真介様
勝見様 印象に残っている例として、定例会で「『残高照会』というキーワードの検索数が多い」という話をもらったことがあります。金融機関に長年在籍していると、残高照会は誰もが難なくできるはずだと思いがちですが、困っている方がそれだけいらっしゃるのだと気付かされました。これは検索ログのデータが取れていないと気づけなかったことだったと思います。第三者視点からのこうした指摘は貴重ですし、自分たちの当たり前を疑う大切さを改めて感じます。
また、お客様自身もわからない点が不明瞭なまま問い合わせるケースがあると先ほど申しましたが、FAQでも最初に思い浮かんだキーワードを入力するのだと気づきました。お客様は、当行が設けているサービス名ではなく、自分が操作したいことや疑問に思ったことをそのまま入力して検索するのですよね。ですからお客様の思考に沿ってFAQを作る重要性を実感しています。
年間8.5万人増でユーザー数が増える中、問い合わせ数は横ばいに抑制。FAQに対する行員の意識も醸成
── Helpfeelで役立っていると感じる機能はありますか。
青木様 記事の作成や修正をすると、すぐ反映されるのがありがたいです。以前のFAQは制作会社に依頼して更新していたため、軽微な修正でも2週間ほどかかるケースもありましたが、Helpfeel導入後は早ければ即日反映できるため、スピード感が大きく変わりました。
── 導入してからの具体的な効果を教えてください。
勝見様 この1年でのアプリ新規登録者が約85,000人に達するなどユーザー数が増え続ける中、問い合わせ数は横ばいに留められています。非対面チャネルの機能が増え、お客様が窓口に行かずに利用できるサービスが多くなっていることをふまえると、大きな成果だと思います。
青木様 個別の問い合わせ内容を見ると、住所変更など基本機能にまつわる問い合わせ数は減少傾向にあり、FAQで自己解決できていることがうかがえます。アプリからHelpfeelへの導線を早期に設けたのも良い判断でした。
── 運用している皆さまや、行員の方々からのHelpfeelへの感想もお聞かせください。
西東様 PDCAのサイクルを回すことで、FAQでお困りごとを解決するお客様を増やせている実感があります。自分たちが起こしたアクションに対する手応えがあるのは嬉しいことです。

営業統括部 ダイレクトマーケティング室 主任 西東 瞳様
青木様 他部門の意識も変化しています。行内の啓蒙活動として、定例会の資料を他部門にも共有し、FAQの利用状況や課題を知ってもらうようにしていたのです。その成果として、最近では事務部門などから記事追加や改善の依頼が来るようになりました。
コールセンターのオペレーターからも、記事をより良くするアドバイスをもらっています。オペレーターにとっても、自分の意見がFAQに反映されることでモチベーション向上につながっているようです。
Webやアプリは「非対面店舗」。FAQを起点に情報提供から各種手続きまでをスムーズにつなげ、デジタルバンキング機能を進化させたい
── 今後の展望をお聞かせください。
青木様 現在、非対面チャネルにおける顧客接点の強化という観点で、ホームページのリニューアルを進めています。デジタルが主流となった今、ホームページやアプリは「非対面店舗」としての役割を担っており、お客様が求める商品・サービスの情報に迷わず辿り着けることは、利便性向上の鍵を握ると考えています。
その強力な手助けになるのが、FAQです。単なる問い合わせ対応の手段にとどまらず、商品・サービスを詳しくご紹介し、手続きへと案内する重要なナビゲーション機能を果たせると考えています。たとえば、口座開設、振込、各種変更手続きなど、FAQから関連機能にスムーズにつながる設計を行うことで、より質の高い顧客体験を提供したいと思っています。
今後はAIなどのテクノロジーも活用し、業務効率化と顧客接点の質的向上を図ることで、FAQを起点とした「進化するデジタルバンキング機能」の構築を目指していきたいですね。
勝見様 コールセンターも引き続きFAQの改善活動に寄与していくとともに、電話対応の付随業務を効率化し、お客様対応の質を上げていきたいと考えています。

── 最後に、同様の課題を抱えている企業様にメッセージをお願いいたします。
青木様 Helpfeelは、あらゆる観点で「導入して終わりにならないシステム」だと実感しています。カスタマーサクセスの支援によってスピーディーに改善活動ができ、システムの機能も拡充していくので、我々の運用もアップデートできます。お客様に多くの価値を届ける「非対面店舗」を作るために、Helpfeelは心強いパートナーです。