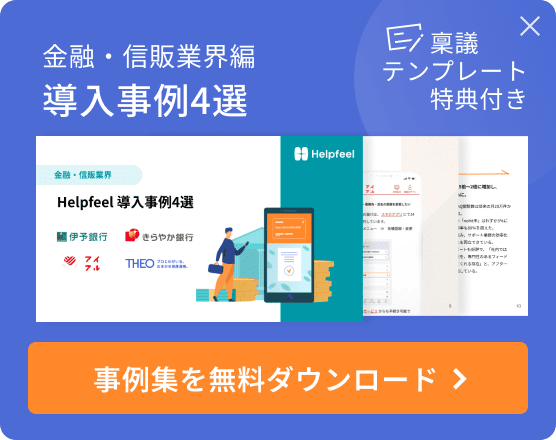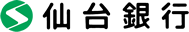月2,000件の電話問い合わせ、コールセンターの人材確保に課題
── はじめに、デジタル・マーケティング部の業務内容を教えてください。
西本様 デジタル・マーケティング部は、北洋銀行におけるデジタルサービス推進やマーケティング機能を担っています。当行のデジタルサービスにはインターネットバンキングとアプリがあり、近年はアプリでご利用いただけるサービスの拡充に注力しています。.jpg?width=809&height=460&name=hokuyobank_07_zoom%20(1).jpg)
新出様 私は、同部でインターネットバンキングの運用および問い合わせ受付をしているダイレクトバンキングセンターにおいて、企画や業務改善を担当しています。
当行のコールセンターは行内と外部委託の両方があり、問い合わせ内容によって役割分担している体制です。行内では、個人のお客さまからの問い合わせを5名のオペレーターで担当しており、お客さまの主な問い合わせチャネルは電話となっています。
── Helpfeel導入前、問い合わせに関してどのような課題がありましたか。
西本様 「お客さまをお待たせすることなく対応したい」という思いから、問い合わせは電話に重きを置いてきました。そのため、コールセンターを頼りにしていた我々にとって、コールセンターの人手不足は大きな課題となっていました。
退職や異動が定期的に起こるほか、派遣社員は労働者派遣法により同じ部門で3年を超えて勤務できず、人員の入れ替えが頻繁に起こり、新たなメンバーを育成する負荷も大きくなっていました。
新出様 問い合わせの数が高止まりしていることにも悩んでいました。行内のコールセンターで受け付ける問い合わせが月2,000件を超えており、5名のオペレーターで対応するキャパシティを超えていたのです。電話問い合わせの応答率は90%を目標にしていたものの、当時は80%を切ってしまう場合もあり、お客さまの不満を招いていたと思います。
スーパーバイザーが新たなオペレーターの育成に時間を割かれ、コールを受ける体制が不十分になり、応答率が下がるという悪循環が起きていました。

デジタル・マーケティング部 副部長 西本 和幸様
── 課題を解決するために、取り組んだ施策はありましたか。
西本様 電話による問い合わせの増加を抑えるべく、ホームページに顧客サポートツールとしてFAQを設置していました。ただ、以前のFAQは検索機能がなく、記事をいくつかのカテゴリに分けて掲載しているだけだったのです。
結果として、「不明点をFAQで調べてみたものの、うまく回答が見つけられなかった」「検索できなさそうだったのでとりあえず電話した」というお客さまも多かったと思います。サービスを利用する際、文章をじっくり読んで不明点を解決しようとするお客さまは少ないことを考えると、月2,000件超という問い合わせ数の多さは起こるべくして起きていた事態だったとも感じます。
FAQ記事の改善もできておらず、更新は新しい商品やサービスのリリース時に記事を追加する程度で最新性にも欠けていましたから、課題解決に向けてツールと運用体制を根本的に見直すことにしました。
── FAQ導入にあたり、Helpfeelを知ったきっかけは何でしたか?また、最終的に導入した決め手も教えてください。
西本様 このような状況を打破するため、チャットボットの導入など、新たな顧客サポートソリューションを模索していました。その際、アライアンスを組んでいる他行がHelpfeelを導入していたことがきっかけで知りました。デモ環境の管理画面を操作してみると、直感的に作業できるのでスムーズに運用が立ち上がりそうだという印象を持ちましたね。
導入を決めた最大の要因は、「運用がしっかり回せること」でした。当部でFAQを運用するのは私を含む3名のみで、その全員が他の業務も担っています。業務が多忙な中で、新しいツールを導入しても運用が滞ってしまっては意味がありません。少数精鋭、かつ、運用にかけられる時間が限られる中でもFAQをより良いものにし、お客さまが求める情報を届けられるようにするには、カスタマーサクセスによる定期的なサポートが受けられるHelpfeelが最適だと判断しました。
データに基づく改善と専任のサポートが運用定着の「鍵」
── 2023年11月にHelpfeelを導入し、どのように運用していますか。
西本様 まずは既存のFAQ記事をもとに、古いコンテンツを除くなどの見直しをしてHelpfeelへ移行し、運用をスタートしました。
以前はFAQの定期的な改善をしていなかったため、運用上のKPIをHelpfeelのカスタマーサクセスに相談して設定しました。FAQによる自己解決を増やすためにアクセス件数をウォッチするとともに、お客さまへ情報を確実に届けるためにno hit(ノーヒット:検索しても記事がヒットしないこと)率を減らすことを目標にしています。問い合わせ数の推移も月次で確認している状況です。

デジタル・マーケティング部 ダイレクトバンキングセンター 主任調査役 新出 拓也様
── Helpfeelのカスタマーサクセスへのご感想もお聞かせください。
西本様 カスタマーサクセスと毎月行う定例会が、我々にとっての良きペースメーカーになっています。KPIを中心にデータを一緒に確認し、改善点を話し合う場は、専任担当者なしでFAQを運用している我々にとって欠かせないものです。
定例会でもらった“宿題”を翌月までに行い、数値の変化を見るというサイクルをしっかり回せているのは、カスタマーサクセスのおかげです。
新出様 これまで、リソース不足ゆえにFAQの分析や改善に着手できていなかったので、カスタマーサクセスの支援があるのはありがたいです。行内のメンバーだけで運用していたら、このような改善活動はできていなかったと思います。
応答率が90%以上に改善し、人件費を増やさずサービス拡充に対応
── Helpfeelを導入してからの具体的な効果を教えてください。
西本様 アプリをはじめ当行のサービスを利用するお客さまが増えている一方、コールセンターへ寄せられるコール数は減っており、Helpfeelの効果が見られています。電話問い合わせの応答率は90%以上に改善し、コールセンターの増員をしなくともお客さま対応を滞りなくできている状況です。
FAQのアクセス件数も増加傾向にあります。一時期、アクセスが伸び悩んだので導線を増やしたところ、アクセス件数が再上昇しました。お客さまへのFAQの認知は確実に広まっています。
アクセスが多くなれば、あとはno hitをなくすことに注力するだけです。上司からも「PDCAがしっかり回っているので、他部門で管轄している情報もFAQで公開して運用を続けていこう」と評価をもらっています。
── その他の効果や、社内の変化などはありますか。
新出様 毎月データ分析を続けていると、継続して検索上位にあがるキーワードが把握できてきます。その傾向から、お客さまが知りたいことやニーズの高い商品・サービスなどがわかるようになってきました。感覚的に思っていたことがデータで可視化されるので、次に取るべきアクションに自信を持てます。
西本様 検索数やコールセンターへの問い合わせが多い内容は、FAQの「よくある質問」に固定表示し、お客さまの目に留まりやすくする工夫もできています。代表的なものは、住所や通知先電話番号の変更、振込・振替の限度額照会などです。

特に「通知先電話番号」に関しては、アプリをローンチしてから問い合わせやFAQ検索が増えました。アプリへの初回ログイン時に認証番号を電話で通知するのですが、固定電話の番号を登録しているお客さまも多いため、携帯電話番号に変更したいというご要望が多かったようです。
さらに、Helpfeelのデータを通して、サービスやアプリ開発で対応すべき点を把握できています。特に、住所変更や振込限度額に関する問い合わせが多いことがデータから判明したため、これらに対応するシステムを改修し、顧客利便性を向上する取り組みを進めています。最近では、アプリ関連の記事を充実させており、当行が戦略的に注力する分野をFAQでも対応できるようになりました。
デジタル技術で、お客さまの自己解決を支援し、安心と満足を提供していく銀行へ
── 今後の展望をお聞かせください。
西本様 引き続き、データ分析に基づいたFAQの改善を重ね、FAQ記事を拡充させるとともに、今まで以上に商品・サービス強化につなげていきたいです。さらに今後は、デジタル・マーケティング部が管轄していないコールセンターの問い合わせ状況も把握し、FAQをさらに充実させて当行全体での問い合わせ数削減を目指します。
こうした取り組みを通じて、顧客サポートの質を全体的に向上させていく計画です。将来的には、ホームページに電話番号を掲載する必要がなくなるくらい、お客さまが自然と自己解決できる環境を構築したいと考えています。
新出様 今は個人のお客さま向けにFAQを運用していますが、将来的には法人向けのFAQ記事も増やし、より多くの方にご利用いただけるようにしていきたいと考えています。
── 最後に、貴行と同様の課題を抱える企業へのメッセージをお願いいたします。
新出様 当行のお客さまは年齢層も幅広いですが、HelpfeelはFAQの画面がシンプルで、ITに不慣れなお客さまでもスマホが少し使えさえすれば、迷うことなく検索できるのが利点だと思います。
西本様 我々のように少数精鋭で人材確保に課題を感じている企業は、上手にHelpfeelのような業務に馴染むAIを取り入れていくとよいのではないでしょうか。
FAQの運用に十分なリソースをかけられない企業にとって、AIプロダクトが優れていることはもちろんのこと、その上で運用をサポートしてくれるカスタマーサクセスは必須です。FAQを設置しているもののお客さまに活用いただけないことに悩んでいるのであれば、知見が豊富なプロの伴走は役立つかもしれません。
当行は今後もHelpfeelを含むAIツールを活用し、顧客サポートの質と業務効率を同時に高めていきます。お客さまのニーズに寄り添い、進化を続ける銀行でありたいですね。