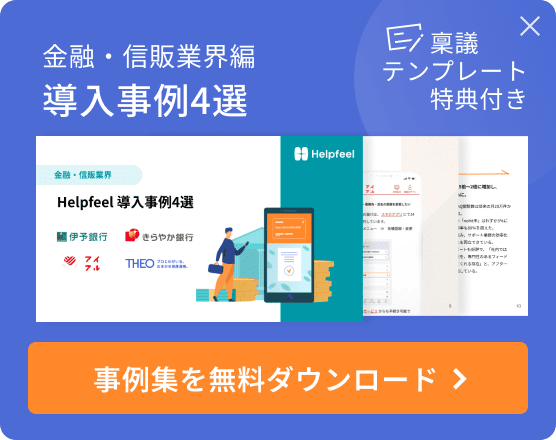株式会社北陸銀行は、富山県富山市に本店を置き、北陸3県のほか北海道、三大都市など広域にわたって地域の発展を幅広いサービスで支える金融機関です。
同行では、約150の営業店から本部に寄せられる問い合わせが多いことに悩んでいました。行内ヘルプデスクを活用して行内の情報周知をスムーズに行い、行員が現場で不明点を解決できることを目指してHelpfeelを導入しています。
Helpfeelの導入理由や運用方法、効果などについて、営業統括部 主任の北島 瑞貴様、総合事務部 事務管理グループ 部長代理の五十嵐 恵様に話を伺いました。
営業店からの問い合わせ多発を受け、各現場で不明点を解決できる業務改革に着手
── はじめに、北島様、五十嵐様の業務内容を教えてください。
北島様 営業統括部で、商品・サービスの企画や戦略立案を担当しています。名前の通り営業生産性を高めるための横断的な施策を企画することも私たちの部門の業務です。

営業統括部 主任 北島 瑞貴 様
五十嵐様 私は総合事務部の事務管理グループに所属しており、預金事務にまつわる企画や、営業店のサポートが主な業務です。そのサポートの1つとして、営業店の皆さんからの照会対応もしています。
── Helpfeel導入前、行内の情報伝達や周知に関して、どのような課題がありましたか。
五十嵐様 マニュアル等の格納場所が散在していて、必要な情報を調べるのが大変だったり、本部からの情報周知がうまくできていない結果、営業店からの照会対応に多くの時間を割いていることに悩んでいました。
行内の業務環境としてはイントラネットで閲覧する通達や事務取扱要領、各種マニュアルがあり、個別の質問は電子会議室というインターネット掲示板のようなツールを用いています。ただ、早急に回答が必要な場合や、込み入った質問なども少なくないため、電話で問い合わせをもらうことも多いです。また個別の照会票や資料を見てもらいたいときは、”回覧レポート”という電子メールのような個別ツールでやり取りすることもあります。
電話や回覧レポートでのやり取りは、質問をした本人以外に情報が共有されないため、同じ内容の照会が何度もあることに課題感がありました。
また、照会事項への返信には時間がかかることもあり、総合事務部内の業務が逼迫してしまっていました。お客様の情報を調べないと質問に答えられないケースや、内容に誤りがないようダブルチェックして回答することもあり、1回答に30分以上かかるのもよくあることです。
総合事務部には行内からの質問を優先して対応する担当者が2名いるものの、すべての照会をカバーしきれず、他のメンバーも通常業務と並行して回答しています。特定の分野に詳しいメンバーに照会が集中し、属人的になっているという悩みもありました。
北陸銀行本店社屋
── 行内ヘルプデスク(行内FAQ)を導入することになったきっかけと、Helpfeelを選んだ理由をお聞かせください。
五十嵐様 照会対応の負荷が高くなっていることに加え、異動や長期休暇などによってメンバーが入れ替わるとノウハウが組織内に定着しにくいことが、行内ヘルプデスク導入のきっかけです。そこで、行内の情報を蓄積して簡単に調べられるツールを探すことにしました。
北島様 他社同様当行においても人員不足の状況下において、多岐にわたる業務マニュアル等の検索・照会に要する負担が大きい点を課題に感じていました。若手層など、経験の浅い行員も自ら調べれば業務知識を習得できる環境をつくり、お客様に提供するサービスの質を保つため、行内ヘルプデスクの導入に踏み切りました。
行内ヘルプデスクの比較検討で重視したのは、行員に情報が正しく伝わるかという点でした。金融機関という業種の性質上、法律を遵守して業務を正確に行い、お客様へも正しい内容をご案内することが求められるためです。最終的にHelpfeelに決めた理由は、行員が理解しやすいUI(ユーザーインターフェース)であり、明確で間違いのない回答を提示できること、そしてサポート体制の手厚さでした。
段階的に記事を追加する戦略的なスモールスタートにより行員の利用定着を狙う
── Helpfeelを導入し、どのようなことから運用を始めましたか。
北島様 行内ヘルプデスク用の記事がほとんどない状態だったので、行内の掲示板である電子会議室にあるデータをもとに、記事を作成することからスタートしました。既存のデータを活用し、Helpfeelが提供する生成AIによるドラフト生成機能を使って記事の下書きが作成できたのは、大変助かりました。ゼロから記事を作成するのは負荷があまりに高く、現実的ではないと思っていたためです。
カスタマーサクセスと相談した結果、行内にある膨大な情報をいくつかの領域に分類し、優先度の高い記事から段階的に作成を進めました。

総合事務部 事務管理グループ 部長代理 五十嵐 恵 様
五十嵐様 導入時に苦労したのは、Helpfeelの行内ヘルプデスクに合わせたリライト作業でした。電子会議室の投稿は行員誰でも見られるものですが、照会された特定のケースにおける回答であることも多く、行内ヘルプデスクの記事に求められる汎用性が低いです。幅広いケースで参考になるように内容を書き換えながら、正しさをチェックする作業が必要でした。
この作業をしっかりできなければ、行内ヘルプデスクを見たとしても解決できず、再度、総合事務部に電話で照会することになり、状況は改善しません。そうならないよう、Helpfeelのテクニカルライターの力も借りながら3か月ほどかけて記事を推敲し、行内ヘルプデスクをリリースしました。
── 行員の皆様がHelpfeelを業務で活用するために、どのようなことに注力して運用していますか。
五十嵐様 照会元である営業店で使ってもらえなければ全く意味がありません。だからこそ、その周知を大事にしています。現在までに約1,800の記事を掲載しており、更新した記事を毎月の通達で知らせています。事務に関する質問の範囲は広く深い、そして変更頻度も高いものです。こうした背景から「改善し続けていること」を皆さんに知ってもらうことが大切だと考えています。
また、役席者(管理職)の会議でHelpfeelの活用方法を説明し、各営業店で伝えてもらうようにもしています。営業店も業務で忙しい中、習慣から変えていくのはエネルギーのいること。だから身近な存在である上司から「まずは使ってみよう」と発信してもらうことが欠かせません。
このように本部から活用を促すだけでなく、営業店の中でも話題にしてもらうなど、浸透に向けてあらゆる形で周知しているところです。
── カスタマーサクセスへの感想もお聞かせください。
北島様 導入当初はHelpfeelに掲載している記事も少なく、記事の作成に割くリソースも不足している状況でした。
そんな中で、道標になってくれたのがHelpfeel社のカスタマーサクセスでした。何度も富山まで足を運んでくださった上で運用側の実情と行員側の期待値を見極め、段階的な改善計画をしき、ペースメーカーとして月次のヘルプデスク改善をリードしてくださっています。彼がいなければ今の改善体制はありません。

五十嵐様 導入当初は、営業店の皆さんが疑問点をすぐに解消できるツールを用意してあげたいという思いが強く、「完璧な行内ヘルプデスクを作らなければならない」と思っていました。でも完璧なものを作るのは現実には不可能。なかなか利用を開始できず、いつの間にか時間だけが経っていました。
そんな考えの私たちに対し、カスタマーサクセスが根気強く対話してくださり、実現可能なアイデアをくださいました。
「特定の分野の記事を用意することからスタートし、『この内容の情報であれば、行内ヘルプデスクに必ずあるはずだ』と思ってもらうことを最初の目標にするといいのではないか」
「実際にHelpfeelで検索したら必要な情報に辿り着けたという成功体験があればまた使ってくれる。そうして利用率が上がるはず」
もちろんアイデアがうまくいかないこともあります。そんな中でもカスタマーサクセスは、私たちが次の一歩として何をすべきかを常に示してくれるのでありがたいですし、なにより心の支えになっています。
意図予測検索によって「欲しい情報が行内ヘルプデスクにあるか」がすぐ判別できる
── Helpfeelの機能で、役立っていると感じるポイントはありますか。
五十嵐様 やはり検索性です。営業店の皆さんに使ってもらう上で意図予測検索の存在は大きいです。記事数が1,800と膨大になった中でも、今必要な記事が「見つかる」ことが使い続けてもらうためには必須だと思います。HelpfeelはSaaSでネット接続が必要なため、当行の業務用PCではすぐに見ることができません。行内ヘルプデスクが開くまで少し待つ必要があるんです。そういった意味でも、時短につながる検索性の高さはとても役に立っています。
「見つかる」と同じくらい大事なのが「見つからないことが分かる」ことだとも考えています。一般的なQ&Aシステムであれば、「検索する単語を変えたら、情報が見つかるかもしれない」と思い、あらゆるキーワードで検索し続けてしまうかもしれません。こうした時間のロスが発生しないことで「一回Helpfeelで探してみよう」という気持ちを生んでいるように思います。
── Helpfeel導入後、北島様や五十嵐様、行員のみなさまの業務に変化はありましたか。
五十嵐様 今はまだ行内ヘルプデスクの記事を追加作成し、行内に周知している最中なので、目に見える生産性改善が出てくるのはこれからだと思っています。
ただ、現状の可視化が進んだことは大きな変化です。総合事務部に寄せられた電話照会の件数や内容を分析したところ、行員が疑問を抱くことが多い分野や、電話対応にどのくらいの負荷がかかっているかが明らかになってきました。これを生かして改善、どんな記事を作成したら役に立つのか突き詰めていきたいと思っています。
行内ヘルプデスクを実際に使ったユーザーとの交流も起きてきています。Helpfeelのフィードバック機能を活用し、行員から行内ヘルプデスクに対する要望をあげてもらっています。最も多いのは、行内ヘルプデスク上にまだ用意できていない記事のリクエストです。行員の意見から、次に作成すべき記事や文章を見直すヒントをもらっています。このような意見は、役席者や渉外担当者から寄せられることもあります。お客様と商談している場ですぐに不明点を解決したいケースも少なくないのだと気付かされました。
これらのデータやHelpfeelの検索履歴を参考にしながら、ニーズが高い内容の記事を優先的に追加し、行員が自ら疑問点を解消できる環境づくりを進めていきたいと考えています。
長期化するナレッジ課題は運用支援のサポートも得て着実に進捗させる
── 今後の展望をお聞かせください。
北島様 まずは引き続き、ヘルプデスクのコンテンツを充実させることに注力します。行員は使い慣れているツールを優先的に利用するのが自然だと思うので、Helpfeelで行内の情報を網羅し、各現場で自然と「Helpfeelを見れば不明点が解決できる」という会話がなされることが理想です。
五十嵐様 行内ヘルプデスクを進化させることで、総合事務部の照会対応の負荷を減らし、事務の効率化や堅確化となる企画にももっと時間を使えるようにできればいいなと思っています。現場の声をリアルに感じられる部署であるメリットを活かし、お客様への提供価値を生み出すための時間を捻出できるようにしたいですね。
そして将来的には、行内の問い合わせチャネルを整理したいと考えています。今はこの行内ヘルプデスクや電話、電子会議室、回覧レポートなど煩雑。行員としては「自分の疑問をどうやって解決したらいいのか」がわからず不安な状況です。電話が一番早いと思っても、通話中でがっかりしている方もいるでしょう。だからこそ、ちょっとした不明点は行内ヘルプデスクで素早く解決し、個別事案や複雑な質問をじっくり相談できる体制を目指したいです。
── 最後に、貴社と同様の課題を抱える企業へのメッセージをお願いいたします。
五十嵐様 Helpfeelのようなツールの費用対効果を定量的に示すのは難しく、行内への浸透も時間がかかるものなので、運用担当者は孤独になりがちです。Helpfeelは導入時からカスタマーサクセスが伴走してくれるので、やるべきことに迷わなくなりますし、心強い存在になると思います。行内のナレッジ課題はツールだけでは解決しないからこそ「改善のパートナー」として二人三脚で歩んでくれるツールベンダーがいてくれることが大事だと感じています。
Helpfeelは優れたAI技術だけでなく、運用における豊富なノウハウも持っているので、私たちの事情をふまえた最適解を示してくれます。少子高齢化や働き方の多様化が進む中、人材不足はあらゆる業界にとって避けられない社会課題となりつつあります。この構造的な課題に立ち向かうには、経験や勘に依存した属人的な知識の継承から脱却し、組織に眠るナレッジを資産として活用する仕組みをつくることが不可欠です。
AIの力を借りて「知」を仕組みに変えることで、人が入れ替わっても業務の質を維持できる体制が整います。そうした意味でも、機能面だけでなく運用ノウハウにも優れたHelpfeelのようなツールを、情報連携の基盤として活用することには大きな価値があるのではないでしょうか。
※同社の顧客向けAI-FAQの導入事例はこちら