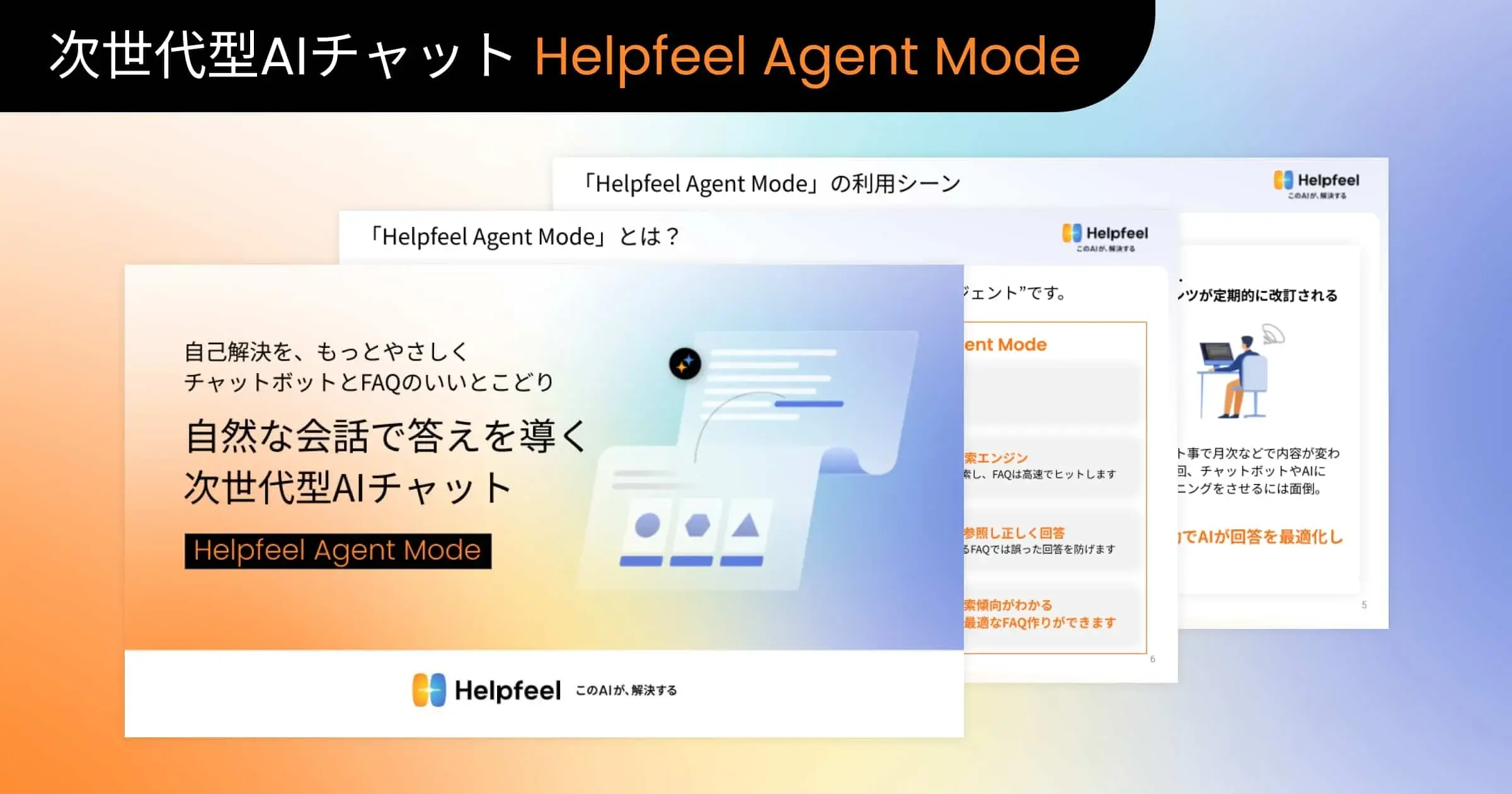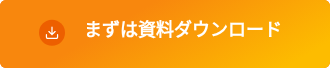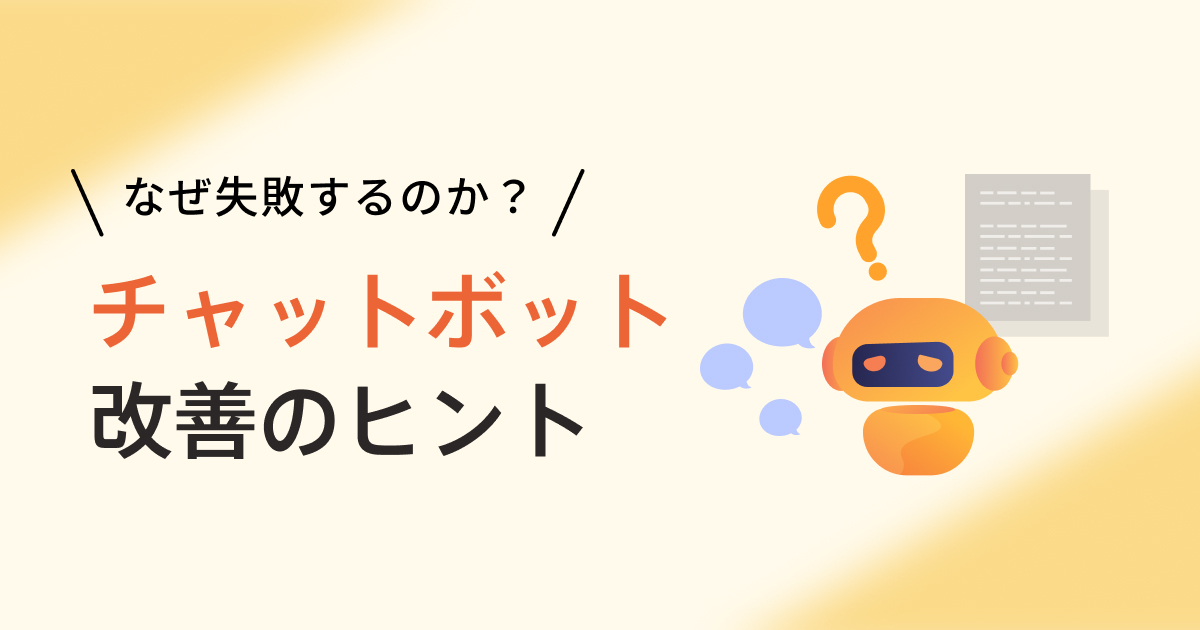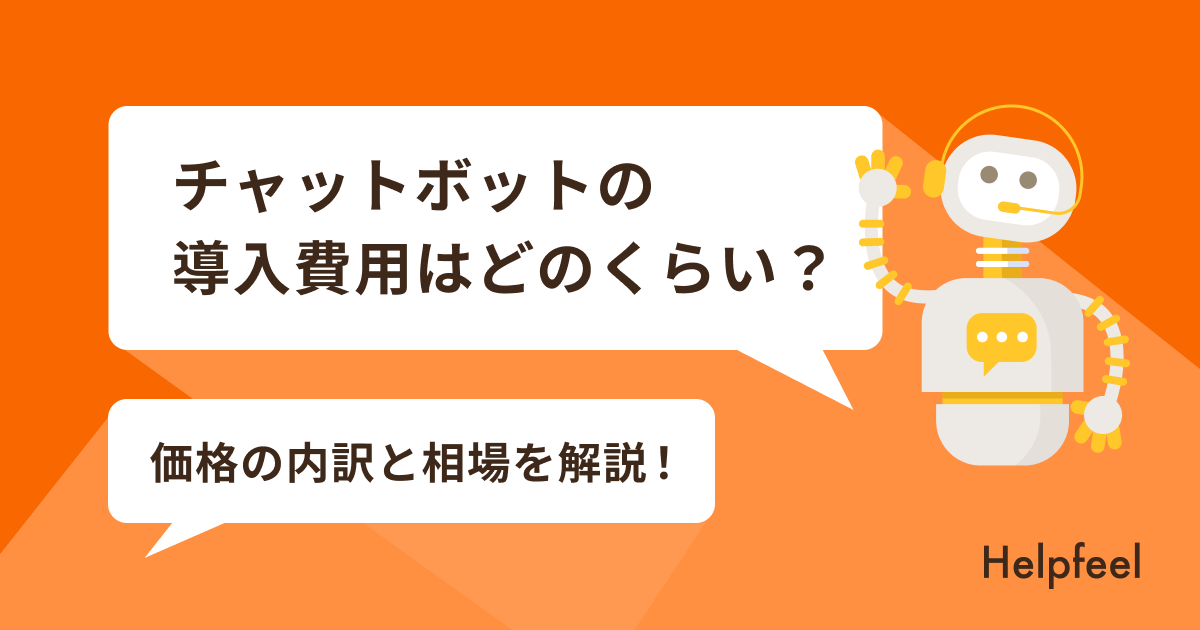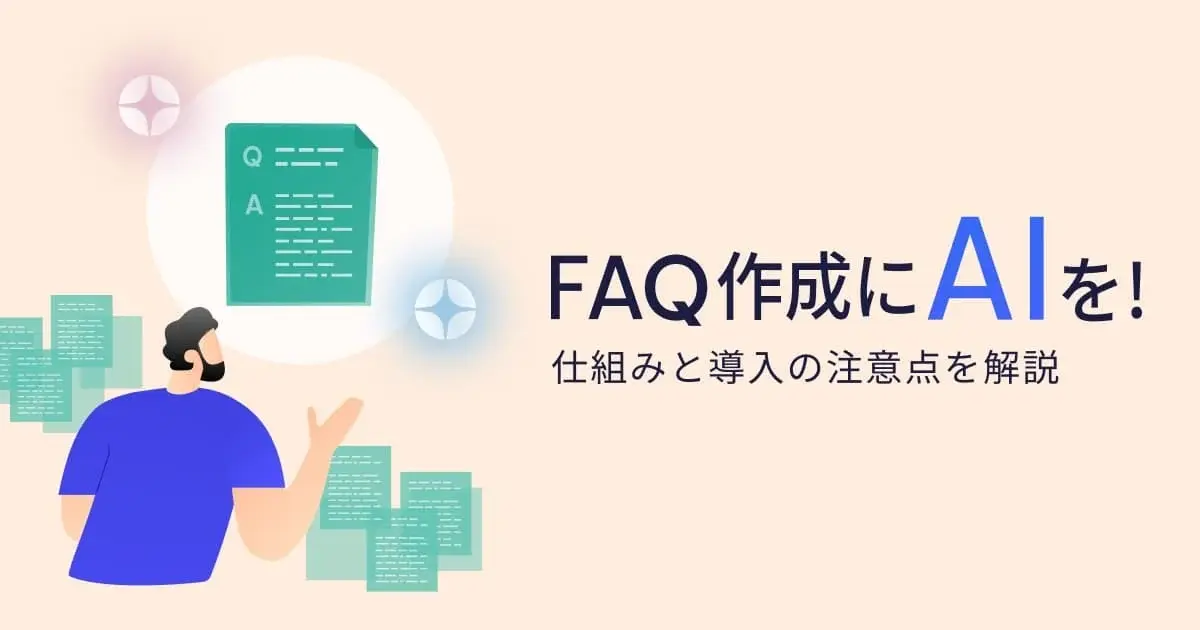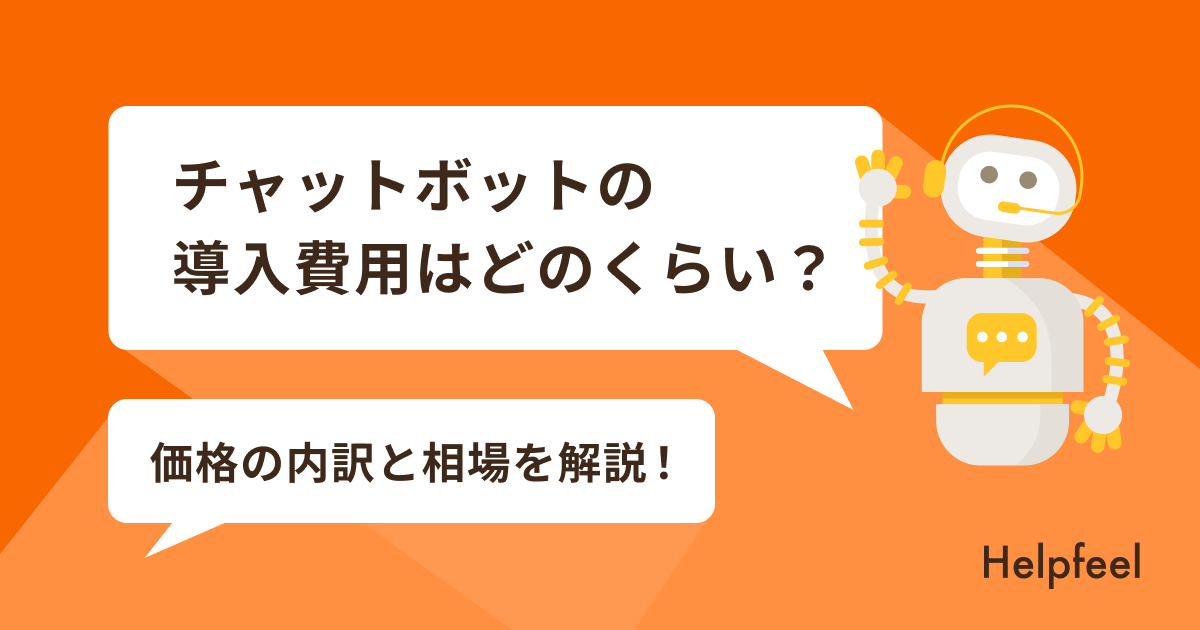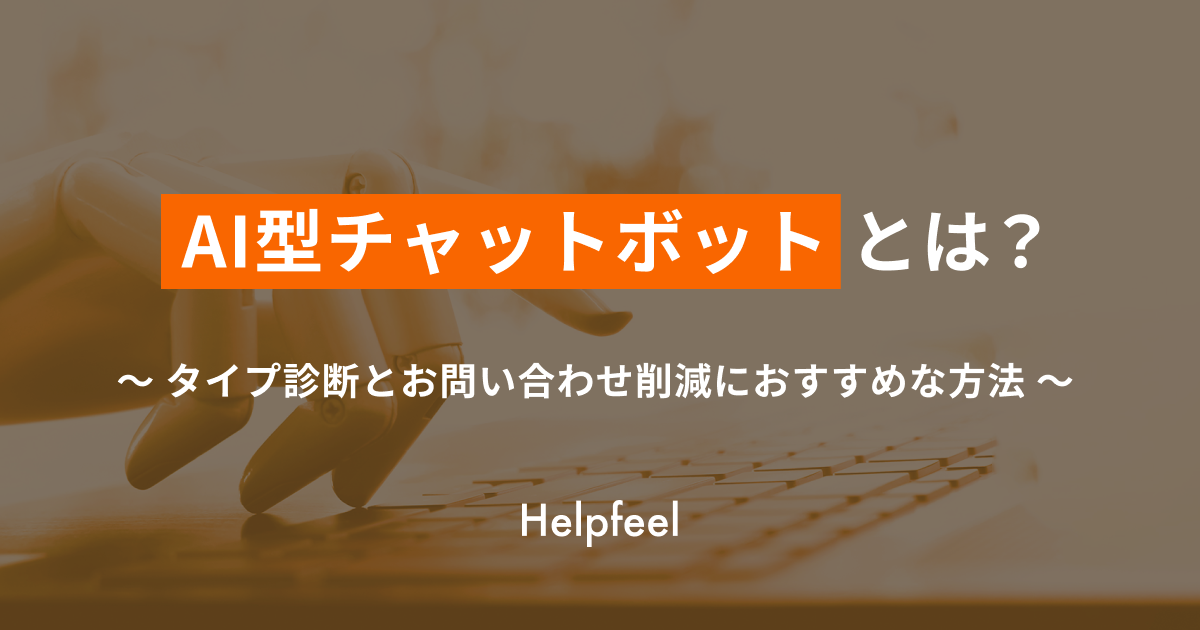社内ヘルプデスクとは

チャットボットの主な用途の一つが、社内ヘルプデスクです。社内ヘルプデスクとは、従業員からのIT関連の問い合わせに対応する業務のことを指します。
例えば、「ツールの使い方を教えてほしい」「パソコンがフリーズした」「システムにログインできない」などの問い合わせに対して、問題が解決するまで適切な回答・サポートを行います。
▼社内ヘルプデスクの役割や課題感など詳しく知りたい方は、こちらも併せてご覧ください。
社内SEとの違い
社内ヘルプデスクと社内SEの違いは業務内容です。
|
従業員からのIT関連の問い合わせに窓口として対応 |
|
社内システムの開発や改善を担当 |
ただし、企業によっては両者に明確な違いを設けず、「社内ヘルプデスク=社内SE」という位置付けで、ITサポートから社内システム開発まで幅広く業務を行っているケースもあります。
社内ヘルプデスクにおける「よくある課題」

社内ヘルプデスクに関して、多くの企業が直面しているよくある課題には、以下の4つがあります。
これらの課題を放置してしまうと、さまざまな問題に発展してしまう可能性が高いでしょう。以下、上記4つの課題について詳しく解説します。
対応業務が多く、社内ヘルプデスク業務に集中しにくい
社内ヘルプデスクは、IT関連の問い合わせ対応だけでなく、パソコン機器の管理やセッティング、各種アカウント設定・管理など、多様なITサポート業務も並行して行っています。
そのため、ITサポート業務が立て込んでいる場合は社内ヘルプデスク業務に集中できず、対応が後手に回るリスクがあります。
迅速な対応を急に求められる
社内ヘルプデスクへの問い合わせの中には、「ネットワークにつながらない」「システムにログインできない」など、迅速な対応を求められるものもあります。
こうした緊急性の高い問い合わせが同時に複数寄せられてしまうと、社内ヘルプデスク担当者は予定していた業務を進めることが難しくなり、業務が滞りがちになります。
さらに、いつ急な対応を求められるのかわからない状況では、仕事の見通しを立てにくく、常にストレスを抱えながら仕事を進めなければなりません。
同じような質問に何度も回答。モチベーションが維持しにくい
従業員がぶつかりがちな問題や課題は似ているため、社内ヘルプデスクには「同じような問い合わせが繰り返し寄せられる」という状況がよくあります。
しかし、同じような受け答えを何度も繰り返すことで、担当者のモチベーション低下を招く恐れがあります。
打開策として社内wikiや社内FAQの整備をリクエストしても、予算の都合などから実現されない場合もあるでしょう。しかし状況を改善できないと、担当者が離職してしまう事態にもなりかねません。
業務が属人化しやすい
問い合わせ対応の記録やマニュアルが整備されていないと、特定の担当者に業務が集中する「属人化」が起こります。
その結果、担当者の不在時に対応が滞ったり、情報共有の不足による対応漏れが発生したりと、業務の安定性が損なわれるリスクが生じます。そして、引き継ぎが難航すると、新任の担当者の育成に時間や負担がかかるケースも珍しくありません。
属人化を防ぐには、対応履歴の記録やナレッジの共有、FAQの整備といった「情報の見える化」が重要です。組織としての対応力を維持・強化するためにも、属人化の解消は優先度の高い課題といえます。
社内ヘルプデスクの属人化を防ぐには、ナレッジの共有と定着が不可欠です。Helpfeelは、検索性に優れた社内FAQを通じて、情報の属人化を解消し、誰でも対応できる体制を支援します。
>> Helpfeelの「社内FAQシステム」を詳しく見る
社内ヘルプデスクの課題解決に必要なのは従業員の「自己解決」促進

社内ヘルプデスクが抱える課題を根本から解決するためには、「従業員一人ひとりが自分で問題を解決できる環境づくり」、すなわち「自己解決」の促進が重要です。これは、担当者の業務負荷を軽減するだけでなく、対応スピードの向上や属人化の防止にもつながります。
特に「同じような質問が繰り返される」「属人化により特定の人に業務が集中してしまう」といった課題は、社員が自ら情報を探し、解決できる仕組みを整えることで改善が可能です。
例えば、よくある問い合わせや操作手順を集約したFAQページやナレッジベース、業務マニュアルの整備などが挙げられます。
ただし、情報が整理されていなかったり検索性が低かったりすると、自己解決のハードルは上がり、結果として従業員は「人に聞く」選択肢を取りがちです。そのため、ナレッジの体系化・可視化に加えて、検索のしやすさやUI/UXの設計も重要なポイントといえます。
さらに、最近では社内チャットツールと連携したチャットボットの導入により、従業員が「気軽に質問できる環境」も整えやすくなりました。チャットボットを活用すれば、簡単な問い合わせに対して即時に自動回答できるため、社内ヘルプデスク担当者が都度対応する必要がなくなり、リソースの最適化にもつながるでしょう。
▼あわせて読みたい
社内ヘルプデスクの業務支援には「チャットボット」が有効
従業員の「自己解決」を促進し、社内ヘルプデスクの業務負担を軽減する手段として近年注目されているのが、チャットボットの導入です。チャットボットは、ユーザーからの質問に自動応答する仕組みです。定型的な問い合わせに即時で対応できる点が最大の特長といえます。
社内ヘルプデスクに寄せられる質問の多くは、「メール設定の方法は?」「Wi-Fiがつながらない」「システムのパスワードを忘れた」など内容が類似しており、パターン化されています。こうした繰り返しの対応をチャットボットに代替させることで、担当者の手を煩わせることなく、従業員が自ら解決にたどり着けるようになるでしょう。
▼あわせて読みたい
また、チャットボットは24時間稼働が可能であるため、担当者が対応できない時間帯や、繁忙期でも即時対応が可能です。特に、リモートワークやフレックス勤務が進む中で、「いつでも」「どこでも」アクセスできる自己解決ツールとしての価値が高まっています
さらに、FAQやナレッジベースと連携することで、適切なマニュアルや記事への誘導も可能です。ユーザーの質問意図を解析し、必要な情報を提示する仕組みを整えれることで、従業員満足度の向上にもつながります。
▼Helpfeelでは最新技術を用いた次世代のAIチャットボットを提供しています。詳細は資料からぜひご確認ください。
チャットボットは3種類。生成AIを活用したチャットボットが徐々に普及
チャットボットは主に以下の3種類に分類されます。
|
AI関連技術を搭載したチャットボット。質問文に応じて、事前に人がチェックした回答文が柔軟に表示される |
|
生成AI技術を搭載したチャットボット。質問内容に応じて、AIが考えた回答文が表示される |
|
あらかじめ設計されたシナリオ通りの動作を実行するチャットボット。シナリオに沿った回答が表示される |
上記のうち、特に導入が増えているのが「生成AIチャットボット」です。生成AIの進化に伴い、社内ヘルプデスクだけでなく公式サイトに搭載して社外向けに活用する事例も増えています。
▼本記事に関連したお役立ち資料をご用意しています。ぜひ併せてご覧ください。

社内ヘルプデスクにチャットボットを導入するメリット

こうした課題を解決し得る手段として、チャットボットの導入が挙げられます。具体的なメリットは以下の5つです。
|
それぞれのメリットについて、詳しく解説します。
社内ヘルプデスクの業務負荷を軽減できる
チャットボットを導入することで、基本的な疑問は自身で解決してもらえるようになります。
パスワードのリセット手順やシステムへのログイン方法、アプリのインストール方法など、定型的な業務に関する質問をチャットボットに回答してもらうだけでも、社内ヘルプデスク担当者の業務負荷は一定軽減することでしょう。
また、担当者に寄せられる問い合わせ数が減ること自体も、業務負荷軽減につながります。同じような質問を繰り返し受けることが減るため、担当者のストレスの緩和が期待できます。
時間や場所を問わず問い合わせが可能
チャットボットを導入する最大のメリットの1つが、24時間365日、時間や場所に縛られずに問い合わせができる点です。
リモートワークやフレックスタイムが普及する中で、社内ヘルプデスクの営業時間外に発生する問い合わせも増加傾向にあります。チャットボットであれば、深夜や休日でも即時に対応でき、従業員が自分のタイミングで問題解決できる環境を整えられるでしょう。
また、拠点や部門が複数ある企業においても、全国どこからでも均一なサポートが受けられる点も大きなメリットです。問い合わせ対応の柔軟性を高めることで、従業員満足度の向上にもつながり、結果的に全社の生産性向上に大きく貢献します。
データの蓄積や分析が可能
チャットボットには回答率や解決率、有人対応をした件数、利用満足度など、さまざまなデータが蓄積されます。これらのデータを分析することで、社内ヘルプデスクの改善につなげられます。
例えば解決率が低い回答の精度を上げることで、よりチャットボットの利用率を向上させられるでしょう。
よくある質問に自然な会話で回答してくれる
チャットボットは、従業員からよく寄せられる質問やすでに回答が用意されている質問などに対して、自然な会話形式で回答します。
AI技術を搭載したチャットボットであれば、あいまいな質問やワンフレーズを入力するだけでも、会話をしながら的確な回答に導いてくれるでしょう。従業員は業務マニュアルを検索するよりも、必要な情報を簡単に得ることが可能です。
人に聞きにくいことも質問できる
「基本的すぎて聞きにくい」「同じ質問を繰り返しづらい」といった場合でも、チャットボットなら気兼ねなく質問できます。また相手がチャットボットであれば、どのように質問するのかを事前に深く考える必要もありません。
結果的に、社内ヘルプデスク担当者だけでなく、質問者自身のストレス軽減にもつながるでしょう。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

チャットボット導入・運用のポイント

スムーズにチャットボットを導入し、効率的に運用するためのポイントは以下3つです。
それぞれ詳しく解説します。
チャットボット導入の目的やゴールを明確化する
導入前に「何のために導入するのか」を明確にしましょう。導入目的・ゴールが明確になるほど、自社に必要な機能・特徴を搭載したチャットボットを導入できる可能性が高まります。
例えば、「有人対応率を70%削減する」「正答率85%を目指す」など、具体的なゴールを設定しておくことで、導入後に運用の改善点を洗い出しやすくなり、運用の質も高められます。
チャットボット運用に必要なデータを漏れなく用意する
チャットボットの構築時は、既存マニュアルや社内FAQなどから問い合わせに関連する情報を集めたり、過去に寄せられた問い合わせ履歴を分析したりして、チャットボット運用に必要なデータを収集しましょう。
場合によっては、他部署の協力が必要になることもあります。従業員が求める情報やよく直面する問題を分析するために、アンケートを実施するのも有効です。
学習データは多ければ多いほど、受け答えの精度は高まります。上記のようなさまざまな手法を駆使して、チャットボットに学習させるデータを漏れなく準備しましょう。
利用状況を把握・分析し、運用を改善する
チャットボットの活用には、利用状況に基づいた継続的な改善が欠かせません。
「満足度の低い回答が多い」「誤解を招く回答が多く、解決率が低い」などの状況が常態化すると、従業員のチャットボット離れが起こり、業務負荷は低減できません。「チャットボットを導入すればすべて解決する」とは考えず、導入後の改善作業にも注力しましょう。
▼チャットボット導入前に知りたいポイントをまとめたお役立ち資料をご用意しています。
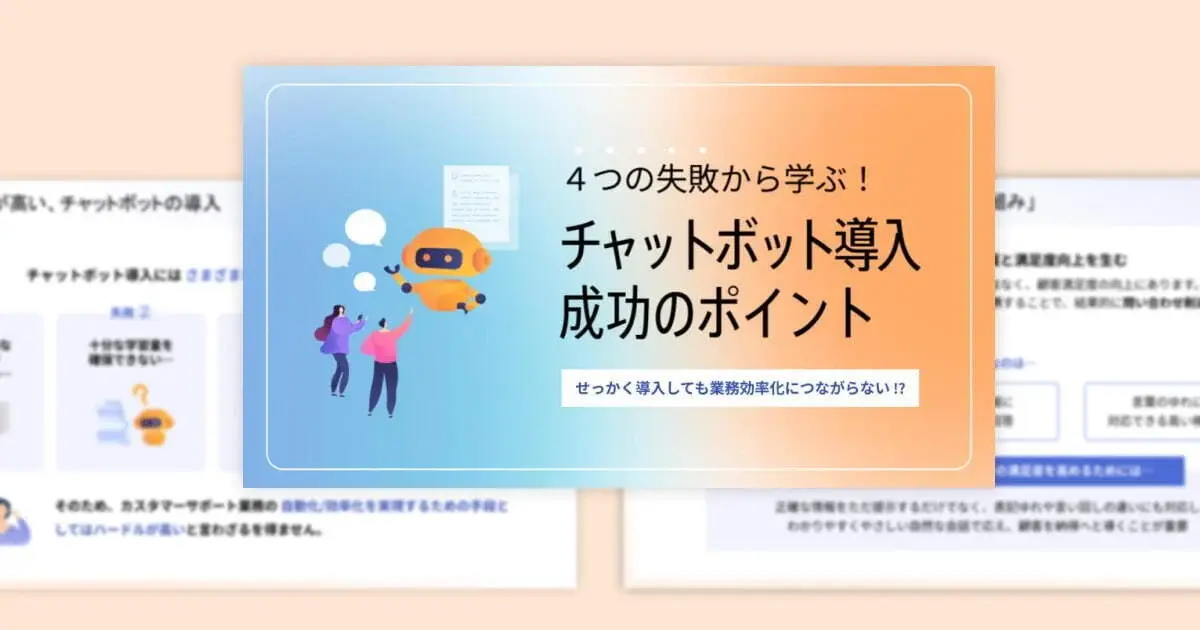
チャットボットを導入する際の注意点

チャットボットは便利なツールですが、導入しただけですぐに効果が出るわけではありません。まず注意すべきは、「目的の明確化」です。業務効率化なのか、社員満足度の向上なのか、導入目的を明確にしないまま運用を始めると、期待外れの結果に終わる可能性があります。
また、チャットボットが対応できる範囲と、人による対応が必要な範囲をあらかじめ切り分けておくことも重要です。すべてを自動化しようとすると、かえってユーザーの不満を招くことがあります。
さらに、導入後の運用改善が成功の鍵を握ります。FAQの定期的な見直しや利用データの分析を通じて、常に使いやすく進化させていくことが大切です。導入はゴールではなく、スタートだという認識を持ちましょう。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

社内ヘルプデスクのチャットボット導入事例

ある中堅企業では、社内からのIT関連の問い合わせ対応が業務を圧迫しており、ヘルプデスク部門の負担が課題となっていました。
そこでチャットボットを導入した結果、「パスワードの再発行方法」「VPN接続の手順」といった定型的な質問の約60%を自動応答で処理できるようになり、担当者の対応時間が大幅に削減されました。
また、従業員が時間を気にせずに質問できるようになったことで、社内の満足度の向上にもつながっています。
導入後はログデータをもとにFAQを定期的に更新し、チャットボットの精度を高める運用体制を構築しています。チャットボットの活用が業務効率化だけでなく、社内コミュニケーションの質の向上にも貢献した成功事例です。
“賢く答える”AIチャットボットで社内ヘルプデスクを改善しよう
%20(1).webp?width=694&height=328&name=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%20(1)%20(1).webp) AIチャットボットを導入することで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、社内ヘルプデスクの負担を軽減することもできます。「問い合わせが多く対応漏れが起きている」「対応品質を安定させたい」などの課題を感じている場合は、AIチャットボットの導入を検討してみましょう。
AIチャットボットを導入することで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、社内ヘルプデスクの負担を軽減することもできます。「問い合わせが多く対応漏れが起きている」「対応品質を安定させたい」などの課題を感じている場合は、AIチャットボットの導入を検討してみましょう。
Helpfeel Agent Mode(AIチャットボット) は、ユーザーの質問に対してAIがその場で回答を生成し、柔軟かつ自然な対話で課題解決へ導きます。従来のFAQやシナリオ型チャットボットでは拾いきれなかった質問にも対応でき、掘り下げたやりとりも可能です。
独自の「意図予測検索3」によって社内ドキュメントやFAQを横断検索し、信頼できる情報をもとに回答を提示。“答える”だけでなく“理解して導く”AIとして、Helpfeel Agent Modeは自己解決体験を新しいレベルへ進化させます。
AIチャットボットを導入することで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、担当者の負担軽減など企業側にもメリットがあります。Helpfeel Agent Modeで、自己解決体験の新しいスタンダードをぜひ体感してください。