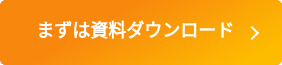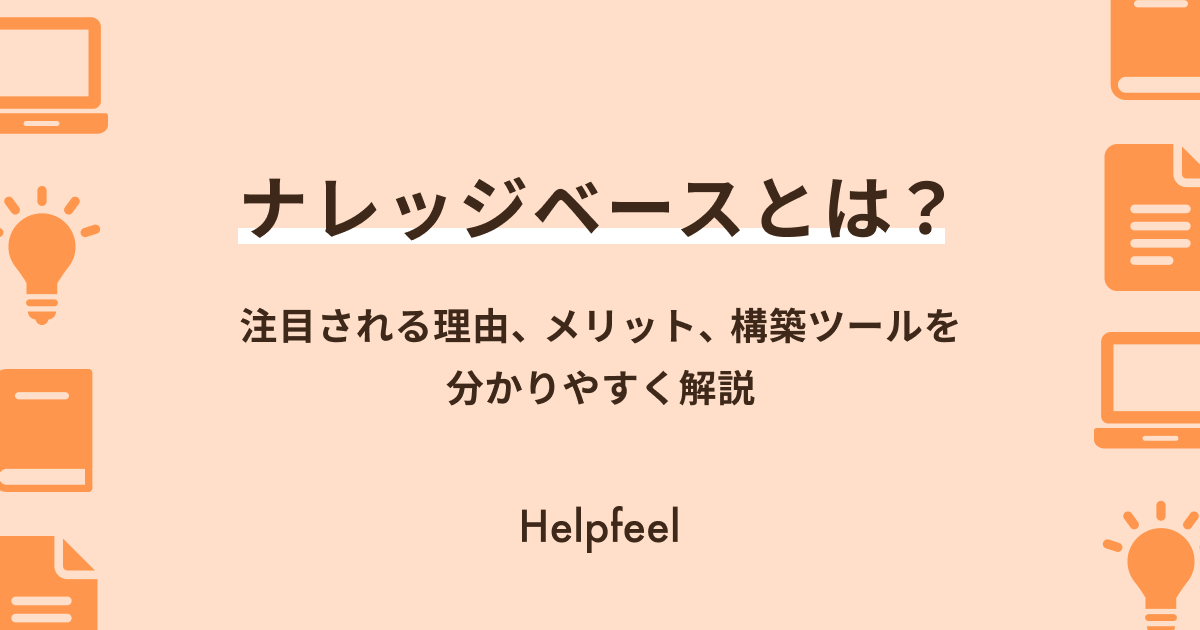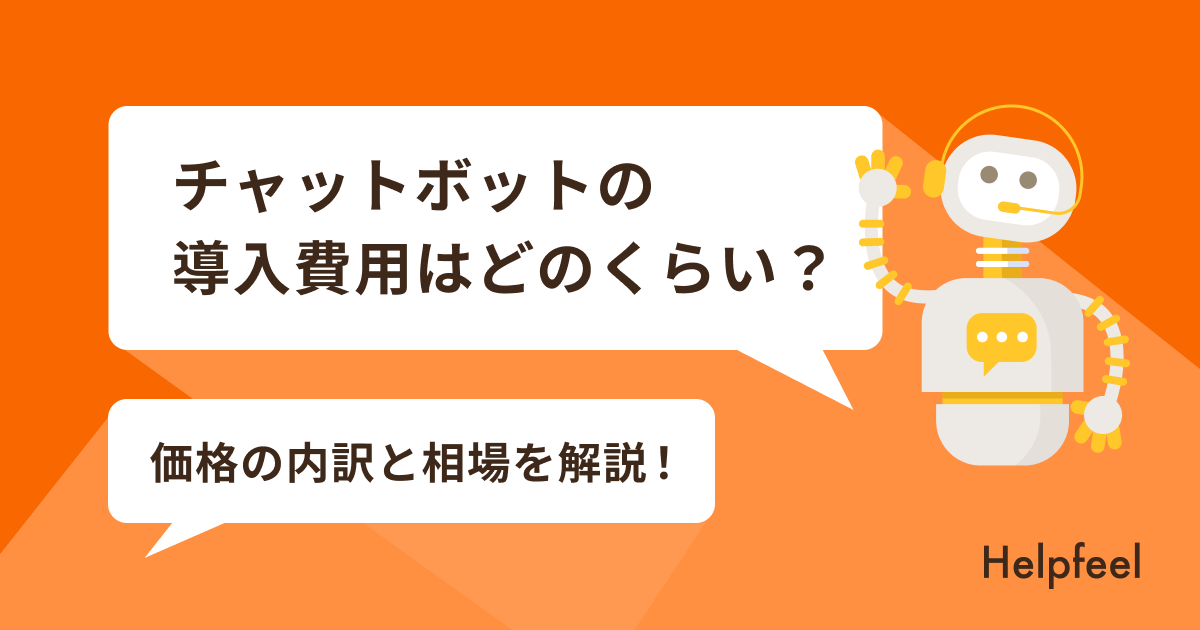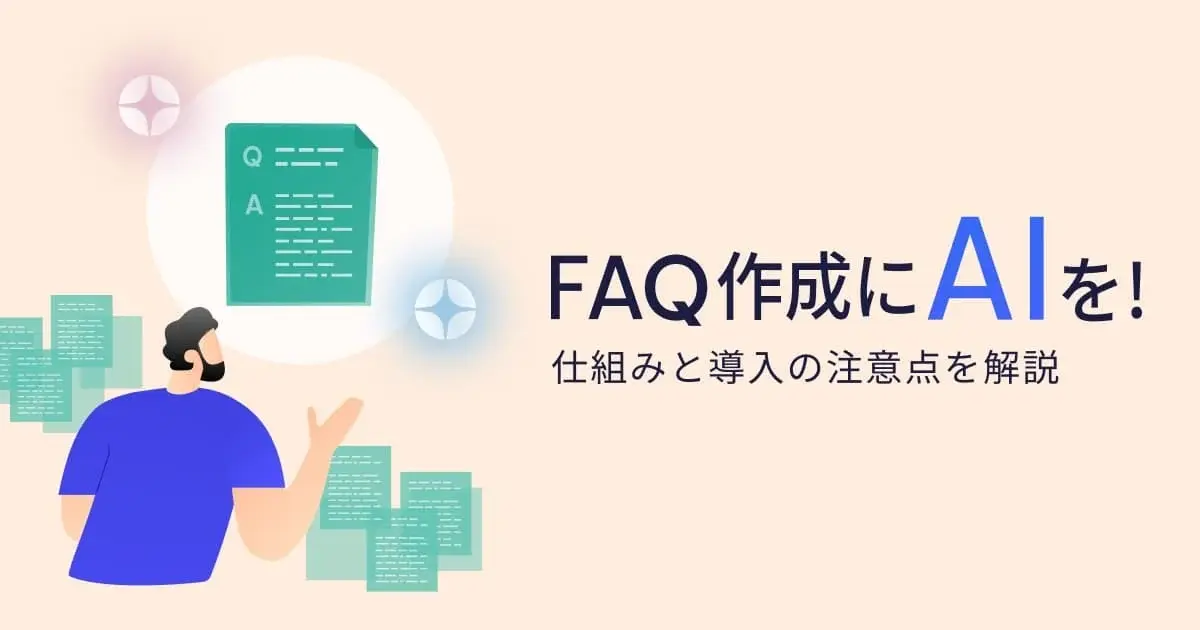KCS(ナレッジセンターサービス)とは

KCSは「Knowledge-Centered Service」の略で、ナレッジ(ノウハウや経験)を活用するためのプロセスを表します。アメリカの非営利組織「サービスイノベーション・コンソーシアム」が1992年に発表した方法論として知られています。
多くのサポートセンターでは、マニュアルやFAQを定期的に見直すことでナレッジを管理しています。しかし、ナレッジに到達するまでに時間がかかったり、ナレッジの修正が追いつかなかったりなどの課題を抱えることも少なくありません。
KCSの目的は、オペレーターが業務内で蓄積したナレッジを構造化し、組織で共有・活用しながら問題解決の効率を上げることです。KCSを取り入れることで、顧客満足度の向上や業務の効率化、属人化の防止などが期待できます。
社内外の満足度を高めるには、誰もが使いやすく、常に活きたナレッジを運用できる仕組みが不可欠です。Helpfeelの社内ナレッジシステムなら、KCSの運用を支える土台を構築できます。
>> Helpfeelの「ナレッジシステム」を詳しく見る
KCSが注目されるようになった背景

KCSが注目されるようになった背景には、サポートセンターが抱える課題の複雑化が挙げられます。
近年、サポートセンターに見受けられる主な課題は以下の通りです。
|
上記のような課題が多くのサポートセンターで生じるようになった結果、「ナレッジマネジメントのレベルを引き上げるべき」という機運が高まったと考えられます。
蓄積したナレッジを課題解決に役立つコンテンツに発展させるための仕組みとして、KCSの重要性が注目されるようになったのです。
▼あわせて読みたい
KCS運用により期待される効果

KCS運用で期待できる効果は、以下の4つです。
|
KCSでは、発生した問題を全てコンテンツ化できるため、スピーディーかつ網羅的にナレッジを蓄積できます。問題が起きた際は蓄積したナレッジを確認するだけで済み、一から対策を考えたり、上司の判断を仰いだりする必要が少なくなるため、業務効率が向上します。
さらに、データベース化したナレッジを活用することによって、新人オペレーターでも複雑な問い合わせに対応しやすくなります。業務の属人化を防ぐことで、オペレーターの対応品質が均一になり、問題解決の効率向上や顧客満足度向上につながるでしょう。
こうしたKCSの考え方を実践するには、誰もが迷わずナレッジにアクセスできる仕組みが不可欠です。Helpfeelなら、高精度な検索性と運用しやすい管理機能により、ナレッジの蓄積・活用を現場に根づかせることができます。
KCSの2つのプロセス

KCSの2つのプロセスは、以下の通りです。
|
個人と組織の両方で適切なプロセスを踏み、蓄積したナレッジを有用なコンテンツに昇華させることがKCSのゴールです。
SOLVE(解決ループ)
SOLVEの4つのステップは、以下の通りです。
|
問題の把握 |
|
ナレッジの組み立て |
|
ナレッジの再利用 |
|
改善へつなげる |
各ステップについて、詳しく解説します。
Capture:問題の把握
まず、サポートセンターに寄せられた問題を的確に捉えます。ポイントは、顧客の問い合わせ内容から「顧客の目線」かつ「顧客の表現」で問題を捉えることです。
KCSでは、新たなコンテンツを一から作るのではなく、対応業務の中でコンテンツ化できる情報を抽出することを重視します。
問い合わせ対応の自然な流れの中で、顧客が直面している問題と解決策を具体的なナレッジとして文章化してみてください。プロセスの大切なベースとなるステップであるため、顧客がどのような問題を抱えているのか細かく捉えていく必要があります。
▼あわせて読みたい
Structure:ナレッジの組み立て
問題を整理・分類し、ナレッジを組み立てます。KCSでは「問題・原因・解決策」というテンプレートで簡潔にまとめるのが基本です。
例えば「外付けHDDがパソコンに接続できない」という問い合わせがあった場合、下記のように内容をまとめます。
|
記載する内容は、文章である必要はありません。必要な単語を網羅して簡略化することで、ナレッジとしての検索性が上がり、再利用しやすくなります。
▼あわせて読みたい
Reuse:ナレッジの再利用
組み立てたナレッジを、オペレーターが再利用(検索)できる状態で共有します。オペレーターが問い合わせに対応する際に、ナレッジの検索結果を参考にしてスムーズに問題を解決できるでしょう。
また、顧客の自己解決を促進するために、FAQ(よくある質問)やポータルサイトにナレッジを公開する場合もあります。顧客が自分で問題を解決できる状態を作れば、サポートセンターへの問い合わせが減り、オペレーターの負担軽減につながるのが利点です。
問い合わせが減りオペレーターに余裕が生まれれば、対応品質が上がり、顧客満足度の向上につながります。
Improve:改善へつなげる
KCSでは「ナレッジを組み立てたら終わり」ではなく、再利用を通じて改善することが重要です。ナレッジを利用した際に不足点や誤りを見つけた場合は、その度に情報の修正・更新を行います。
また、ナレッジをより検索しやすくするために記載内容をブラッシュアップすることも大切です。すでに解決策がある場合でも、既存の解決策が時代遅れになっていたり、より簡単な方法が見つかったりすることがあります。
継続的に改善し、よりナレッジの精度を高めなくてはなりません。
EVLOVE(発展ループ)
EVOLVEの4つのステップは、以下の通りです。
|
コンテンツの保全 |
|
ナレッジベースの利用拡大 |
|
オペレーターの実績を評価 |
|
コミュニケーションとリーダーシップでKCSを定着 |
各ステップを詳しく解説します。
Content Health:コンテンツの保全
コンテンツを健全に保ち、SOLVEのフローを組織に定着させるためのステップです。効率的に組織への定着を進めるなら、ツールを活用するのがおすすめです。
たとえ有用なナレッジベースでも「検索しづらい」「どう扱えばよいかわからない」などの問題が生じると組織に定着しにくくなります。便利ツールを導入することで、スムーズな定着につながるでしょう。
例えば、ログを入力するだけで解決策が提示されるツールを導入すれば、検索の利便性が向上します。また、ナレッジ用データサーバーやサポートサイトの構築など、システム面から定着を進められるようにインフラを整備することも大切です。
Process Integration:ナレッジベースの利用拡大
次に、ナレッジベースの利用拡大を推進します。ポイントは、小さなグループで使い始めてから、徐々に大きなグループへと拡大していくことです。
例えば、最初は二次対応窓口でナレッジベースの使用をスタートし、一定の利用回数を超えたら一次窓口にも開放します。一次窓口でも頻繁に利用されるようになったら、顧客向けに内容を見直してWebサイトに公開する、という流れが考えられるでしょう。
いきなり大規模展開をすると、不備が頻発して利用に滞りが生じる可能性があります。段階的に様子を見ながら利用範囲を広げていくことで、失敗を防ぐことができます。
▼あわせて読みたい
Performance Assessment:オペレーターの実績を評価
KCSの取り組みに対するオペレーターの実績評価を行います。例えば、KCSのプロセスをきちんと理解して実践できているかを評価し、「KCSレベル1」「KCSレベル2」「KCSレベル3」のようにポジションを与えるのも1つの方法です。
たくさんの人に利用される「質の高い解決策」を作成した人はポジションが上がり、報奨を受けられるようにすると、やりがいを引き出しやすくなります。
他にも、解決策の更新数や作成数、利用回数に応じてインセンティブを与え、適切に評価すれば、モチベーションの向上につなげられるでしょう。
Leadership & Communication:コミュニケーションとリーダーシップでKCSを定着
KCSを定着させるためには、強いリーダーシップが欠かせません。組織内に「なぜKCSを導入するのかわからない」「新しい取り組みは面倒」という空気が漂っている状態では、運用に支障を来す可能性が高まってしまいます。
まずは、組織の成功にKCSがどのように関わっていくのかを明確にし、理解してもらう必要があります。リーダーが自らコミュニケーションを取りながら、個人やチームが目指すべきビジョンを明示し、指導することが大切です。
▼本記事に関連したお役立ち資料をご用意しております。ぜひ併せてご覧ください。

KCS導入の成功事例

KCSを導入したコールセンターやカスタマーサポートサービスの成功例では、愛媛県松山市に本店を構える伊予銀行があります。
以前は400冊ほどのマニュアルに頼っていた伊予銀行のコンタクトセンターですが、移転に伴い、デジタル化が避けられない状況となりました。デジタル化する際にKCSに着目し、「Helpfeel Cosense(コセンス)」を導入して効率的なナレッジ運用を図ったのです。
移転までに400冊もの紙のマニュアルをなくすことを目指し、ナレッジの運用改善を図っています。アナログのマニュアルからKCSへと移行していく中で、一部のオペレーターへ負担が偏っていた状況を改善し、全てのオペレーターへ分散しました。
▼事例詳細はこちら
伊予銀行が、KCSの実現に向け、組織が変わるナレッジイネーブルメントツール「Helpfeel Cosense(ヘルプフィール コセンス)」を導入
KCSの課題
KCSは「SOLVE」と「EVOLVE」のダブルプロセスで行うため、オペレーターに負担がかかる場合があります。急な負担の増加は、業務効率や品質の低下につながるため注意が必要です。
オペレーターの負担軽減には、自動要約機能や音声テキスト化機能を搭載したツールの活用が有効です。問い合わせの後処理で生じる手間が減り、KCSのプロセスを実行するための時間を創出できます。
また、オペレーター自身がKCSを理解していなければ運用は定着しません。研修を実施し、ナレッジの構造化や改善に関する指導を行ってください。オペレーターの負担を考慮しながらKCSの周知と運用を進めることで、迅速な業務効率化が叶うでしょう。
▼あわせて読みたい
KCSを始めるなら「Helpfeel Cosense」がおすすめ
Helpfeel Cosense(コセンス)は、1人ひとりのオペレーターがメモをとる感覚で作成したものが、そのままチームナレッジとなるツールです。顧客のニーズや、顧客が抱える問題点などをリアルタイムで把握して、オペレーター用FAQへ生かせます。
全てのオペレーターが「探す」「読む」「書く」といった作業を無理なく実践できる仕組みで、KCSへの活用が可能です。独自の特許技術により、検索精度の高さを実現している点も、Helpfeel Cosense(コセンス)の強みです。
▶︎「Helpfeel Cosense」について詳しくはこちら
KCSでカスタマーサポートセンターの生産性を上げるなら「Helpfeel」
オペレーター用のFAQを効率的に利用するには、知りたいことを検索したときに、適切な情報を得られることが求められます。有用な情報を得るためには、ナレッジの蓄積と活用が欠かせません。
Helpfeelは、高精度な検索技術でナレッジベースから最適な回答を瞬時に見つけ出し、効率的な問い合わせ対応をサポートするFAQシステムです。Helpfeelを導入すれば、カスタマーサポートセンターのナレッジ蓄積からオペレーター用FAQの生成、問い合わせ対応の品質向上まで一貫して行えます。
オペレーター用FAQを拡充することで、オペレーターは必要な情報を瞬時に検索でき、顧客対応に集中できるようになるでしょう。その結果、顧客満足度の向上とオペレーターの離職率低下も期待できます。KCSの体制構築にオペレーター用FAQシステムを導入したいと考えている方は、ぜひHelpfeelを試してみてください。
まとめ:システムを導入してオペレーター業務の効率化を図ろう!

この記事では、KCSでカスタマーサポートを効率化させ、顧客満足度を向上するためのプロセスを解説しました。KCSを導入すれば、企業としてナレッジの蓄積が可能になります。
オペレーターが個々で持つ知識や情報は、個人差が大きくなりがちで、顧客の不満につながりかねません。KCSでは対応品質を均一に保てることから、顧客満足度の向上が期待できます。オペレーターの教育や日々の業務を効率化すれば、利益の安定につながるでしょう。
カスタマーサポート体制を一新したいと考えているなら、KCSの導入は有効な選択肢です。まずはツールを活用しながら、一歩踏み出してみてください。