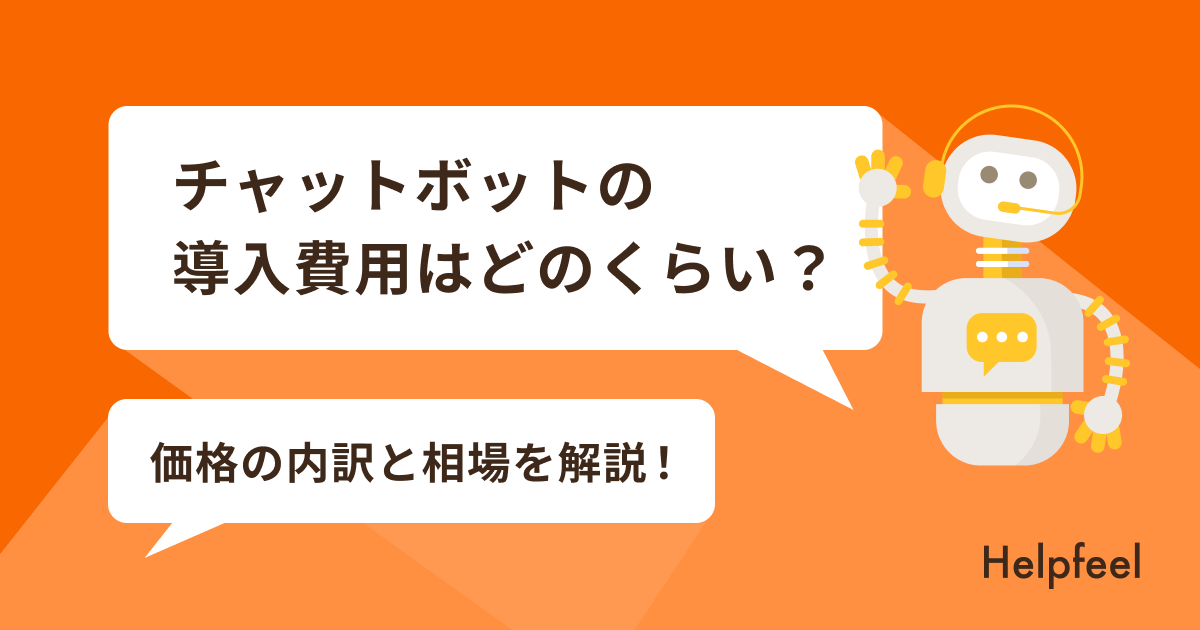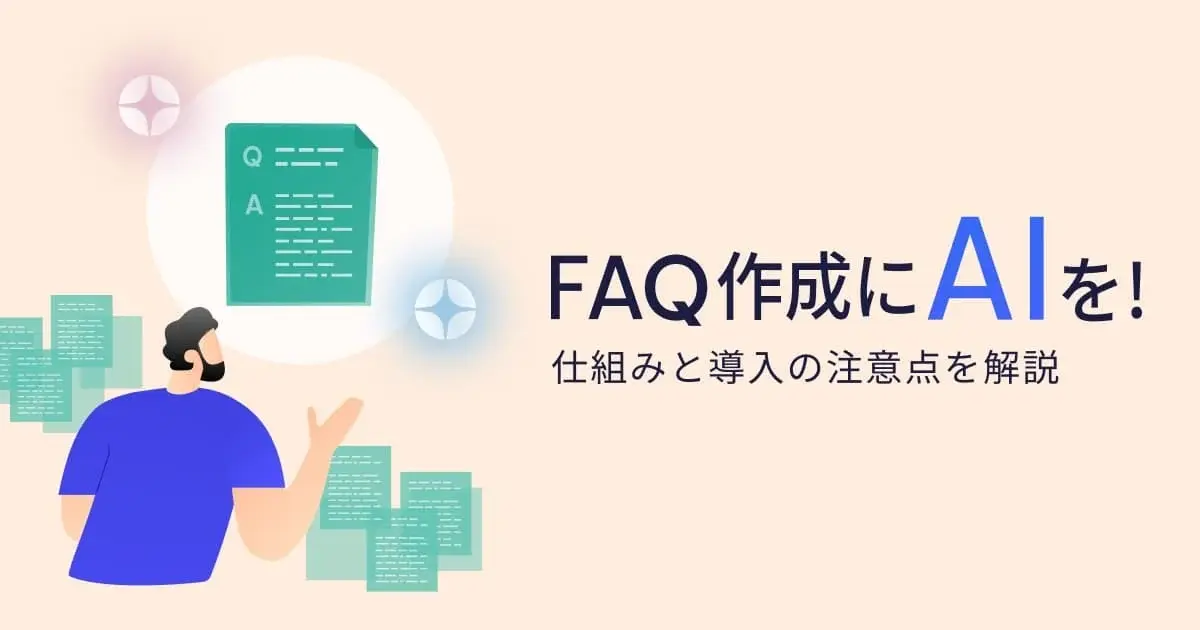FAQとは? どんな意味がある?
FAQ(読み方:エフ・エー・キュー)とは、「よくある質問」と「それに対応する回答」という意味です。
Frequently Asked Questionsの略語であり、英語を直訳すると「よくある質問」となりますが、実際には質問だけではなく、それに対応する回答(Answer)も含んだ意味合いで使われています。
FAQとQ&Aの違いとは?
FAQと似た言葉に「Q&A」があります。Q&Aは「Question and Answer」の略で、シンプルに言うと「質問とその答え」をまとめたものです。マニュアルの巻末などで、一問一答形式で載っているケースが多く見られます。
一方でFAQは、「頻繁に尋ねられる質問」を集めたものです。Q&Aの中でも、とくに問い合わせ頻度が高いものだけを抜き出して整理しているイメージです。
つまり、FAQは「よくある質問だけを厳選してまとめたもの」、Q&Aは「質問と回答を一問一答形式で並べたもの」というイメージです。ただし、現場ではどちらも「よくある質問とその回答」を指す言葉として混在して使われることも少なくありません。
FAQの種類と目的の違い
 FAQには、大きく分けて次の3つの種類があります。
FAQには、大きく分けて次の3つの種類があります。
|
上記3つのFAQは、それぞれ目的が異なります。以下で、FAQの種類と目的について詳しく見ていきましょう。
1.顧客向けのFAQ
顧客向けのFAQは、顧客から問い合わせの多い内容と回答をまとめたものです。一般的に、顧客向けFAQは誰でも見られるように、自社サイトなどに公開します。これにより、疑問や困りごとがあった際に顧客が自分で解決策を見つけられます。
顧客向けFAQを整備しておくと、問い合わせる手間が省けるため、顧客満足度の向上につながります。また、問い合わせ件数の減少によってコールセンターの工数削減など、企業側にもメリットがあります。
▼あわせて読みたい
2.社内向けのFAQ
社内向けのFAQは、経費処理の方法や業務システムの使い方など、社員からバックオフィス部門への問い合わせをまとめたものです。
社内での利用を想定しているので、基本的に社外に公開することはありません。社内向けFAQを用意しておくと、社員が自分で不明点や疑問点を解消できます。これにより、バックオフィス部門は問い合わせ対応に追われることなく、本来の業務に集中できるようになります。
▼あわせて読みたい
3.コールセンター向けのFAQ
コールセンター向けのFAQは、想定される問い合わせ内容とその回答や、トラブルが発生した時の対応方法などをまとめたものです。オペレーターが問い合わせ対応時にFAQを参照することで、誰が対応しても一定水準の回答ができるようになり、応対品質の均一化が図れます。
また、一般的な問い合わせならFAQを見れば対応可能なため、新人教育にかかる手間や時間の削減につながるのも、コールセンター向けFAQの役割のひとつです。
▼あわせて読みたい
FAQがもたらす効果・メリットとは?
顧客が製品やサービスに関して疑問を持つ際、まずFAQページを参照することが一般的です。FAQは単なる「よくある質問集」ではなく、ビジネス全体の生産性向上にもつながる多くのメリットを持っています。ここでは、具体的な4つの効果について見ていきましょう。
効果1:問い合わせ件数の減少による顧客対応業務の負担軽減
FAQは、顧客や従業員が抱える疑問を自己解決へと導くため、電話やメールでの問い合わせ件数を大幅に削減します。
これにより、コールセンターやカスタマーサポートスタッフは、FAQで解決できない複雑な問題や、より専門的な対応に集中できるようになり、業務の効率化と負担軽減が図れます。
「社内向けFAQ」の場合も同様に、労務部、総務部、情報システム部といったバックオフィス部門への定型的な問い合わせが減り、担当者が本来の業務に注力できるようになります。
これは人件費や通信費といった業務コストの最適化、人為的なミスの防止、さらには離職率の低下といった二次的な効果も期待できます。
導入実績800サイト以上の「Helpfeel」を導入された企業では、問い合わせ件数を最大で64%削減した実績があります。業務負担の軽減は、結果として顧客満足度の向上にも直結します。その詳細については、次の項目で詳しく解説します。
▼Helpfeelの詳細はこちら
効果2:顧客満足度の向上
FAQページを充実させることで、多くの顧客はオペレーターの手を介さずに、自らトラブルや疑問をその場で解決できるようになります。その結果、顧客満足度の底上げにつながり、リピーター増や顧客単価増、解約率改善が期待できます。
「電話がつながらない」「メールの返信が遅い」といった状況は、顧客の不満やクレームに繋がり、顧客離れを引き起こす可能性があります。FAQがあれば、顧客は自身の都合の良いタイミングで、待つストレスなく迅速に情報を得ることができます。
また、「コールセンター向けFAQ」を通じて、オペレーターは常に正確で一貫した情報を提供できるようになります。これにより、顧客対応の品質が安定し、支援不足によるトラブルを未然に防ぎ、企業イメージの向上やリピーターの増加にも繋がります。
さらに、顧客から寄せられた疑問や悩みをFAQのデータとして分析することで(VOC分析)、製品開発やサービス改善に活用することも可能です。
▼あわせて読みたい
効果3:SEO対策に有効
FAQはSEO(検索エンジン最適化)対策としても非常に有効です。
顧客は製品やサービスに関する疑問をGoogleなどの検索エンジンで検索することが多いため、「〇〇の使い方」「△△の料金」「□□との違い」といった具体的な質問やキーワードをFAQページに自然な形で含めることで、検索結果での上位表示が期待できます。
SEOに最適化されたFAQコンテンツは、検索エンジンからの評価を高め、ウェブサイトへのオーガニックなトラフィック(自然検索からの訪問者)を増加させます。これにより、広告費用をかけずに顧客との接点を増やし、コンバージョン率の向上に貢献することが可能です。
また、FAQページのアクセス数が増えることで、サイト全体のPV数やユニークユーザー数(UU)も増加し、サイト全体の評価向上にもつながります。
▼FAQ最適化の関連事例はこちら
効果4:ナレッジの蓄積
問い合わせの多い内容と回答をFAQにまとめておくと、ナレッジ蓄積ツールとしても活用できます。「FAQを見れば誰でも対応できる」という環境を整えておけば、「この業務についてはあの人に聞かないと分からない」といったいわゆる属人化を防げます。
業務が属人化してしまうと、「担当者が席を外している間は確認ができない」「問い合わせ対応に追われて本来の業務に手が回らない」など、業務効率の低下を招きます。また、ナレッジが共有されていないと、退職者が出る度に業務の質も低下してしまうため、注意が必要です。
FAQを作成してナレッジを蓄積できる環境が整っていれば、上記のような事態を防ぎ、業務効率の向上にもつながります。
▼800社以上を支援してきたHelpfeelのCX改善ナレッジノウハウを、無料で公開中です。
今後の業務にぜひお役立てください。
.webp)
FAQページの作成手順

ここでは、実際にFAQを作成する時の手順を解説します。効果的なFAQを作成するには、以下の3ステップで進めましょう。
|
それぞれのステップで取り組む内容を、以下で詳しく見ていきましょう。
1. 目的を設定する
まず、FAQを作成する目的を明確にしてください。多くの場合、FAQの導入には「特定の課題を解決したい」という背景があります。解決したい課題の内容に応じて、作成すべきFAQの種類が変わってくるため、どのような課題を解決したいのかを具体化しましょう。
例えばコールセンターの業務効率を上げたい場合、以下の対応ができます。
|
このように、解決したい課題や対象者によってFAQの種類や内容が変わるので、最初に目的を明確化しておくことが重要です。
2. 情報を収集し質問と回答を作る
FAQの目的を設定したら、必要な情報を収集して質問と回答を作成します。この時に重要となるのは、「こういう問い合わせが多いだろう」と推測で内容を決めるのではなく、実際の問い合わせデータに基づいて作成することです。
以下に、参考にするべきデータの例を紹介します。
|
「社内向けFAQ」を作成する場合は、上記のようなデータが残っていないケースも多いため、各部門の担当者へのヒアリングなどが必要になります。
また、FAQに掲載する質問は「問い合わせ件数が多いもの」を優先しましょう。明確に回答が決まっていない要望やクレームのような内容はFAQには不向きなので、質問と回答を作る際には、FAQで解決可能な内容かどうかを見極めることも重要です。
▼よくある質問を作成する際のヒントになるテンプレートをまとめたお役立ち資料をご用意しています。ぜひ併せてご覧下さい。

3. レギュレーションに合わせチェックと調整を行う
質問と回答をまとめたら、公開前にレギュレーション(社内ルール)に合わせてチェックと調整を行います。ユーザーが理解しやすいFAQとなるように、以下を確認しましょう。
|
例えば「顧客向けFAQ」の場合、企業の担当者は日常的に使うワードであったとしても、顧客にはなじみがない可能性があります。「ユーザーがひと目で理解できるか」という視点で最終チェックを実施してください。
FAQには、以下の要素が正確に掲載されているかを確認しながら作成を進めましょう。
|
チェックと調整が完了したら、ユーザーが迷わずアクセスしやすい場所にFAQを公開します。
例えば「顧客向けFAQ」なら、SEO対策をすることで、顧客が調べた際に上位表示されやすくなります。検索エンジンからたどり着きやすいように、キーワードを盛り込みましょう。「社内向けFAQ」なら、社内サイトの目立つ場所に分かりやすく掲載するのがおすすめです。
▼読み手に伝わるFAQライティングについて、以下のお役立ち記事で詳しく実践的にまとめています。ぜひ併せてご活用ください。

FAQページの作り方のポイントは?
 多くのユーザーに活用されるFAQページを作成するには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。ここでは、FAQ作成時のポイントを8つ紹介します。
多くのユーザーに活用されるFAQページを作成するには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。ここでは、FAQ作成時のポイントを8つ紹介します。
ポイント1:質問には端的に答える
ユーザーがひと目で解決方法を理解できるように、質問には端的に答えましょう。
FAQを開いた時に長過ぎる回答文が表示されると、回答を読む意欲を削いでしまいます。余計な情報を詰め込まず、ユーザー目線で「1記事1トピック」を意識した上で、疑問に対して即答する内容にするのがポイントです。
ポイント2:専門用語の説明は丁寧にする
業界用語や略語を多用すると、初心者ユーザーの離脱を招きます。用語を使用する場合は、補足説明や用語集へのリンクを添えるなどの工夫が必要です。
ポイント3:関連情報の説明は「リンク」で飛ばす
端的な回答と専門的な情報を両立させるためには、詳細な解説は別ページにまとめてリンクを設置するのが効果的です。必要なユーザーだけが閲覧できる構造にすることで、本文はすっきりと保てます。
ポイント4:カテゴリー分けをする
FAQの利便性は「探しやすさ」にかかっています。ユーザーが目的の回答を探しやすいように、質問はカテゴリーごとに分けておきましょう。質問の種類や数が多いと、カテゴリー分けされていなければ、目的の回答にたどり着きにくくなります。
ポイント5:検索できるようにする
掲載する質問の数が多いFAQは、カテゴリー分けだけでは回答を見つけられない可能性があります。そのため、キーワード検索機能を導入し、ユーザーが目的の質問を素早く見つけられるようにしましょう。よく検索されているキーワードのサジェストやタグ付け機能も有効です。
ポイント6:ユーザーが使いやすいデザイン・検索しやすいデザインを意識する
FAQは掲載内容の充実や、カテゴリー分け・キーワード検索といった機能性に加えて、ユーザー目線を意識したデザイン性も求められます。
代表的な施策は以下です。
|
想定外の不具合や詳細な確認が必要な問い合わせなど、FAQだけでは対応できないものもあります。そのため、「解決できなかった場合はこちら」のように問い合わせフォームや、カスタマーサポートへの導線も作っておくと良いでしょう。
▼あわせて読みたい
ポイント7:評価と改善を行う
FAQは公開して終わりではなく、評価と改善を繰り返すことが大切です。
具体的には以下のデータを確認することが重要です。
|
これらのデータを定期的に分析し、「どのFAQが読まれているか」「どこが改善ポイントか」を可視化した上で、継続的に改善を重ねましょう。
ポイント8:定期的にFAQをアップデートする
FAQは一度作成したら終わりではありません。製品やサービスの内容が変化したり、顧客のニーズが移り変わったりするため、定期的に内容を精査し、最新の状態に保つことが不可欠です。
アップデートすべき内容は、問い合わせの傾向や顧客の行動から見えてきます。例えば、「コールセンターに頻繁に寄せられるようになった質問」や、「既存のFAQページでは解決しきれていない疑問点」などを分析することが重要です。
アップデートを持続するためには、「誰が」「いつ」「どのように」更新作業を行うのか、運用体制とフローの確立が求められます。
更新に手間がかかると後回しになりがちですが、HelpfeelのようなFAQシステムを導入することで、シンプルで直感的な編集画面を通じて記事作成・更新が容易になり、AIを活用したドラフト作成機能で業務負荷を軽減できます。
これにより、信頼性の高いFAQを提供し続けることが可能となり、顧客満足度の向上につながるでしょう。
▼これからFAQを用意or改善する方へ。すぐに使えるテンプレート付きのお役立ち資料をご用意しております。ぜひ併せてご活用ください。

FAQシステム・ツールを導入すれば問い合わせ件数を60%削減できる可能性も!
FAQシステム・ツールとは、FAQページの作成・管理・分析といった機能をもったシステム・ツールです。FAQサイトの構築や運用だけでなく、カスタマーサポート部門やコールセンターにおける顧客対応ナレッジの一元化を目的に活用している企業も少なくありません。
利便性の高いFAQを作成するには、目的に合った質問と回答をピックアップし、ユーザー目線に立って、文章やデザインを整えることが大切です。
FAQシステム・ツールを活用すれば、FAQの作成・管理・分析を効率的に進められるので、問い合わせ件数の削減にもつながります。必要に応じて、FAQシステムの導入を検討してみてください。
>> HelpfeelのFAQシステムを詳しく見る
FAQシステム・ツールの活用事例

FAQシステム・ツールに興味がある人は、実際の活用事例も気になるポイントでしょう。ここでは、検索型FAQシステム「Helpfeel」を活用した課題解決の事例を2件紹介します。ぜひ参考にしてください。
検索ヒット率50%向上|ラクスルの活用事例
ラクスルは、ネット印刷・集客支援プラットフォームや物流プラットフォーム、運用型テレビCMサービスなど幅広い事業を手掛ける企業です。
以前からFAQを用意していましたが、約700ページに渡る膨大なコンテンツ量がありながら検索にヒットしないno hit率が約40%に上り、十分に活用されていませんでした。
ユーザー数の伸びに応じて問い合わせ件数も増える中、限られた人員でより高品質なサポートを提供するためにFAQシステムにメスを入れました。
Helpfeelを導入した結果、わずか1週間で検索ヒット率が50%向上し、no hit率は約32%減少しました。テレビCMの放映によって問い合わせが急増したものの、FAQシステムの活用でカスタマーサポートの応対品質を下げずに乗り越えられました。
▼事例詳細はこちら
有人問い合わせ60%削減|ニュートンの活用事例
ニュートンは、「カラオケ パセラ」や貸切スペース「GRACE BALI」を運営する企業です。
元々問い合わせは各店舗の電話窓口で受け付けていて、FAQも店舗独自で作成したものを使用していました。これでは会社として回答の方向性が統一できないため、問い合わせ窓口の本社一元化とFAQシステムを活用したFAQの統合に取り組みました。
FAQシステムを活用してFAQを整備したところ、導入後1ヶ月で有人対応すべき問い合わせ件数を約60%も削減できています。問い合わせ窓口を一元化する際に人員を大幅に減らしたものの、運営に支障は出ていません。
▼事例詳細はこちら
問い合わせ削減も、CX改善も実現できるFAQシステム
Helpfeelは画期的な検索技術と圧倒的な検索スピードを備えたFAQシステムです。
ユーザーの不明点や課題をスピーディかつ的確に答えへと導き、個別に寄せられる問い合せを削減し、CX(カスタマーエクスペリエンス)を改善します。
すでに業界のリーディングカンパニー含め800サイト以上で採用されており、顧客向け・社内向け・コールセンター向けなど幅広くご利用されています。
▼検索型FAQシステム「Helpfeel」の活用方法や利用事例はこちら
①独自技術で圧倒的な検索ヒット率と検索スピード
Helpfeelは「どんな表現で検索してもすぐに見つかる」を実現します。
FAQに寄せられる質問1つに対して表現パターンを50倍以上に拡張し、漢字とひらがなの違い、送り仮名の違い、スペルミスや、感情的、抽象的な表現などのパターンに対応します。

検索結果の表示スピードにもこだわり、従来のFAQに比べ1,000倍速い高速応答を実現し、ユーザーの欲しい回答を瞬時にお届けできます。
②AI搭載で検索も作成も分析も効率的に
Helpfeelは検索機能の調節や、FAQのドラフト作成、FAQサイトの利用分析に生成AIの技術を活用しています。
信頼性の必要な部分には人の手を介する仕組みを備えているため、間違った情報を伝える心配はありません。金融、医療、行政など、情報の正確性が求められる業界でも安心してご利用頂いています。

③導入〜運用〜改善まで支える充実の伴走支援
システム導入する際はHelpfeelで専門チームを立ち上げ、スピーディーな作成・移行を実行します。
導入して終わりではなく、定例会にてレポート分析と目標達成までの改善策をご提案し、継続的な改善を通じて使いやすい・お客様の目標達成につながるFAQを実現します。

「問い合わせ数が多くて困っている」「FAQの運用に課題がある」「既存FAQに大きな不満はないが見比べたい」という方は、ぜひ一度Helpfeelのサービス資料をご覧ください。





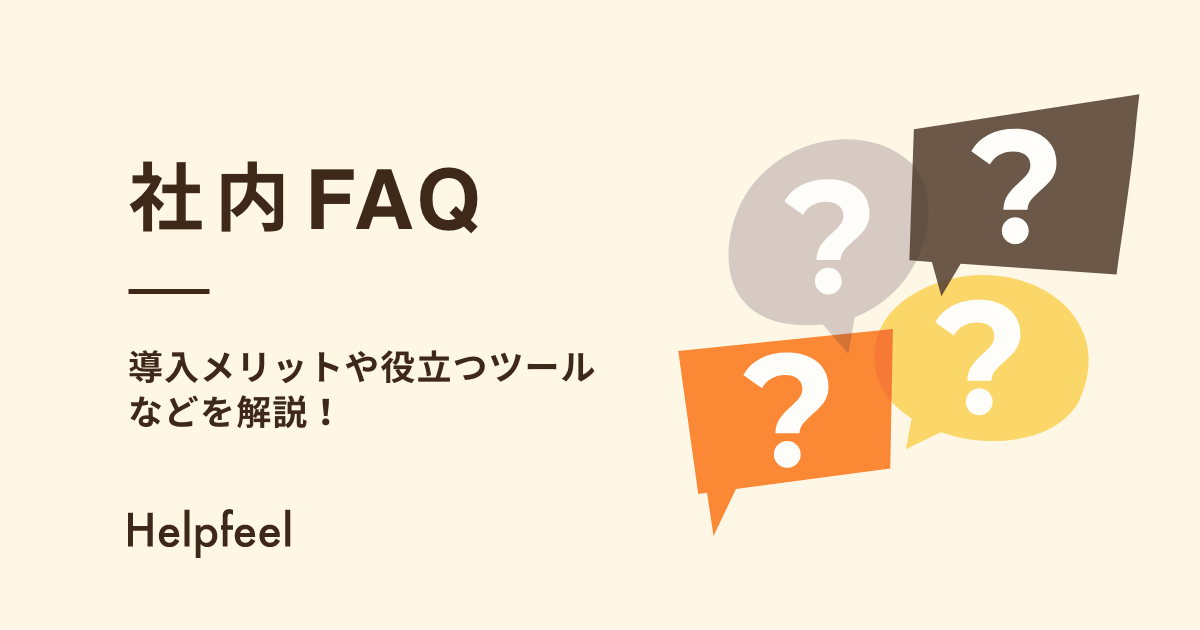


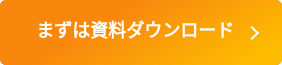










.png)