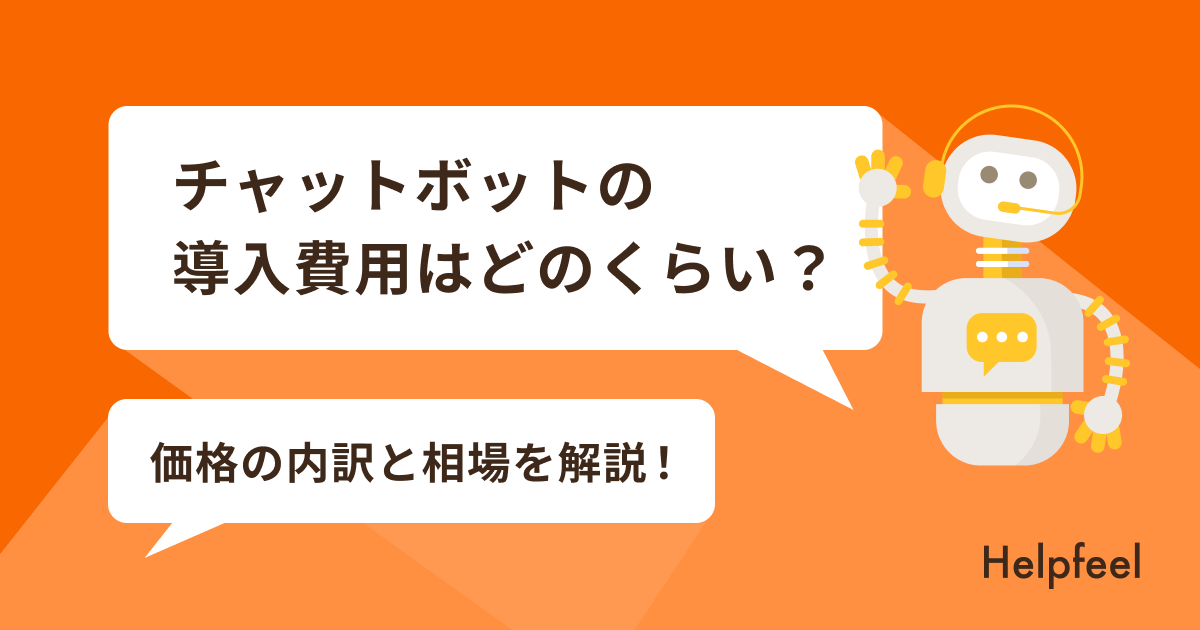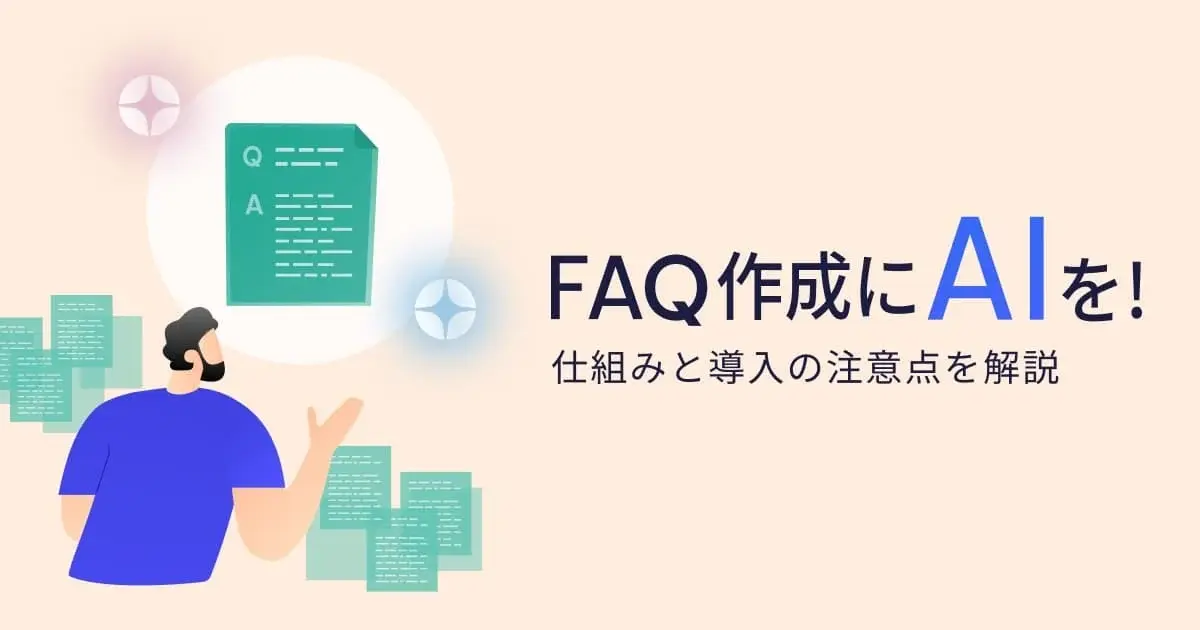▼本記事に関連したFAQ運用のお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。
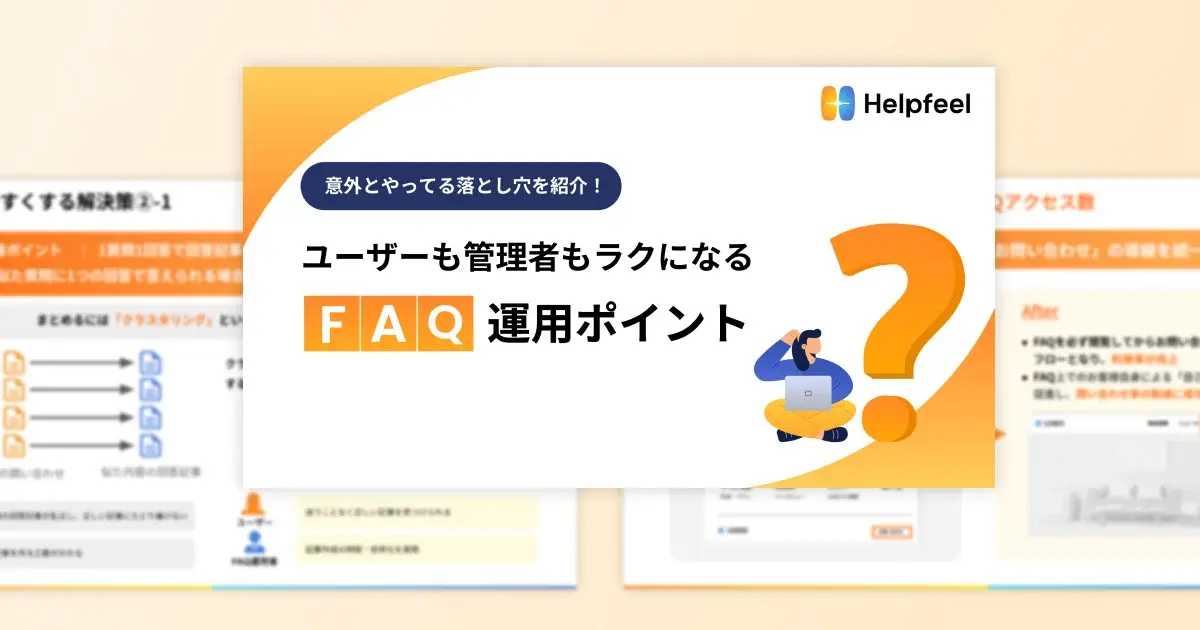
Q&A(FAQ)テンプレートとは、想定される問い合わせに対する回答のこと
 「Q&Aテンプレート」とは、よくある質問とその回答をあらかじめ整理・記載するフォーマットのことです。まずはFAQとの違いや、マニュアルとの使い分けを理解しましょう。
「Q&Aテンプレート」とは、よくある質問とその回答をあらかじめ整理・記載するフォーマットのことです。まずはFAQとの違いや、マニュアルとの使い分けを理解しましょう。
Q&AとFAQの違い
「Q&A(質問と回答)」と「FAQ(よくある質問)」とは似た言葉ですが、以下の違いがあります。
|
特定の質問に対して順番に回答する形式。社内外問わず幅広く使われ、発信者視点で構成される。 |
|
「よくある質問集」としてユーザーが自力で問題を解決できる構成。ユーザー視点で「困りごとに対する解決策」を提示する。 |
Q&Aは「想定される質問とその返答」をあらかじめ並べるスタイルであるのに対して、FAQはユーザー視点で「困りごとに対する解決策」を提供します。
目的や読み手によって、どちらの形式を採用するかを選ぶことが重要です。テンプレートを作る際には、この違いを理解した上で構成しましょう。
▼あわせて読みたい
マニュアルとQ&Aテンプレートの違い
マニュアルと「Q&Aテンプレート」はどちらも情報提供の手段ですが、下記のように役割と構造が大きく異なります。
|
業務や操作の手順を体系的かつ網羅的に説明する文書のこと。ゼロから順に読み進める構成。 |
|
特定の質問とその答えにフォーカスした構成。読者が必要な情報に短時間でアクセスしやすい点が特徴。 |
業務手順全体を理解してもらうにはマニュアルが適しており、問い合わせ対応の効率化や自己解決の促進にはQ&Aテンプレートが有効です。用途や目的に応じて、両者を使い分けてください。
▼あわせて読みたい
Q&Aテンプレート活用のメリット
Q&Aテンプレートを活用することで、FAQ作成や顧客対応の効率化が図れます。情報の整理や回答内容の統一がしやすくなるだけでなく、担当者ごとの対応のばらつきを防ぐことで、ユーザー体験の質も安定するでしょう。
ここでは、テンプレートを使うことで得られる具体的な3つのメリットについて解説します。
実際にどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
回答の統一化で一貫性のある応対と質の平準化が可能になる
Q&Aテンプレートを活用することで、質問に対する回答の統一化を図ることができます。これにより、一貫性のある応対と回答の質の平準化が実現します。
特に、ユーザーからの問い合わせに対応するオペレーターにとって、ブレない情報提供ができる点は大きなメリットといえるでしょう。
読みやすいFAQを短い時間で作成できる
読みやすいFAQを短時間で作成できるのも、Q&Aテンプレート活用のメリットです。あらかじめ用意された質問と回答のテンプレートを用いれば、予備知識やスキルが不要になるため、誰でも一定の品質を保ったFAQを作成できます。
さらに、業界ごとにカスタマイズされたQ&Aテンプレートを使うことで、より回答の精度は高まるでしょう。
回答の手間が省けるため生産性向上につながる
Q&Aテンプレートを使用してFAQを作成することで、よくある問い合わせに対する個別対応の件数を減らすことができます。
対応業務の負担が軽減できることで、他の業務に集中したり、リソースを割いたりできるので、結果としてチーム全体の生産性向上につながるでしょう。
Q&AテンプレートによるFAQの作成方法
Q&Aテンプレートを使ってFAQを作成する方法には、さまざまな手段があります。
|
ここでは代表的な3つの作成方法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
表計算ソフト(Excel・スプレッドシートなど)
Q&Aテンプレートは、Excelやスプレッドシートなどの表計算ソフトを使って作成することが可能です。ウェブ上で無料で公開されているQ&Aテンプレートもあります。表計算ソフトを活用することで、問い合わせに対応できる基本的な質問と回答を容易に作ることが可能です。
通常業務で使っている表計算ソフトをベースにすれば、操作に慣れているため扱いやすく、有料のシステムを導入するのに比べてコストを抑えられるというメリットもあります。
その反面、検索性に乏しかったり、情報量が増えるにつれて動きが重くなったりするデメリットがあるため注意が必要です。また、表計算ソフトのFAQは、社外のユーザー向けに展開するには不向きといえます。
▼あわせて読みたい
チャットボット
チャットボットは、AIを活用した自動会話用プログラムです。専用のシステムを活用すれば、あらかじめ作成用テンプレートが用意されているものも多いため、比較的簡単に作成することが可能です。
ただし、チャットボットは、導入・運用に手間や時間がかかる点や、全ての質問に対応できるわけではない点がデメリットです。用途や対応範囲を明確にした上での活用が求められます。
▼あわせて読みたい
FAQシステム
FAQを作成するには、専用のFAQシステムを使うと便利です。FAQシステムは、Q&AやFAQの作成・運用に特化して設計されているため、簡単に使いやすいFAQを作成することが可能です。
「Helpfeel」のように生成AIを活用し、メールやメモ書きのほか、PDFからFAQのドラフト(草案)を使って社内FAQを作成できるシステムもあります。
導入に一定の費用は必要となるものの、検索性の高いFAQを作ることができるのは、ユーザーや問い合わせ対応を行うオペレーターにとって大きなメリットといえるでしょう。
▼あわせて読みたい
【業種別】Q&Aテンプレートのサンプル事例

業種によって「よくある質問」は異なります。ここでは飲食・小売・不動産などさまざまな業界別に、実際の現場で役立つQ&Aテンプレートの具体例を8つ紹介します。
飲食店
| Q | 予約をキャンセルする場合、キャンセル料はかかりますか? |
| A | キャンセルは〇日前まで無料、それ以降はキャンセル料が発生します。 |
| Q | アレルギー対応メニューはありますか? |
| A | 一部アレルギー対応メニューをご用意しています。詳細は、スタッフにお尋ねください。 |
| Q | テイクアウトは可能ですか? |
| A | 一部のメニューはテイクアウトに対応しています。対象商品は店舗スタッフにご確認ください。 |
飲食店では、来店前の確認事項に関する質問が多く、テンプレートでよくある質問を整理しておくと、接客効率が向上します。アレルギー対応やキャンセル条件など、事前に明示することで顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
小売店
| Q | 返品や交換はできますか? |
| A | 商品到着後7日以内、未使用品に限り対応いたします。レシートをご提示ください。 |
| Q | ギフトラッピングは可能ですか? |
| A | 店頭・オンラインともに対応しています。(有料/無料の選択可) |
| Q | ポイントはいつ付与されますか? |
| A | 商品購入後、2〜3日以内に自動で付与されます。 |
小売店では、購入後の対応に関する質問が中心です。返品・ポイント・ラッピングなど、Q&Aを明文化しておくことで、スタッフの回答も統一され、顧客への案内もスムーズになります。
サービス業
| Q | 事前予約は必要ですか? |
| A | 当日受付も可能ですが、事前予約をおすすめしています。 |
| Q | 所要時間はどのくらいですか? |
| A | メニューによって異なりますが、平均30〜60分程度です。 |
| Q | キャンセル料はかかりますか? |
| A | ご予約前日までは無料、当日のキャンセルは料金の50%を頂戴します。 |
美容院やクリーニングなどのサービス業では、予約・時間・料金に関する事前質問が多く見られます。テンプレートを整備しておくことで、電話対応の時間削減や、顧客とのトラブル防止にも効果的です。
金融業
| Q | 口座開設に必要な書類は何ですか? |
| A | 本人確認書類(運転免許証など)とマイナンバーが必要です。 |
| Q | キャッシュカードはいつ届きますか? |
| A | 口座開設から5営業日ほどで発送いたします。 |
| Q | ネットバンキングの登録方法は? |
| A | 専用サイトよりログインし、初回登録を行ってください。詳しい手順は別紙に記載しています。 |
金融業では、制度や手続きに関する質問が中心です。テンプレートを整えることで、複雑な業務内容を誰が対応しても一定レベルで案内でき、顧客対応の均質化に役立ちます。
IT企業
| Q | ログインできない場合はどうすればいいですか? |
| A | パスワードを再設定してください。それでも解決しない場合はサポートまでご連絡ください。 |
| Q | アップデートのタイミングは決まっていますか? |
| A | 毎月第2火曜日に自動アップデートを実施しています。 |
| Q | APIの利用制限はありますか? |
| A | プランにより制限があります。詳細は開発者向けドキュメントをご確認ください。 |
IT企業では、トラブル対応や技術的な設定に関する質問が多く寄せられます。Q&Aテンプレートに、操作ガイドや開発資料のリンクを併記することで、自己解決率が高まり、問い合わせ対応の効率化につながるでしょう。
不動産会社
| Q | 初期費用には何が含まれますか? |
| A | 敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などが含まれます。 |
| Q | ペット可の物件はありますか? |
| A | はい、ございます。地域や条件により異なるため、担当までご相談ください。 |
| Q | 物件の内見は可能ですか? |
| A | 事前予約制でご案内しています。希望日時をお知らせください。 |
不動産業では、物件内容や契約条件に関する質問が多く、事前にテンプレートで情報を整理しておくことで、問い合わせ対応のスピードと正確性が向上します。FAQとして公開すれば、検討者の自己解決も期待できるでしょう。
通販サイト
| Q | 配送にはどれくらいかかりますか? |
| A | 通常、注文から2〜5営業日でお届けします。 |
| Q | Q:注文内容の変更は可能ですか? |
| A | 発送前であれば変更可能です。マイページから申請をお願いします。 |
| Q | Q:ギフト用の包装はありますか? |
| A | 有料でギフト包装をご用意しています。注文時にオプションを選択してください。 |
通販サイトでは、注文・配送・アフターサポートまで幅広い質問が発生します。Q&Aテンプレートを工程別に整理することで、カスタマーサポートの品質とスピードが安定するでしょう。
社内向け
| Q | 経費精算はどのように提出すればよいですか? |
| A | 毎月20日までに専用フォームに入力の上、領収書を添付してください。 |
| Q | 社用パソコンの不具合はどこに連絡すればよいですか? |
| A | 情報システム部(内線:1234)までご連絡ください。 |
| Q | テレワーク申請の方法は? |
| A | 勤怠システムで「在宅勤務」を選択し、上長承認を得てください。 |
社内FAQでは、情報システムや総務などへの問い合わせが集中する傾向があります。よくある質問をテンプレートで整備しておくことで、自己解決が促進され、管理部門の業務負担を大幅に軽減できるでしょう。
▼さらに詳しく実践的に待つようできる「FAQ回答テンプレート」をご用意しました。併せてご活用ください。
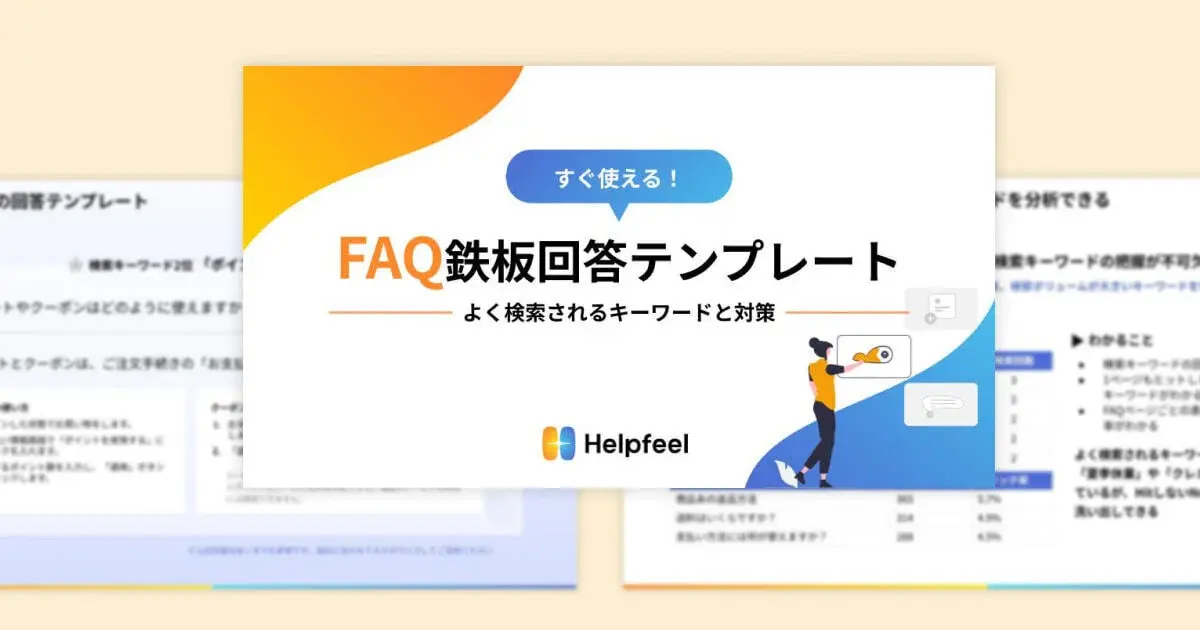
Q&Aテンプレートの作成手順5ステップ

Q&Aテンプレートは、やみくもに質問と回答を並べればよいものではありません。
|
実用的かつ継続的に使えるFAQを作成するために必要な、5つのステップを紹介します。
Step1. 目的と活用イメージを明確にする
最初に、「誰に向けて、どのような目的でQ&Aテンプレートを作成するのか」を明確にすることが重要です。例えば、顧客対応を効率化したいのか、社内の問い合わせを減らしたいのかによって、テンプレートの内容や表現が大きく変わります。
また、ウェブ上で公開するのか、社内で共有するのかといった活用シーンによって、適切なフォーマットや回答の深さが異なります。最初にゴールを定めておくことで、後工程の作業がブレずに進められ、実務に即したFAQを作成できるでしょう。
Step2. よくある質問を洗い出す
目的が定まったら、次に取り組むのは「よくある質問(FAQ)」の洗い出しです。
現場で実際に寄せられる問い合わせや、サポート担当者が頻繁に対応している内容を中心に収集しましょう。具体的には以下が挙げられます。
|
この段階では、量を気にせず、なるべく多くの質問を出すことがポイントです。
▼あわせて読みたい
Step3. 質問内容を分類・整理する
洗い出した質問をそのまま掲載すると、FAQが煩雑になってしまいます。そのため、それらの質問をテーマごとに分類・整理する作業を行います。
例えば、「注文」「配送」「返品」などカテゴリーに分けることで、閲覧者が必要な情報にたどり着きやすくなるでしょう。また、質問の表現を簡潔かつ統一感のあるものに見直すことも大切です。分類と整理を丁寧に行うことで、読みやすさと検索性の高いFAQに近づけられます。
Step4. 回答方針と運用ルールを決める
質問を整理した後は、どのようなトーンや情報レベルで回答するかといった「回答方針」を統一しましょう。具体的には、下記の3つが考えられます。
|
上記のように、ルールを明確にしておくことで、複数人で作成してもブレが生じません。
また、FAQの更新頻度や責任者を定めておくことも重要です。運用ルールが曖昧だと、情報の陳腐化や重複が発生しやすくなるため、初期段階から整備しておくと長期的に活用しやすくなります。
Step5. テンプレートを作成して共有する
最後に、決定した質問と回答をもとにQ&Aテンプレートを作成します。業務フローやチームの運用方針に合わせて、扱いやすい形式で整備することで、社内共有や管理がスムーズになります。
また、表形式やカテゴリー別レイアウトを活用すれば、UIを考慮した見やすさや検索性の向上にも効果的です。作成後は、共有フォルダなど対象者がアクセスしやすい場所に保存し、共有・活用を促すことが重要です。
必要に応じてフィードバックをもらい、定期的に改善を加えていく運用体制も整えておきましょう。
▼あわせて読みたい
テンプレートでFAQを作成する際のポイント
Q&Aテンプレートを活用するだけでは、使いやすいFAQは完成しません。より実用的で効果的なFAQにするためには、表現や構成、運用面での工夫が必要です。
ここでは、以下の4つのポイントを解説します。
質問や回答をわかりやすい表現にする
質問や回答は、読み手の理解を前提にした、簡潔かつ具体的な表現を心がけましょう。社外向けのFAQであれば顧客に、社内向けのFAQであれば従業員や問い合わせ対応を行うオペレーターに、伝わりやすいものを作成することが大切です。
専門用語を多用した冗長な表現や、何度読み返しても要領を得ない回答は、利用する側に対して不便な印象を与え、FAQの利用をあきらめてしまう可能性があります。
優先度順に並べる
Q&AテンプレートによるFAQは、優先度に応じて質問と回答を上から順に並べるようにしましょう。具体的には、製品・サービスに関する基本的な内容や、よくあるトラブルへの対処法などが、優先度の高い質問と回答に挙げられます。
優先度の高い質問が上部に表示されることで、検索しなくても目当ての質問と回答を見つけやすくなるからです。
検索性向上のため、キーワードを盛り込む
質問や回答文には、検索されやすいキーワードを盛り込みましょう。例えば、俗称や略語など利用者が実際に使う言葉や、検索ログから抽出したワードなどが挙げられます。
検索されやすいキーワードを含めておくことで自己解決率が高くなり、従業員の利便性が大きく向上するでしょう。
定期的に更新する
Q&Aテンプレートで作成したFAQは定期的に更新し、内容の見直しを図るようにしてください。古い情報を放置していると誤った回答に結び付き、従業員の効率を下げたり、オペレーターの手間を増やしてしまったりするリスクがあるのが理由です。
更新ルール(例:月1回/四半期ごと)を明確に定め、担当者が責任を持って管理する体制を整えましょう。
▼ユーザーの自己解決を促進する、今すぐ使えるFAQ回答テンプレートをまとめた資料もご用意しています。ぜひあわせてご活用ください。
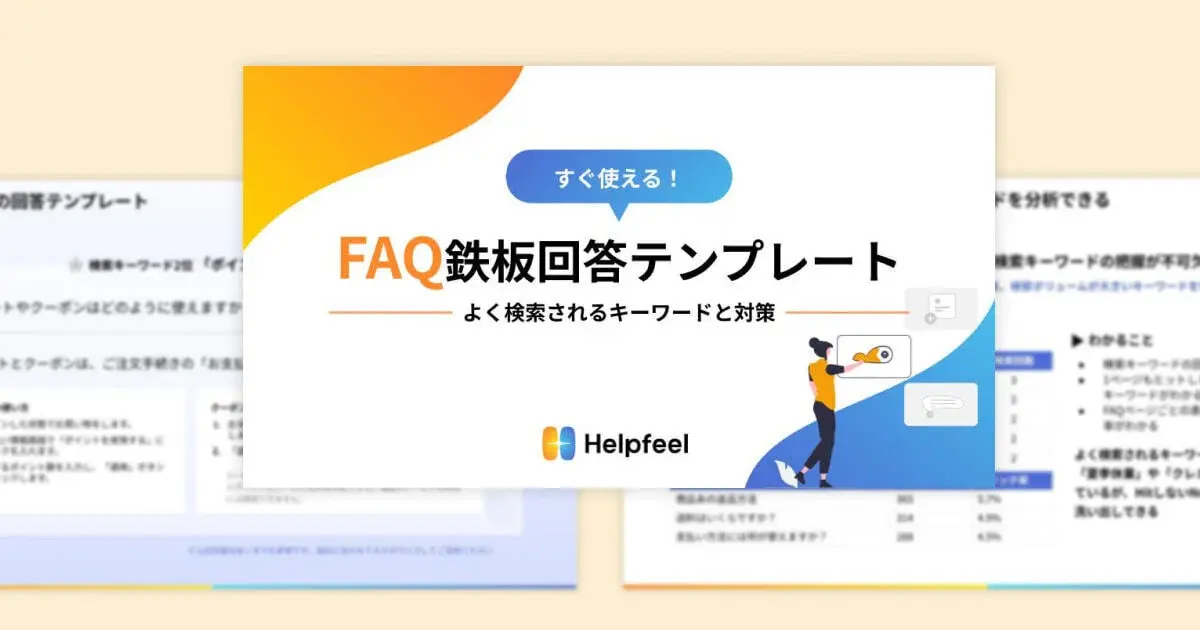
テンプレート活用でFAQの使いやすさを最大化しよう
Q&Aテンプレートは、問い合わせに対する回答を定型化したもので、一貫性のある対応や回答品質の平準化を実現できます。結果として、業務効率化や生産性向上に大きく貢献するでしょう。
Excelや自社開発してサイトに実装することも可能ですが、社内外両方のニーズに対応する高品質なFAQを効率的に作成するなら、FAQシステムが最適です。
例えば、導入実績800サイト以上の検索型FAQシステム「Helpfeel」を利用することで、生成AIを活用した独自の特許技術「意図予測検索」が可能になったり、VoC分析機能によって行動を調査しやすくなったりします。
「Helpfeel」を導入して、ユーザーの満足度向上につながるFAQを構築してみてはいかがでしょうか。
問い合わせ削減も、CX改善も実現できるFAQシステム
Helpfeelは画期的な検索技術と圧倒的な検索スピードを備えたFAQシステムです。
ユーザーの不明点や課題をスピーディかつ的確に答えへと導き、個別に寄せられる問い合せを削減し、CX(カスタマーエクスペリエンス)を改善します。
すでに業界のリーディングカンパニー含め800サイト以上で採用されており、顧客向け・社内向け・コールセンター向けなど幅広くご利用されています。
▼検索型FAQシステム「Helpfeel」の活用方法や利用事例はこちら
①独自技術で圧倒的な検索ヒット率と検索スピード
Helpfeelは「どんな表現で検索してもすぐに見つかる」を実現します。
FAQに寄せられる質問1つに対して表現パターンを50倍以上に拡張し、漢字とひらがなの違い、送り仮名の違い、スペルミスや、感情的、抽象的な表現などのパターンに対応します。

検索結果の表示スピードにもこだわり、従来のFAQに比べ1,000倍速い高速応答を実現し、ユーザーの欲しい回答を瞬時にお届けできます。
②AI搭載で検索も作成も分析も効率的に
Helpfeelは検索機能の調節や、FAQのドラフト作成、FAQサイトの利用分析に生成AIの技術を活用しています。
信頼性の必要な部分には人の手を介する仕組みを備えているため、間違った情報を伝える心配はありません。金融、医療、行政など、情報の正確性が求められる業界でも安心してご利用頂いています。

③導入〜運用〜改善まで支える充実の伴走支援
システム導入する際はHelpfeelで専門チームを立ち上げ、スピーディーな作成・移行を実行します。
導入して終わりではなく、定例会にてレポート分析と目標達成までの改善策をご提案し、継続的な改善を通じて使いやすい・お客様の目標達成につながるFAQを実現します。

「問い合わせ数が多くて困っている」「FAQの運用に課題がある」「既存FAQに大きな不満はないが見比べたい」という方は、ぜひ一度Helpfeelのサービス資料をご覧ください。






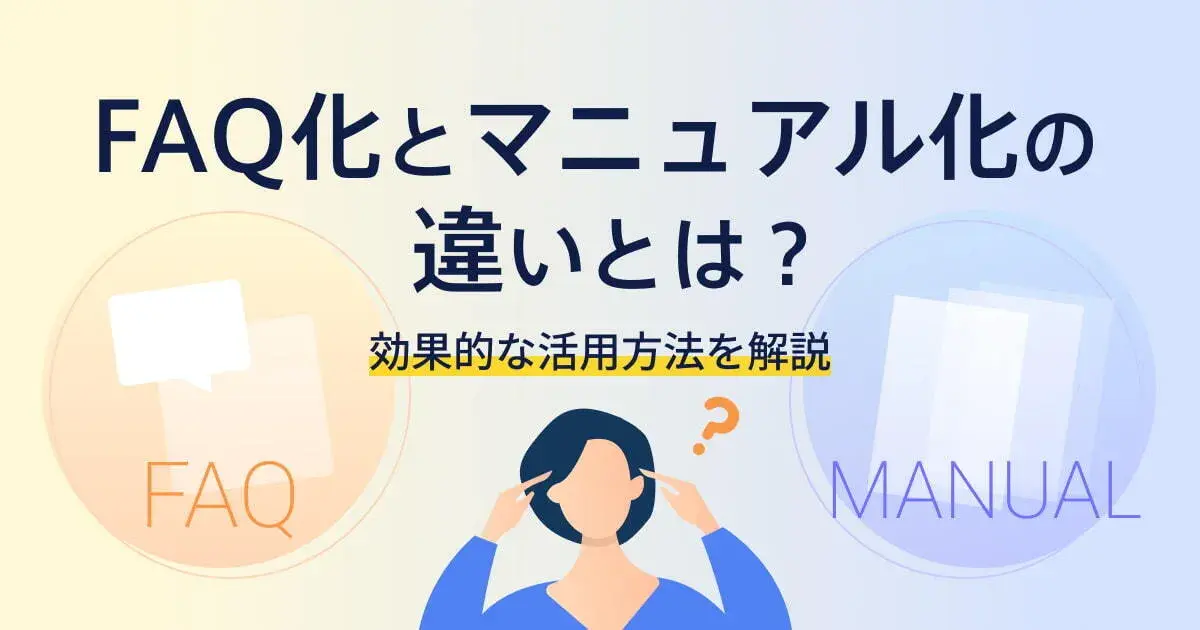






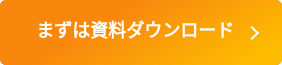





.png)