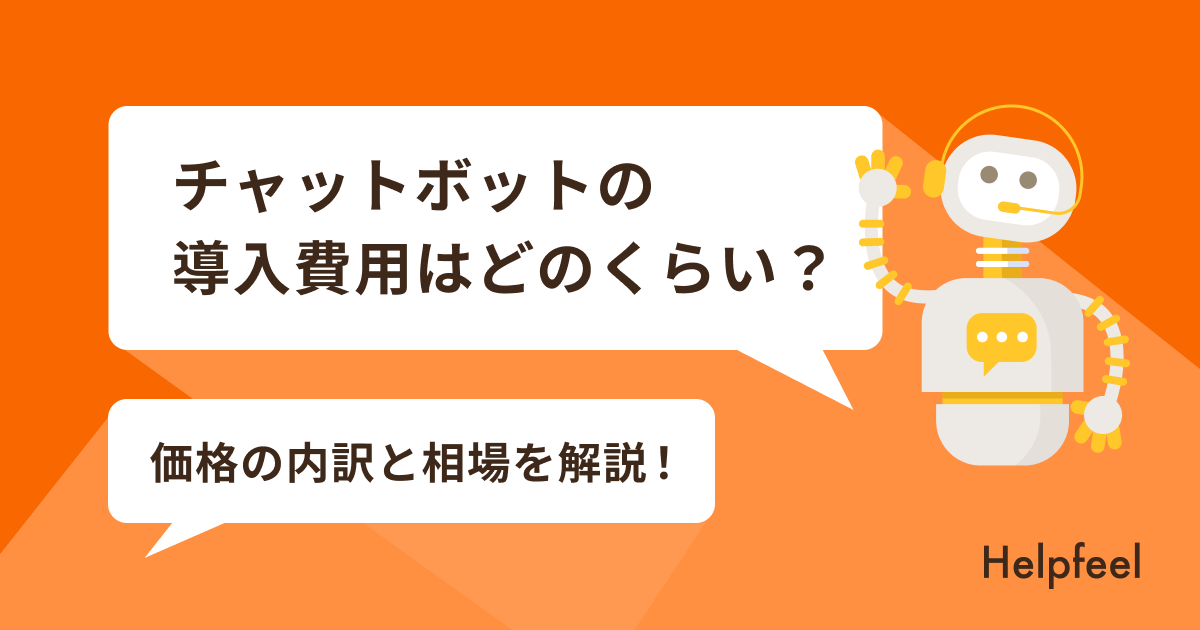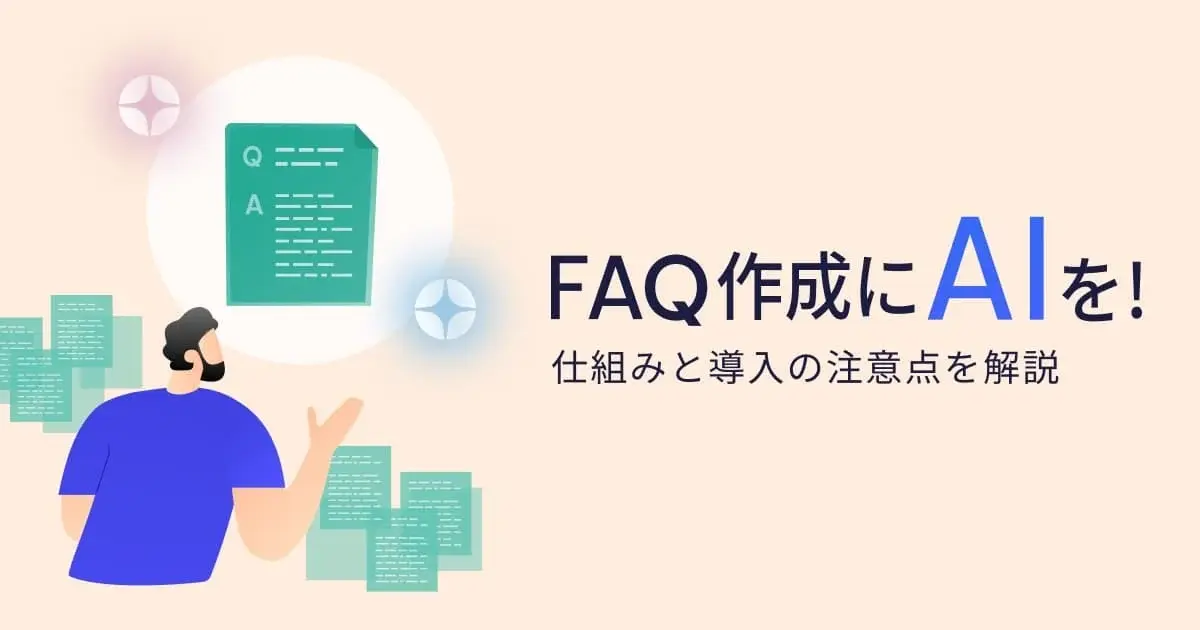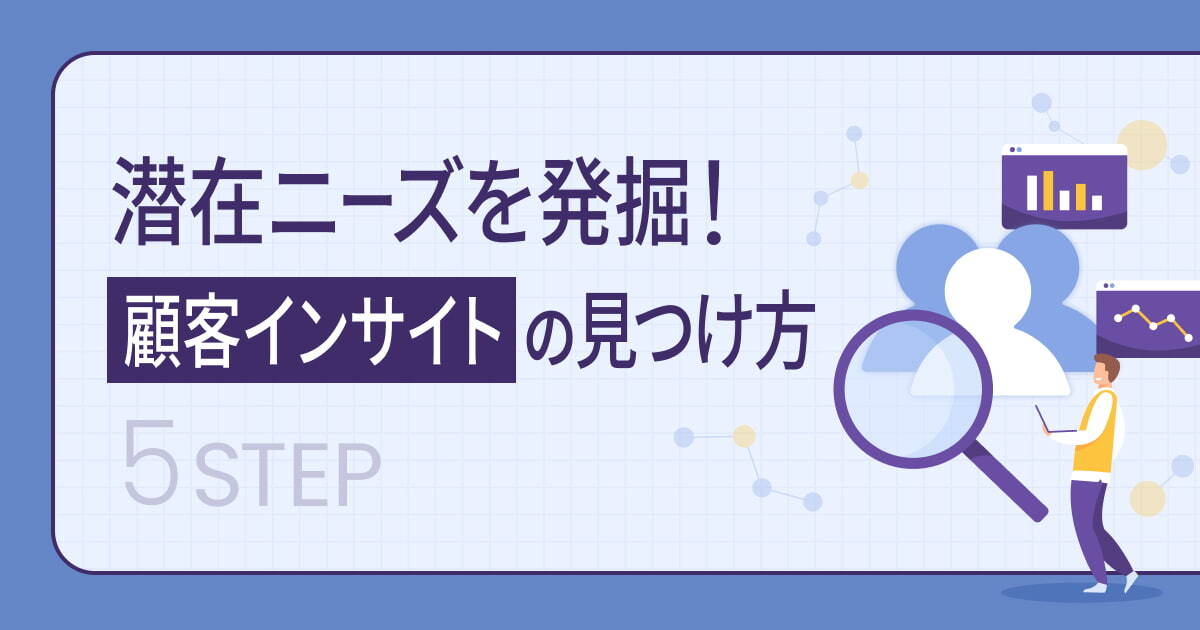離脱率の改善が必要な理由

離脱率の改善は、単なる数値改善ではなく売上や顧客獲得に直結する重要な施策です。特に注目すべきは「問い合わせページ」と「カートページ」です。
コーポレートサイトやサービスサイト、BtoBサイトで問い合わせページでの離脱が多いと、せっかく獲得した見込み客を逃してしまいます。フォームの入力項目が多い、デザインが使いにくい、信頼性が伝わらないなどの理由があると、ユーザーは離脱し、結果的に商談の機会を失うことがあるでしょう。
一方で、ECサイトでは、カートページの離脱率が直接売上に影響します。送料や手数料の表示が不明確、決済方法の選択肢が少ない、購入フローが複雑といった要因が「カゴ落ち」を引き起こします。改善できなければ、広告や集客で増やしたアクセスが利益につながらず、投資効率も低下してしまいます。
このように、離脱率の改善はコンバージョン率の向上だけでなく、集客コストの最適化や収益最大化に欠かせない課題と言えます。
▼EC業界に関わる方必見のお役立ち資料もご用意しておりますので、併せてご覧ください。
.webp)
離脱率の計算方法と目安

サイトのページ改善の指標として離脱率を利用する場合は、正確な計算方法と目安を理解しておく必要があります。
ここでは、以下の3点を解説します。
|
自社のサイトの状態を適切に把握するためにも、それぞれのポイントを理解しておきましょう。
離脱率の計算方法
離脱率の計算方法は、以下の通りです。
|
離脱数とは、そのページがセッション内で最後に閲覧された回数を示します。つまり、「訪問してからサイト内で最後に開いたページ」が当該ページであった場合にカウントされます。
逆に、当該ページからサイト内の別のページへ遷移した場合は、離脱数にカウントされません。離脱率は、「サイトから離れたユーザーの割合」を示すための指標です。なお、離脱率の測定を行う場合は、アクセス解析ツールを使うと便利です。
直帰率・回遊率との違い
直帰率と回遊率は、離脱率と並んでサイト改善に欠かせない指標です。
|
ユーザーが最初に訪れたページだけを見てサイトを離れてしまった割合 |
|
1回の訪問(セッション)で平均して何ページ見られたかを示す数字 |
直帰率が高ければ、最初のページで興味を失った可能性があります。回遊率が低ければ導線がわかりにくく、目的の情報にたどり着けなかった可能性があるでしょう。
直帰率・回遊率・離脱率の3つを組み合わせて分析することで、問題点をより正確に見つけられます。それぞれの数値を改善できれば、ユーザーにとって満足度の高いサイトづくりにつながります。
離脱率の目安
離脱率には、全てのサイトに適用できる基準となる目安は存在しません。サイトによってコンテンツが異なり、ユーザーの性質も違うため、離脱率の目安を定めるのが難しいためです。
離脱率を判断するポイントをまとめました。
|
離脱率85%程度が許容範囲。 それ以上なら改善の余地あり |
|
離脱率が高くても自然なため問題ない |
|
離脱が売上の機会損失に直結するため改善が必須 |
重要なのは、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを使って離脱率を定期的にモニタリングすることです。単純に数値の高さだけを見るのではなく、ページの性質と過去の推移を比較することで、本当に改善すべき箇所を特定できます。
離脱率の数字を「目安」として捉えつつ、継続的にチェックすることが、リテンション(維持)率を高め、精度の高いサイト改善へとつながります。
▼あわせて読みたい
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意しています。ぜひ併せてご覧ください。

離脱率が高くなる4つの原因

離脱率が高くなる4つの原因は、以下の通りです。
離脱率がなぜ高くなるのか原因を特定できれば、改善策の検討が可能です。それぞれについて詳しく解説します。
ユーザーのニーズに応えられていない
サイト内のコンテンツがユーザーのニーズに応えられていなければ、離脱率が高くなってしまいます。ユーザーが、自身の求める情報を得られないと判断して、別のサイトを検索する行動に移るためです。
ターゲット設定やキーワード選定が曖昧な状態では、検索意図とサイトのコンテンツにズレが生じ、ユーザーのニーズに応えられません。
ユーザーは、検索エンジンで表示されるタイトルやディスクリプションからサイトの内容を把握します。検索意図を意識してタイトルやディスクリプションを作成しなければ、ユーザーのニーズに応えられず、離脱数が増加するでしょう。
▼あわせて読みたい
サイトのデザインが使いにくい
サイトのデザインや使いやすさに問題があると、ユーザーはストレスを感じて離脱してしまいます。サイトのデザインが使いにくい具体例を、以下にまとめました。
|
特にスマートフォン閲覧時の不具合(文字が小さい、レイアウト崩れなど)は大きな離脱要因です。ユーザーが快適に利用できるデザインを意識しましょう。
▼あわせて読みたい
ページの表示速度が遅い
ページの表示速度が遅いと、ユーザーがページを離れやすくなります。ページの表示に3秒以上かかると離脱率が急激に高まると言われています。
ページの表示速度が遅い原因は、以下の通りです。
|
サイトが保有するデータ量が多いケースだけではなく、サーバーやコードに問題が生じているケースもあります。サイトやサーバーの現状をチェックして原因を探り出し、適切に対処して問題を解消しましょう。
訴求が強すぎる
サイトの訴求が強すぎると、ユーザーに悪印象を与えて離脱させるケースがあります。訴求の強いサイトは怪しいと判断するユーザーが多いからです。
例えば、「誰でも絶対に成功する」など根拠のない断定的な表現を多用すると、ユーザーに不信感を与えます。また、ページ内に広告が大量に貼られている場合は、ユーザーを不快にさせやすい傾向があります。
訴求が強すぎるサイトは、ユーザーが離脱するだけではなく、検索エンジンからの評価も下がります。過剰な表現や過大広告などを続けると、企業としての信頼も失うでしょう。自然な文脈の中で適度に訴求を行うことで、ユーザーに安心感を与えることができます。
▼本記事に関連したお役立ち資料をご用意しておりますので、あわせてご覧ください。
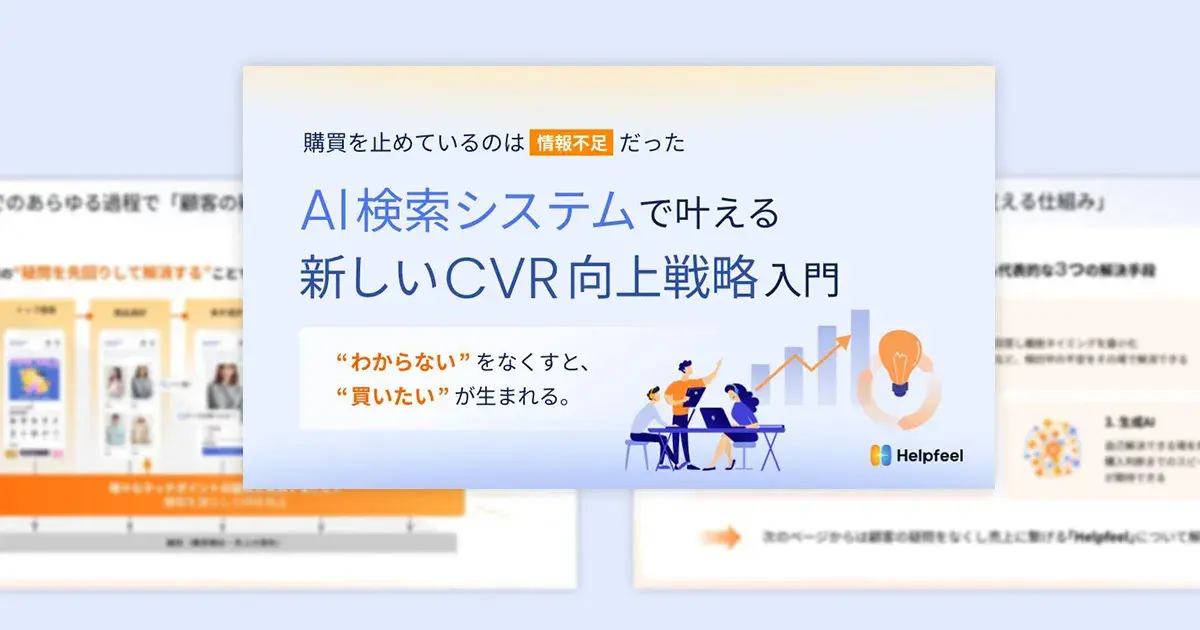
離脱率を改善する7つの方法

離脱率を改善しようと考えたときに、何からはじめればいいのかわからないこともあるでしょう。離脱率を改善するために効果的な7つの方法をまとめました。
|
それぞれの方法を、詳しく紹介します。
内容が検索意図に合っているか確認する
離脱率を改善するには、サイトのコンテンツがユーザーの探しているものに合っているか確認しましょう。ユーザーが求める情報とサイトの内容が微妙にズレているだけでも、離脱の原因になります。
特に、タイトルや見出しと本文の内容の不一致に注意してください。ユーザーが期待する内容とページの記載が異なっていると、離脱につながります。
具体的には、検索エンジンから流入したユーザーの「検索していたキーワード」を調査することが大切です。キーワードから検索意図を読み取り、コンテンツの内容を調整しましょう。
ユーザーの知りたい情報や解決したい課題を網羅できれば、満足度が高まり、ページを読み進めてもらえる可能性が高まります。
ヒートマップを分析する
「ヒートマップ分析」をすると、ユーザーがページを訪れてから離脱するまでの行動を可視化できます。サイト内でユーザーが注目しているエリアやページ内での行動、離脱したポイントなどの把握が可能です。
可視化できる点は、主に以下の通りです。
|
ヒートマップ分析でユーザーが興味を示さなかったエリアを特定できれば、改善に役立ちます。サイト内で重点的に改善すべきエリアが明確になるので、コンテンツの内容やデザイン、レイアウトなどを改善すれば離脱率を下げられるでしょう。
入力フォームを改善する
入力フォームを最適化するとユーザーのストレスが減るため、離脱率を改善できます。
具体的な改善方法は、以下の通りです。
|
入力項目を減らしたり、ボタンの大きさを変えたりすれば、スムーズに入力作業を進められるようになります。過去の入力履歴を自動保存させて自動で反映させる機能の導入も、効果的です。
項目数を最小限に抑えて、シンプルなデザインを心がけましょう。
▼あわせて読みたい
表示速度を改善する
サイトの表示速度の改善は、離脱率を下げるのに大きな効果を期待できます。
主な改善方法は、以下の通りです。
|
定期的にサイトの表示速度を計測して、問題があればすぐに改善することが大事です。
レスポンシブに対応しているか確認する
「レスポンシブ対応」とは、PC・スマートフォン・タブレットなど、ユーザーの使うデバイスに最適化したデザインやレイアウトにすることです。
スマートフォン上ではメニューが表示されない、文字が切れるなどレイアウトが崩れるケースは珍しくありません。さまざまなデバイス上で、自社サイトが問題なく閲覧できるかチェックしましょう。
レスポンシブ対応を実現すれば、どんなデバイスを使うユーザーにも見やすいサイトを実現できます。
A/Bテストを実施する
「A/Bテスト」とはサイトや広告などで複数のパターンを準備して比較する手法です。ユーザーの反応を数字で比較できるため、改善施策を考えるのに役立ちます。
離脱率の改善では、テキストや画像、CTAなど、ページの要素を変更して影響を分析することが効果的です。分析することで、離脱率を下げるのに最適なコンテンツやデザインが、データとして明らかになります。
A/Bテストは十分な検証期間とサンプル数を確保し、目的を明確にした上で実施することが重要です。継続的に実施・分析をして次の改善に生かすサイクルを回せば、サイトのコンテンツやデザインが最適化されるでしょう。
FAQへの動線を改善する
ユーザーの離脱を防ぐのに、FAQ(よくある質問)の活用は効果的です。サイトからの離脱はなんらかの疑問が発生し、サイトのどこを見ても解決できない時に発生することもよくあります。FAQによって疑問点をすぐ解決できれば、離脱せずにサイト内にとどまってくれます。
サイト内で離脱の多い部分について、FAQを充実させてください。例えば、ユーザーが購買前に事前に気になるような「送料」や「キャンセルに関して」など、購入や契約の手続きに関する情報を充実させておくと、入力フォームからの離脱を軽減できます。
離脱の多いページから、FAQサイトへ誘導するのも方法の一つです。例えば、専門用語が使われている箇所にFAQサイトへの導線を作ることで、ユーザーは知りたい情報にすぐにアクセスでき、元のページに戻ってくれるでしょう。
▼FAQの動線改善について詳しく解説したお役立ち資料もご用意しております。併せてご確認ください。

離脱率の改善には自己解決できるFAQが効果的
 FAQによる自己解決を促せば、離脱率の改善を期待できます。現在のFAQが必要な情報が整備されているか、疑問発生したタイミングでFAQへ誘導できているかなど、利用状況を定期的に分析し、改善を繰り返せば利用率は向上するでしょう。
FAQによる自己解決を促せば、離脱率の改善を期待できます。現在のFAQが必要な情報が整備されているか、疑問発生したタイミングでFAQへ誘導できているかなど、利用状況を定期的に分析し、改善を繰り返せば利用率は向上するでしょう。
FAQを閲覧してから契約・購入ページにユーザーが戻っているのか導線分析です。FAQから元のページに戻っていない場合は、FAQの内容では解決ができなかった、元のページに戻る導線がわかりにくいなどの原因が考えられます。
FAQサイトを改善したいならば、導入実績800サイト以上の「Helpfeel」がおすすめです。自己解決を促進するAIシステムとして、疑問解決起点の新しいマーケティング手法を提案しています。購買前に疑問を感じたユーザーへ、必要なタイミングで、即座に回答を提示し、購買へ結びつけることが可能です。
FAQの検索ログや行動履歴から、ユーザーが探している情報は何かというインサイトの発見も可能です。離脱率の改善を、従来のマーケティング手法以外のアプローチで検討されている場合は、Helpfeelのサービス資料をご覧ください。
まとめ|FAQを活用して離脱率を改善しましょう
 本記事では、離脱率が高くなる原因と改善策について紹介しました。離脱率が高いと機会損失を招くため、早急な対策が必要です。改善策としては、ヒートマップ分析や表示速度の改善、FAQへの導線の整備などが効果的です。
本記事では、離脱率が高くなる原因と改善策について紹介しました。離脱率が高いと機会損失を招くため、早急な対策が必要です。改善策としては、ヒートマップ分析や表示速度の改善、FAQへの導線の整備などが効果的です。
特に、FAQは自己解決を促すことから、契約・購入ページからの離脱を防ぐのに効果的です。離脱率改善のための施策として、FAQの活用や入力フォームの改善などに取り組んでみてください。



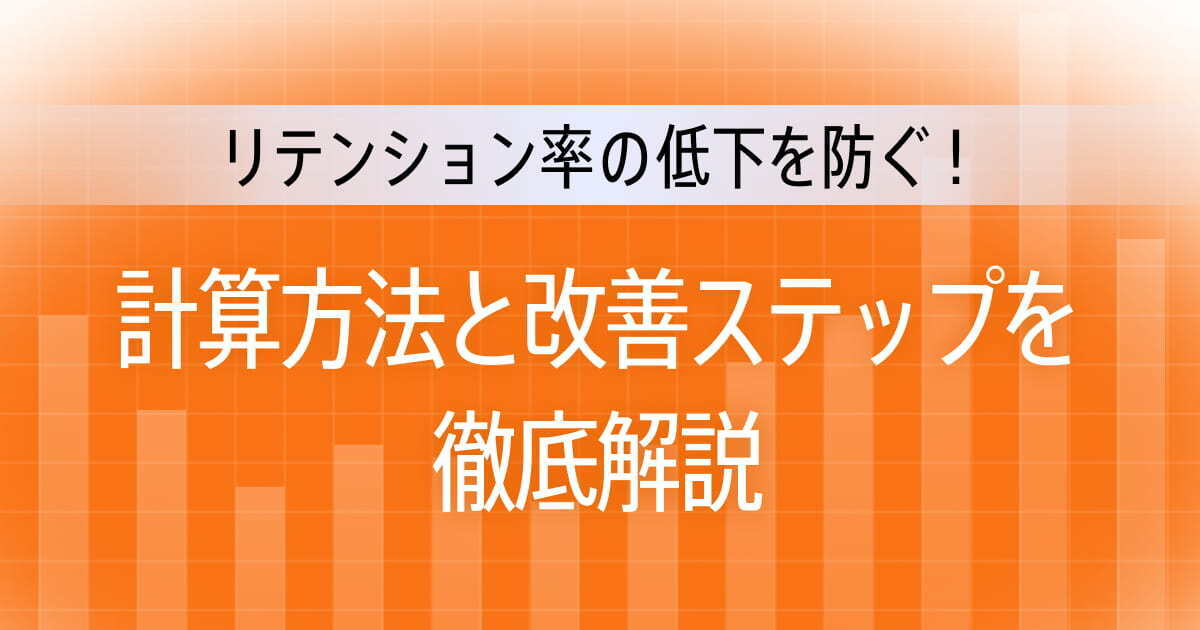


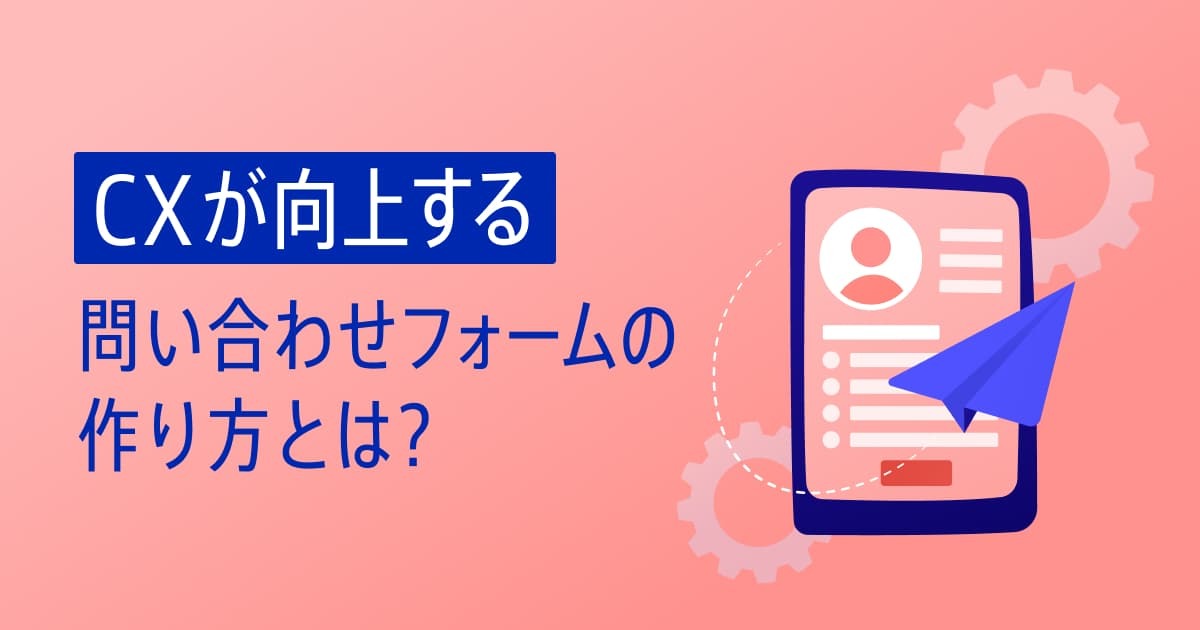

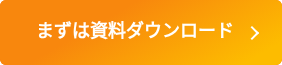



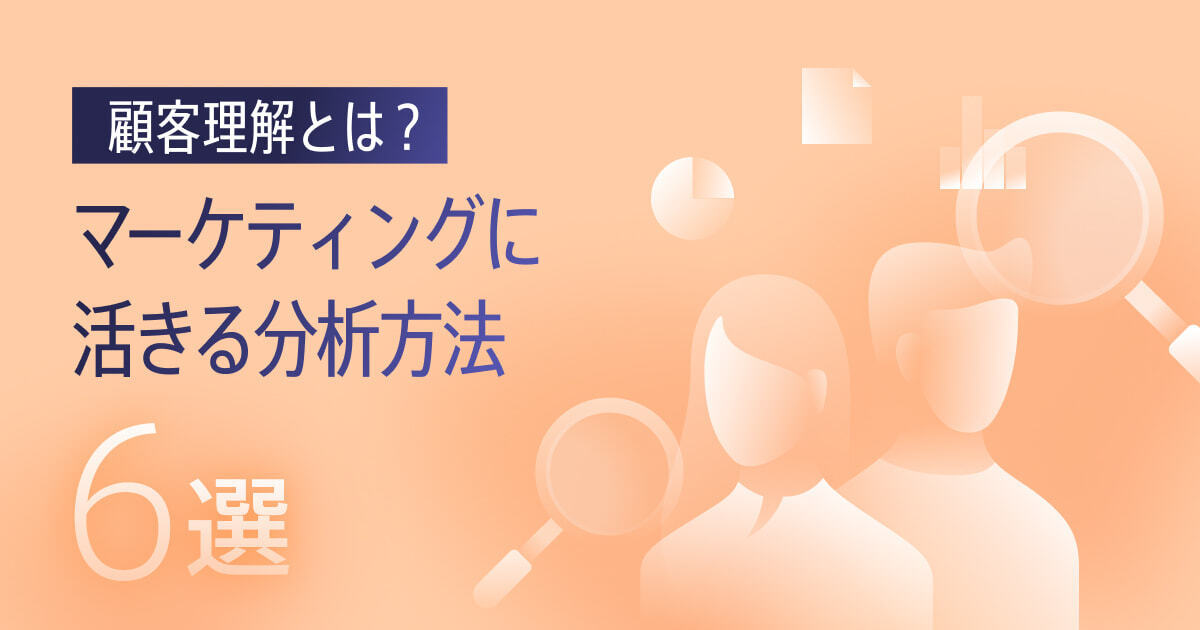
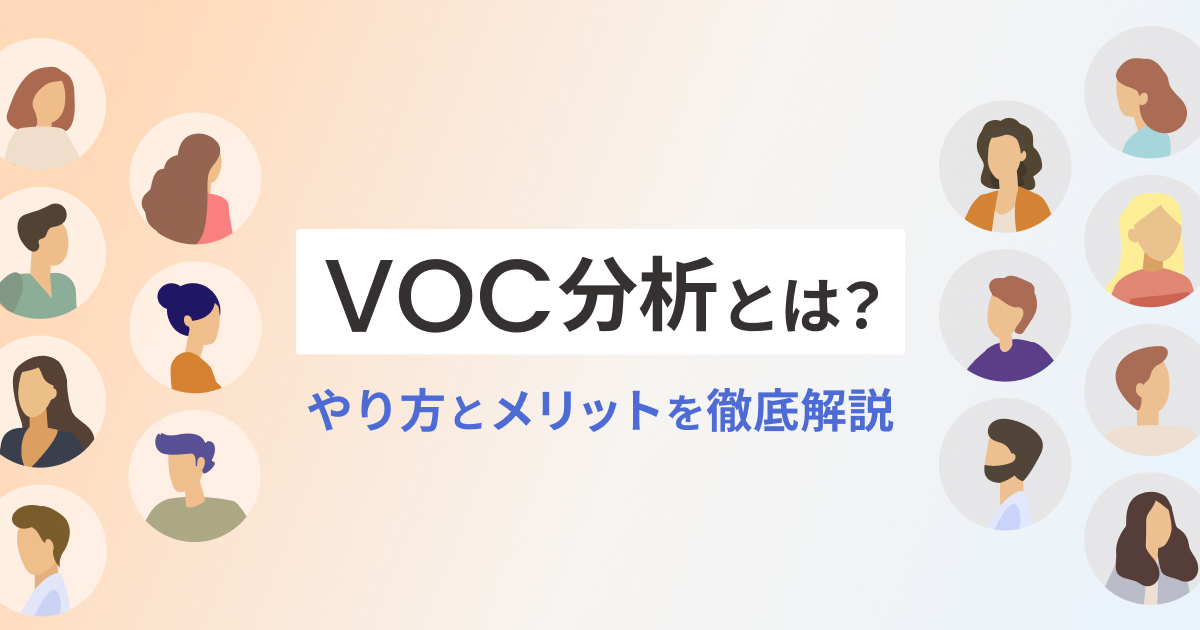
.png)