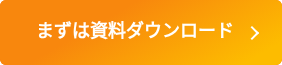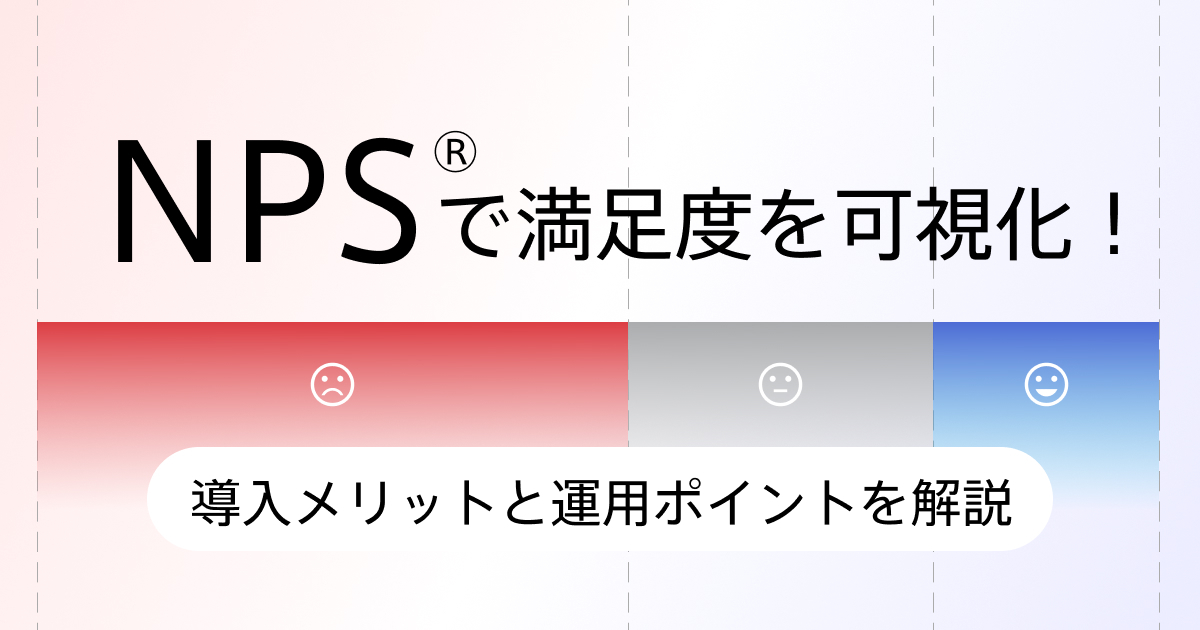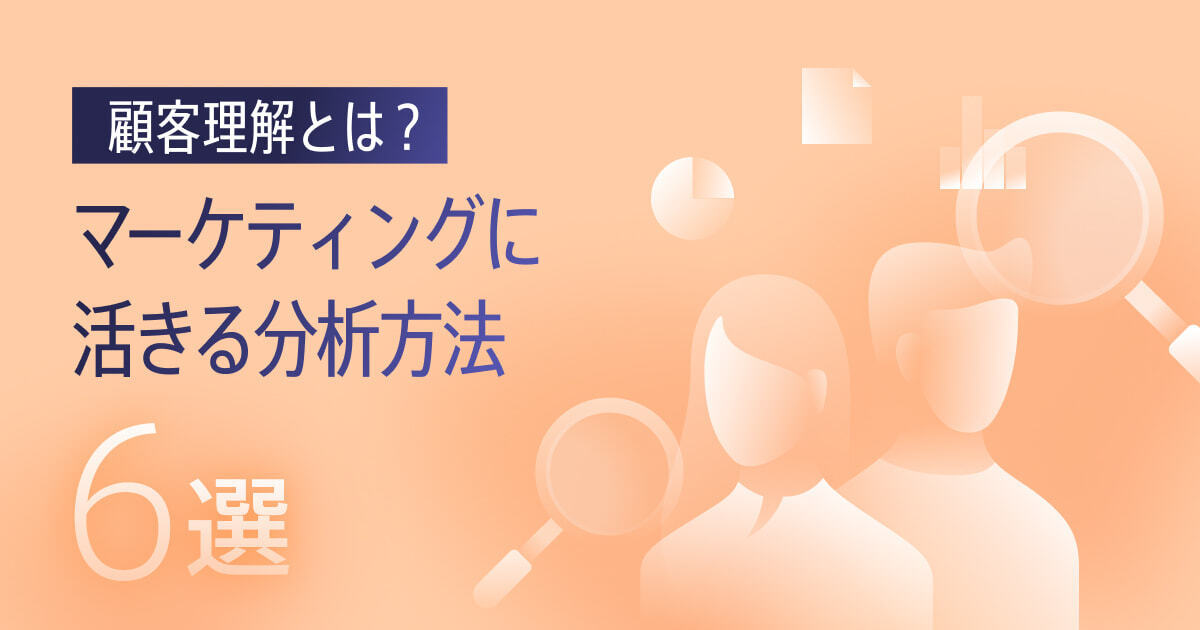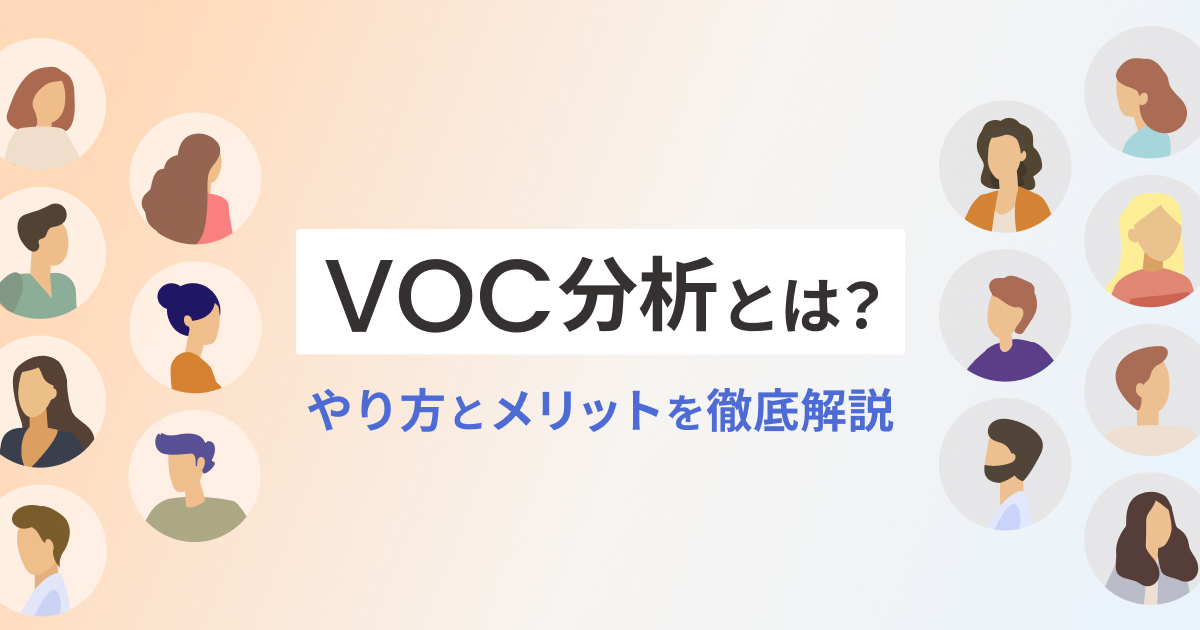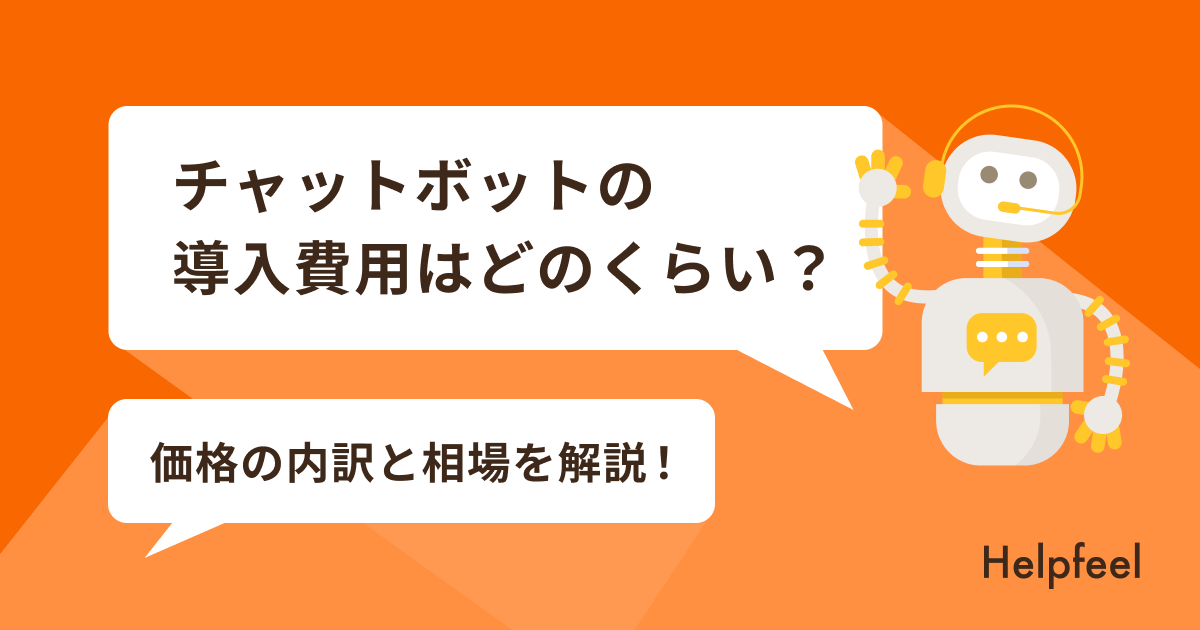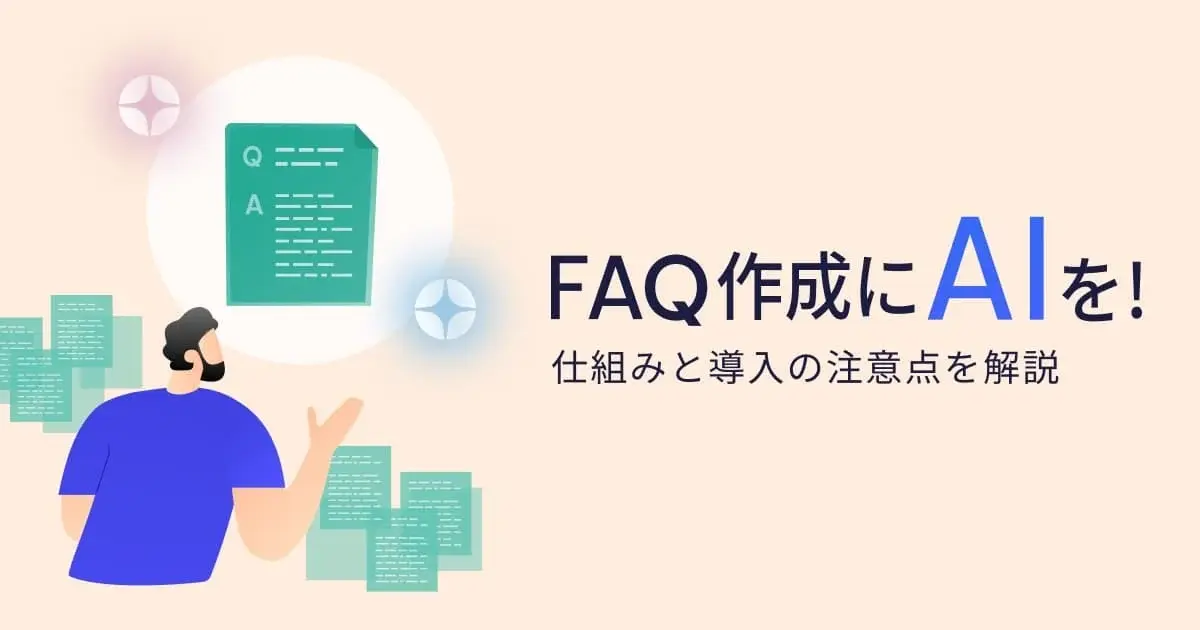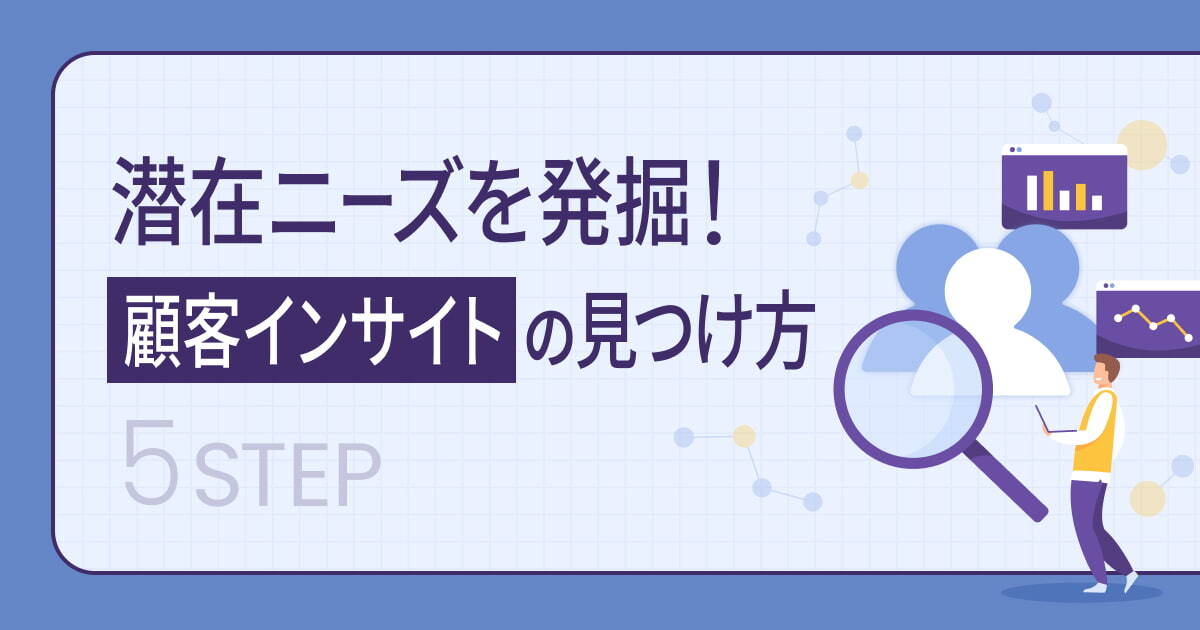顧客ニーズとは?簡単に解説

まずは顧客ニーズについて、以下の3点を解説します。
|
顧客ニーズを理解するために知っておきたい点を詳しく見ていきましょう。
顧客が求める最終的な成果のこと
顧客ニーズとは、顧客の求める最終的な成果を指します。つまり、顧客が商品やサービスを選ぶときの基準になるものです。例えば、「健康的な体を保ちたい」という顧客ニーズがあれば、そのニーズを満たす手段として、スポーツジムや低カロリー食品などが選ばれます。
顧客ニーズを正しく把握することで、顧客の購買意欲を高める商品やサービスを開発でき、広告やキャンペーンなどのマーケティング施策にも活かせます。
そのためには、顧客が何を求めているのかを深く理解することが大切です。さまざまな方法でデータを収集・分析し、顧客が望む最終的な状態を明らかにしていきましょう。
ウォンツとの違い
顧客ニーズと混同されやすい概念に、ウォンツがあります。ウォンツとは、ニーズを満たすための具体的な手段や解決策のことです。例えば、「営業の効率化」というニーズがある場合、営業アプリやチームの再編などがウォンツに該当します。1つのニーズに対して、複数のウォンツが存在することもあります。
ここで注意したいのは、ウォンツ=ニーズではないことです。例えば、顧客が「営業アプリを導入したい」と言っていても、真のニーズは「営業アプリ」そのものではなく、「営業を効率化したい」ということかもしれません。
そのため、ヒアリングの際には、顧客の言葉がニーズなのかウォンツなのかを見極めることが重要です。何度も質問を重ねることで、顧客自身も気づいていない本当のニーズを引き出せます。顧客ニーズを正しく把握できれば、本来の課題に合った最適な提案が可能になります。
潜在ニーズと顕在ニーズ
顧客ニーズには、大きく分けて潜在ニーズと顕在ニーズの2種類があります。潜在ニーズと顕在ニーズの定義は、以下の通りです。
|
顧客が自覚していないニーズ |
|
顧客が自覚しているニーズ |
潜在ニーズとは、顧客がまだ言語化できていない欲求や要望のことです。例えば「なんとなく疲れやすい」「家事をもっと楽にしたい」といった気持ちはあるものの、具体的な解決策や原因までは自覚していない状態です。そのため、潜在ニーズを見つけ出すには工夫が必要で、ヒアリングや観察を通して少しずつ明らかにしていきます。
一方、顕在ニーズは顧客が自覚しているため、行動につながりやすい特徴があります。「掃除機を買い替えたい」「効率的なスケジュール管理アプリが欲しい」といった具体的な要望は、アンケートやインタビュー調査などで比較的簡単に把握できます。
顧客のニーズを満たす商品・サービスを作るには、顕在ニーズだけでなく潜在ニーズを理解することが欠かせません。潜在ニーズを掘り起こせれば、顧客のより深い欲求を満たす魅力的な商品やサービスを提供できるでしょう。
▼顧客ニーズを掴むなら、お客様のリアルな声を分析して可視化することが大切です。Helpfeelなら、顧客理解で得た情報をマーケティングに活かせます。
顧客ニーズを把握する5つの方法

顧客ニーズを把握するには、顧客の意見を直接収集するのが効果的です。ここでは、顧客ニーズを把握する5つの方法を紹介します。
|
それぞれついて、詳しく解説します。
1. 顧客アンケート
顧客アンケートは、大人数から情報を集めるのに適した手法です。近年はオンラインで実施されるケースが一般的で、手軽に行えます。
実施する際は、知りたい内容を明確にして質問を設計することが重要です。特にQ&A形式では、質問文や順序、選択肢を工夫しないと、回答が偏ったり誘導的になったりする恐れがあります。
顧客アンケートでは、次のような情報が得られます。
|
これらのデータを活用すれば、顧客が何を求めているのかを把握しやすくなります。効果的なアンケートを実施することで、顧客ニーズを正確に理解するための貴重なヒントが得られるでしょう。
2. インタビュー調査
インタビュー調査は、顧客と直接対話して情報を集める方法です。アンケートではわかりにくい細かなニュアンスを把握できる点が特徴で、表情やしぐさなども確認できるため、顧客を深く理解するのに役立ちます。
実施方法には、大きく2つあります。
|
1対1で行い、個人的な感情や意見をじっくり掘り下げられる |
|
複数人で議論してもらい、多様な意見を幅広く集められる |
顧客アンケートが数値で示せる定量的な情報を集めるのに適している一方で、インタビュー調査は背景や感情といった定性的な情報を得るのに向いています。両者を組み合わせることで、顧客理解をより深められるでしょう。
3. ソーシャルリスニング
ソーシャルリスニングは、SNS上で顧客の声を収集する手法です。SNSでは多くの人が本音を投稿しており、商品やサービスに対するリアルな意見を幅広く集められます。これにより、顧客ニーズを深く理解する手がかりが得られます。
ソーシャルリスニングの特徴は以下の通りです。
|
ソーシャルリスニングは、顧客アンケートやインタビュー調査では把握しにくい層の声も拾えま す。SNS利用者は年々増えているため、多様な視点を得るには欠かせない方法といえるでしょう。
ソーシャルリスニングを活用すれば、顧客が今何を考え、何を感じているかをタイムリーに把握することも可能です。得られた情報を商品開発やマーケティングに生かすことで、企業の競争力強化にもつながります。
4. NPS®︎調査
NPS®︎(Net Promoter Score)とは、顧客が商品やサービスを他人に勧めたいと思う度合いを数値化したものです。顧客ロイヤルティ(商品やサービスへの信頼・愛着)を測定する代表的な方法で、
世界共通の計算方法で算出されるため、競合他社との比較がしやすいのが特徴です。NPS®︎調査のスコアから以下のことがわかります。
|
満足度が高く、推奨者が多い |
|
改善が必要な顧客体験がある |
スコアが高いほど自社の商品やサービスに満足している顧客が多く、推奨者が増えることで売上アップにもつながります。
ただし、NPS®︎調査だけでは得られる情報が限られるため、顧客の具体的なニーズを把握するにはアンケートやインタビューなど他の調査と組み合わせることが重要です。
▼あわせて読みたい
5. 行動観察調査
行動観察調査は、調査員が顧客の行動を直接観察し、その結果を分析する方法です。顧客本人が意識していない潜在ニーズを探るのに適しています。
この調査では、顧客の日常生活に入り込み、商品の選び方やサービスの使い方を実際に観察します。行動観察調査の例は以下の通りです。
|
行動観察調査の大きなメリットは、リアルな情報が得られることです。アンケートやインタビューでは分からない顧客の行動パターンを把握でき、潜在ニーズの発見につながります。
一方で、実施するには高いハードルがあります。事前準備が多くコストもかかるほか、プライバシーの配慮も必要です。そのため、調査を行う際は対象者への十分な説明と同意を得ることが欠かせません。
▼本記事に関連したお役立ち資料をご用意しておりますので、あわせてご覧ください。
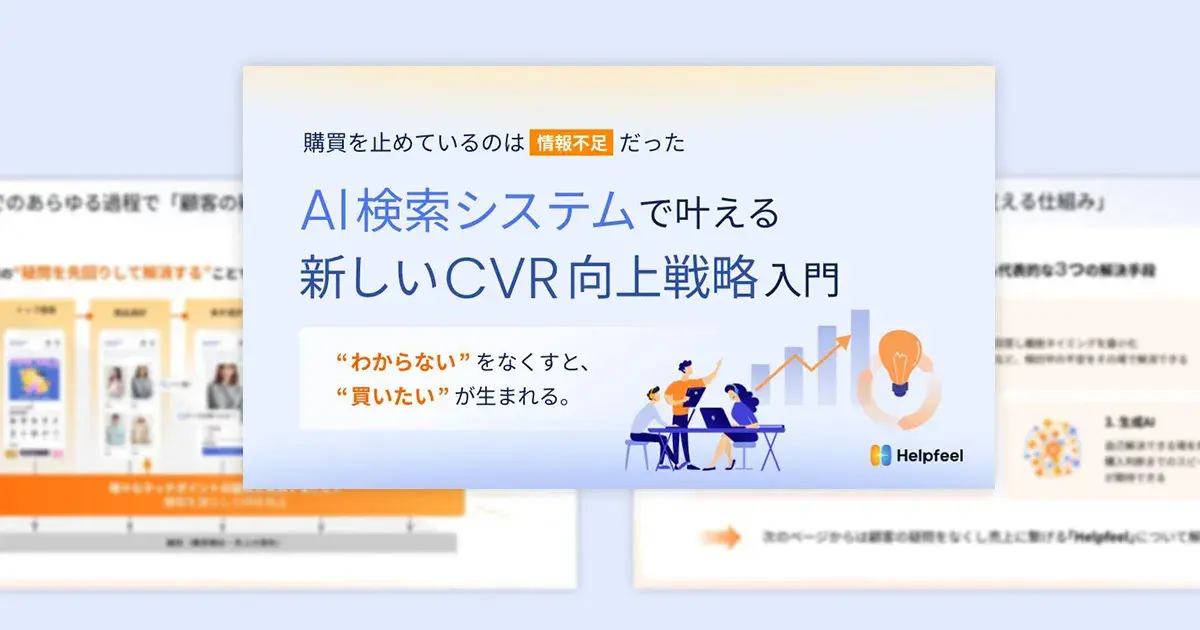
顧客ニーズのデータを分析する5つの手法
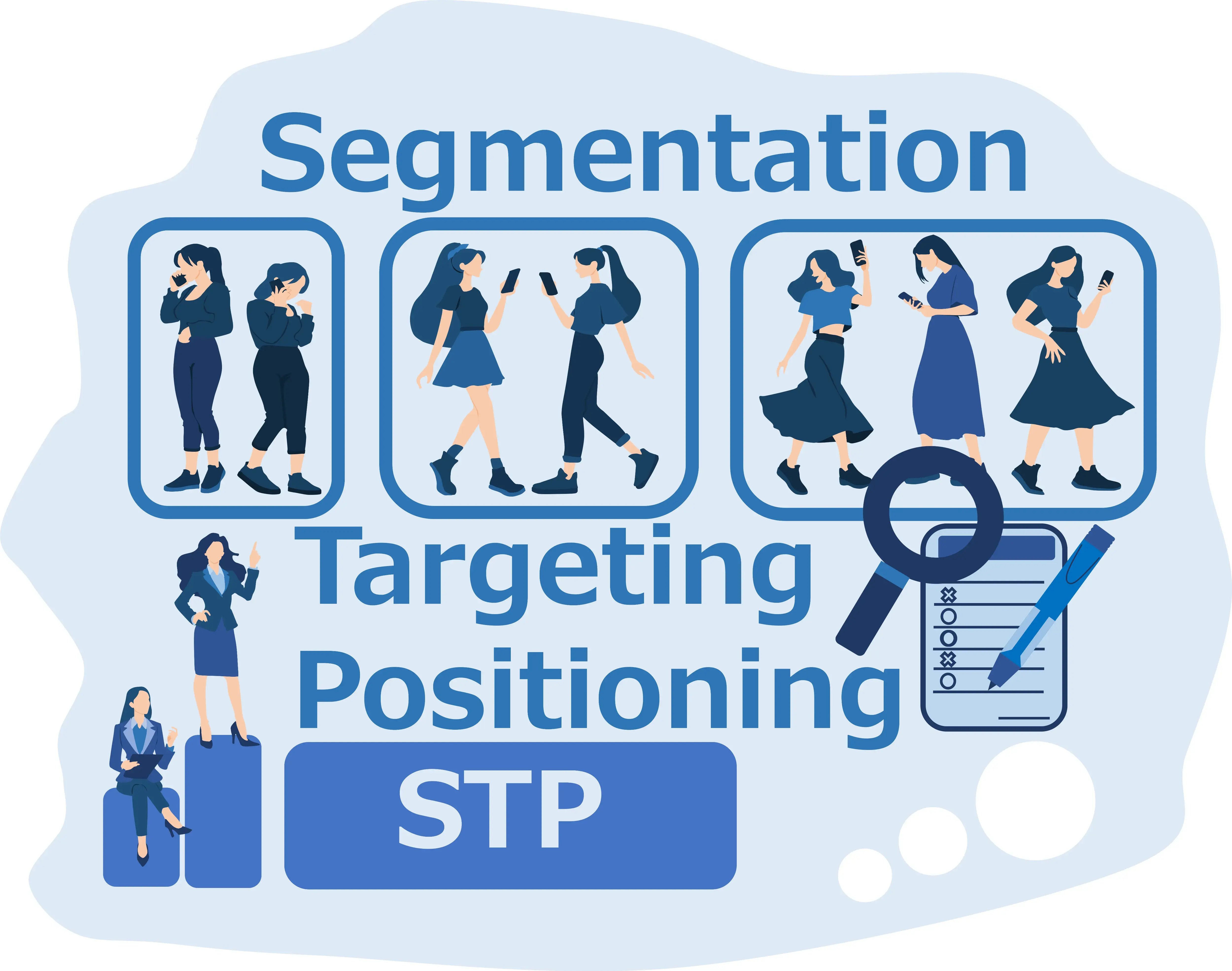
顧客ニーズの把握には、収集したデータの分析も重要です。ここでは、顧客ニーズを分析する5つの手法を詳しく解説します。
|
1つずつ、詳しく解説します。
1. RFM分析
RFM分析は、以下の3つの指標で顧客の分類や評価をする手法です。
|
最後に購入した日付が近いほど高スコア |
|
多いほど高スコア |
|
高いほど高スコア |
この3つの指標にスコアをつけ、組み合わせることで顧客をいくつかのグループに分けます。例えば、購入頻度と購入金額は高いものの、最終購入日が古い顧客グループは、購買力はあるが他社に流れてしまうリスクが高い層といえます。
このように分類することで、各グループに最適な施策を検討できます。RFM分析を行うことで、顧客の購買行動パターンの把握だけでなく、潜在ニーズの発見にも役立つでしょう。
2. セグメンテーション分析
セグメンテーション分析は、対象者をグループ(セグメント)に分類していく分析手法です。分類に使われる主な評価軸は、次の4種類です。
|
年齢、性別、職業、収入 など |
|
地域、人口密度、気候 など |
|
購買履歴、利用頻度、アクセス履歴 など |
|
価値観、ライフスタイル、嗜好 など |
目的に応じて、どの評価軸を組み合わせるかを決めます。一般的には、2つの評価軸を組み合わせて4つの象限に分け、それぞれのセグメントに該当する顧客を深く分析します。
顧客を分類して理解を深めることで、より正確な顧客ニーズの把握につながり、効果的なマーケティング施策の立案が可能です。
3. カスタマージャーニー分析
カスタマージャーニー分析とは、顧客が「商品を知る」から「購入・利用に至る」までのプロセスを可視化する手法です。この流れを図式化したものを「カスタマージャーニーマップ」と呼びます。
例えば、「どんなきっかけで商品を知ったのか」「購入を決めた理由は何か」といった情報を整理することで、顧客の行動背景を深く理解するのに有効です。
また、カスタマージャーニー分析を定期的に繰り返すことで、顧客ニーズの変化の把握が可能です。顧客の気持ちや考えを丁寧に分析することは、信頼関係の構築や長期的な関係づくりにもつながるでしょう。
▼あわせて読みたい
4. 自社サイトの流入分析
自社サイトの流入分析は、顧客ニーズを把握するための貴重な情報源です。確認すべき主な指標を以下にまとめました。
|
よく見られているページやコンテンツ |
|
検索から訪問した際の検索語句 |
|
サイト内での行動結果 |
よく閲覧されているページやコンテンツ、検索からの流入キーワードを分析することで、顧客が何を求めているかを推測できます。
例えば、流入キーワードを確認すれば、顧客がどんな情報を探しているのかが分かります。そのニーズに合ったコンテンツを提供することで、離脱率の低下や成約率の向上が期待できるでしょう。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意しています。ぜひ併せてご覧ください。

5.VOC分析
VOC(Voice of Customer)分析とは顧客の声を収集・分析して商品やサービスの改善に役立てる取り組みです。
VOC分析では、以下のようなさまざまなチャネルからデータを収集します。
|
収集したデータはテキストマイニングなどの手法で分析します。分析結果から商品・サービスの改善やマーケティング戦略の見直しなどを図ります。
VOC分析をして改善をするサイクルを繰り返せば、顧客ニーズを満たした商品・サービスを実現できるでしょう。
▼あわせて読みたい
顧客ニーズの把握にはHelpfeelがおすすめ
顧客ニーズを正確に把握するためには、顧客が日々どんな疑問や不満を抱えているのかを知ることが重要です。しかし、アンケートやアクセス解析だけでは、顧客の本音や潜在的な課題までは見えにくいものです。
そこでおすすめなのが、AI検索・回答機能付きの「Helpfeel」です。Helpfeelを導入すれば、顧客が知りたいことに対して即時かつ高精度な回答が可能になります。同時に、サイト内の検索ログを収集できるため、顧客がどんなことに興味を持ち、どんな悩みや不満を抱えているのかをデータとして可視化できます。
この検索ログを分析することで、顧客ニーズを具体的に把握でき、商品開発やマーケティング施策に活かせます。さらに、よく検索されるキーワードや疑問に対応するコンテンツを充実させることで、顧客の問題解決力が高まり、購買行動の後押しにもつながるでしょう。
顧客理解を深めたい、顧客満足度を高めたいと考えている方は、ぜひHelpfeelの導入を検討してみてください。
活用事例:株式会社平和堂
ここでは、「Helpfeel」を活用して検索ログを分析し、顧客ニーズの把握に成功した株式会社平和堂の事例を紹介します。同社は、クレジットカードの申込み完了率が低いという課題を抱えていました。
この課題を解決するためにHelpfeelを導入し、検索ログを詳細に分析。その結果、顧客が実際に抱えている疑問や不満を正確に把握できるようになりました。
分析で得られたデータをもとに記事を作成・充実させるとともに、店舗やコールセンターで寄せられる問い合わせ内容もFAQページに統合。顧客が必要な情報をスムーズに得られる体制を整えました。
こうした施策の結果、クレジットカードの申込者数は前年比1.9倍に増加しました。検索ログを活用して顧客の潜在ニーズを可視化し、大きな成果を上げた成功事例です。
▼事例詳細はこちら
まとめ

顧客の求めるものを提供するためには、顧客ニーズの把握が欠かせません。もし顧客ニーズを誤って理解すると、顧客の期待と自社のサービスや商品にズレが生じ、顧客満足度の低下につながります。企業が競争力を高めるためには、正しい方法で調査・分析することが重要です。
アンケートやインタビューなどでデータを集め、さまざまな分析手法を活用することで、顧客が本当に求めていることを推測できます。その結果をもとに商品やサービス、広告を改善すれば、売上や申込件数の増加といった目標達成に近づけます。本記事で紹介した調査と分析方法を実践し、自社のビジネスの成長につなげていきましょう。



潜在的な顧客ニーズを効率的に見つけるために、まず何をすべきでしょうか?
顧客ニーズを見つけるには、アンケートなどの「点」の調査だけでなく、行動ログという「線」のデータを追いましょう。アンケートは用意された選択肢から選ぶため、回答が制限されがちです。一方で、ユーザーが自ら動いた検索ログやサイト内の動線には、意図せず漏れ出た本音が隠されていることが多いです。


集まった膨大なデータからニーズを特定するコツはありますか?
「共通する悩み」のパターンを見つけ出し、仮説を立てることです。断片的な意見を眺めるのではなく、多くの人が同じ言葉で検索しているが、解決できていないことを探します。その不満や不便の解消こそが、強力な顧客ニーズの特定に繋がります。