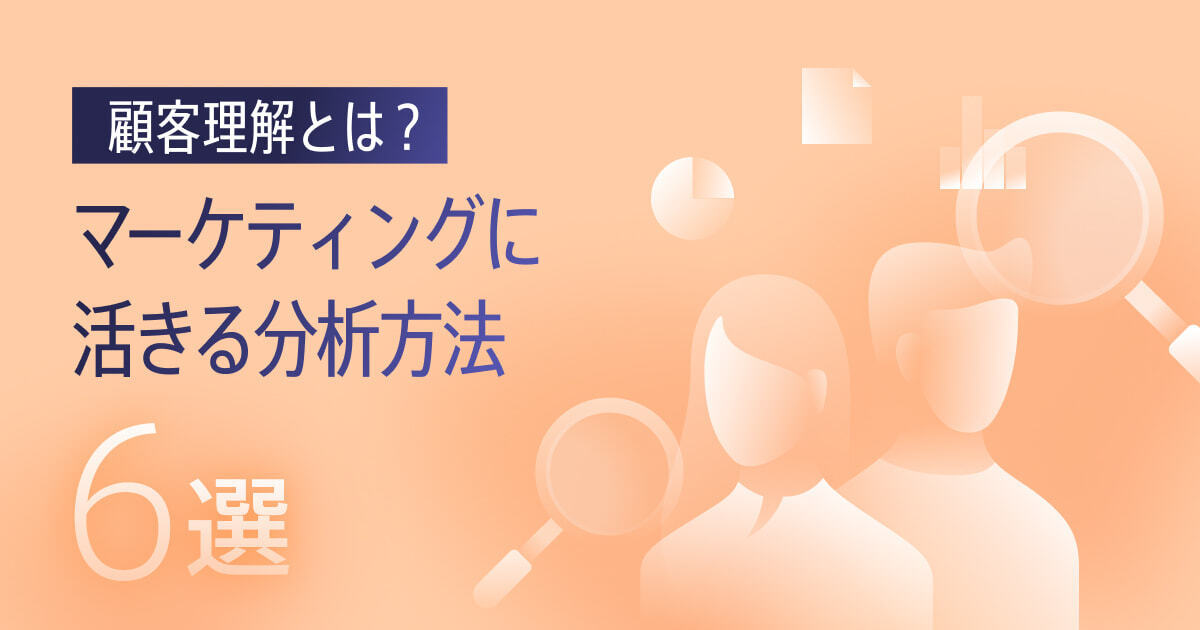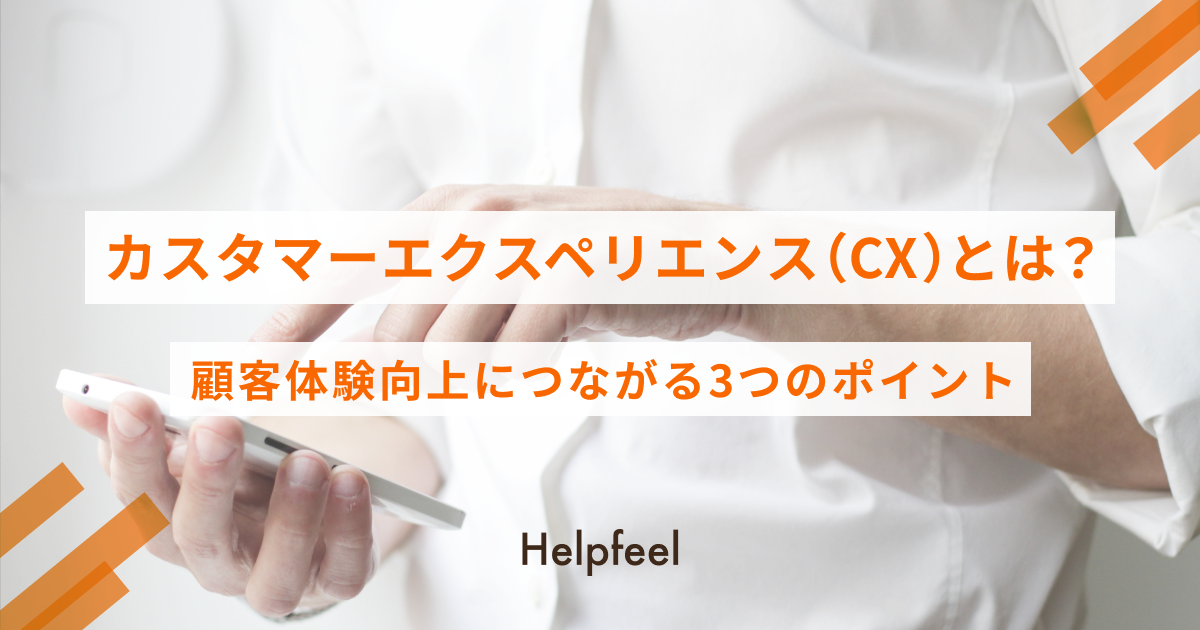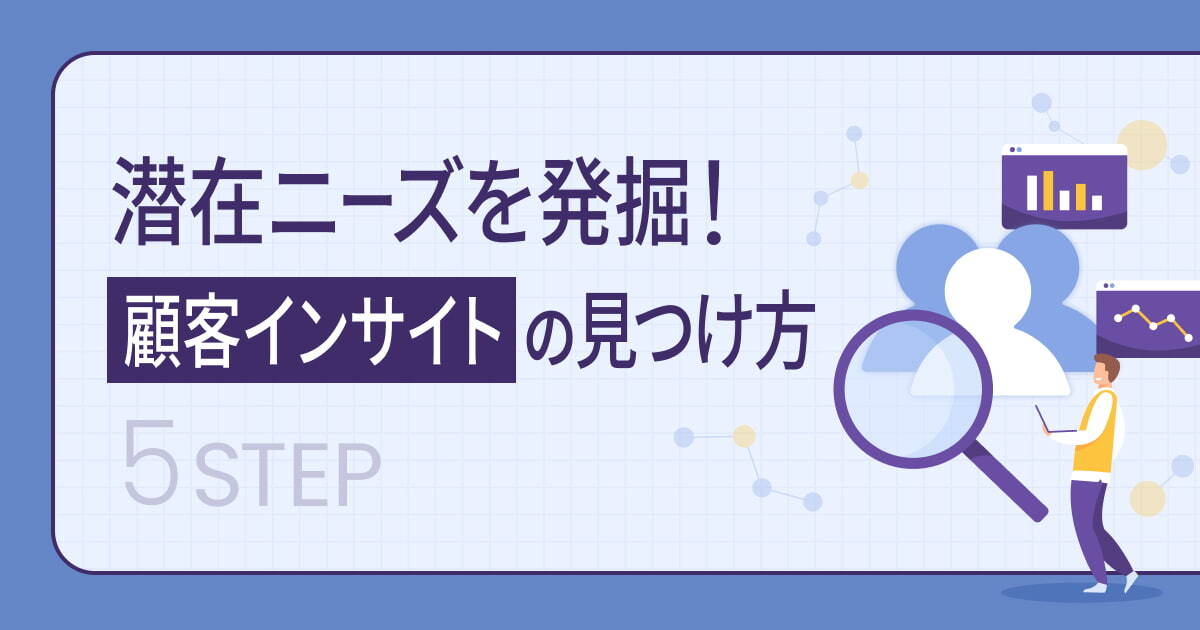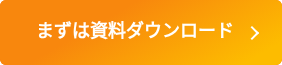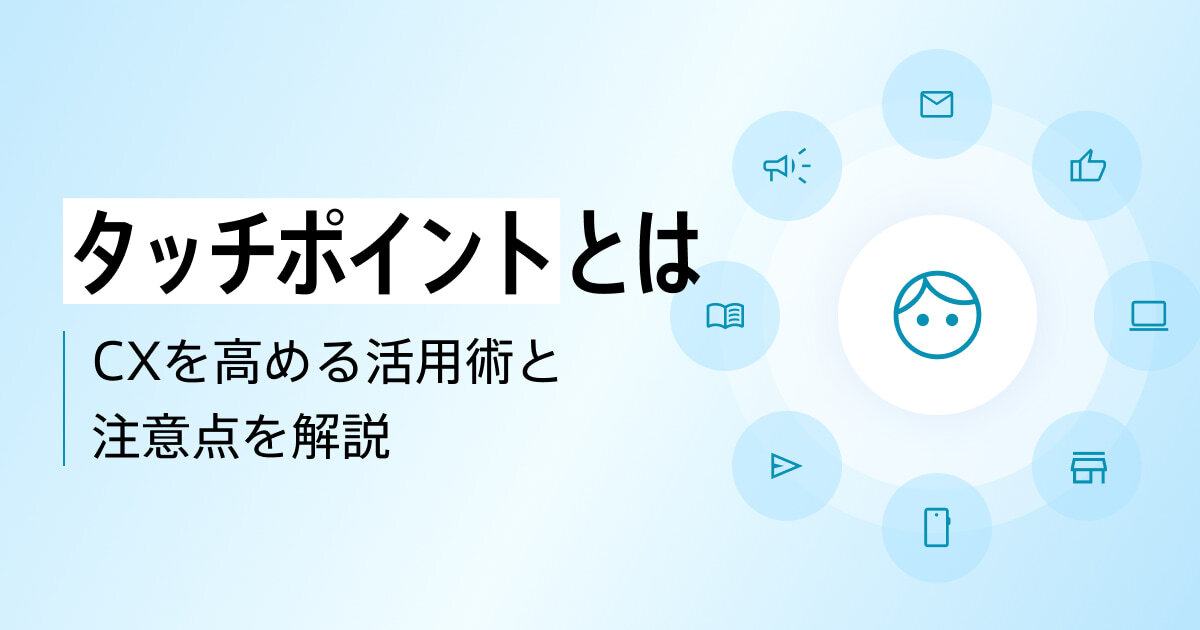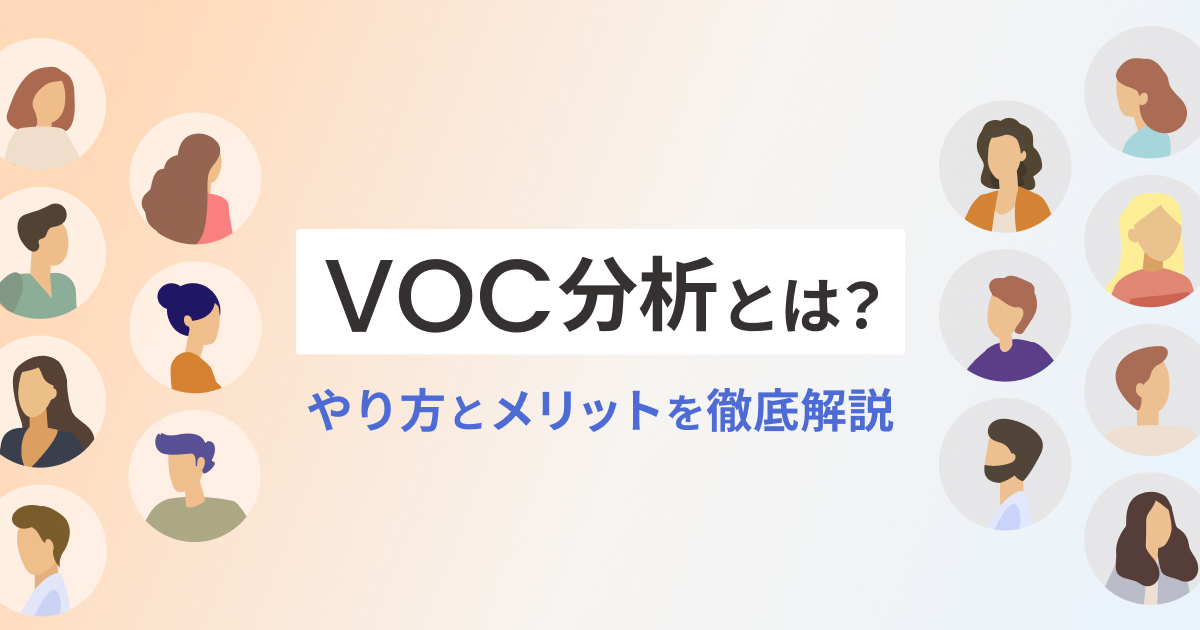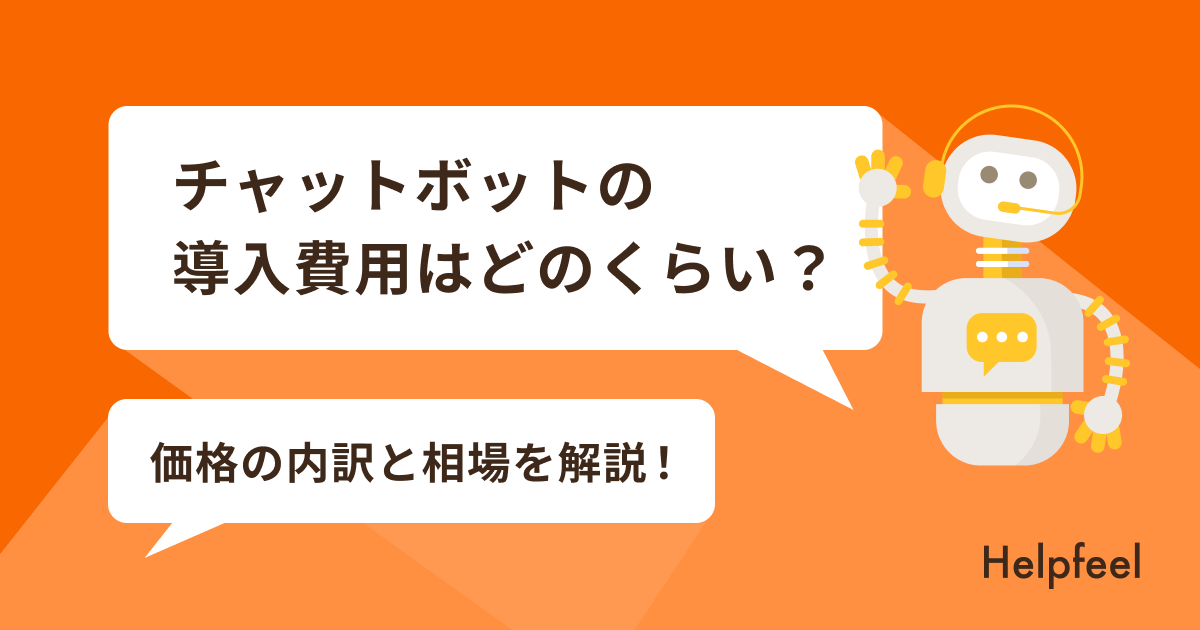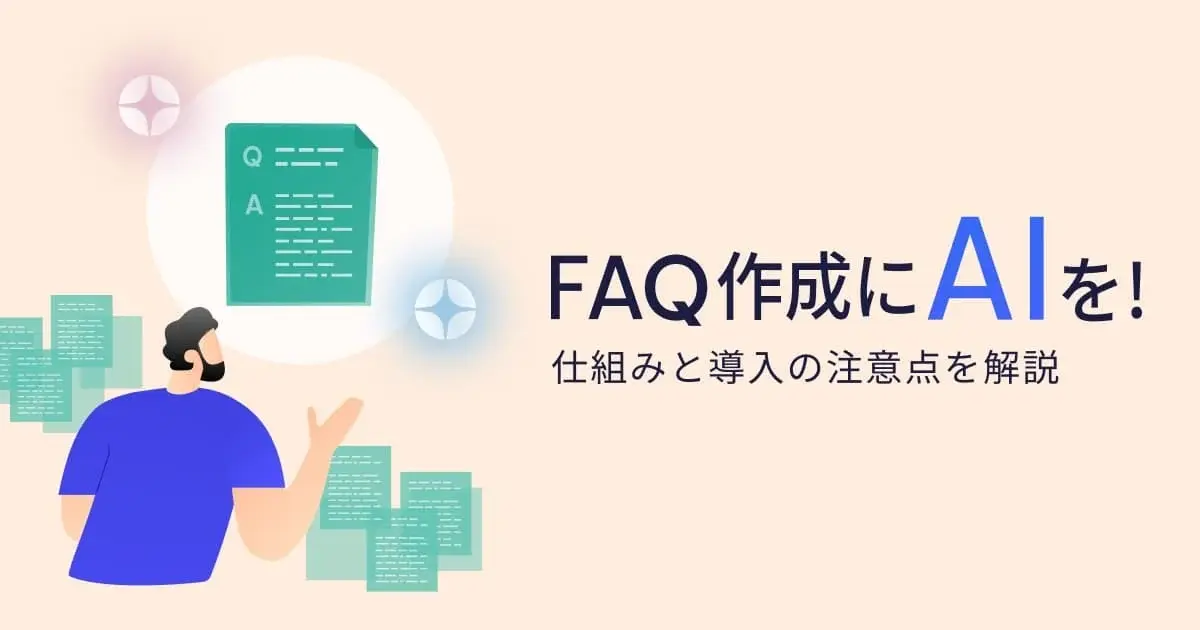顧客理解とは

顧客理解とは、顧客が抱えている課題や欲しいと思っている商品・サービスを把握することです。顧客のニーズを的確に汲み取ることで、リピーター獲得や売上アップにつながるマーケティング施策を立てられるようになります。
顧客理解を深めるためには、アンケート調査やデータ分析、市場調査などの多角的なアプローチが欠かせません。顧客の属性や購買行動から、下記のように顧客視点で検討することが大切です。
|
顧客が本当に必要とする商品を提供し、事業を成功に導くためには、顧客理解が必要不可欠といえるでしょう。
▼本記事に関連したお役立ち資料をご用意しておりますので、あわせてご覧ください。
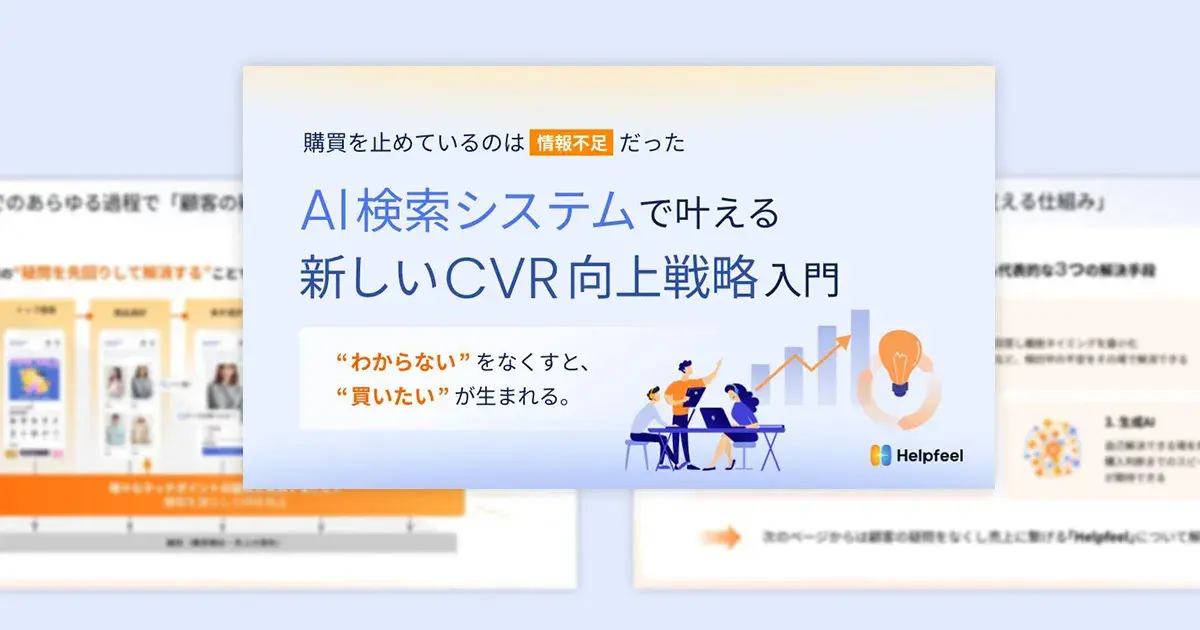
顧客理解が重要な理由

顧客理解が重要な理由は、下記の5つです。
|
それぞれについて詳しく解説します。
マーケティング施策の立案
顧客を深く理解することは、効果的なマーケティング施策の立案につながります。例えば、購買行動を分析すると、商品購入に影響した広告や適切なチャネルが明確になるでしょう。実際に商品を購入した顧客の属性を分析し、ターゲット層を絞り込むことも可能です。
分析結果をもとに広告やチャネルを見直し、ターゲット設定を調整することで、マーケティング施策の精度を高められます。なお、複数のマーケティング施策を並行して実施している場合は、それぞれの施策を統合して分析することも重要です。
CX向上・競合差別化に直結
CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、購入からアフターフォローまでの一連の顧客体験を指します。顧客の考えや行動を理解し、期待以上の体験を提供することでCXの向上を期待できます。
CXが向上すれば、商品や企業に対する満足度が高まり、顧客ロイヤルティも高まるでしょう。顧客ロイヤルティとは、顧客が商品や企業に対して抱く愛着のことです。顧客ロイヤルティが上がれば、リピーターの増加を見込めます。
また、顧客のニーズをくみ取り、他では得られない体験を提供することでブランドの独自性を高められるのも重要なポイントです。商品の特別感が増し、競合との差別化を実現しやすくなります。
▼あわせて読みたい
エフォートレスな体験を生み出せる
ビジネスにおける「エフォートレスな体験」とは、少ない手間で顧客が商品やサービスを利用できる状態のことです。商品を利用する際に余計な手間がかかると、マイナスなイメージを持たれやすくなり、継続利用の障害になります。
例えば「商品の使い方がわかりにくい」「問い合わせ先が限られていて不便」など、顧客が手間を感じる場面はさまざまです。顧客への理解を深め、利用時の障害となる要素を取り除くことでエフォートレスな体験を生み出せるようになります。エフォートレスな体験は顧客ロイヤルティを向上させ、リピーターの増加にもつながるでしょう。
▼あわせて読みたい
顧客インサイトの把握に役立つ
顧客インサイトとは、顧客が購買行動に至るまでの深層心理を指します。顧客に対して商品を購入した理由を聞いたときに「なんとなく好みだから」と曖昧な回答が出た場合も、本人が自覚していない潜在的な欲求が隠れている場合がほとんどです。
顧客の属性や購買行動を分析し理解を深めることで、表面だけでなく潜在的なニーズもくみ取れるようになります。顧客インサイトを把握した上でマーケティング施策を立案すれば、ターゲット層の興味を引きやすくなり、購買意欲の向上や売上アップを期待できるでしょう。
▼あわせて読みたい
新商品やサービスの開発に生かせる
顧客理解を深めることで、商品の改善点が明確になり、より満足度の高い新商品を開発できるようになります。
例えばアイスクリームの場合、「甘くておいしい」という魅力がある一方「カロリーが高くて太りそう」とのイメージから商品購入を諦める場合があります。「ヘルシーで罪悪感のないアイスクリームを食べたい」という潜在的な欲求をくみ取り、「糖質オフ」や「低カロリー」などのアイスクリームを開発すれば、新しい顧客層の獲得やリピーター増加を期待できるでしょう。
このように、顧客理解は商品開発の新たなヒントをもたらします。
▼顧客が求める情報を正確に把握することが、CX向上の第一歩です。Helpfeelなら、そのインサイトをマーケティングに活かせます。
顧客理解の手法6つ

顧客理解の手法は、6つあります。
|
適切な手法を取り入れて、顧客理解に役立ててください。
ユーザーアンケート
ユーザーアンケートは、顧客の声を直接集め、課題や不満、満足度を把握するために役立ちます。アンケート結果は、新商品の開発や改善点を洗い出す際に欠かせない情報源です。顧客の声を分析することで、優先すべき課題や投資領域が明確になります。
アンケートのポイントは、「方法」や「タイミング」を工夫することです。例えば、回答率を上げるために、ポイント付与や割引特典などのインセンティブを設けたり、必要最低限の設問に絞り、短時間で回答できるようにすることが大切です。
顧客データの分析
顧客が求めていることを分析するためには、データの収集が必須です。データの収集には、CRMなどの顧客情報を管理する機能を備えたツールが役立ちます。
顧客の基本情報やオンラインショップ上での行動履歴といったデータを蓄積・分析することで、顧客への理解を深められるでしょう。例えば、収集データをもとに顧客の属性を分析すれば、年齢や性別、居住地域の傾向からターゲットの設定が可能になります。
顧客を曖昧に理解したままでは、効果的なマーケティング施策にはつながりません。データを活用して具体的に顧客を理解することで、「いつ」「何を」「誰に」届けるべきかを明確にできます。
▼Helpfeelなら、FAQ検索データをもとに顧客の関心や課題を可視化できます。“本当に求められている情報”に基づいた施策設計が可能です。
>> Helpfeelの「マーケティング手法」についてはこちら
営業部門のヒアリング
営業部門は、顧客と直接コミュニケーションを取る機会が多い部門です。ヒアリングすることで、顧客視点での意見や現場から見た課題点をくみ取れます。
ヒアリングの際に聞いておきたい項目は、以下の通りです。
|
営業部門のヒアリングとユーザーアンケートを照らし合わせれば、自社と顧客の間で生じている認識の違いも明確になるでしょう。
テストマーケティング
テストマーケティングとは、新しい商品を先行して提供し、顧客の反応を確認する手法です。実際に商品を使ってもらい、率直な感想をもらうことで顧客理解が促進され、改善点を洗い出せるようになります。
テストマーケティングを行う際は、普段から自社の商品を使っている顧客を選ぶのがおすすめです。自社商品を愛用している顧客なら、誰よりも早く新商品が使えることを喜んでもらいやすく、積極的に協力してもらえる可能性が高いでしょう。
得られた結果は、マーケティングメッセージの作成や実際の利用事例紹介などでも活用できます。
ソーシャルリスニング
ソーシャルリスニングとは、InstagramやXなどのSNS、ブログ、レビューサイトなどで発せられた情報を集めて分析し、マーケティングに生かす手法です。
インターネット上には、商品に対するユーザーの率直な感想が投稿されています。ユーザーアンケートに加えてソーシャルリスニングも行うことで、より正確に顧客ニーズをくみ取れるでしょう。
またソーシャルリスニングは、実際に行ったマーケティング施策の効果を確認するのにも有効です。収集したユーザーの意見をもとに改善点を洗い出し、より効果的なマーケティング施策を検討するのに役立ちます。
VOC分析
VOC(Voice Of Customer)分析とは、顧客の声を収集・分析し、現状の課題を見つけ出す手法です。コールセンターへの問い合わせや通話履歴などから、顧客ニーズを導き出すことで、マーケティング施策の最適化や商品改善につなげられます。
VOC分析をする際は、専用ツールを活用するのがおすすめです。例えば、顧客分析機能を搭載したCRMツールでVOCを管理すれば、顧客情報とひもづけながら分析できます。他に、文字列から相関関係や出現頻度を分析できるテキストマイニングツール、音声データを文字化する自動音声認識ツールなども役立つでしょう。
▼VOC分析については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。
顧客理解に役立つフレームワーク

顧客理解に役立つフレームワークは、5つあります。
|
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品を認知してから購入するまでの過程を可視化したものです。「顧客が商品を認知する」→「商品に興味を抱いて購入を検討する」→「最終的な購入に至る」という流れをフェーズごとに図式化します。
カスタマージャーニーのポイントは、各フェーズで生じる商品と顧客の接点(タッチポイント)で起きた心理状態の変化を可視化することです。フェーズごとの変化を目に見える形にすることで、より顧客の行動や心理を理解できるようになります。
また、最終的に購入フェーズへ誘導するために必要なアプローチ方法を検討するのにも役立ちます。
▼あわせて読みたい
ペルソナ分析
ペルソナとは、商品を利用する典型的な顧客像のことです。性別や年齢、居住地域、職業、価値観などを細かく設定し、ターゲットとなる顧客を具体的にイメージできる状態にします。
詳細な顧客像があれば、顧客の心理や行動を理解しやすくなるため、ニーズや課題を適切にくみ取れるでしょう。競合他社との差別化を図る際も、顧客の視点に立って自社にしかない魅力やアピールポイントを洗い出せます。
また、チーム内でペルソナを共有すれば、商品開発やマーケティング施策の方向性が明確になり、ブレることなく戦略を立てられるのもメリットです。
セグメンテーション分析
セグメンテーション分析とは、顧客を特性ごとに分類し、各分類に応じたアプローチを検討する手法のことです。顧客のニーズが多様化する近年、商品のターゲットを明確化するために必要とされています。
一般的な分類方法は、以下の通りです。
|
地域、人口密度、気候 |
|
性別、年齢、職業、家族構成、年収 |
|
価値観、ライフスタイル、性格、嗜好(しこう) |
|
購入時間帯、購入頻度、購入経路 |
セグメンテーション分析でメインとなる顧客の特性や課題を絞り込めば、より効果的なマーケティング施策を検討できるようになります。
CTB分析
CTB分析とは、3つの指標で顧客を分類し、将来的な購買行動を予測する手法です。特に「どのような属性の顧客に、どのようなタイプの商品が売れているか」を理解したいときに役立ちます。
3つの指標は、以下の通りです。
| 指標 | 概要 |
|
商品の種類(例:コスメ、飲料、家電) |
|
嗜好(デザイン・色・サイズなど) |
|
ブランドやブランドイメージ |
CTB分析をすることで顧客が好む商品のカテゴリやテイスト、ブランドがわかり、「売れやすい商品」と「売れにくい商品」が明らかになるでしょう。分析結果は、商品ラインアップの改善やターゲットの見直しなどに活用できます。
RFM分析
RFM分析は、顧客の購買行動を3つの指標で分類し、適切なマーケティング施策を検討するための手法です。3つの指標に分類した上で、数値に応じたスコアを付与します。
|
指標 |
意味 |
ランクの付与方法 |
|
R(Recency) |
最終購入日 |
最終購入日が直近であるほど高いスコアを付与 |
|
F(Frequency) |
購入頻度 |
購入頻度が高いほど高いスコアを付与 |
|
M(Monetary) |
購入金額の合計 |
購入金額が高いほど高いスコアを付与 |
スコアに応じて、顧客を「休眠顧客」「新規顧客」「安定顧客」「優良顧客」に分類します。分類によって、それぞれのグループに適したマーケティング施策の検討が可能です。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意しています。ぜひ併せてご覧ください。

顧客理解には問い合わせやFAQの検索ログ分析も有用
顧客がどのような悩みや疑問を抱えているのかをデータとして可視化できれば、マーケティング施策や新商品の開発に活かせます。「顧客が何に困っているのか」「どんな情報を求めているのか」を数字や実際の声から把握できれば、より具体的で効果的な対策を検討できるでしょう。
そのためには、顧客のお問い合わせログや、実際に入力したFAQの検索キーワードや質問ログを活用するのがおすすめです。「Helpfeel」は、顧客が問い合わせたり、検索した言葉を収集・分析することができます。これまで見えにくかった顧客の不満や要望を浮き彫りにし、商品改善や顧客体験(CX)の向上につなげることが可能です。
さらに、Helpfeelではコンサルティングによる手厚いサポートも提供しています。「分析結果は分かっても、ページ導線やコンテンツ改善の具体策が分からない」という方も安心です。顧客理解を深め、施策に確実につなげたい方は、ぜひHelpfeelの導入をご検討ください。
まとめ|顧客理解をしてマーケティング施策を成功させよう

リピーターや売上アップにつながるマーケティング施策を実施するには、顧客理解が欠かせません。顧客が何を求めて、何を課題に感じているのかを把握し、適切に対策することでCX向上や競合他社との差別化につながります。
また、既存商品の改善点が明らかになり、新商品の開発に役立てられるのも大きなメリットです。顧客のニーズとマッチした新商品が実現できれば、さらなる業績の向上が期待できるでしょう。
顧客理解には、ユーザーアンケートや顧客データ分析、営業部門のヒアリングなど、複数の手法を取り入れることが大切です。分析する際は、専用ツールを使うと迅速かつ正確に顧客の状況を把握できます。今回紹介した方法を活用しながら顧客理解を深め、マーケティング施策を成功に導いてください。