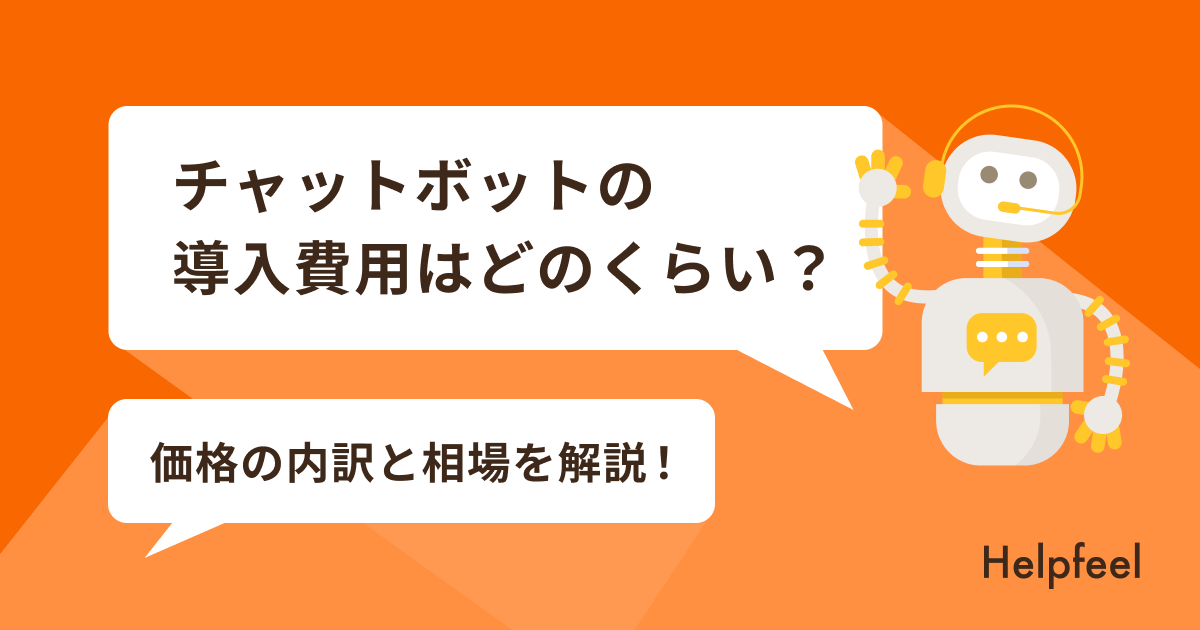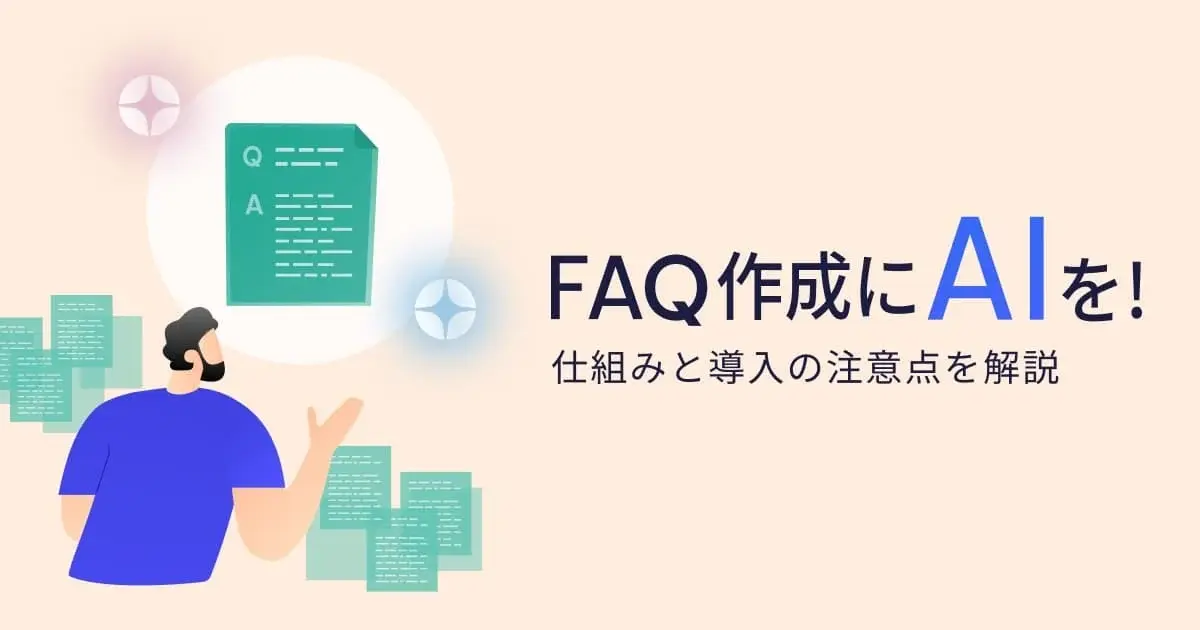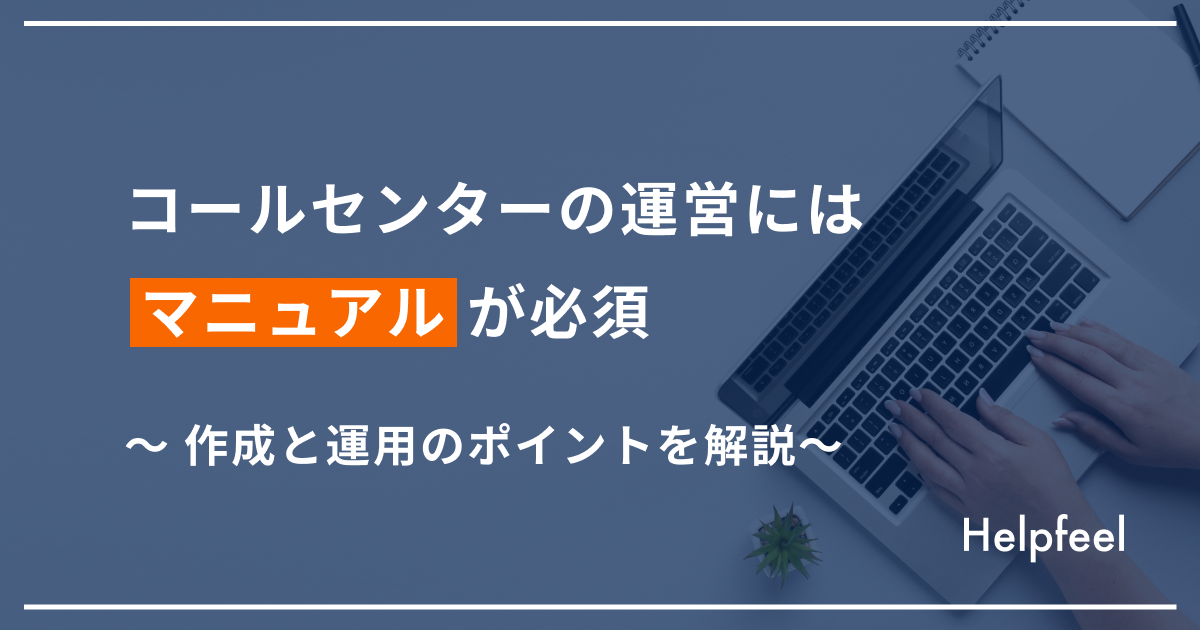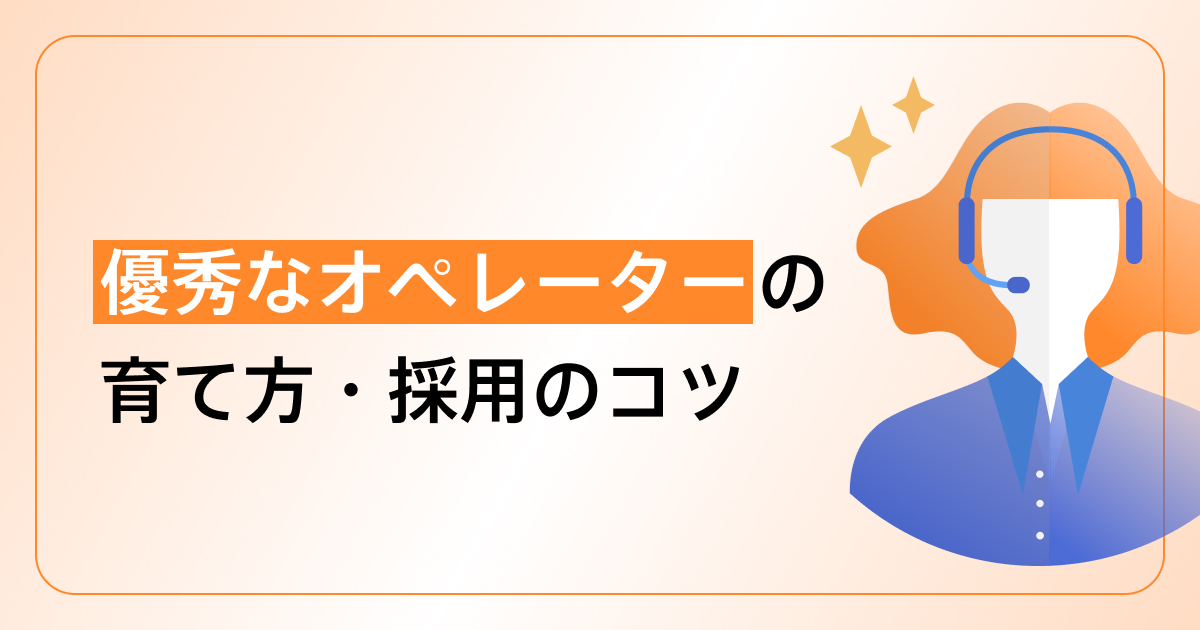▼本記事に関するお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

コールセンターにおけるDXとは
 DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略で、IT技術を活用して業務やビジネスの在り方を抜本的に見直し、新たな価値や競争力を生み出す取り組みです。
DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略で、IT技術を活用して業務やビジネスの在り方を抜本的に見直し、新たな価値や競争力を生み出す取り組みです。
近年、コールセンターを取り巻く環境は大きく変化し、人手に頼る従来の運営では対応が難しくなってきました。そのため、顧客対応の効率化や情報管理の最適化、働きやすい環境の整備を目的に、多くの現場でDXが進められています。
コールセンターのDXが必要な理由

DXがコールセンターに必要とされるのには、以下の3つの理由があります。
問い合わせの多様化に対応する
コールセンターにおけるDXは、顧客からの問い合わせ手段が多様化する現代において、スムーズな対応を可能にするために欠かせません。従来は電話やメールが中心だった問い合わせも、近年はSNSやチャット、専用アプリなど、チャネルが多様化しています。
顧客行動の変化に対応できなければ、やり取りの行き違いが生じ、満足度の低下やクレームの原因となる可能性があります。
たとえば、SNSでの問い合わせ履歴と電話対応の情報が共有されていない場合、顧客は何度も同じ説明をする必要があり、ストレスや不信感につながるでしょう。こうした状況を防ぐには、情報を一元管理し、リアルタイムに連携できる仕組みが必要です。
複数チャネルにまたがる問い合わせに一貫して対応できる体制を整えることは、顧客満足度を維持・向上させる上で重要です。
カスタマーエクスペリエンスの向上を図る
コールセンターのDXは、カスタマーエクスペリエンス(CX)の向上に不可欠な取り組みです。顧客との良好な関係を築き、満足度やLTV(顧客生涯価値)を高めるには、個々一人一人のニーズに合わせた柔軟な対応が求められています。
従来の画一的な応対では、顧客が求める「スピード」「正確さ」「気配り」に応えることが難しいケースも少なくありません。
たとえば、過去の購入履歴や問い合わせ内容をもとに最適な商品を提案する、あるいは問い合わせ前にFAQやチャットボットで必要な情報をタイムリーに届けるといった仕組みを導入することで、顧客はストレスなくサービスを利用できるようになります。
▼あわせて読みたい
慢性的な人材不足を解消する
コールセンターのDXは、人手不足の課題を根本的に解消する手段として有効です。コールセンター業務はストレスや負担が大きく、離職率も高いため、慢性的な人材不足が課題の1つです。
限られた人員で多くの問い合わせに対応する従来の体制には、すでに限界が見え始めているため、DXの導入によってその打開が期待されています。たとえば、よくある質問に対してはAIチャットボットやFAQシステムで自動応答することで、オペレーターの対応件数を減らすことが可能です。
また、CRMやナレッジ共有ツールを活用することで、業務の属人化を防ぎ、効率的な運営が実現します。人手に頼るだけでは立ち行かなくなっている現場において、DXはオペレーターの負担軽減と業務の安定化を同時に進めるための鍵となるでしょう。
▼あわせて読みたい
コールセンターのDX重視すべき3つのテーマ

コールセンターではサービスや製品に関するカスタマーサポートを行うため、顧客満足度を高めることが大切です。しかし、顧客満足度を高めるためには、オペレーターが働きやすい環境を整えることも欠かせません。
顧客からの問い合わせに対して効率良く対応できることや、オペレーターが顧客に関する情報を簡単に確認できる一元管理の実現などが挙げられます。
ここでは、コールセンターのDXにおいて重要な3つのテーマを解説します。
問い合わせ対応の効率化
コールセンター業務を効率化するうえで、DXの活用は欠かせません。すべての問い合わせを人力で対応していては、対応が追いつかず、オペレーターの負担も大きくなります。
そこで有効なのが、FAQやAIチャットボットの導入です。顧客のよくある質問に自動で対応することで、一次対応の負担を大幅に軽減できます。
また、IVR(自動音声応答)システムを使えば、電話を内容ごとに適切な担当者へ振り分けることも可能です。有効なツールを導入することで、限られた人員でもスムーズな対応を実現できます。
▼あわせて読みたい
顧客情報の一元管理
電話・メール・チャット・SNSなど、問い合わせチャネルが多様化する中で、顧客情報を一元管理することは重要です。
各チャネルでの対応履歴や購入履歴、過去の問い合わせ内容などを統合して管理することで、オペレーターは顧客の状況を迅速に把握することができます。
さらに、CTI(Computer Telephony Integration)システムを導入すれば、電話着信時に顧客情報が自動で画面に表示され、スムーズな対応が見込めます。DXによって、情報の分散によるミスや手間を減らすことで、対応品質の向上につながるでしょう。
働きやすい環境づくり
コールセンターのDXは、働きやすい職場環境の実現にも貢献します。なかでも注目されているのが、「リモートワークの導入」です。クラウド型の対応システムや通話ツールを活用すれば、自宅にいながらでも通常の業務が可能になり、出社の負担を軽減できます。
▼あわせて読みたい
多様な働き方に対応することで、子育てや介護などの事情を抱える人も働きやすくなり、ワークライフバランスの向上が期待できます。さらに、居住地にとらわれない採用が可能になることで、人材確保の幅も大きく広がるでしょう。
▼コールセンターを根本から変革するお役立ち資料もご用意しております。ぜひ併せてご覧ください。
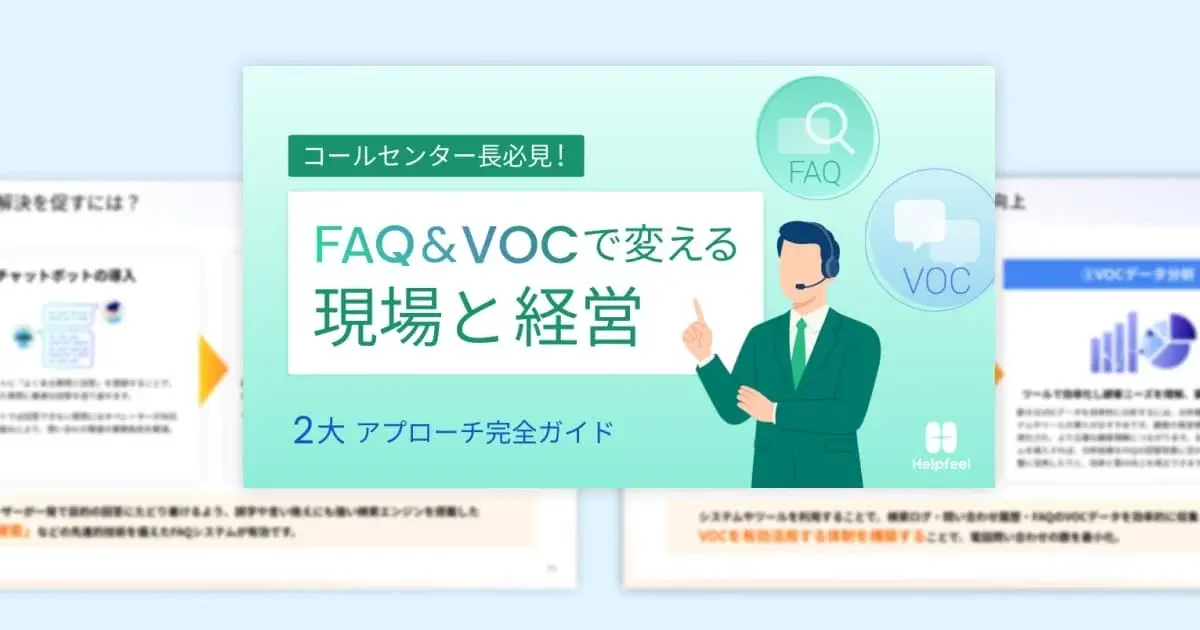
コールセンターのDXを実現するためのシステム

コールセンターのDXに必要なシステムとは、顧客の待ち時間の短縮や、オペレーター対応の効率化などです。ここでは、DXの実現に必要な7つのシステムについて解説します。
処理速度を向上させる「CTI」
CTIは「Computer Telephony Integration」の略で、電話やファックスをコンピューターと連携させるシステムです。CTIを利用すると、かかってきた電話の顧客情報を自動的に表示できるため、スムーズな顧客対応が実現できます。
1件あたりの対応時間や、顧客の待ち時間の短縮など、さまざまな効果が期待できるため、コールセンターの業務効率化には欠かせないシステムの1つです。
対応業務を効率化する「IVR」
IVR(Interactive Voice Response)は、自動音声で顧客の問い合わせを振り分けるシステムです。「○○に関するご用件は1番を押してください」といった音声ガイダンスに従って、顧客が選んだ内容に応じて、適切な担当部署へ電話をつなぐことができます。
よくある質問などは自動音声で対応できるため、オペレーターの負担を軽減しつつ、対応の効率化が期待できるでしょう。
▼あわせて読みたい
待ち時間を短縮する「ACD」
ACD(Automatic Call Distribution)は、コールセンターにかかってきた電話を自動的にオペレーターへ振り分けるシステムです。
対応可能なオペレーターの状況やスキル、通話履歴などに基づいて振り分けられるため、最適な人材が迅速に対応でき、顧客の待ち時間を大幅に短縮できます。
また、あらかじめ設定した条件に沿って均等に配分することで、特定のオペレーターに負担が集中することを防ぎ、業務効率と職場環境の改善にもつながるでしょう。
対応履歴を一元管理する「CRM」
CRMは「Customer Relationship Management」の略で、顧客情報や対応履歴などを一元管理するシステムです。
顧客情報が電話番号とひも付いていれば、問い合わせがあった際に、顧客のサービス利用状況や過去の問い合わせ履歴などをスムーズに参照し、状況に応じて対応できます。
また、CRMによって対応状況の管理を行えば、コールセンターでの対応漏れなど、人的なミスを防げるというメリットもあります。
24時間体制が実現する「チャットボット」
チャットボットは、AI(人工知能)を使って自動で会話するツールで、24時間365日、問い合わせに対応できます。タイプは大きく分けて「シナリオ型」と「AI型」の2つです。
シナリオ型は、よくある質問やアンケートなど、あらかじめ決められた流れで答えるのが得意で、導入も比較的簡単です。一方で、AI型はより柔軟で、複雑な質問や会話にも対応できるという特徴があります。
利用が増えるほど学習して回答の精度も上がるため、幅広い問い合わせに対応したい場合に向いています。チャットボットの活用は、コールセンターの24時間対応を無理なく実現する手段の1つです。
▼あわせて読みたい
記録と分析に役立つ「音声認識システム」
音声認識システムとは、顧客とオペレーターの会話内容を自動でテキスト化するツールです。通話中にオペレーターが手入力する必要がなくなるため、会話に集中でき、応対品質の向上にもつながります。
さらに、テキスト化されたデータを分析することで、応対の傾向を把握したり、オペレーターの教育に活用したりすることが可能です。
キーワード検索により、クレームの内容をすばやく把握でき、コンプライアンス違反のチェックにも活用できます。記録と分析の効率化により、業務の改善サイクルをスムーズに回せる点が大きなメリットです。
顧客の自己解決を促す「FAQ」
FAQ(Frequently Asked Questions)は、「よくある質問」をまとめたコンテンツで、顧客が自分で疑問を解決できるようにするための仕組みです。
WebサイトやサポートページにFAQを設けておけば、顧客は問い合わせをする前に自分で情報を探すことができ、電話やメールをする手間が省けます。
顧客側はスムーズに問題を解決でき、コールセンター側も問い合わせ数を減らすことで業務負担の軽減が可能になります。正確でわかりやすいFAQを整備することは、顧客満足度の向上と効率的な運営の両立に大きく貢献するでしょう。
▼あわせて読みたい
コールセンターのDXの進め方

コールセンターではどのようにDXを進めていけばよいのか、成功できる進め方を解説します。DXを成功させるためには、次の4つのステップをクリアすることが必要です。
|
現場が抱える課題を明確化する
最初に、自社のコールセンターの現場では何が問題なのか、課題を明確にすることが大切です。
例えば、コールセンターにありがちな課題は、1件あたりの対応に時間がかかるなど、効率的に対応できていないことです。顧客からの質問に対する適切な回答を見つけられないため、顧客を待たせる時間が長くなる恐れがあります。
対応時間が長くなれば他の顧客は電話がつながりにくくなり、対応率だけでなく、全体的に顧客満足度も低下してしまうでしょう。オペレーターやマネジメント部門など、それぞれの担当ごとに問題点を洗い出していくことが重要です。
業務フローを見直す
コールセンターの課題が明確になったあとは、原因に応じた対処法を検討していきます。業務の一部をデジタル化することで効率化が図れる場合もあるため、どの業務がデジタル化に適しているのかを見極めることが大切です。
また、ツールを導入するだけでなく、運営体制そのものを見直す必要がある場合もあります。業務全体の流れを整理し、どこに無駄や非効率な部分があるのかを洗い出すことで、DXの効果を最大化できる体制づくりにつながるでしょう。
目的に合ったツールを導入する
DXを成功させるためには、目的に合ったツールを導入することが重要です。たとえば、顧客情報の管理にはCRM、対応業務の効率化にはIVRやチャットボットなど、目的に応じて適切なシステムを選びましょう。
ツールを選定するときには、「業務効率の向上」「顧客満足度の向上」「将来的な拡張性」の3点が満たされているかを確認してください。
条件を満たさないツールは、かえってDX推進の妨げになる可能性もあるため注意が必要です。場合によっては、すでに導入しているツールについても改めて見直す必要もあるでしょう。
実行プランを策定し進める
DXツールの導入が決まったら、スムーズに移行できるよう、業務に支障が出ない計画を立てることが重要です。
新しいシステムの導入に伴い、業務フローの見直しが必要になる場合もありますが、その間も対応品質を維持する体制づくりが求められます。
特に、業務プロセスを変更する際には、従業員への丁寧な研修や、新しい運用ルールの整備が不可欠です。無理のないスケジュールで段階的に導入を進め、現場への影響を最小限に抑える実行プランを策定することで、DXを成功に導けるでしょう。
▼コールセンターのDX化に関して、より実践的に解説したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

コールセンターのDX!成功事例2選

実際にコールセンターでDXを行い、成功させた事例を2つ紹介します。どちらもDXによって業務を効率化とオペレーターの負担軽減を実現しながら、顧客満足度の向上にもつなげている点が注目ポイントです。
問い合わせ数を削減しつつ契約数は増加|株式会社きらやか銀行
山形県に本店を置く「きらやか銀行」は、ネットバンキングの利用拡大と顧客の利便性向上を目指してDXの推進に成功しました。以前は口座を開設する際、居住地に制限がありましたが、ネットバンキングの口座開設を全国で可能としたことがDXのきっかけです。
全国から口座開設が可能となったことで、遠方の顧客からの問い合わせが増えることを見越し、FAQシステム「Helpfeel」を導入しました。
これにより、土日や夜間など営業時間外でも顧客が自分で疑問を解決できるようになり、電話での問い合わせ数を大幅に削減できました。業務負担の軽減と同時に契約数の増加にもつながり、DXが成果を生む好事例となっています。
▼事例詳細はこちら
電話応対を96%抑制し少ない担当者で運営が可能に|小田急電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社では、実店舗の「小田急トラベル」で取り扱っていた個人向け旅行商品を、ネット販売に移行するタイミングでDXを進めました。
これまで対面や電話で行っていた予約・購入対応を、顧客自身がウェブサイトやアプリで完結できるようにしたのです。この移行にあわせて導入されたのが、FAQシステムの「Helpfeel」です。
予約方法や商品内容など、顧客が疑問に思う点を自分で調べて解決できる仕組みにより、電話での問い合わせ件数はなんと96%減少しました。
少人数でも対応が可能となり、業務効率が大幅に向上したとのことです。サービス内容の変更による問い合わせ増加にも、自己解決できるシステムが功を奏したといえます。
▼事例詳細はこちら
コールセンターのDXを実現するなら「Helpfeel」がおすすめ
 コールセンターで問い合わせ対応の効率化を目指すなら、FAQの改善が有効です。FAQの導入によってユーザー自身で疑問を迅速に解決でき、顧客満足度の向上につながります。
コールセンターで問い合わせ対応の効率化を目指すなら、FAQの改善が有効です。FAQの導入によってユーザー自身で疑問を迅速に解決でき、顧客満足度の向上につながります。
また、FAQを活用することでカスタマーサポートへの問い合わせ件数が減少し、サポートスタッフの負担軽減や業務の最適化が図れるのも魅力です。FAQの利用状況を分析すると、顧客の潜在ニーズが把握でき、新たな商品やサービスの提案に生かすこともできます。
「Helpfeel」は、独自のAI技術と検索特許技術を備えた検索型AI-FAQシステムです。どのような検索キーワードでも欲しい回答に導いて自己解決を促すため、個別の問い合わせ件数の削減が実現できます。
導入前後のサポートも充実しているため、初めてFAQ改善を行う方にもおすすめです。コールセンターのDXを推進したい方は、ぜひHelpfeelの導入を検討してみてください。
まとめ:コールセンターのDXを図りましょう
 コールセンターのDXは、業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上やオペレーターの働きやすさにもつながる重要な取り組みです。FAQやチャットボット、音声認識などのツールを活用すれば、24時間いつでも顧客が自己解決できる環境が整い、対応件数の削減や待ち時間の短縮が期待できます。
コールセンターのDXは、業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上やオペレーターの働きやすさにもつながる重要な取り組みです。FAQやチャットボット、音声認識などのツールを活用すれば、24時間いつでも顧客が自己解決できる環境が整い、対応件数の削減や待ち時間の短縮が期待できます。
また、業務フローの見直しやツールの適切な導入により、限られた人材でも安定した運営が可能になります。この記事を参考に、自社に合ったDXの進め方を検討し、より良いコールセンター運営を目指しましょう。


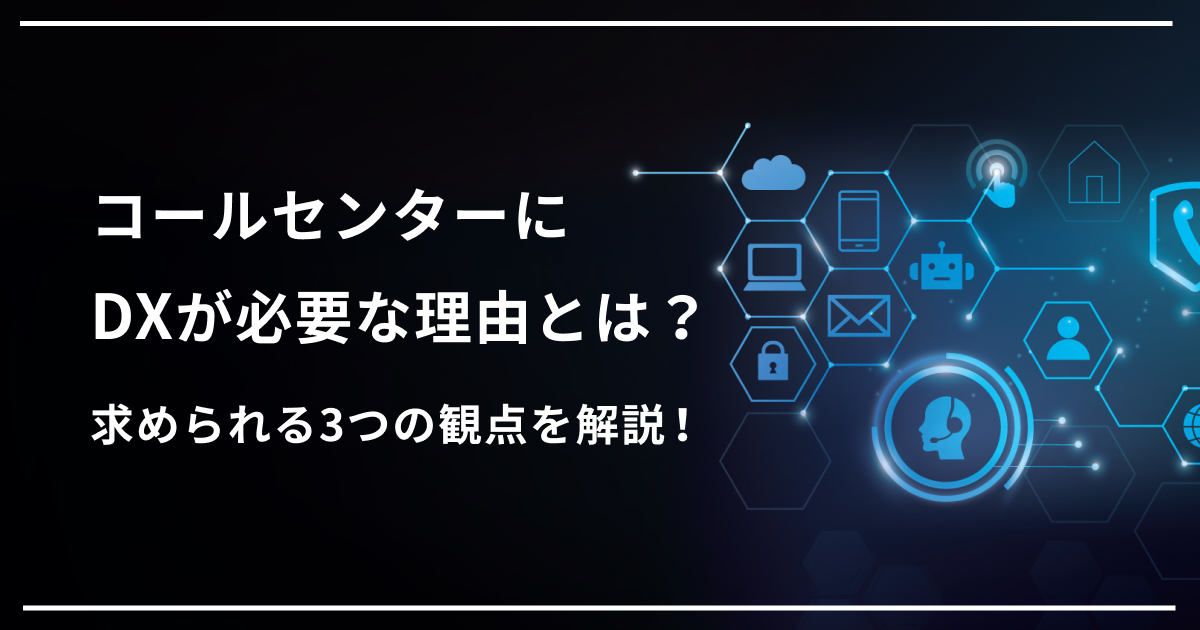
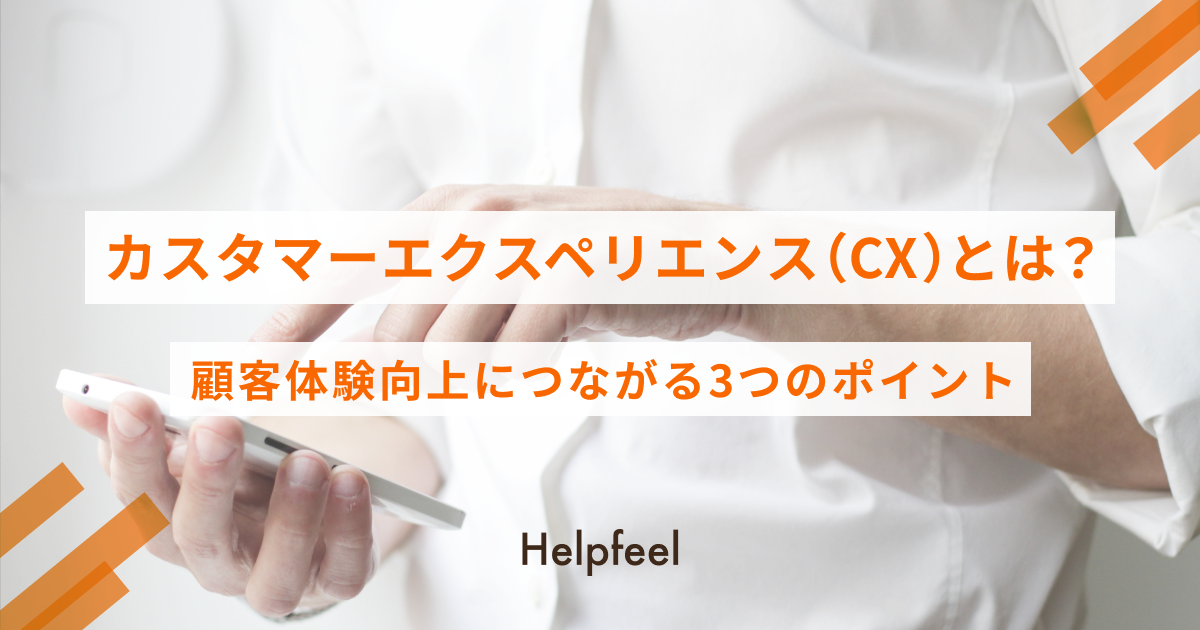

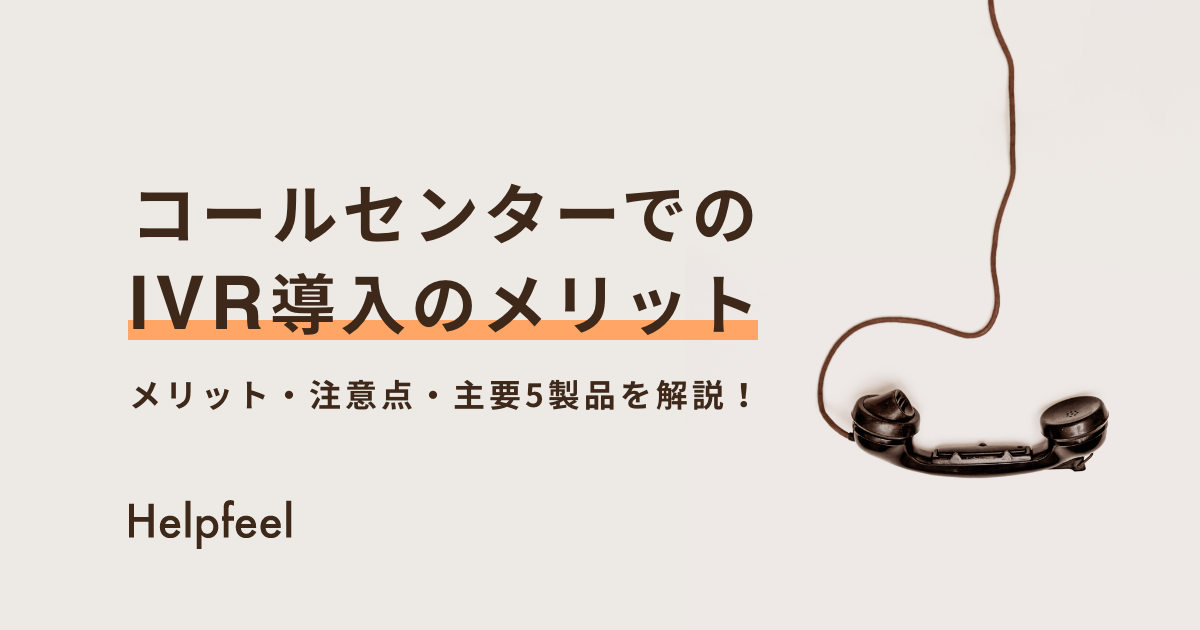
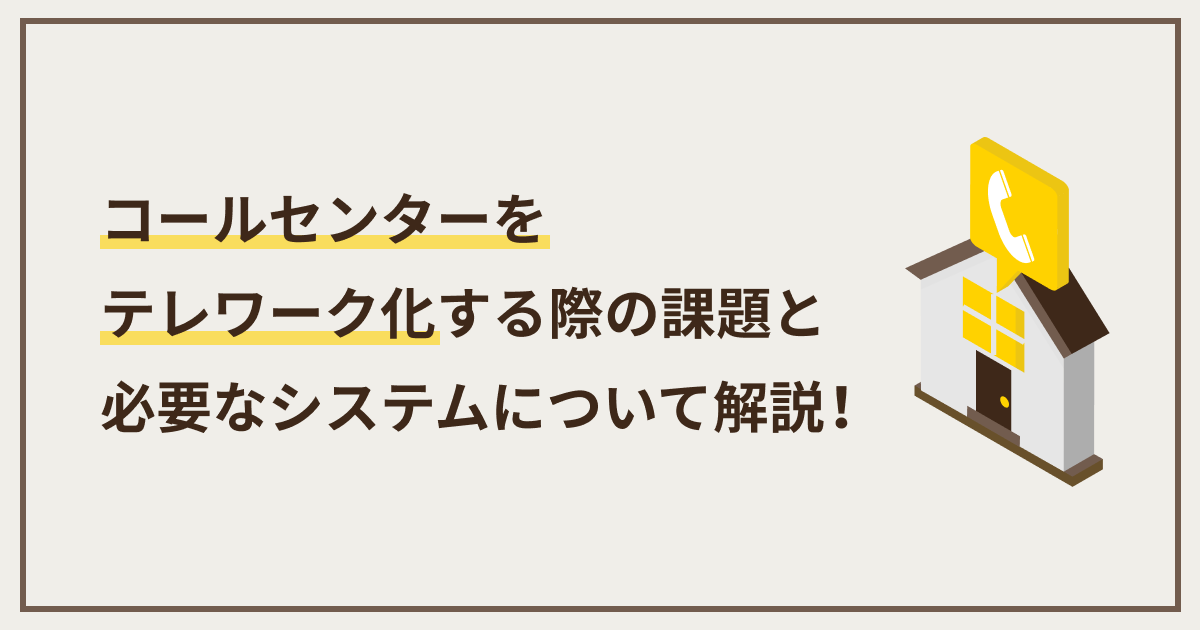








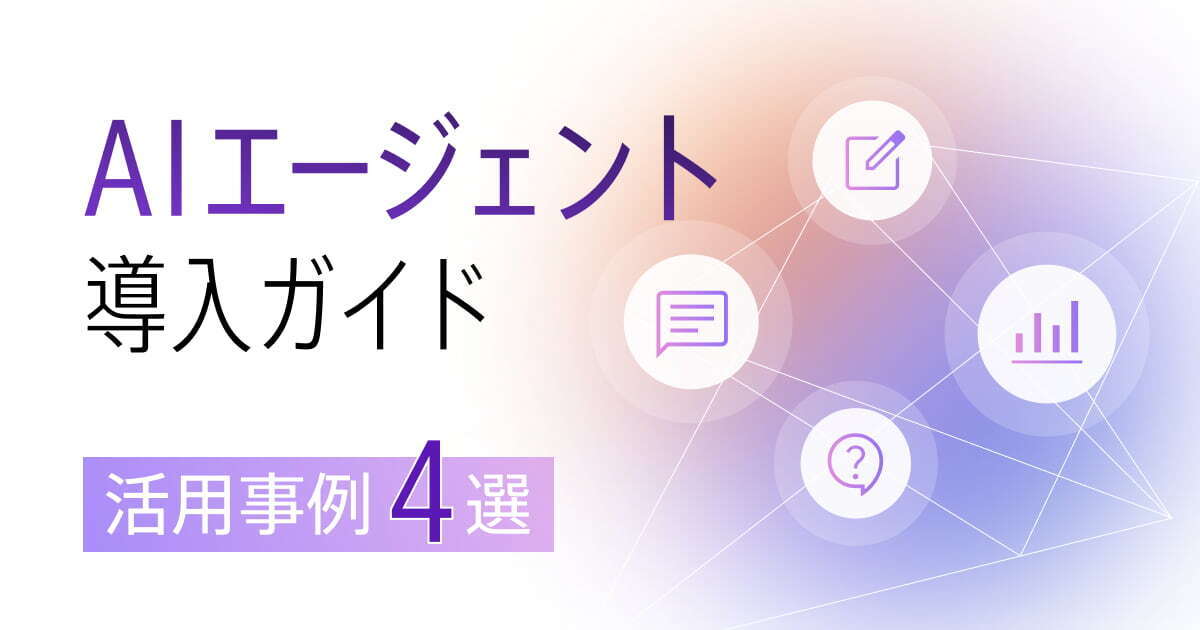


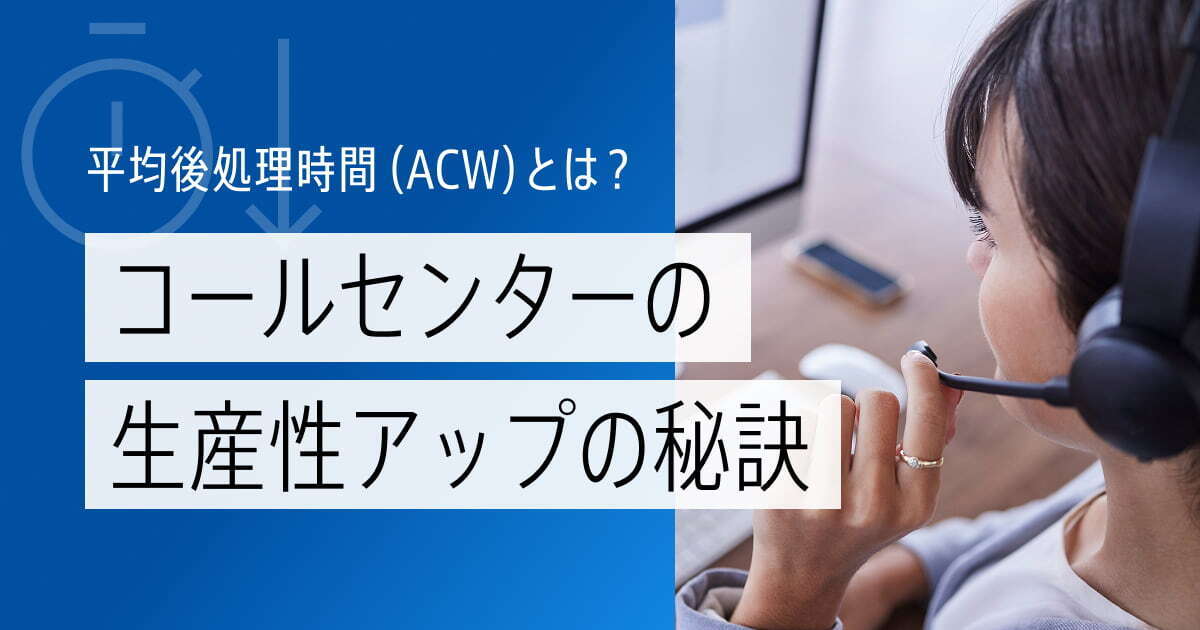
.png)