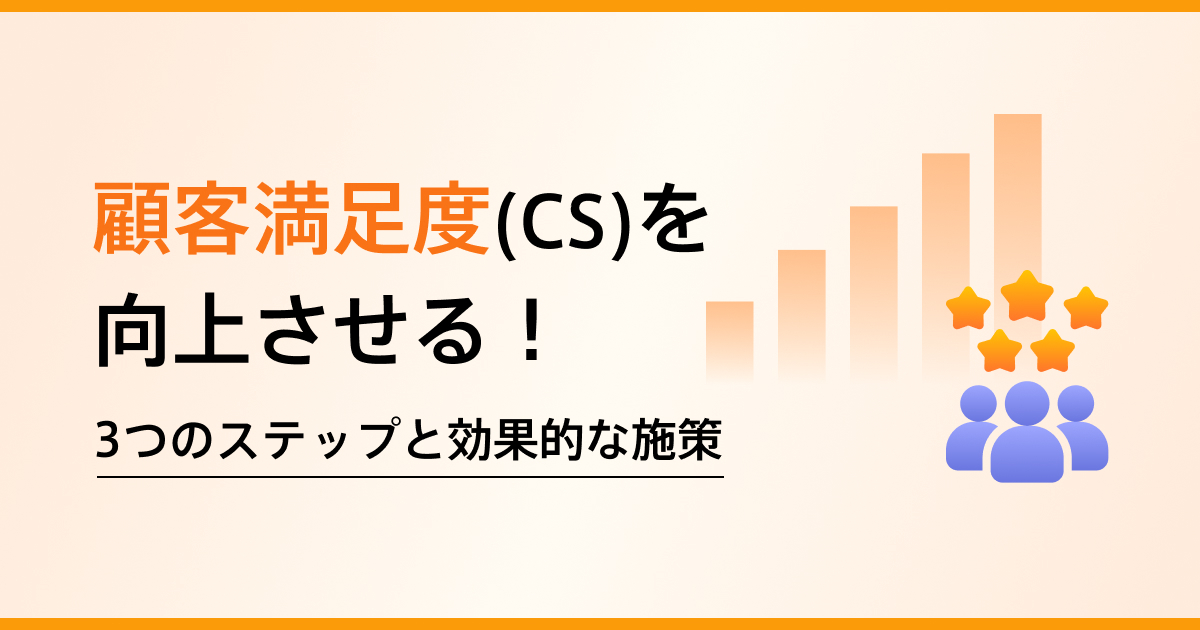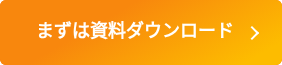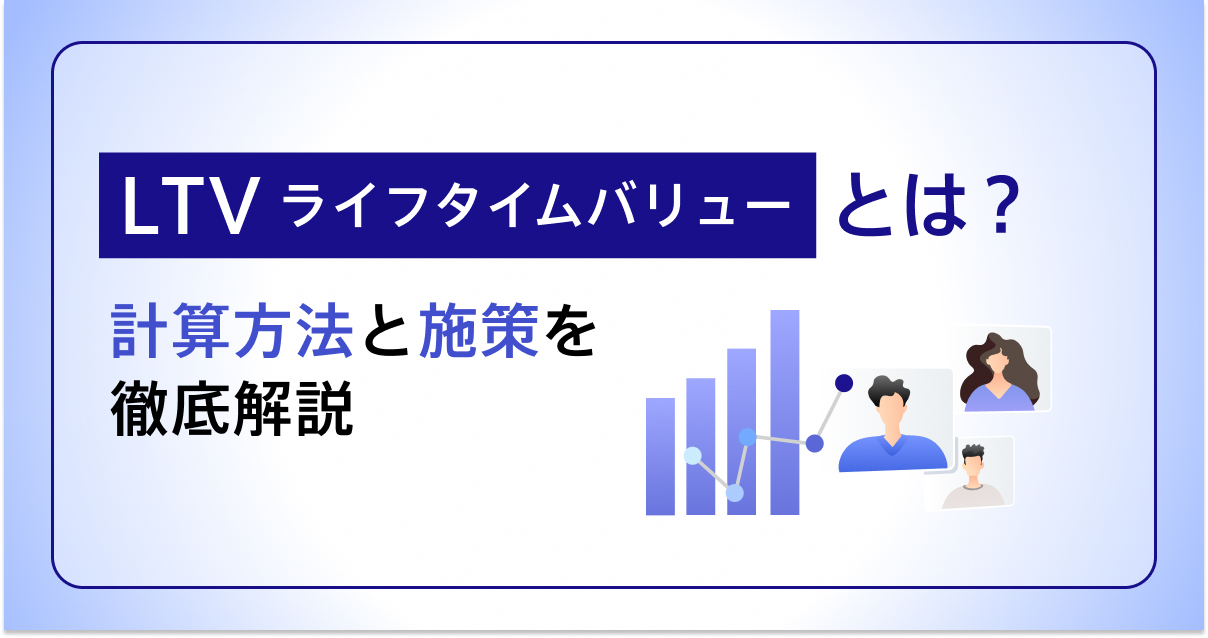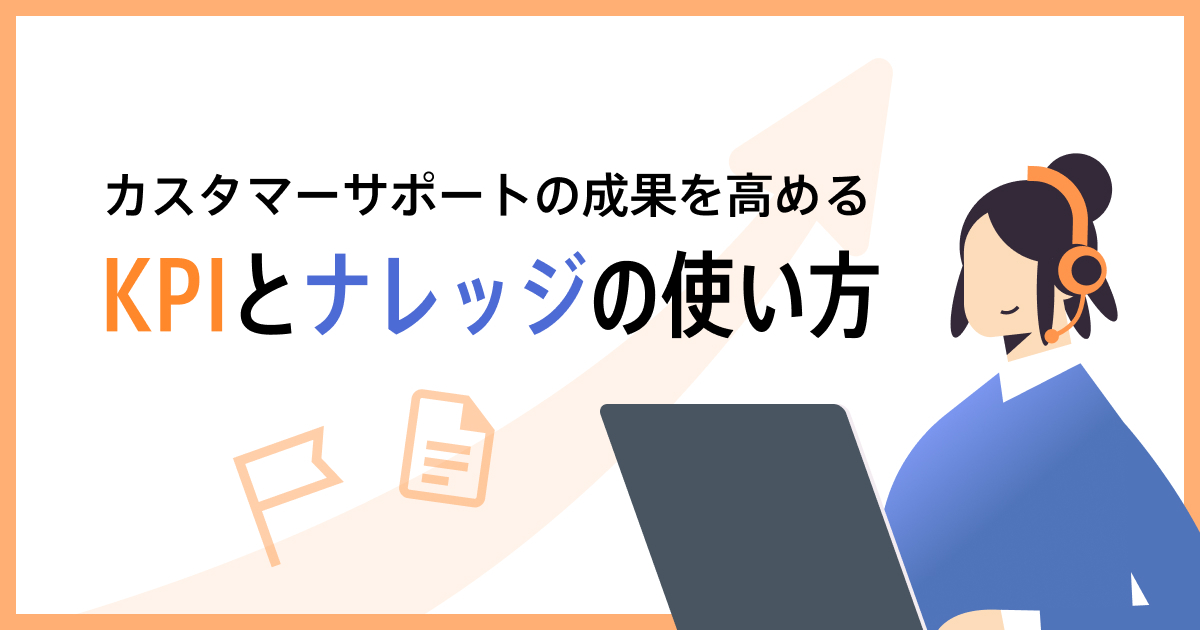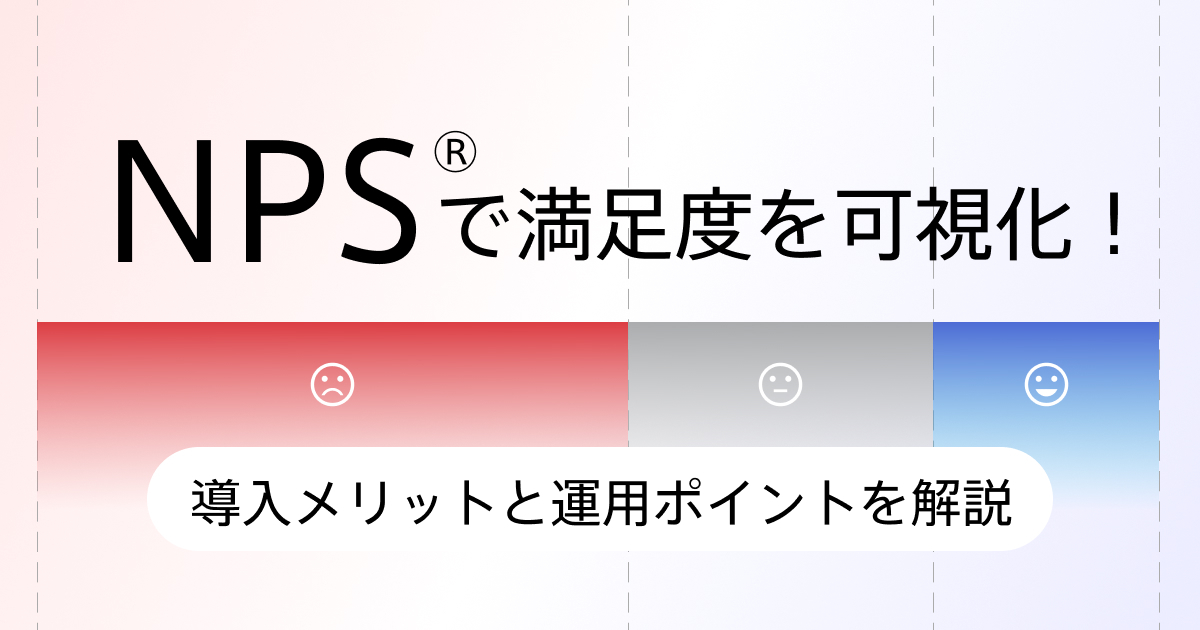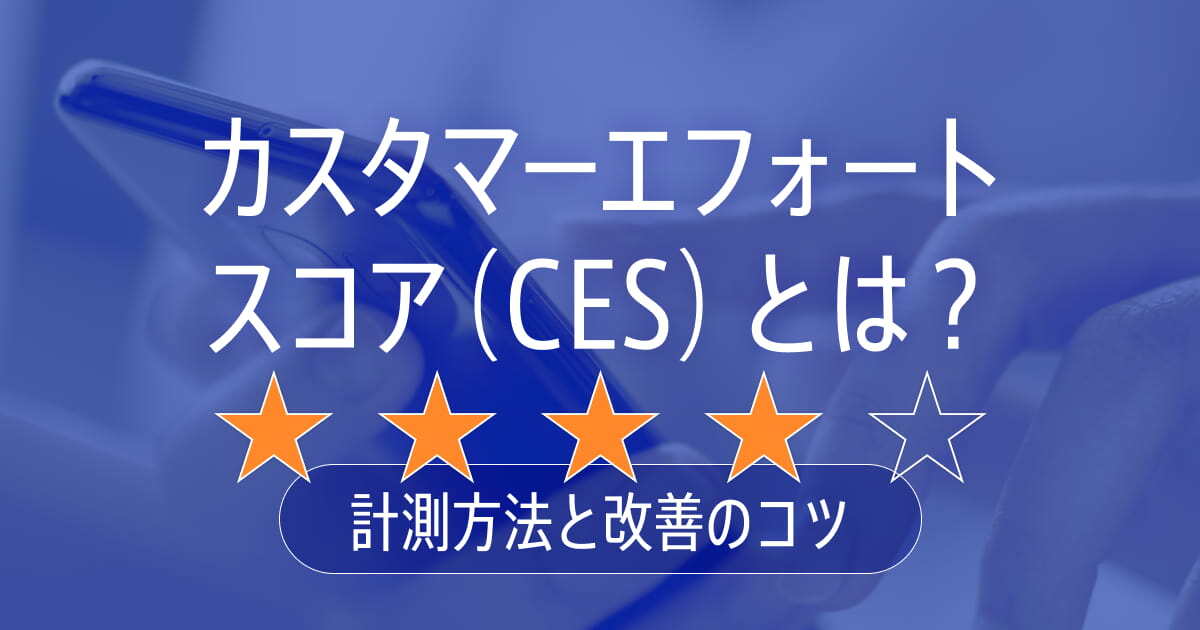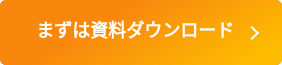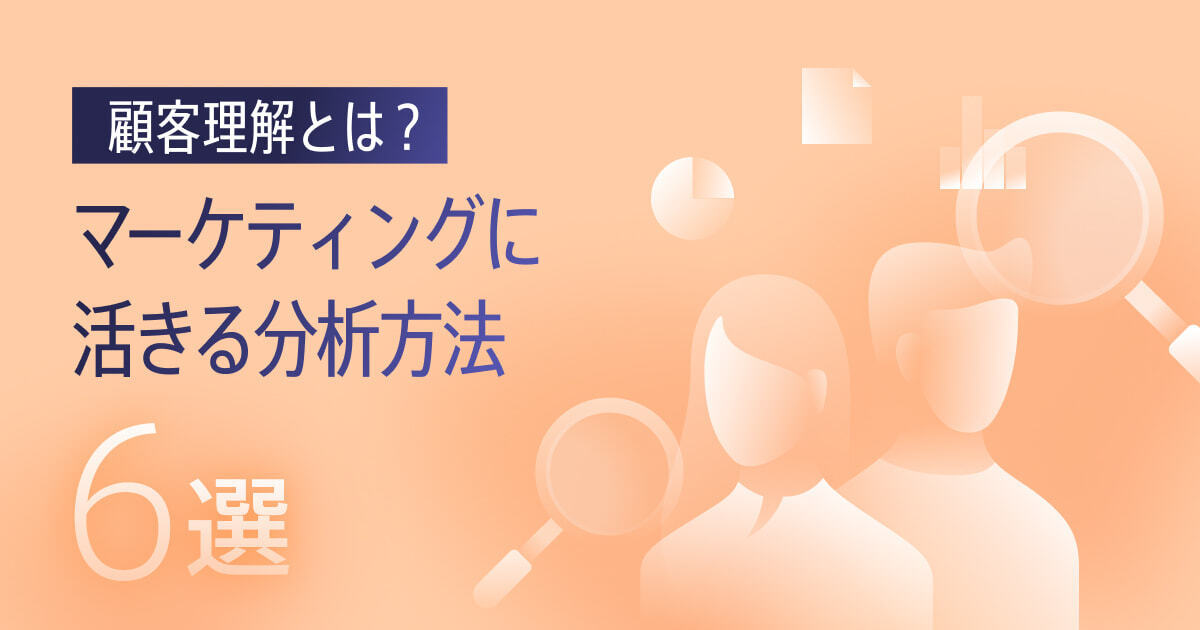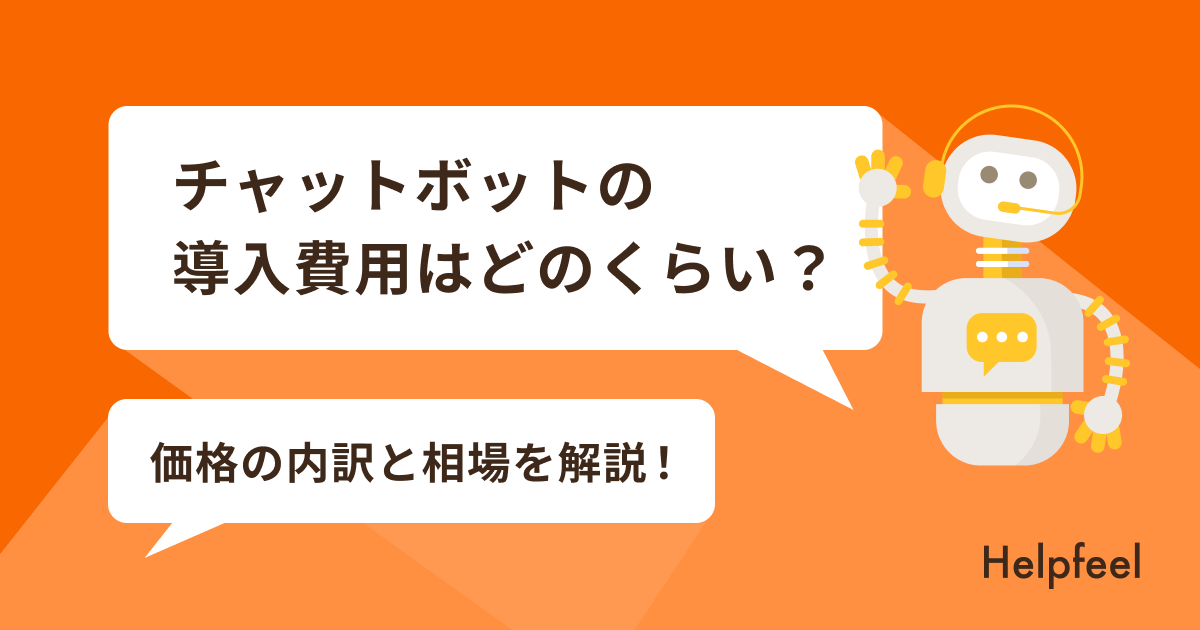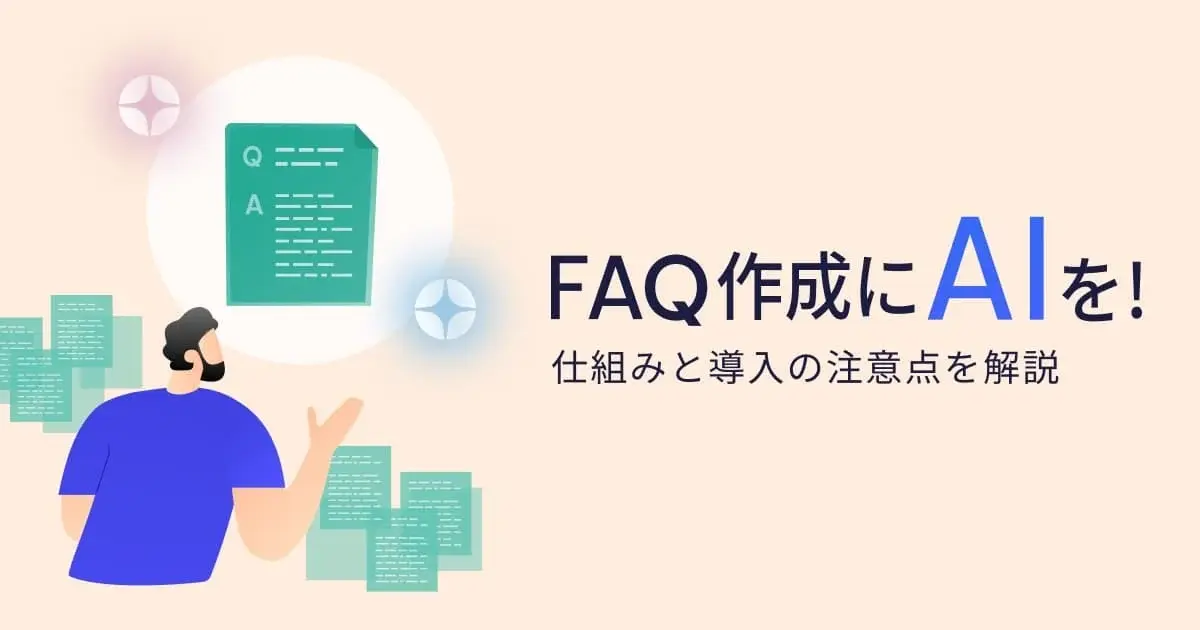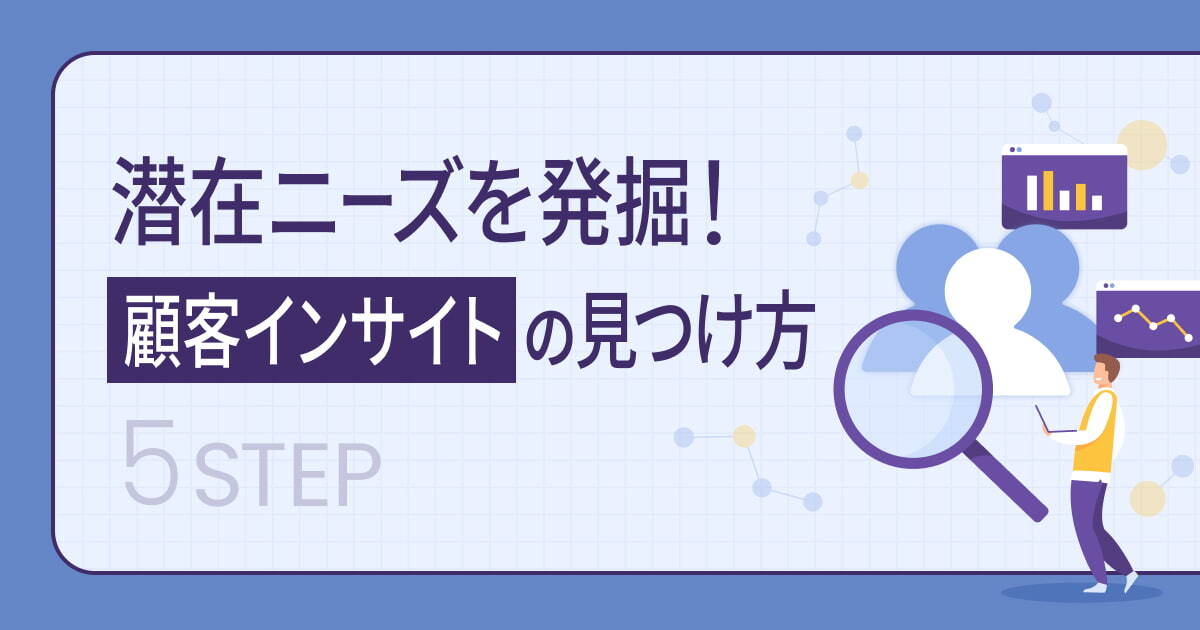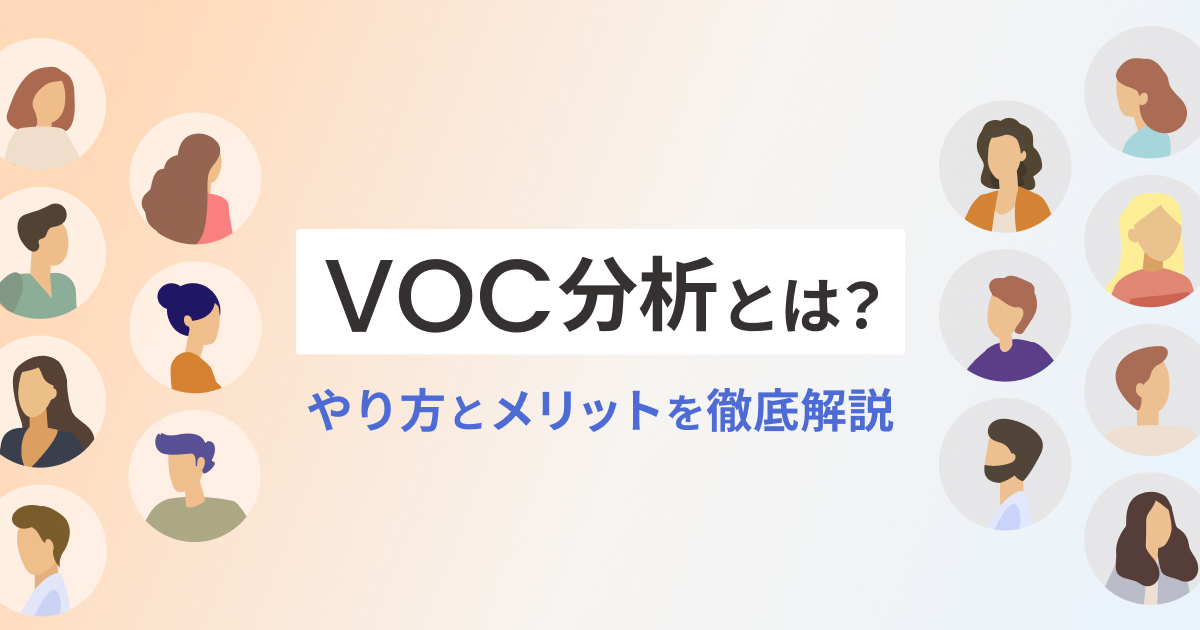顧客ロイヤルティとは?

顧客ロイヤルティとは、お客さまが企業やブランドの商品やサービスに対して感じる「好き」という気持ちや「信頼感」のことです。顧客ロイヤルティが高いお客さまは、企業やブランドのファンになり、繰り返し利用してくれる傾向があります。
例えば、「いつもこのお店で買い物する」「この商品を友人に勧めたい」といった行動を取るお客さまを「ロイヤルカスタマー」と呼びます。ロイヤルカスタマーは、競合他社の商品に目移りしにくく、好意的な口コミを通して新しいお客さまを連れてきてくれる可能性もあります。

顧客ロイヤルティと顧客満足度の違いとは?

顧客ロイヤルティと顧客満足度は似た言葉ですが、意味が異なります。
|
「商品やサービスを使って満足したかどうか」を表す指標で、一度の取引や体験に基づくもの |
|
「この企業やブランドをこれからも使い続けたい」と感じる気持ちを指し、長期的な関係性を重視する |
例えば、ある商品に満足しても、次回は別の企業の商品を選ぶことがあります。この場合、顧客満足度は高いですが、顧客ロイヤルティは低いといえます。
一方、顧客ロイヤルティが高いお客さまは、どの選択肢があっても同じ企業やブランドを選び続ける傾向があります。
▼あわせて読みたい
顧客ロイヤルティが注目される背景

顧客ロイヤルティが注目される背景には、消費者行動の変化があります。従来の消費者は商品自体に価値を感じる傾向があったため、マーケティング業界では顧客満足度が重視されていました。しかし、現代の消費者は「モノ消費」から「コト消費」へと移行しています。
「モノ消費」と「コト消費」とは
モノ消費とは、商品の購入で得られる満足感を重視する消費形態です。一方で、コト消費は感情的な価値を重視し、体験を求める消費形態を指します。コト消費に移行した現代は、体験が消費者行動に大きな影響を与えるといえるでしょう。
例えば、商品自体の顧客満足度が高くても、サポート体制に不満を感じた場合、次の購入は控えられるかもしれません。そのため、商品の質だけでなく、体験を通じて信頼や愛着を抱いてもらうことに重点を置いた顧客ロイヤルティの重要性が高まっているのです。
▼顧客が求める情報を正確に把握することが、顧客ロイヤルティ向上の第一歩です。Helpfeelなら、そのインサイトをマーケティングに活かせます。
顧客ロイヤルティの向上によるメリット

顧客ロイヤルティの向上によるメリットは、3つあります。
|
それぞれのメリットを確認し、マーケティングに生かしてください。
リピート率の向上
顧客ロイヤルティが向上すると、リピート率も上がりやすくなります。特に、頻繁に使用する消耗品は、同じ商品をリピートしてもらうことが多くなるでしょう。
例えば、他社から同じ分野の魅力的な新商品が登場したとしても、顧客ロイヤルティが高ければ「いつも使っている企業の方が信頼できる」という理由で、自社商品を継続購入してもらえる可能性が高まります。
また、サブスクリプションサービスや会員サービスなどの場合は、更新時期の解約率低下を期待できます。自社が提供するサービスに信頼と愛着を持ってもらうことで、他社サービスへの乗り換えを防げるでしょう。
顧客単価の向上
顧客単価の向上に影響を与えることも、顧客ロイヤルティ向上のメリットです。
例えば、お客さまが特定のブランドのファンになった場合、以前購入した商品より高価格帯の商品を購入してもらいやすくなります。さらに、同じブランドの関連商品を複数購入したり、購入頻度が増えたりすることも期待できるでしょう。
1回あたりの購入単価だけでなく、購入頻度も高くなることで、年間の顧客LTV(ライフタイムバリュー)が増加します。ブランドに止まらず、企業自体のファンになってもらえれば、同一の企業が運営する他ブランドの商品にも関心を持ってもらえるかもしれません。
▼あわせて読みたい
口コミ効果
顧客ロイヤルティが高いと「自分の好きな商品を他の人にも知ってもらいたい」という思いから、好意的な口コミが拡散されやすくなります。
例えば、SNSでブランドや商品の魅力を発信したり、購入を迷っている人に対して「このブランドなら信頼できる」と後押しするような声をかけたり、といった行動が期待できるでしょう。
高評価の口コミが拡散されると、それを見た人の興味や信頼感が高まり、新規顧客を獲得しやすくなります。新規顧客の獲得は、既存顧客の維持よりコストがかかる場合がほとんどです。
口コミ効果で新規顧客を得られる状態を作ることができれば、マーケティングコストの削減につながります。
▼あわせて読みたい
顧客ロイヤルティを向上させる方法

顧客ロイヤルティを向上させる3つのステップは、以下の通りです。
|
それぞれのステップを確認し、顧客ロイヤルティの向上を目指してください。
STEP1:顧客ロイヤルティの数値化
まずは、現状を把握するために顧客ロイヤルティを数値化します。顧客ロイヤルティは心理的な問題のため、数値とは関係ないと思う場合もあるかもしれません。しかし、顧客ロイヤルティを数値化することで、客観的な視点から対応策を考えられるようになります。
数値化には、以下のようなデータの収集・整理が必要です。
|
顧客ロイヤルティを数値化するための具体的な指標は後述の見出し「顧客ロイヤルティを測定するには?主要な指標と分析方法を解説」で解説しているため、参考にしてください。
STEP2:KPI設定と分析
次に、数値化した顧客ロイヤルティを収益指標と掛け合わせながら分析します。顧客ロイヤルティの向上が収益アップにつながる理由は、企業のビジネススタイルによって異なります。
そのため「顧客ロイヤルティのどういった要素が収益に結びつくのか」「収益へのインパクトが大きい顧客群にはどのような要素があるか」などを分析して割り出すことが大切です。
また、分析結果を踏まえて「KPI(重要業績評価指標)」を設定する必要があります。KPIとは中間目標であり、ゴールを達成するまでのプロセスを可視化した目標数値です。顧客ロイヤルティを向上させるため、優先的に改善すべき目標を設定しましょう。
▼あわせて読みたい
STEP3:顧客ロイヤルティ向上施策の実施
目標を達成するために必要な施策を検討・実施します。顧客ロイヤルティを向上させるためのポイントは、「カスタマーエクスペリエンス(顧客体験)」の改善です。
カスタマーエクスペリエンスとは、お客さまがブランドや商品に接する際の体験を指します。商品の利用体験だけでなく、カスタマーサポートの対応や店頭での接客態度、広告のイメージ、企業SNSの投稿など、さまざまな接点も含むのが特徴です。
カスタマーエクスペリエンスを改善するための施策を実施し、問題点を洗い出すことで、顧客ロイヤルティの向上につながるでしょう。
▼800サイト以上を支援してきたHelpfeelのカスタマーエクスペリエンス改善ノウハウを、無料で公開中。顧客ロイヤルティ向上にお役立てください。
.webp)
顧客ロイヤルティを測定するには?主要な指標と分析方法を解説

顧客ロイヤルティを高めるためには、現状を正確に把握することが重要です。この章では、顧客ロイヤルティを測定するための代表的な4つの指標について解説します。
NPS®︎(ネットプロモータースコア)
NPS®︎(ネットプロモータースコア)とは、顧客ロイヤルティを測定するための指標です。お客さまが商品やブランドに抱いている愛着や信頼を数値化することで、顧客評価を可視化できます。
NPS®︎を計算するためには、アンケートを実施するのが基本です。「該当商品を友人に勧める可能性はどのくらいですか?」という質問に対して0〜10点で評価してもらい、回答を以下の点数ごとに分類します。
|
9~10点 |
|
7~8点 |
|
0~6点 |
次に、以下の計算式でNPS®︎を算出します。
|
NPS®︎の点数範囲は−100~100で、数値が高い場合は「口コミの拡散」「顧客の紹介」などを期待できます。
▼あわせて読みたい
注:ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標、またはサービスマークです。
NRS(ネットリピータースコア)
NRS(ネットリピータースコア)とは、継続利用の意思を数値化した指標です。
上記で解説したNPS®︎と同様にアンケートを実施し、「1年後も継続してこの商品を使っていると思いますか?」という質問に1〜5点で回答してもらいます。次に、回答結果を以下のように分類してください。
|
5点 |
|
4点 |
|
1~3点 |
NRSは、以下の計算式で算出できます。
|
NRSの数値が高い場合は「顧客単価アップ」「リピート購入率」などを期待できます。NPS®︎とは効果が異なるため、NPS®︎とNRSを掛け合わせて調査した方が、顧客評価の実態を把握しやすいでしょう。
CES(カスタマーエフォートスコア)
CES(カスタマーエフォートスコア)とは、顧客が商品を利用する際の手間や時間の程度を表す指標です。
利用シーンとしては、カスタマーサポートへの問い合わせやECサイトの購入手続きなどが挙げられます。CESが高いほど、顧客に手間や時間をかけさせていることになり、顧客ロイヤルティが低下する原因になるでしょう。
CESを測定する際は「商品を使うときにストレスを感じましたか?」という質問に1〜7点で回答してもらい、結果を下記のように分類していきます。
|
1~2点(手間が少ない) |
|
5〜7点(手間が大きい) |
次に、以下の計算式でCESを算出します。
|
▼あわせて読みたい
LTV(ライフタイムバリュー)
LTV(ライフタイムバリュー)とは、1人の顧客が生涯を通じて自社にもたらす利益を示す指標です。感情面は含まれないため、行動面で顧客ロイヤルティを把握したい場合に役立ちます。
LTVを計算すれば、長期的な利益を測れるのに加え、既存顧客の維持や新規顧客の獲得などに投資できる範囲も明確にできるでしょう。LTVの計算方法には複数の種類があるため、自社の業態や規模に合うものを選んでください。
◼️ 代表的なLTVの計算方法
|
▼あわせて読みたい
顧客ロイヤルティが向上した成功事例

ここでは、3つの成功事例を紹介します。
|
具体的な事例を確認し、施策を検討する際の参考にしてください。
楽天モバイル
楽天モバイル株式会社は、お客さまからの声をサービスに反映し、ネットワーク品質の継続的な改善やサービスの拡充などを実施しています。
その結果、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会が発表した「2024年度 JCSI(日本版顧客満足度指数)第1回調査」で、携帯電話の大手キャリア(メインブランド、サブブランド)部門の顧客満足度を表す6指標のうち、4項目で第1位を獲得しました。
楽天モバイルが1位を獲得した指標は「顧客期待」「知覚価値」「顧客満足」「ロイヤルティ」で、顧客から高い評価を得ていることがわかります。また、該当企業・ブランドを利用した際に驚くような経験や感動をした度合いを表す「感動指標」でも第1位に輝いています。
参考:https://corp.mobile.rakuten.co.jp/news/press/2024/0730_02/
ソニー生命
ソニー生命保険株式会社は、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が実施した調査で、対象の生命保険会社12社のうち、最もNPS®︎が高い企業として評価されました。(※本調査は、保険金・給付金の請求体験に焦点を当てたものです。)
ソニー生命では、契約者を対象とした「お客さまアンケート」を年に1回実施し、企業としての信頼性と姿勢、保険商品と保障内容、営業担当者などについてのリアルな声を集めています。
担当ライフプランナーに関するアンケートも行い、満足度の高いコンサルティングフォロー態勢の実現を目指しているのもポイントです。また、カスタマーセンターに寄せられた要望を関係部署や担当者へ迅速に伝達し、スピーディーな顧客対応を推進しています。
参考:https://www.sonylife.co.jp/company/cs/collection.html
野村不動産
野村不動産株式会社は、新築マンション購入者が選ぶ顧客満足度調査「SUUMO AWARD 2025」で最優秀賞を獲得しました。首都圏版・関西版を合わせて、最多項目となる16部門を受賞しています。
例えば、ハイブランド部門の受賞につながった取り組みとしては、高額物件のニーズやトレンドを収集・分析し、商品企画に反映したことが挙げられています。アフター点検満足度部門では、アンケートをもとに施工会社との意見交換会や振り返りミーティングを実施し、お客さまの声を改善に生かした点などが評価されました。
また、お客さま一人ひとりの時間や生活に寄り添うことを重視し、商品企画から品質管理、営業、用地取得まで密に連携し合いながら住まいの価値を高めていることも、受賞のポイントとされています。
参考:https://www.nomura-re-hd.co.jp/chtml/news/6275.html
FAQの改善が顧客ロイヤルティ向上に繋がる?
FAQは、お客さまの疑問を解決するための重要なツールです。充実したFAQを提供することで、顧客体験を向上させ、顧客ロイヤルティを高めることができます。
FAQが顧客体験に与える影響とは?
FAQを使いやすく整備することで、お客さまは疑問が生じた際にわざわざ問い合わせることなく、自分で疑問をすぐに解決できます。これにより、ストレスなく商品やサービスを利用でき、企業への信頼感の向上や、顧客ロイヤルティの向上につながります。
FAQを改善し、顧客ロイヤルティ向上を実現させよう
ただFAQを設置しただけでは、顧客ロイヤルティの向上は実現できません。FAQはあるものの、よくある質問に対する答えが用意されていなかったり、回答があっても検索ヒットせずに、結局自力で解決できないというシーンは良くあります。
「Helpfeel」は、画期的な検索技術とAIを活用して、お客さまが求める回答を瞬時に提示するAI-FAQシステムです。これを導入することで、FAQの質を向上させ、顧客満足度や顧客ロイヤルティを高められます。
「FAQの改善を通じて顧客満足度や顧客ロイヤルティを高めていきたい」という方は、ぜひ一度Helpfeelのサービス資料をご覧ください。
▼検索型FAQシステム「Helpfeel」サービス資料はこちら