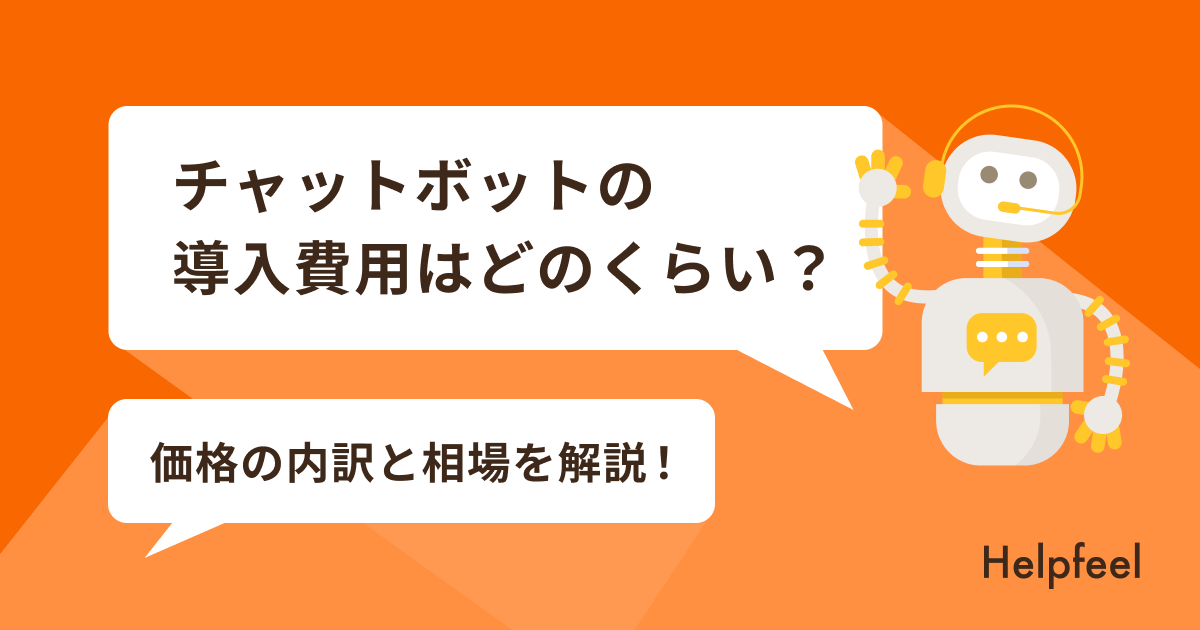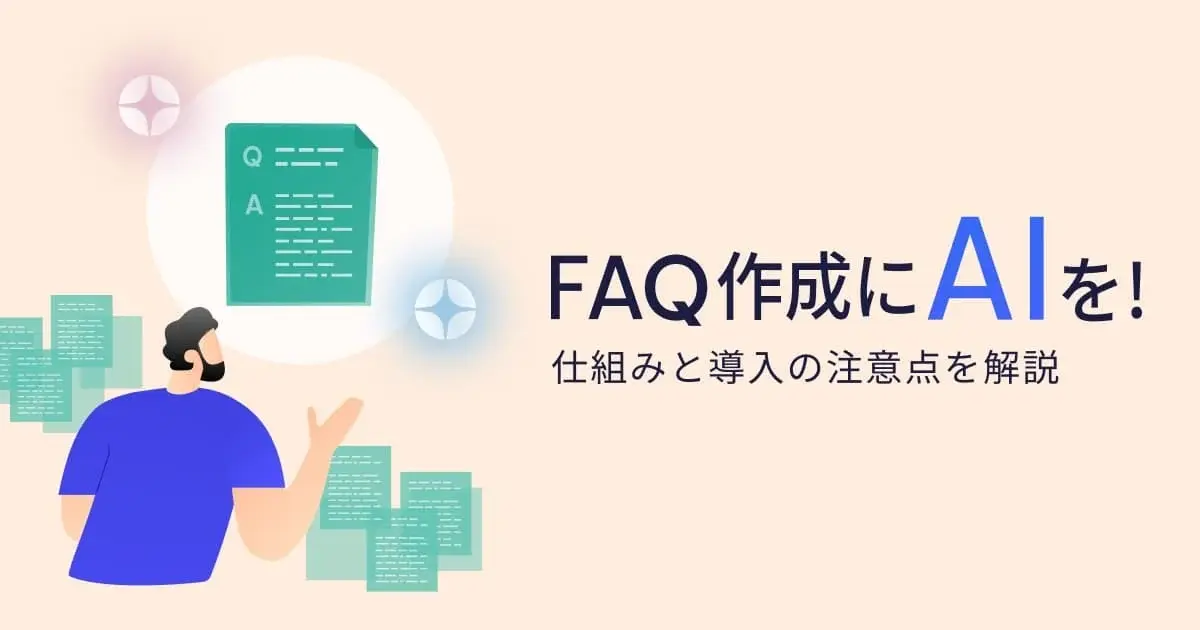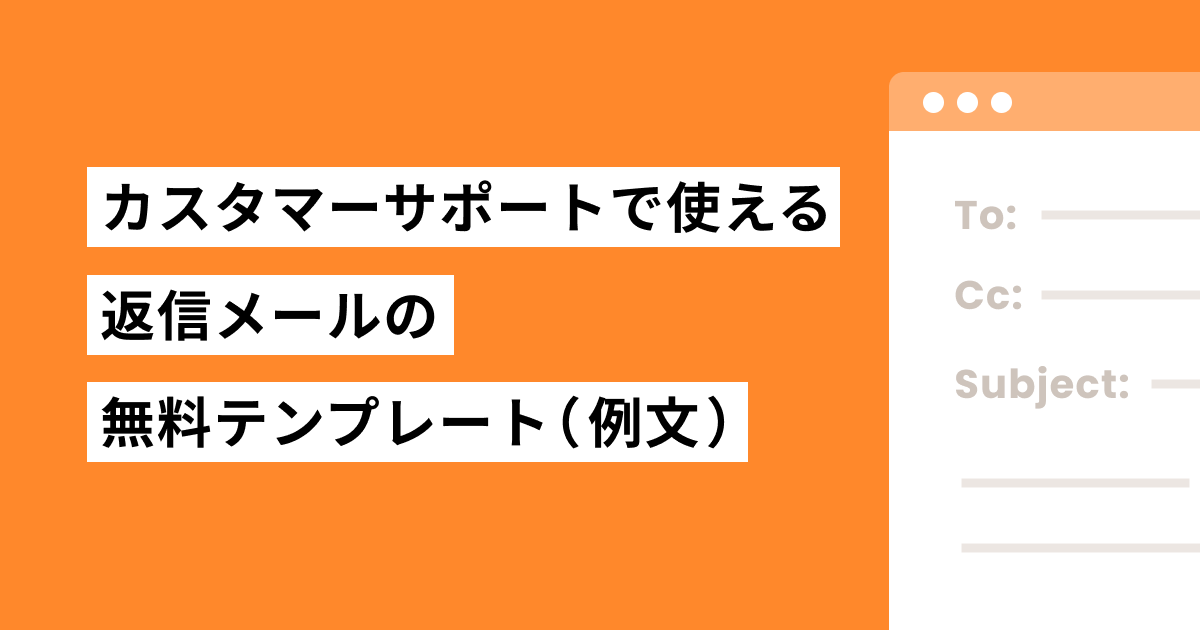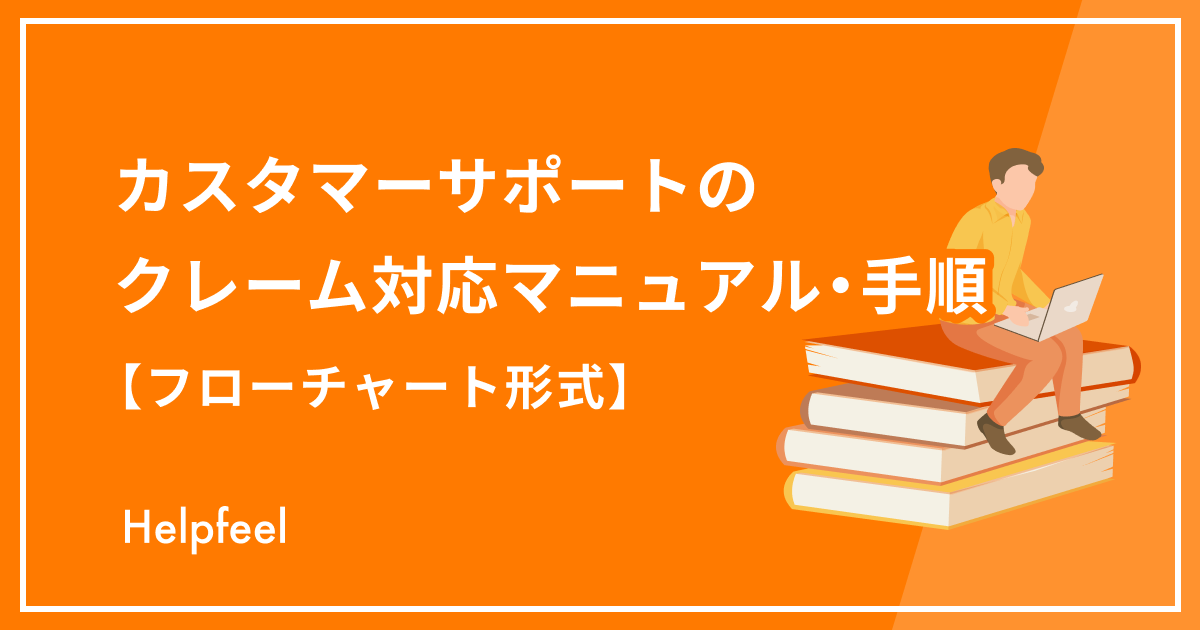カスタマーサポートKPIとは?定義と重要性を解説
カスタマーサポートの活動成果を測定し、より良いサービス提供体制を構築するためには、具体的な指標が不可欠です。
ここでは「カスタマーサポートKPI」に焦点を当て、そもそもKPIとは何か、なぜカスタマーサポートで設定が重要なのか、そして最終的な目標(KGI)との関係性について解説します。
なお、カスタマーサポートの基本的な役割や重要性は下記で解説していますので併せてご覧ください。
KPIの基本的な定義と役割
KPIとは「Key Performance Indicator」の頭文字をとった略称で、日本語では「重要業績評価指標」と呼ばれます。これは、組織が設定した最終的な目標(KGI)に到達するまでの過程で、その達成度合いを評価するための中間指標です。
カスタマーサポートという領域においては、顧客対応の品質向上や効率化など、設定した目標がどれだけ達成されているかを客観的に測るために用いられます。
例えば、下記のような項目を数値化して捉え、パフォーマンスの評価指標とします。
|
複数の測定可能な指標を設定することで、現状を正確に把握し、改善の方向性を定めることが可能になります。
カスタマーサポートでKPI設定が重要視される理由
カスタマーサポート部門でKPIを設定することには多くのメリットがあります。まず、成果を客観的に評価できるため、担当者やチーム全体の強みや弱みを明確に把握できます。これにより課題を特定し、解決に向けた対策を講じやすくなります。
また、KPIという具体的な数値目標をチーム全体で共有することで、「何を達成すべきか」が明確になり、メンバーの行動指針が定まります。目標に向かう共通認識が生まれ、モチベーションの維持・向上にも繋がります。
目標が未達の場合も、複数のKPIを分析することで、どこに問題があったのか原因を探ることができます。分析をもとに改善策を実行し、効果を測定するというPDCAサイクルを回すことで、継続的なサービス品質の向上や効率化を実現できます。
KPI設定はカスタマーサポート全体のマネジメントにおいても重要な役割を果たし、パフォーマンスの底上げに貢献します。
KGIとKPIの関係性
KGI(Key Goal Indicator:重要達成目標指標)は、企業や組織が最終的に達成したいゴールのことです。一方KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、KGIを達成するために、日々の活動や中間段階の成果を測るための指標です。
つまり、KPIはKGI達成のための「道標」や「マイルストーン」のような役割を担います。KPIは、KGIからブレイクダウンして設定されます。
例えば「事業全体の売上を〇%向上させる」といったKGIに対し、カスタマーサポート部門が「顧客満足度を〇%向上させることで顧客離脱を防ぎ、リピート率を向上させる」という目標を設定したとします。この目標を達成するために、KPIとして「初回解決率を〇%にする」「平均応答時間を〇分以内にする」といった具体的な指標を設定します。
このように、KGIから順にブレイクダウンしてKPIを設定することで、個々のKPIが最終的な経営目標とどのように繋がっているかが明確になり、チームの努力が全体の成果に貢献するという意識を持つことができます。
KGIを基準に現実的で達成可能なKPIを設定することが、チームのモチベーションを保ちながら目標達成を目指す上で非常に重要です。
▼本記事に関連したお役立ち資料をご用意していますので、併せてご覧ください。

カスタマーサポートで重視すべきKPI指標一覧

カスタマーサポートのパフォーマンスを評価するために様々なKPIが存在します。これらの指標は、サポートの質、効率性、そして顧客体験など、多角的な視点から現状を把握するために役立ちます。
ここでは、多くの企業で重視されている主要なKPI指標について、内容と重要性を解説します。
顧客満足度に関するKPI
顧客満足度を重点に置く場合によく設定するKPI指標は下記の4点が挙げられます。
1. 顧客満足度や顧客体験(CX)
顧客満足度や顧客体験(CX)はカスタマーサポートの成果を示す重要な指標のひとつです。サポートを通じて顧客がどのような感情を抱いたかは、その後の顧客ロイヤルティや企業の評判に大きく影響します。
▼あわせて読みたい
2. 顧客満足度スコア(CSAT)
顧客満足度スコア(CSAT)は特定のサポート体験に対する顧客の満足度を直接的に測定する指標です。「ありがとう」といった感謝の言葉の数も質的な満足度を示す要素になります。通常はアンケート形式で収集されます。
3. ネットプロモータースコア(NPS®)
ネットプロモータースコア(NPS®)は顧客がそのサービスやブランドを友人や同僚にどの程度勧めたいかを測る指標であり、顧客ロイヤルティや将来の事業成長予測に用いられます。批判者、中立者、推奨者に分類して算出します。
▼あわせて読みたい
4. カスタマーエフォートスコア(CES)
カスタマーエフォートスコア(CES)は顧客体験の測定に用いられ、問題解決などに要した顧客の労力を測る指標です。
▼あわせて読みたい
これらの指標は、顧客の感情や意見といった定性的な要素を数値化するものや、顧客体験の容易さを測る指標であり、サポート対応の質を評価し、改善点を見つけるために非常に有効です。
▼800サイト以上を支援してきたHelpfeelの顧客満足向上ノウハウを、無料で公開中。
カスタマーサポート部門の業務改善・満足度向上に、ぜひお役立てください。
.webp)
業務効率に関するKPI
カスタマーサポートの業務効率を重点に置く場合によく見ておきたい指標は下記の7点が挙げられます。
1. 一次応答時間(FRT)
一次応答時間(FRT)は顧客が問い合わせを行ってから、サポート担当者による最初の応答があるまでの時間を測定します。この時間は、サポート担当者が問い合わせ量を捌く能力を示す指標となり、多くの企業でSLA(サービスレベルアグリーメント)として目標値を定めています。
2. 平均処理時間(AHT)
平均処理時間(AHT)は、1件の問い合わせ対応を開始してから完了するまでにかかる平均時間です。これは、担当者の効率性や問い合わせ内容の複雑さを示す指標となります。ただし、AHTが短すぎると問題解決が不十分になり、顧客満足度が低下する可能性があるため、他の指標とバランスを見て評価することが重要です。
▼あわせて読みたい
3. サービスレベル(SL)
サービスレベル(SL)は、設定した応答時間内に対応できたコールの割合を示す指標で、特に電話サポートで重要視されます。
4. 平均応答速度(ASA)
平均応答速度(ASA)は電話が着信してからオペレーターが応答するまでの平均時間を表し、顧客の待ち時間を示します。
5. 稼働率
稼働率は、担当者が実際に顧客対応やチケット解決に費やしている時間の割合を示す指標です。
▼あわせて読みたい
6. 放棄呼率
放棄呼率は、電話がかかってきたものの、顧客がオペレーターに繋がる前に切ってしまったコールの割合で、待ち時間の長さを示す重要な指標です。
▼あわせて読みたい
7. 問題解決ごとのコスト(Cost per conversation)
効率を示す指標となり、総コストをサポート件数で割って算出します。これらの効率性・スピードに関するKPIを追跡することで、人員配置の最適化やプロセス改善のヒントを得ることができます。
問題解決に関するKPI
カスタマーサポートでの問題解決を軸に、解決数や効率性を重点に置く場合に見るべき指標は下記の5点が挙げられます。
1. 初回解決率(FCR)
初回解決率(FCR)は、顧客が最初に問い合わせをした際に、そのコンタクトのみで問題が解決した割合を示す指標です。この数値が高いほど迅速に問題解決できたことになり、顧客満足度の向上に繋がります。
ただし、簡単な問い合わせが多い場合にもFCRは高くなるため、他の指標と併せて総合的に評価する必要があります。
2. 課題解決率
課題解決率とは、受け付けた問い合わせのうち、問題が解決に至った割合です。ワンストップ処理率も関連する指標で、問題を他の部門に引き継ぐことなく、担当者のみで解決できた割合を指します。
3. エスカレーション回数/率
エスカレーション回数/率は、担当者が自身では解決できず、より経験豊富な担当者や上司に引き継いだ問い合わせの回数や割合を示します。
エスカレーションが多いと、顧客を待たせる時間が増え、不満に繋がる可能性があります。マニュアル整備や担当者のトレーニングを通じてエスカレーションを減らすことが対策となります。
▼あわせて読みたい
4. チケットの再オープン率(再問い合わせ率)
チケットの再オープン率(再問い合わせ率)は、解決後に再度の問い合わせが発生した割合を示し、前回の対応で問題が完全に解決されなかった可能性を示唆します。
5. 平均解決時間(ART:Average Resolution Time)
平均解決時間(ART:Average Resolution Time)は、問い合わせが発生してから問題が最終的に解決されるまでにかかる平均時間で、解決の迅速性を示す重要な指標です。
これらの指標を分析することで、担当者のスキルやナレッジベースの質、サポートプロセスの課題などを特定できます。
自己解決率と問い合わせ削減に関するKPI
顧客自身がFAQやヘルプコンテンツなどを活用して問題を解決できる「自己解決」は、カスタマーサポートの効率化を進める上で非常に重要な要素です。
1. 自己解決率
自己解決率とは、サポート担当者に問い合わせる前に、顧客がWebサイト上の情報などで問題を解決できた割合を示す指標です。自己解決率が高いほど、サポート部門に直接寄せられる問い合わせ件数は減少します。
これにより、サポート担当者は対応負荷が軽減され、より複雑な問題や、担当者でなければ対応できない問い合わせに集中できるようになります。結果として、人件費を含む対応コストの削減にも繋がります。
FAQシステムのようなツールは、ユーザーが求める情報に簡単にたどり着けるよう工夫されています。特にHelpfeelのような「意図予測検索」 を持つシステムは、表記揺れやあいまいな表現にも対応できるため、自己解決率の向上に大きく貢献します。
▼あわせて読みたい
2. その他に見るべき指標
フォーラムvsチケット比や検索クリック率といったセルフサービスに関する指標も、自己解決の状況を測る上で参考になります。
自己解決率やそれに伴う問い合わせ件数の変化をKPIとして追跡することで、FAQサイトやヘルプコンテンツの効果を定量的に評価し、コンテンツの改善や導線の最適化を進めることができます。
▼自己解決につながる4つのKPIについて、以下のお役立ち資料でより詳しく解説しています。ぜひ併せてご活用ください。

ビジネス貢献に関するKPI
カスタマーサポートは、単に顧客の問題を解決するだけでなく、企業の収益や成長に貢献する可能性を秘めた部門です。そのため、顧客維持や売上に関連するビジネス指標をKPIとして設定することも有効です。
1. リテンション率(継続率)
一度サービスを利用した顧客が継続してくれる割合を示す指標です。質の高いカスタマーサポートは、顧客満足度を高め、顧客ロイヤルティを醸成するため、リテンション率の向上に貢献します。
新規顧客の獲得には既存顧客の維持よりもコストがかかることが多いため、リテンション率をKPIとして追跡し、サポートが顧客維持にどれだけ貢献しているかを評価することは重要です。
▼あわせて読みたい
2. コンバージョン率(CVR)
例えば、ECサイトでの購買プロセス中に顧客が疑問を持った際に、迅速かつ的確なサポートを提供することで、購入完了(コンバージョン)を後押しすることができます。
ビジネス指標に与える影響をKPIとして測定することで、サポート部門が企業の売上や利益にどのように貢献しているかを定量的に示し、価値を高めることができます。顧客生涯価値(LTV)も、リピート率と密接に関わる重要な指標です。
▼あわせて読みたい
効果的なカスタマーサポートの目標設定・KPI運用方法

KPIは設定して終わりではなく、適切に運用し、継続的に改善に取り組むことでその効果を最大限に引き出すことができます。ここでは、より効果的な目標設定とKPI運用を実現するための具体的な方法について解説します。
KGIからブレイクダウンする、KPIツリーの作成
効果的なKPI設定の第一歩は、企業全体のKGI(重要達成目標指標)から、カスタマーサポート部門、そして個々のチームや担当者のKPIへと段階的に落とし込んでいく「KPIツリー」を作成することです。
まず、企業や事業が目指す最終的なゴールであるKGIを明確に定義します。次に、KGIを達成するために、カスタマーサポート部門がどのような貢献を果たすべきかという部門目標を設定します。この部門目標が、KPIツリーの最上位に位置するKPI群となります。
さらに、その部門KPIを達成するために必要な、各チームや個人の具体的な活動や成果に紐づくKPIを設定していきます。
このようにKGIからKPIへと順に「なぜそのKPIを追うのか」という目的を明確にしながらブレイクダウンすることで、設定されたすべてのKPIが最終目標に繋がっている状態を作り出せます。
KPIツリーによって、メンバーは自分たちの業務が組織の目標にどう貢献しているかを理解しやすくなり、一体感を持って目標達成に取り組むことができます。このプロセスは、目標設定の曖昧さや適切な指標選定の難しさといった課題への対策にもなります。
SMART原則に基づく具体的かつ測定可能なKPI設定
KPIが形骸化せず、実効性を持つためには、SMART原則に従って設定することが非常に重要です。SMARTとは、Specific(具体的に)、Measurable(測定可能に)、Achievable(達成可能に)、Relevant(関連性のある)、Time-bound(期限を設けて)の頭文字を取ったフレームワークです。
まず、KPIは抽象的な表現ではなく、誰が見ても同じように理解できる具体的な内容である必要があります。次に、その達成度合いが数値やデータで客観的に測定可能でなければなりません。例えば、「対応を早くする」ではなく「一次応答時間を平均〇分以内にする」のように具体的に、かつ測定可能な形で定義します。
また、設定するKPIは、現在のリソースや状況を踏まえて、現実的に達成可能なレベルであるべきです。非現実的な高い目標は、かえってチームのモチベーションを低下させる要因となります。
さらに、設定したKPIが、上位の目標やKGIに関連していることを確認します。最後に、いつまでにそのKPIを達成するのか、明確な期限を設定することが重要です。
これらのSMART原則を意識することで、目標達成に向けた具体的な行動を促進し、効果を正確に測定できるKPIを設定できます。
チームを巻き込む目標共有とモチベーション維持の工夫
KPIを設定するだけでは、期待する成果を得ることは難しいでしょう。チーム全体が設定したKPIを理解し、その達成に向けて主体的に取り組むための仕組みづくりと、メンバーのモチベーション維持に向けた継続的な働きかけが不可欠です。
まず、設定したKPIとその背景にある目的をチームメンバー全員に明確に共有することが重要です。KPIダッシュボードなどを活用して、チームの進捗状況をリアルタイムで可視化し、いつでも確認できるようにすることも効果的です。これにより、チーム全体で目標達成に向けた意識を高めることができます。
目標達成に向けた取り組みの中で生まれた成功事例を積極的に共有し、チーム全体の士気を高めることも重要です。目標を達成したメンバーや、KPI改善に大きく貢献したメンバーに対しては、適切な評価や報酬、表彰などを行うことで、個々のモチベーションを刺激し、チーム全体の活性化に繋げることができます。
KPIに基づいた定期的なフィードバックを行い、メンバー一人ひとりの成長をサポートすることも、モチベーション維持とパフォーマンス向上に寄与します。
データ分析と問い合わせ管理ツールを活用した継続的改善
KPIの効果測定や、目標達成に向けた改善活動を効率的に進めるためには、データの収集、分析、そしてその結果に基づいたアクションが不可欠です。
問い合わせ管理システムやヘルプデスクツールといったカスタマーサポートツールは、問い合わせ件数、対応時間、解決率、顧客満足度など、様々なKPIに関連するデータを自動的に蓄積・集計する機能を備えています。
これらのツールが提供するレポート機能やダッシュボードを活用することで、KPIの現状値を正確に把握し、目標値との比較や過去からの推移を分析することができます。データ分析の結果、特定の種類の問い合わせが多い場合は、その原因を探り、FAQコンテンツの拡充やマニュアル整備といった対策を講じることが考えられます。
また、顧客からのフィードバック(VOC:Voice of Customer)を分析することで、顧客の隠れたニーズや不満を把握し、サービス改善やFAQコンテンツの質向上に繋げることも可能です。
KPIの達成状況は常に変動するため、定期的にデータを分析し、必要に応じてKPIの目標値や設定自体を見直すことで、カスタマーサポート体制を継続的に改善していくことができます。データ分析を通じて効果を評価し、問題点を明確にすることが、より効果的な改善策に繋がります。
▼あわせて読みたい
陥りがちな課題と対策
KPIを設定、運用していく過程では、いくつかの共通の課題に直面することがあります。例えば、目標設定が曖昧で具体的でないため、チームメンバーが何をすべきか分からない、あるいは目標達成の進捗を正確に測れないといった「目標設定の曖昧さ」 が挙げられます。
また、数多くの指標の中から、自社のビジネス目標や顧客特性に合った適切なKPIを選定することが難しい「適切な指標選定の難しさ」 も課題となります。設定するKPIの数を増やしすぎると、担当者の負担となり、分析が難しくなるため注意が必要です。
さらに、現場の状況を考慮せずに過剰に高い目標を設定してしまい、かえって担当者のモチベーションを低下させてしまうケース も少なくありません。
その他にも、KPIの単独の数値のみに囚われ、他の指標や現場の定性的な状況を考慮しない評価を行ってしまったり、データ収集や分析が十分に行われないために効果測定や改善が進まない、といった課題も起こり得ます。
課題を克服するためには、KGIからKPIをブレイクダウンし、SMART原則に基づいて具体的かつ達成可能な目標を設定すること、複数のKPIや現場の状況を総合的に判断すること、そして問い合わせ管理ツールなどを活用してデータを継続的に収集・分析することが有効な対策となります。
また、チーム全体で目標を共有し、成功事例の共有やフィードバックを通じてモチベーションを維持する努力も重要です。

KPI改善を通じた戦略部門化への道

カスタマーサポート部門は、しばしばコストセンターと見なされがちです。しかし、FAQシステムを効果的に活用することで、様々なKPIを改善し、最終的には企業の成長に貢献する戦略的なプロフィットセンターへと進化させることが可能です。
ここでは、FAQシステムがKPI改善にもたらす具体的な効果と、Helpfeel独自のメソッドである「ナレッジジャーニー」を通じて実現するカスタマーサポートの新たな可能性について解説します。
▼あわせて読みたい
FAQシステムが自己解決の促進に貢献する仕組み
FAQシステムは、顧客が抱える疑問や問題を、サポート担当者に問い合わせる前に、Webサイト上で自分自身で解決できるようにするためのツールです。高品質なFAQシステムは、よくある質問に対する分かりやすい回答を豊富に備えており、顧客は必要な情報を迅速に見つけることができます。
Helpfeelは、独自の「意図予測検索」を採用しており、ユーザーが入力するあいまいな言い回しや表記揺れ、あるいは専門用語を使わない表現でも、その検索意図を正確に理解し、最も関連性の高いFAQ記事を提示することが可能です。
これにより、ユーザーはストレスなく 答えにたどり着けるため、自己解決率の向上に貢献します。自己解決率が高まるほど、電話、メール、チャットといった有人チャネルへの問い合わせ件数は減少し、結果としてサポート担当者の対応負荷が軽減され、対応コストを削減することができます。
KPI測定・改善を強力にサポートするFAQシステムの機能
FAQシステムは、質問と回答を提供するだけでなく、カスタマーサポートのKPI測定と継続的な改善活動を支援するための様々な機能を搭載しています。
多くのFAQシステムでは、各FAQ記事の閲覧回数、検索されたキーワード、そして「役に立った」といった評価などのデータを自動的に収集・分析することができます。これにより、どの記事がよく読まれているか、顧客がどのような情報を求めているか、あるいは記事の質に対する顧客の評価はどうかといった情報を把握できます。
Helpfeelは特に、検索ログや問い合わせ内容を分析するVOC(顧客の声)分析機能に強みを持っており、顧客がどのような課題を抱えているか、どのような情報が不足しているかといった潜在的なニーズを深く理解することができます。
検索されたにも関わらず適切な記事が見つからなかった「nohit率」を分析することも、FAQコンテンツの不足や表現の課題を特定する上で非常に有効です。
これらのデータに基づき、自己解決率、問い合わせ削減率、さらには顧客満足度といったKPIの現状を定量的に把握し、FAQコンテンツの改善、新規記事の作成、検索性の最適化といった具体的な改善策を実行し、その効果を測定することができます。
Helpfeelのサポート体制は、KPIの測定・分析から改善提案まで伴走支援することに強みがあります。
多くの自己解決率向上実績から生まれたメソッド「ナレッジジャーニー」
Helpfeelは、これまで多くの企業の自己解決率向上と顧客体験改善をご支援してきました。蓄積された知見とノウハウを結集して生まれたのが、顧客をスムーズな自己解決へと導くHelpfeel独自のCSメソッド「ナレッジジャーニー」です。
ナレッジジャーニーは、単にFAQシステムを導入するだけでなく、Helpfeelの「意図予測検索」といった高い検索技術 と、FAQコンテンツの作成・改善ノウハウ、そしてHelpfeelの専門チームによる手厚い伴走支援を組み合わせた包括的なアプローチです。
検索データやVOC分析を通じて得られる顧客のニーズを深く理解し、FAQコンテンツを継続的に育てていくことで、ユーザーがどのような表現で検索しても適切な情報にストレスなくたどり着ける環境を構築します。これにより、自己解決率を最大化し、問い合わせ削減や顧客満足度向上といったKPIの改善を実現します。
ナレッジジャーニーは、情報格差を解消し、顧客と企業双方にとってより良い未来を目指すHelpfeelのビジョンを具現化したメソッドです。このナレッジジャーニーの詳細や、KPI改善による具体的な成果事例については、ぜひ資料をダウンロードしてご確認ください。


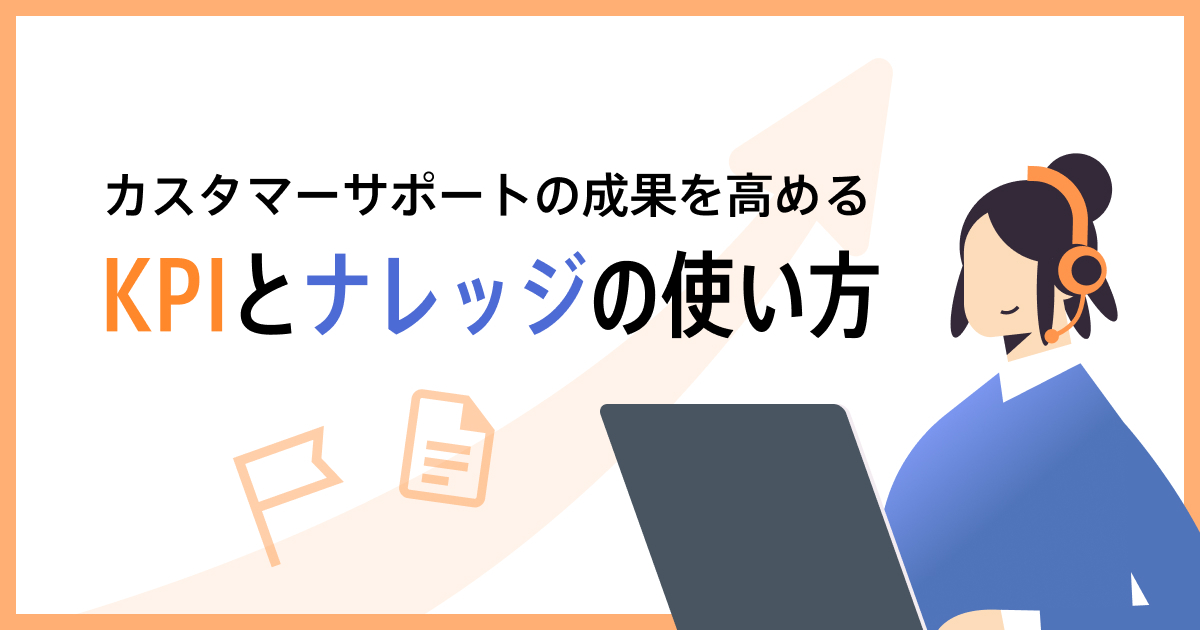
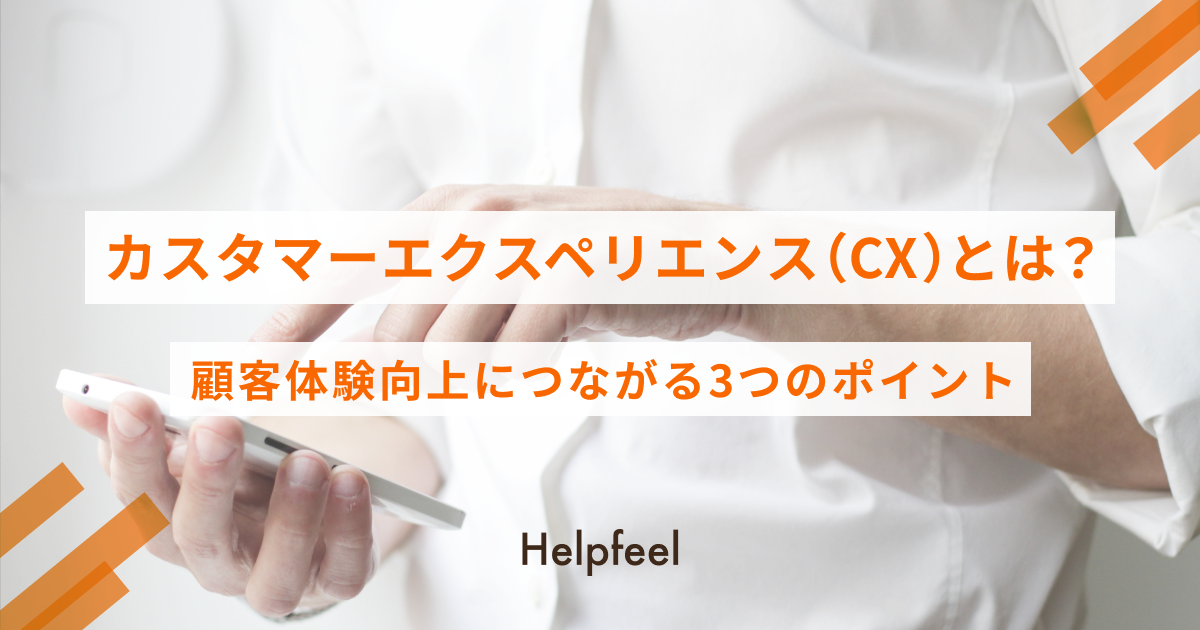
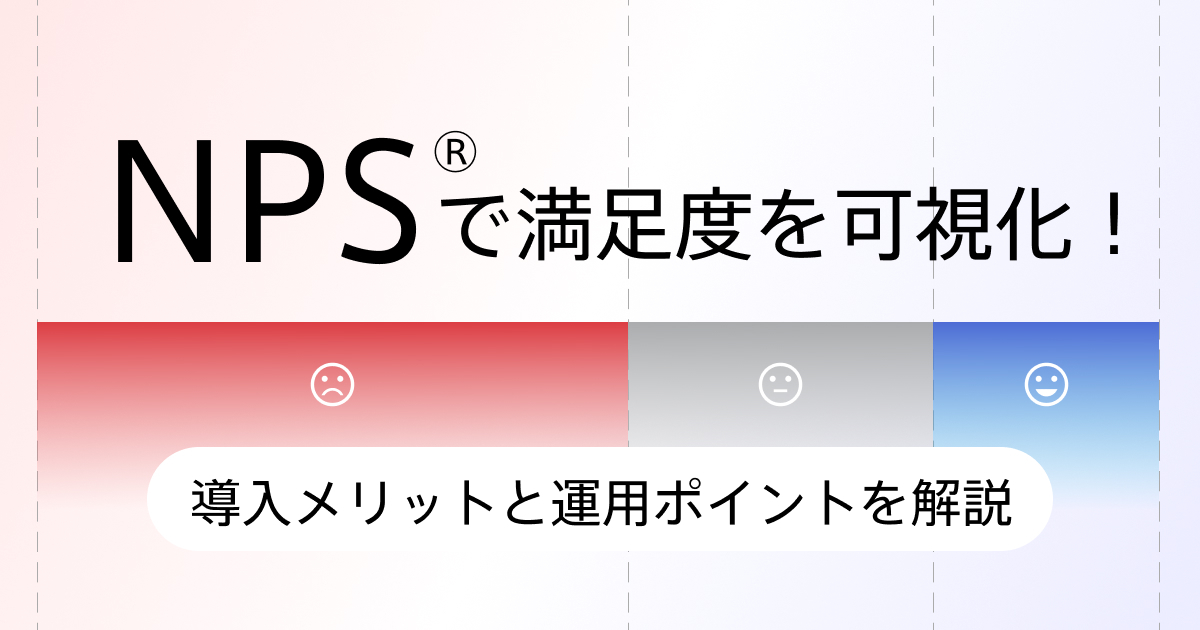
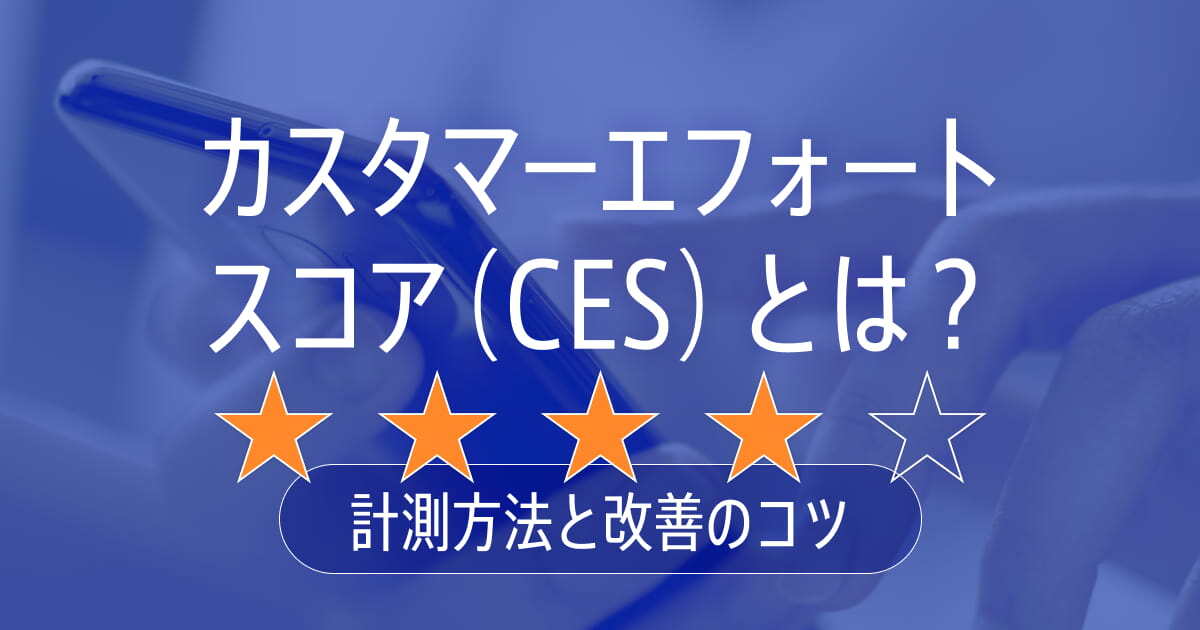

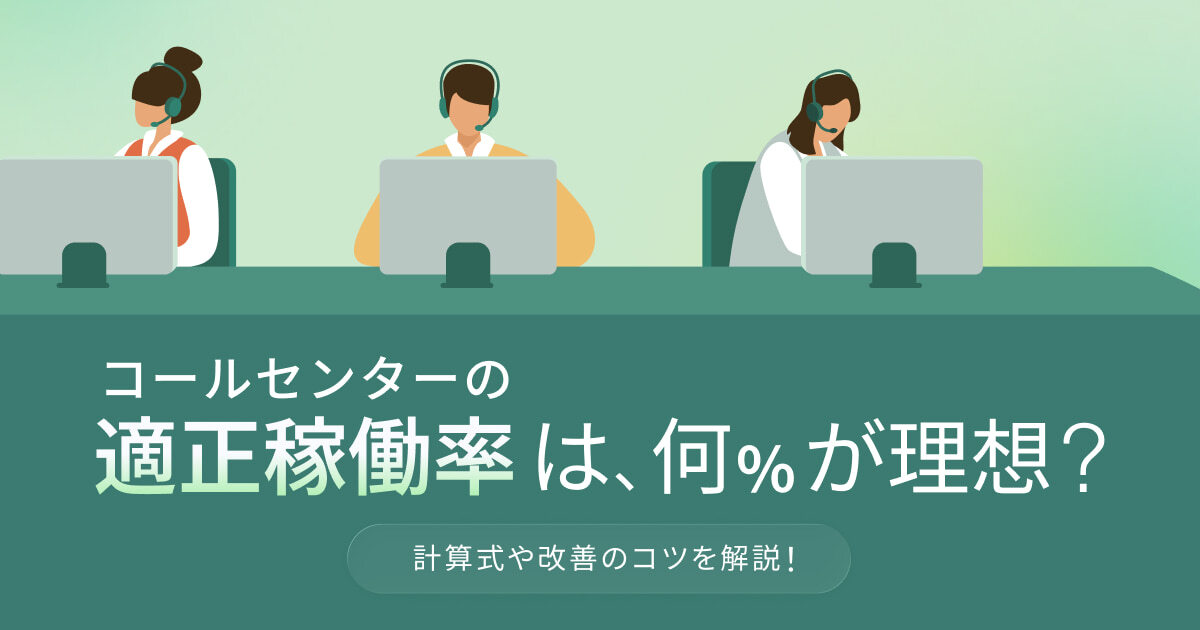
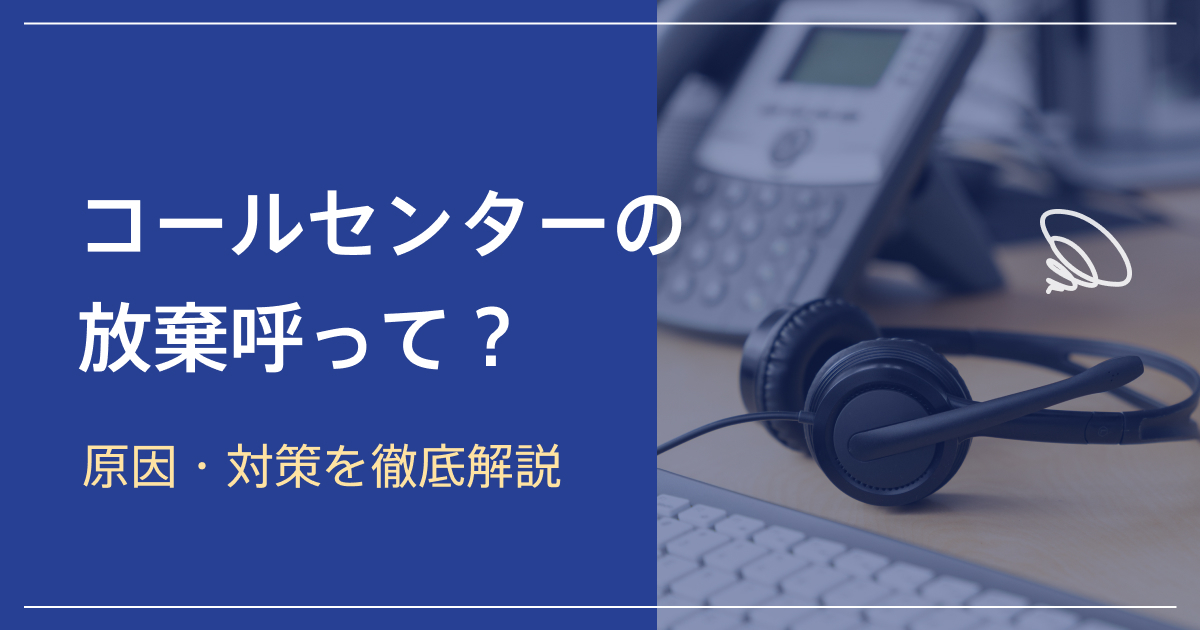


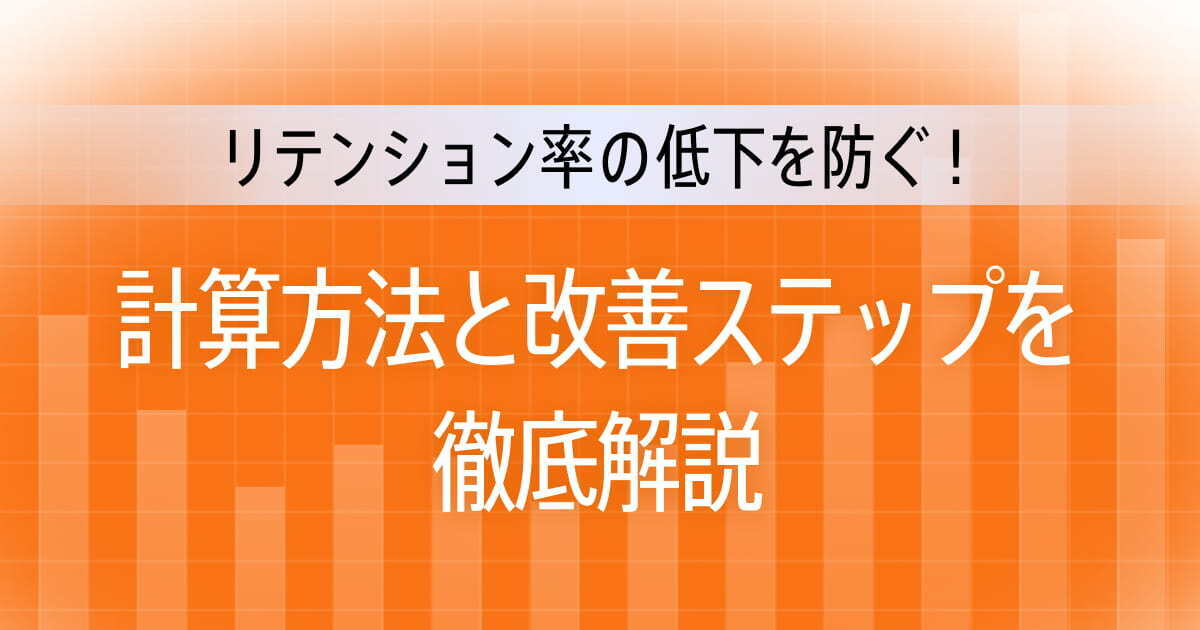
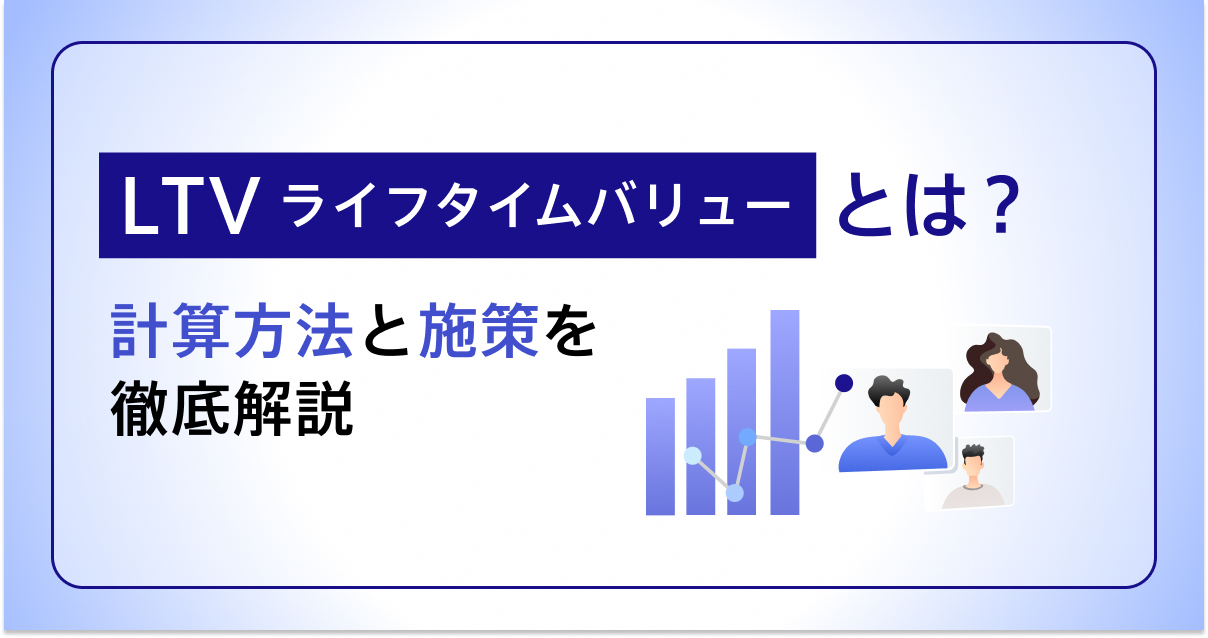
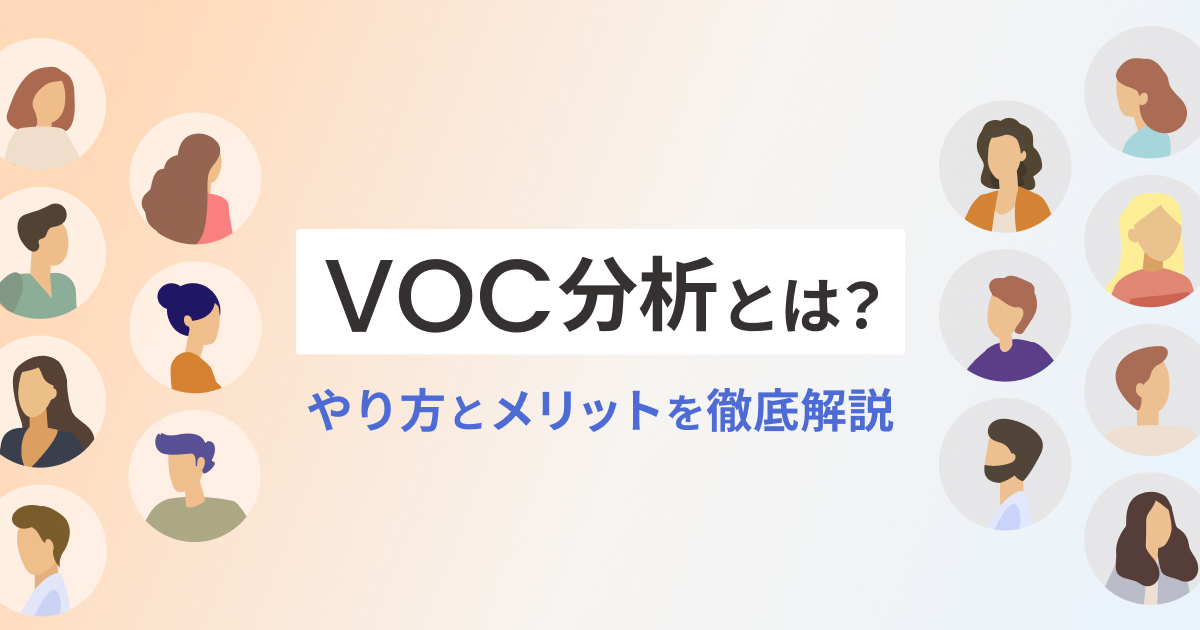


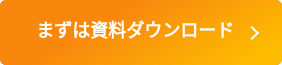







.png)