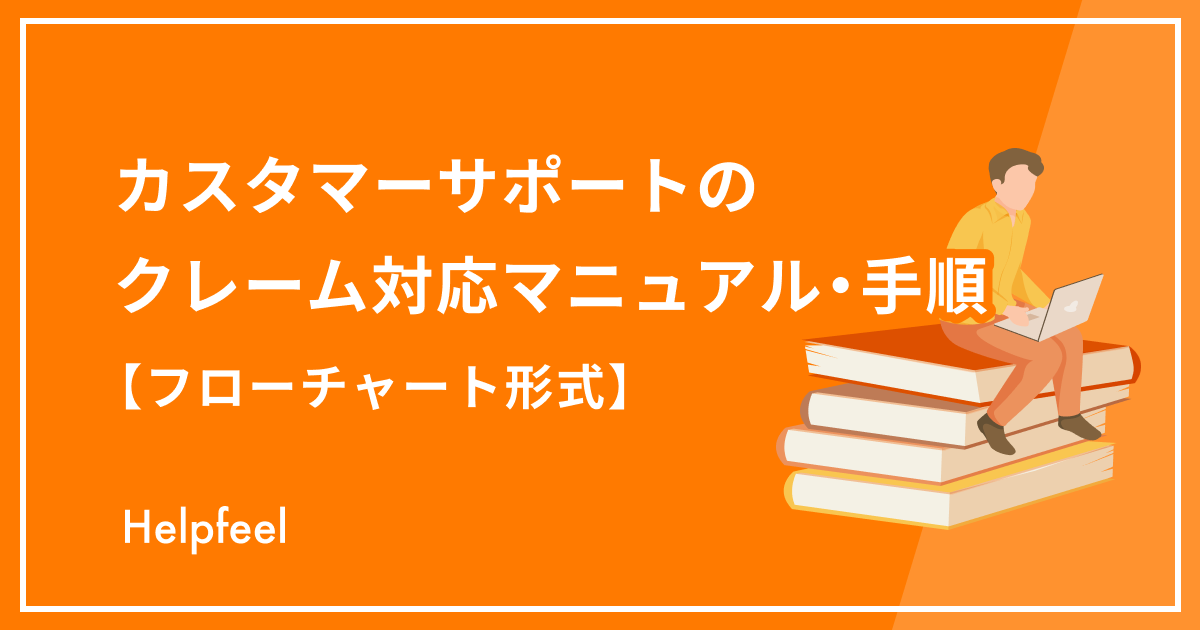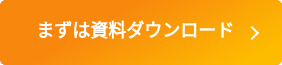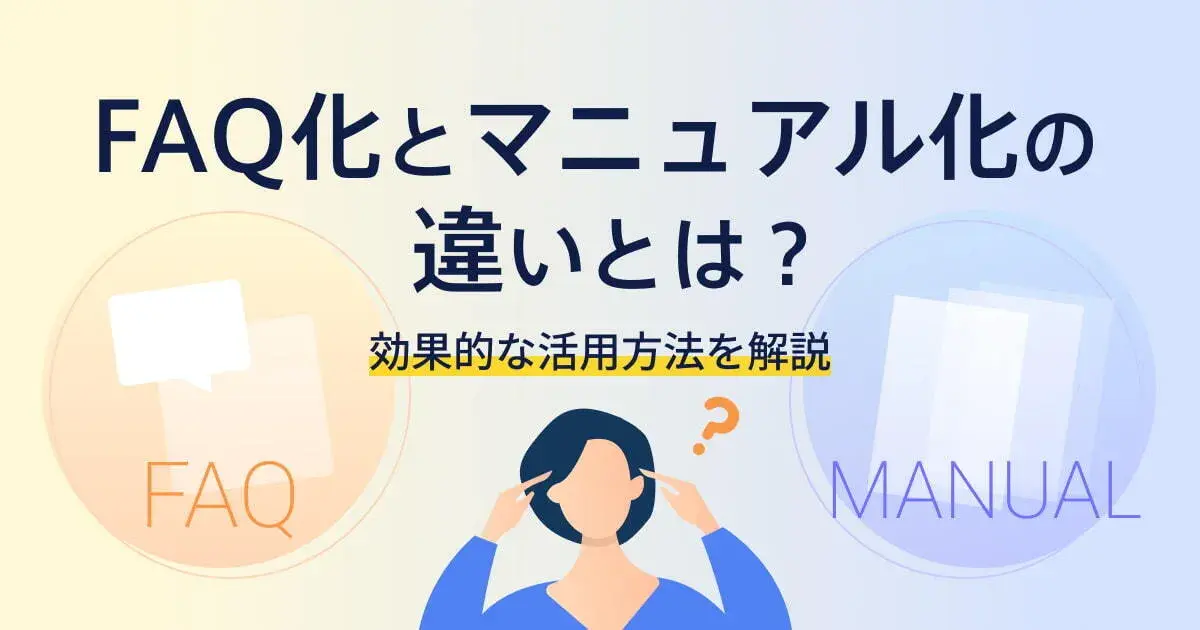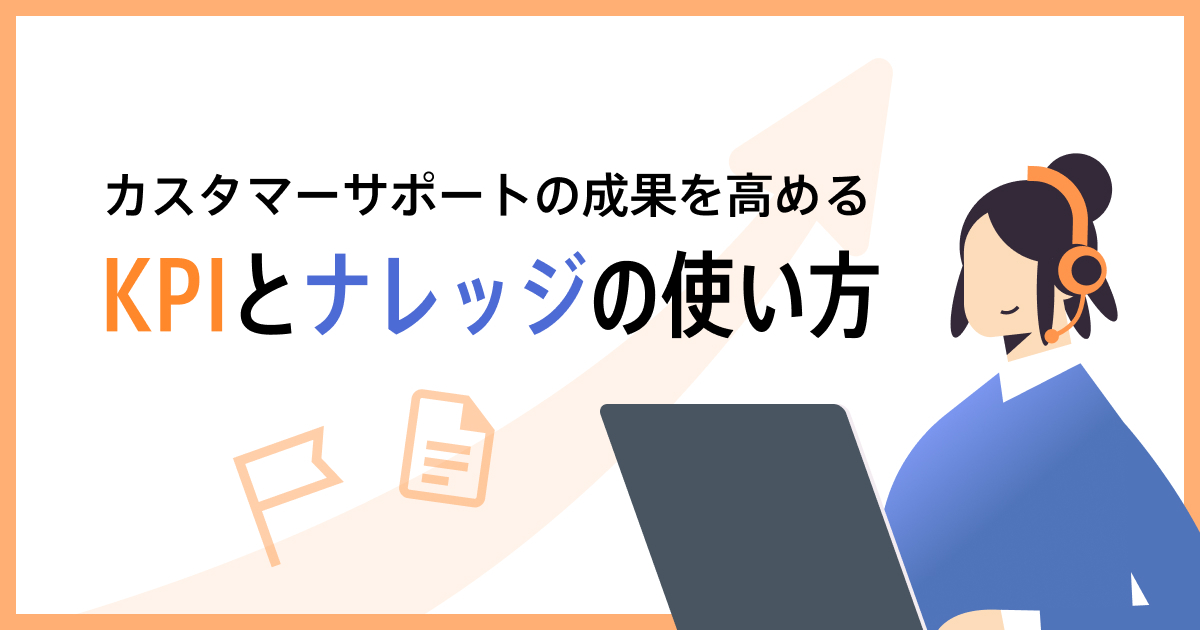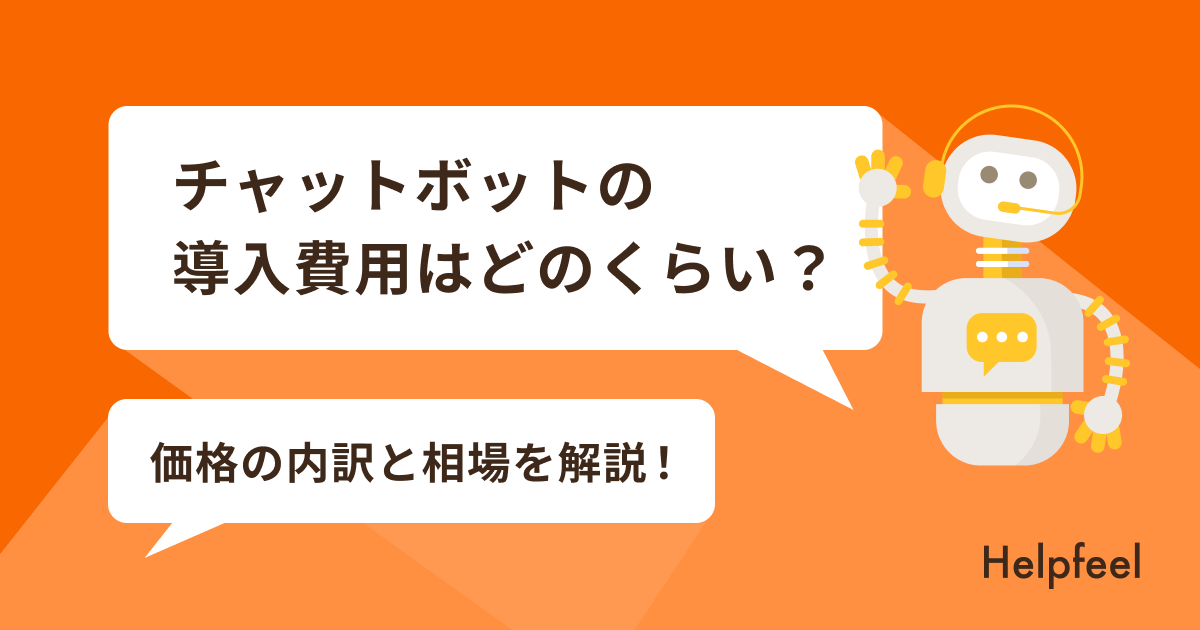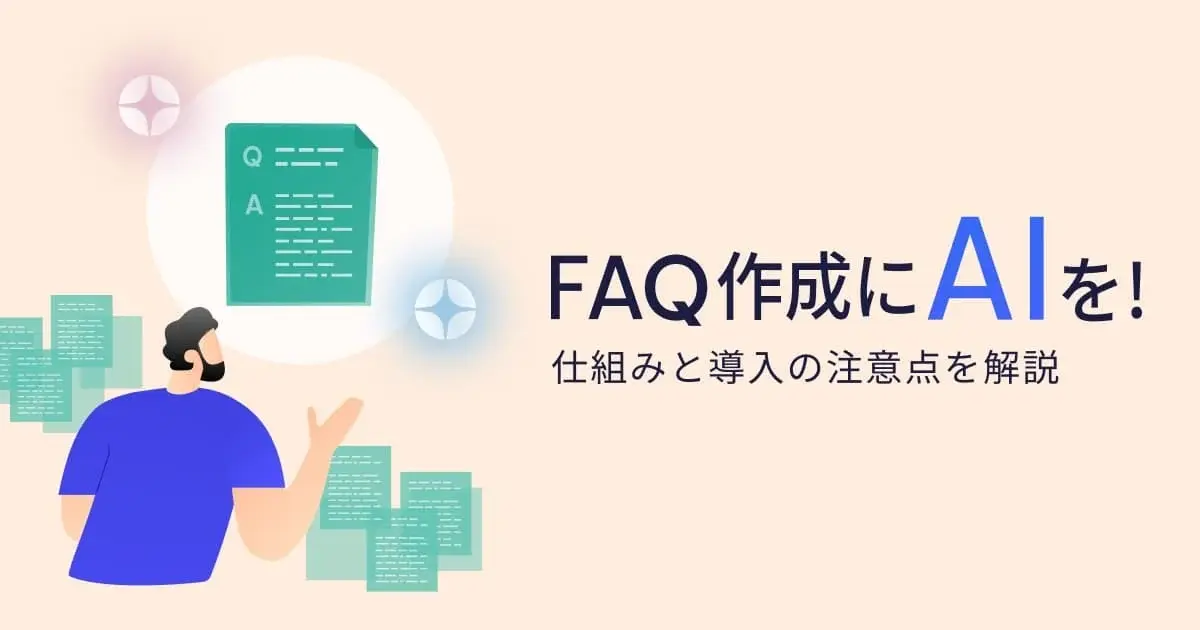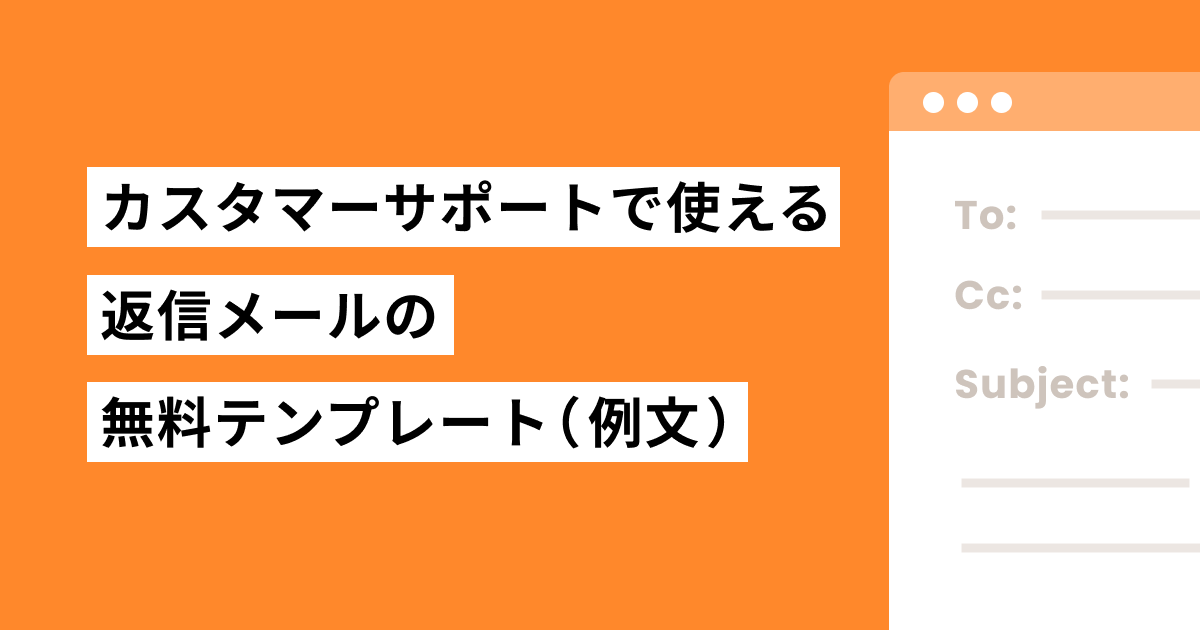エスカレーション(エスカレ)とは?
 エスカレーション(エスカレ)とは、現場の担当者だけでは判断・対応が難しい問い合わせやトラブルについて、上長や専門部署に引き継いで対応を仰ぐことです。
エスカレーション(エスカレ)とは、現場の担当者だけでは判断・対応が難しい問い合わせやトラブルについて、上長や専門部署に引き継いで対応を仰ぐことです。
ただ「分からないから上に回す」ということではなく、あらかじめ決めたルールやフローに沿って、状況に応じて誰に引き継ぐべきかを整理しておくのがポイント。これにより、現場の迷いを減らしつつ、対応の抜け漏れや遅れを防ぎ、結果的に顧客対応の質も守ることができます。
ここでは、エスカレーションについて、以下の2つの視点から解説していきます。
|
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
コールセンターでエスカレーションが必要な主な理由
エスカレーションは、コールセンターでオペレーターだけでは対応できない問題を上位者や専門部署に引き継ぎ、迅速に解決を図るための仕組みです。エスカレーションをすることで、リスクを最小限に抑えながら顧客満足度を高められます。
コールセンターには、さまざまな問い合わせやクレームが寄せられますが、中にはオペレーターの判断だけでは対応しきれないケースが発生することも珍しくありません。具体的には以下のケースが考えられます。
|
エスカレーションは単なる報告ではなく、リスク管理と顧客満足を両立させるために必要な仕組みです。
エスカレーションが発生しやすい職種
エスカレーションは、顧客と直接接する職種や、業務判断が分かれる場面で頻繁に発生します。エスカレーションが発生しやすい職種は、主に次の3つです。
|
それぞれ詳しく解説します。
コールセンター・カスタマーサポート
コールセンターやカスタマーサポートは、顧客との接点が最も多い職種の一つです。一次対応で完結する問い合わせもある一方で、製品不良の対応、重大なクレーム、契約に関するトラブルなど、判断が難しいケースも日常的に発生します。
「返金してほしい」「解約処理ができていない」「システムが使えない」などの複雑な対応には、マニュアル通りでは対処できないことも多く、上長や別部署へのエスカレーションが不可欠です。
また、通話履歴を残しながらタイムリーに対応するためには、迅速かつ正確な判断と、明確なエスカレーションフローを整備しておく必要があります。
▼あわせて読みたい
接客業(店舗・サービス業)
小売店や飲食店、ホテルなどの接客業でも、エスカレーションは日常的に発生します。現場スタッフが判断しきれない状況や、顧客の納得が得られない場合には、店長や本部への対応依頼が必要です。
例えば、料理の提供ミスや衛生面でのトラブル、商品の欠陥、顧客からの過剰な要求などが挙げられます。こうしたケースでは、現場で対応しようとすると、かえって問題がこじれることがあるので、エスカレーションによる適切な処理がトラブルの沈静化には不可欠です。
また、スタッフの感情的負担やストレスを軽減し、円滑な接客を続けるためにも、「エスカレーションしてよい」と安心できる環境を整えることも大切です。
営業職(法人/個人問わず)
営業職は、クライアントとの関係性を築きつつ、契約・提案・交渉といった幅広い業務をこなします。その中で、契約内容の見直しや価格交渉、納期遅延への対応など、個人の裁量だけでは判断できない場面が少なくありません。
例えば、「競合より安くしてほしい」「仕様を途中で変えたい」といった要望に対し、勝手な判断で対応すれば社内の利益や信頼性を損なうリスクがあります。こうした場合は、上司や製品開発部門、法務部などへエスカレーションし、社内調整を経て適切に回答する必要があるでしょう。
また、クライアントと社内の板挟みになることも多いため、営業担当者が孤立せず、迅速にサポートを得られるエスカレーション体制が重要です。
▼エスカレーションをスムーズに行うためには、ナレッジなどの社内の情報をまとめて共有できる「ナレッジシステム」がおすすめです。
スムーズにエスカレーションを行うための3つのポイント

エスカレーションがうまく機能しない原因の多くは、ルールやフローが不明瞭なこと、そして報告者が萎縮する組織風土にあります。
以下の3つのポイントを押さえることで、現場での混乱を防ぎ、迅速で効果的なエスカレーション対応が実現できます。
|
それぞれ、詳しく解説していきます。
エスカレーションを行う際のルールを設ける
エスカレーションの判断基準が不明確だと、現場は「これは報告すべきか?」と迷ってしまい、対応の遅れや二次クレームの原因になります。そのため、「どのような事象を」・「どのレベルで」・「誰に報告するべきか」というルールを明文化することが重要です。
例えば、以下のような具体的なトリガーの例を用意すると、誰でも迷わず判断できます。
|
また、新人やアルバイトスタッフでも判断しやすくするために、簡易フローチャートやチェックリストを活用するのも効果的です。ルールを決めたら、それを定期的に見直し、現場の声を反映し続けることで、より実効性のある仕組みに育てていくことが可能です。
報告のフローを明確にする
エスカレーションがうまくいかない原因の1つに、「誰に何を、どのように報告すればよいか」が不明確であることが挙げられます。報告ルートや手段が統一されていないと、情報が滞留したり、対応の責任が曖昧になったりする可能性が高いでしょう。
下記の通り、報告のルートを整理しておくことが大切です。
|
特に、システムを活用した報告書式(チャットボットやフォームなど)を導入すれば、スピードと正確性の両立が可能になります。
エスカレーション報告者を責めない
エスカレーションが必要な場面では、現場スタッフはすでに困難な状況に直面しています。そのため、「自分の判断ミスだったのではないか」「報告したら怒られるのでは」という不安があると、報告をためらい、結果として問題が深刻化するケースが高まります。
スムーズなエスカレーションを実現するには、報告したこと自体を肯定的に評価する組織風土が欠かせません。例えば、「よく報告してくれた」「対応ありがとう」といった一言が、現場の心理的ハードルを下げ、再発防止にもつながります。
また、報告者に対するフィードバックも重要です。「次回はこの点も一緒に伝えると、もっとスムーズになる」といった建設的なアドバイスは、報告スキルの向上にも役立ちます。逆に、「なぜこんなことで報告したんだ」「自分で考えて処理しろ」といった叱責(しっせき)は、現場からエスカレーション文化を根絶してしまいかねません。
組織全体の対応力を高めるには、誰もが気軽に報告できる雰囲気を作ることが大切です。さらに、報告してくれた人に感謝を伝えることで、安心してエスカレーションできる環境が整うでしょう。
エスカレーションフローの作り方

エスカレーションがうまく機能しない組織の多くは、「何を」「誰に」「どう伝えるか」が曖昧なままになっています。現場任せの対応では、トラブルの早期解決や再発防止が難しくなり、顧客満足度の低下にもつながりかねません。
以下の3つのポイントを押さえることで、エスカレーションを仕組みとして定着させ、現場の混乱や属人化を防ぐことが可能です。
|
それぞれ詳しく見ていきましょう。
報告内容と優先度の基準を明確化する
「どのような内容を、どの段階で、誰に報告すべきか」という基準を設定することが必要です。報告内容が曖昧であったり、優先度の判断が現場ごとに異なったりすると、対応の遅れや混乱が生じてしまいます。
例えば、緊急性の高いトラブル(システム障害・重大なクレームなど)は即時にマネージャーへ報告し、通常業務の改善提案などは週次会議で共有するといった、優先度に応じた報告ルールを整備しましょう。
さらに、報告内容を「事実」「影響度」「希望する対応」の3点に整理するテンプレートを用意すると、伝達の精度とスピードが向上します。
報告手段や報告ルートを定める
エスカレーションの際、「どのツールを使って、誰に向けて報告するか」が曖昧だと、必要な情報が正確に届かず、対応が後手に回る原因となります。
下記のように、報告手段やルートを事前に設定しておくと、現場スタッフも利用しやすいため便利です。
【設定すべき項目】
|
エスカレーション履歴を記録してナレッジ化する
一度対応したエスカレーション内容は、今後の業務に生かすためにも記録・分析し、ナレッジとして蓄積していくことが大切です。
【記録すべき情報例】
|
上記により、類似トラブルの再発防止や教育資料としての活用が可能になります。
例えば、「Helpfeel」のようなナレッジ共有ツールを活用すれば、エスカレーション事例をFAQ化したり、検索性の高いデータベースにまとめることも容易に行えます。
蓄積されたデータは、対応スピードの向上や業務の属人化防止、組織全体のナレッジレベルの底上げにつながるでしょう。
▼あわせて読みたい
エスカレーションのよくある失敗例と注意するポイント

エスカレーションは、トラブルや課題を迅速・的確に処理する上で欠かせない手段です。しかし、実際の現場では「うまくエスカレーションできない」「報告しても対応が進まない」といった失敗も多く発生しています。
これらの失敗は、現場の混乱や顧客対応の遅延を招くだけでなく、組織全体の信頼低下にもつながりかねません。
以下に、よくある失敗例6つとその背景・注意点をまとめました。
|
それぞれ具体的に解説していきます。
エスカレーション先がわからない
最も基本的な失敗例は、「誰にエスカレーションすればよいのかわからない」ことです。例えば、社内で発生した技術的なトラブルに対して、営業担当がサポート部門なのか、開発部門なのか判断できず、報告が宙に浮いてしまうというケースが挙げられます。
これは「報告ルートの不明確さ」に起因しており、部署や職位によって窓口を変える必要がある場合は、あらかじめフローチャートや担当リストを用意することが重要です。
また、シフト制やテレワーク導入企業では、「今対応できる担当者」がわかりにくいため、現在対応可能なメンバーを明示する仕組みを取り入れるとスムーズです。
エスカレーションをためらってしまう
報告が遅れるもう1つの大きな原因は、「こんなことで報告していいのか」と担当者がためらってしまう心理的要因です。
例えば、新人や若手社員が「上司が忙しそう」「報告したら怒られるかも」と感じてしまい、本来すぐに報告すべき重大インシデントを自分で抱えてしまうことがあります。「失敗はすぐ報告してもOK」というメッセージを普段から発信し、報告を奨励する文化を醸成することが重要です。
また、エスカレーションしやすいチャットボットや匿名フォームを設けるなど、心理的ハードルを下げる設計も効果的でしょう。
エスカレーションのタイミングや判断基準が難しい
「今すぐ報告すべきか、それとも様子を見ていいのか」と判断に迷って、対応が遅れるケースもよくあります。
例えば、顧客からの問い合わせがクレームになる前に上司に報告すべきだったのに、「自分で処理できる」と判断して対応が長引くなどの事例です。「このレベルのクレームは即報告」「対応が30分以上かかる見込みなら上長に相談」など、具体的なエスカレーション基準をマニュアル化しておくと、誰でも迷わず対応できます。
また、定期的なロールプレイやケーススタディ研修を行い、タイミングの勘所を身に付けさせることも効果的です。
エスカレーション後に対応が止まってしまう
「報告はしたのに何も返ってこない」「誰も対応してくれない」という状況は、エスカレーションの失敗として非常に深刻です。
このような「報告後の空白」は、対応責任が曖昧な組織や、エスカレーションの受け手が対応を他者に丸投げしてしまうようなケースで起こりやすくなります。
対応責任者をあらかじめ明確に定義しておくこと、エスカレーションを受けた側が「対応ステータス(受付・対応中・完了)」を共有する運用を設けることが重要です。
エスカレーションが多すぎて処理ができない
一方で、エスカレーション件数が多すぎて管理側が処理しきれない、という逆の問題もあります。
原因としては、「何でも報告する風土」「自分で判断できない文化」「対応フローが複雑すぎる」などが挙げられます。これにより、本当に緊急性の高い案件が埋もれてしまい、対応が後手に回るリスクがあるでしょう。
対策としては、エスカレーションをレベル分け(例:レベル1=即時対応、レベル2=翌営業日中、レベル3=週次報告)し、それに応じて処理体制や優先度を調整することが必要です。
また、「報告が多い=悪いこと」ではないので、チャットボットで自動整理→人間対応に仕分けなど、ツールの活用も検討してください。
情報共有不足で対応が遅れる
最後によくあるのが、「報告はされたが、他の関係者に伝わっておらず、対応が進まない」という情報共有不足による遅延です。
例えば、カスタマーサポートで得たトラブル情報が、開発チームに適切に共有されておらず、同様の問い合わせが続発するといった状況などが挙げられます。
この問題は、サイロ化した組織構造でも発生しがちです。エスカレーションは「担当者間のやりとり」ではなく、「全体のナレッジ共有の一環」として捉え、「Helpfeel」のようなツールで履歴を可視化・共有する体制を整えることが重要です。
また、報告だけでなく、進捗(しんちょく)・対応結果も関係者全員に通知する運用を設けることで、対応漏れや重複対応のリスクを大幅に軽減できます。
マニュアル・ナレッジ共有でエスカレーションを効果的に
コールセンターのエスカレーションを効果的に行うには、マニュアルで解決できる問い合わせなのか」「マニュアルで解決できない問い合わせなのか」を迅速に判断できるような環境を整えることが1つの対策です。
全オペレーターが全マニュアルを記憶するのは現実的ではないため、、適切なシステムの導入がおすすめです。
ここでは事例を用いてコールセンターのマニュアルや社内ナレッジの整備と運用をうまく回すことができるシステムについて紹介します。
▼あわせて読みたい
ナレッジ共有の課題を解消した事例
大手企業の第一三共ヘルスケア ダイレクトでは、複数拠点のコールセンターにおけるナレッジ共有の課題を解消するために社内ナレッジ共有・検索システムとして「Helpfeel」を導入しました。
その結果、オペレーターが必要な情報をどこの拠点からでもスムーズに取り出すことができるようになりました。情報の更新や新しい情報の公開が容易になり、低工数でナレッジの共有ができるようになっています。
▼事例詳細はこちらから
Helpfeelを活用してコールセンターの業務を均一に
Helpfeelは、社内にも使えるFAQやナレッジベースの作成と管理に特化した社内ナレッジ検索システムです。Helpfeelを導入することで、コールセンター内のナレッジやマニュアル作成・共有とそれを簡単に見つけることが可能になります。
Helpfeelは導入時のナレッジサイトの構築やコンテンツ移行などを、専任のチームが担当します。さらに、運用中の分析から改善提案まで手厚い伴走支援が付帯しているため、工数が増える心配もありません。
「コールセンターでのオペレーションを均一化したい」、「現場の混乱を極力減らしたい」という方は、ぜひ1度サービス資料をご覧ください。