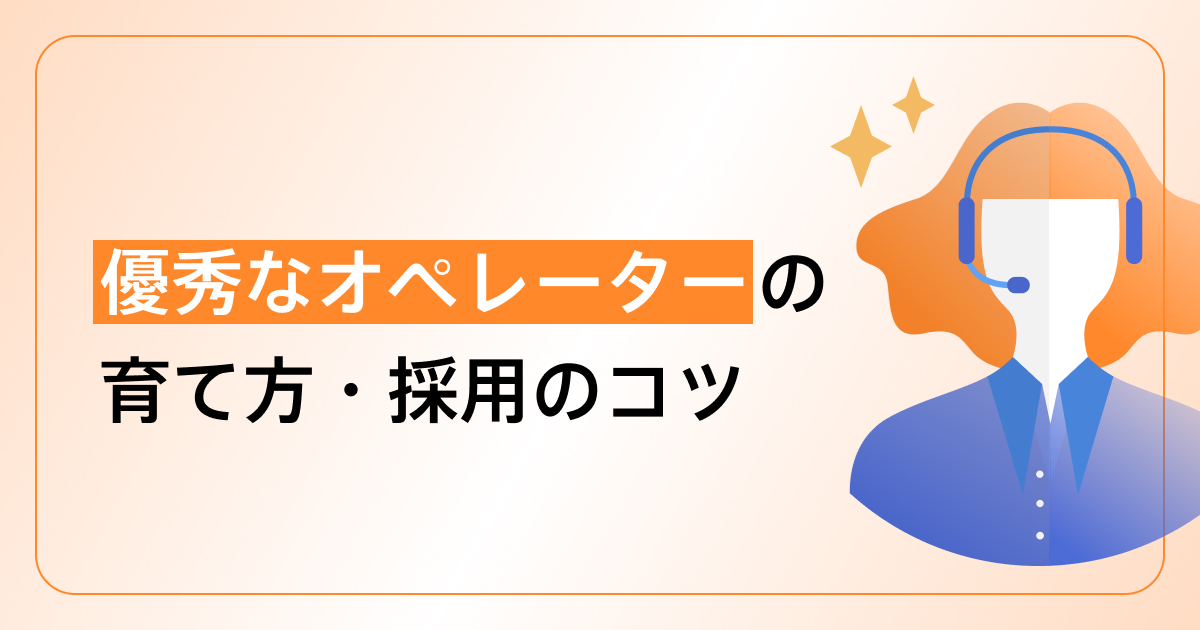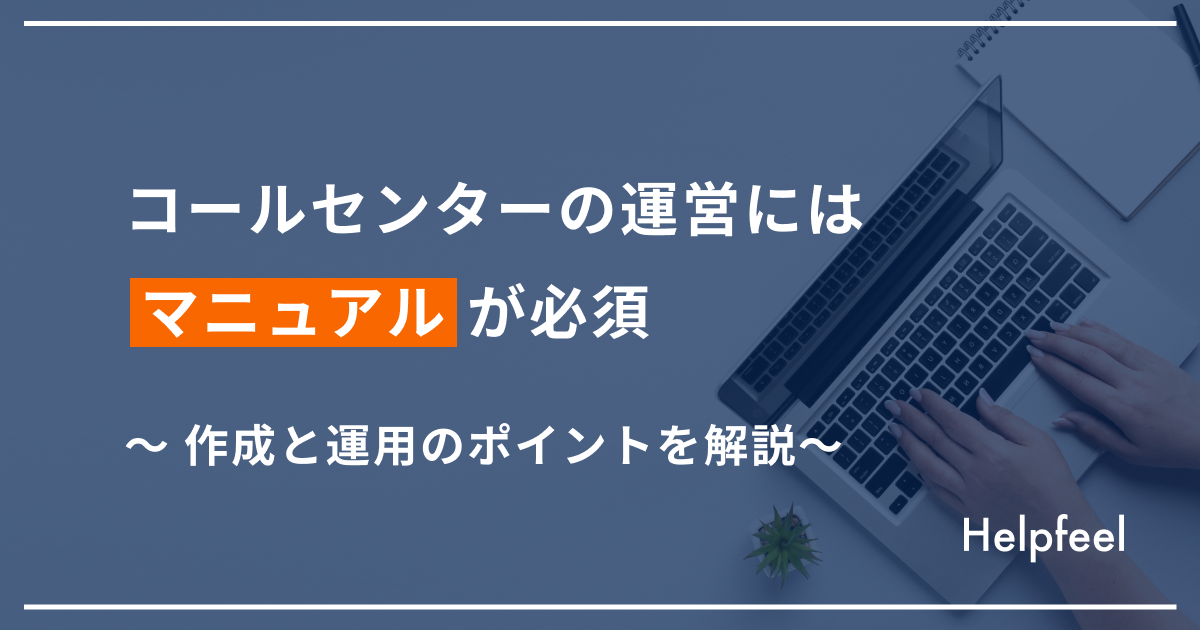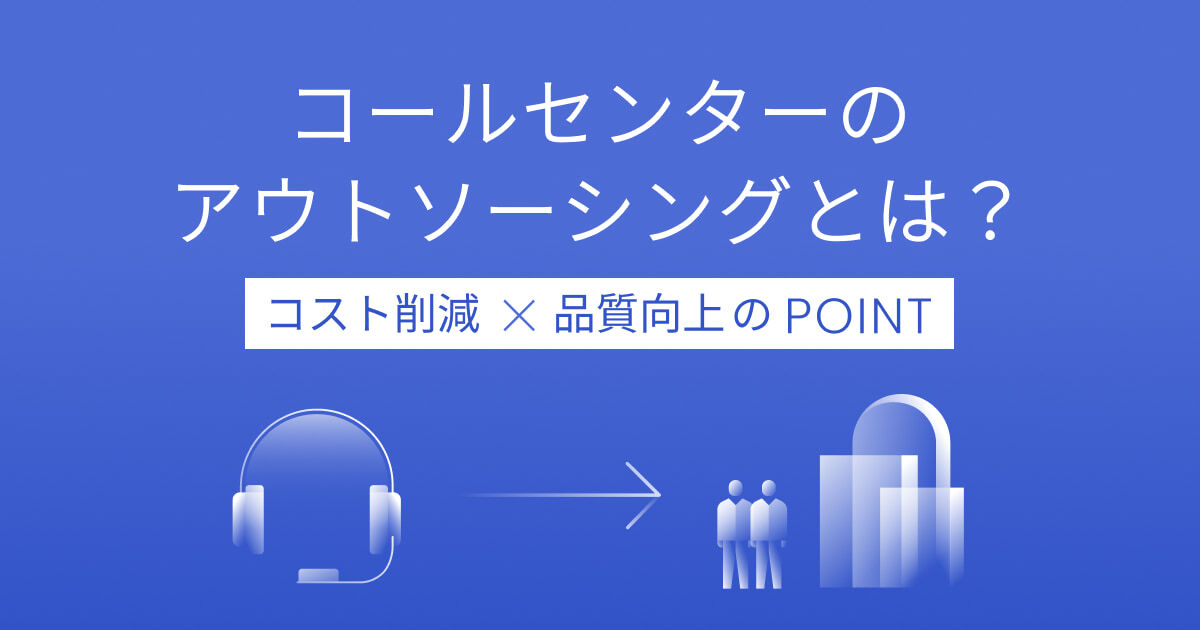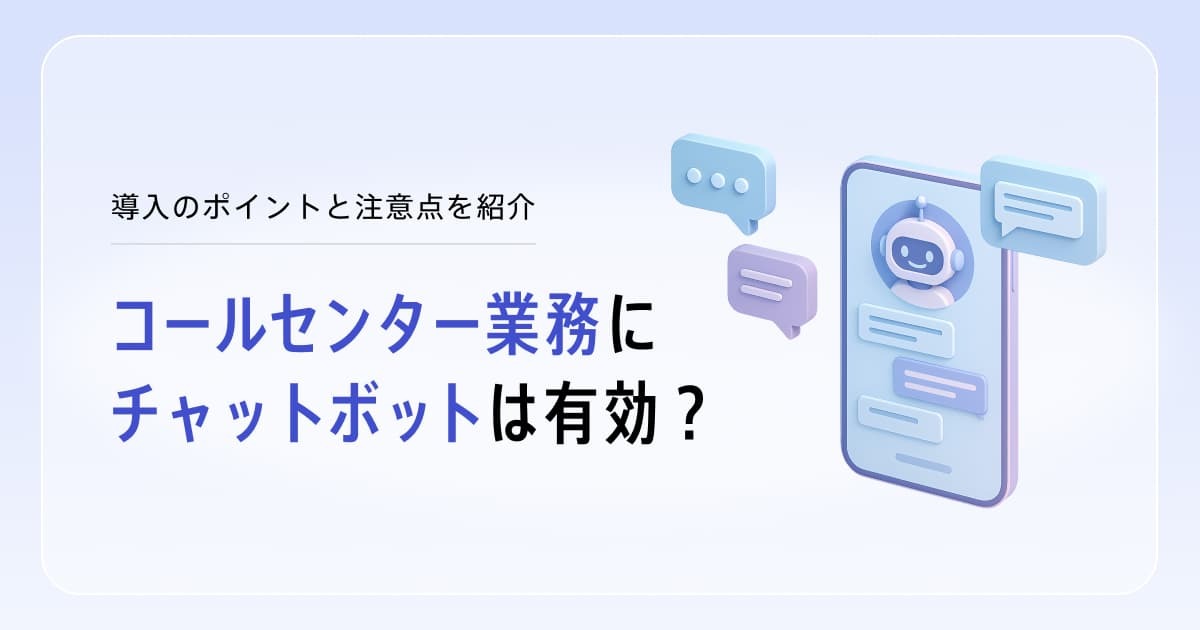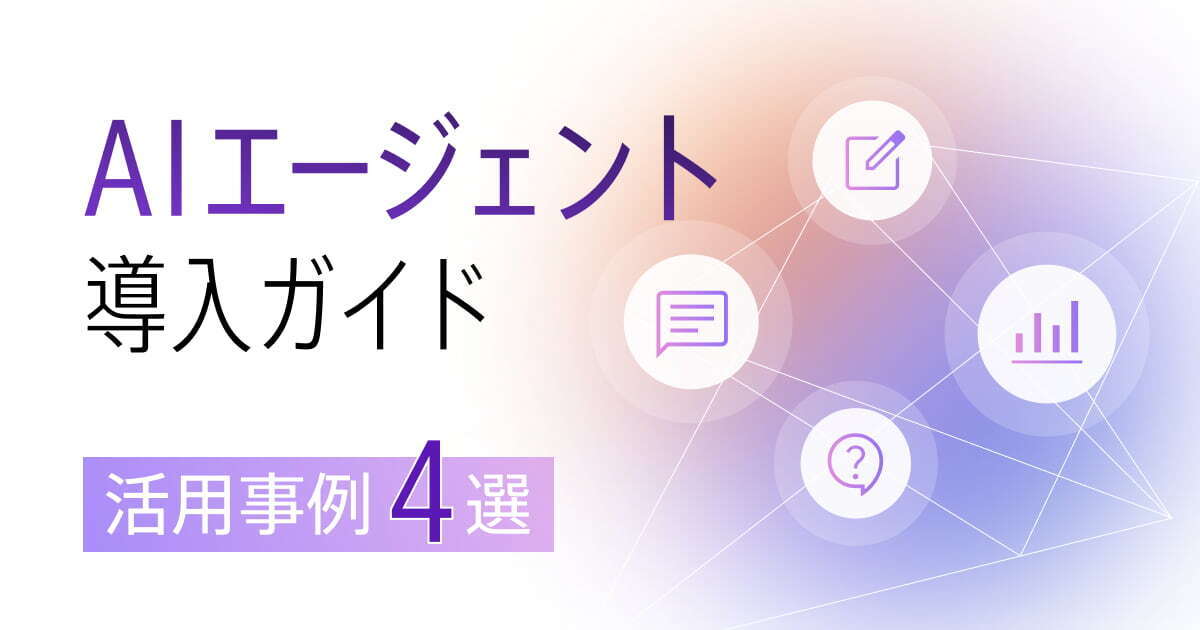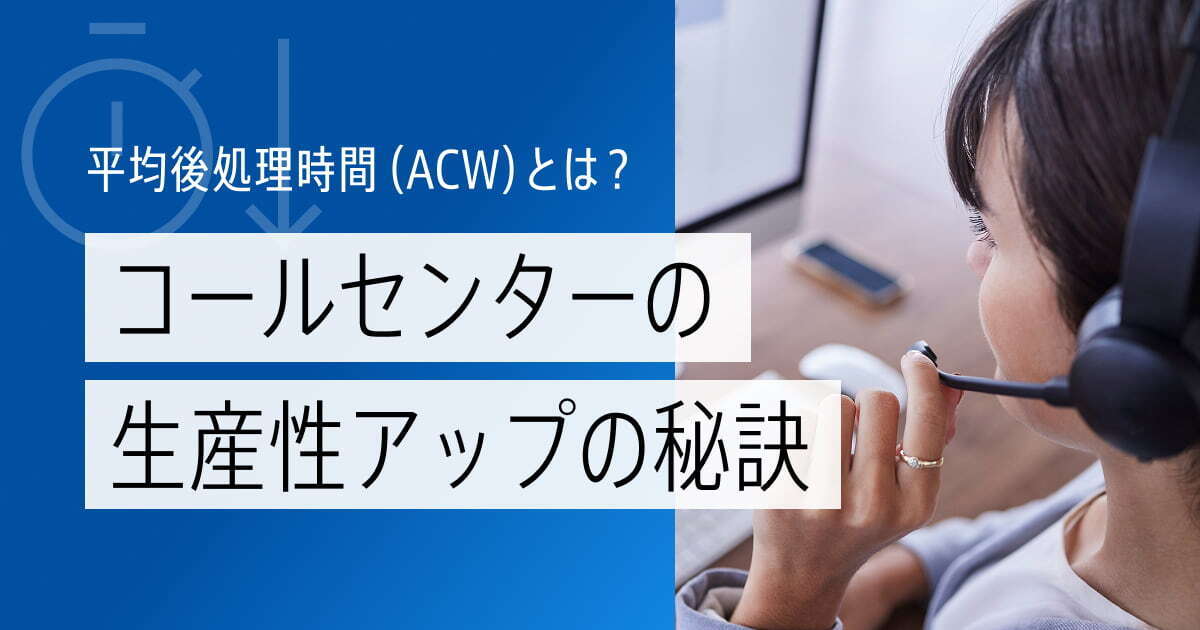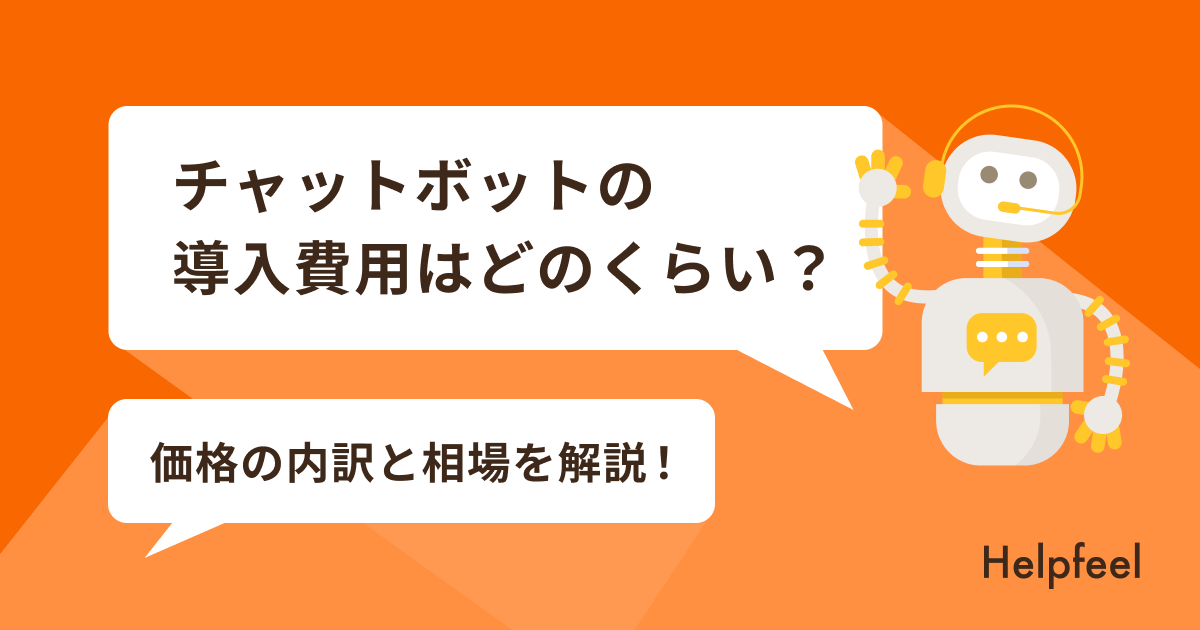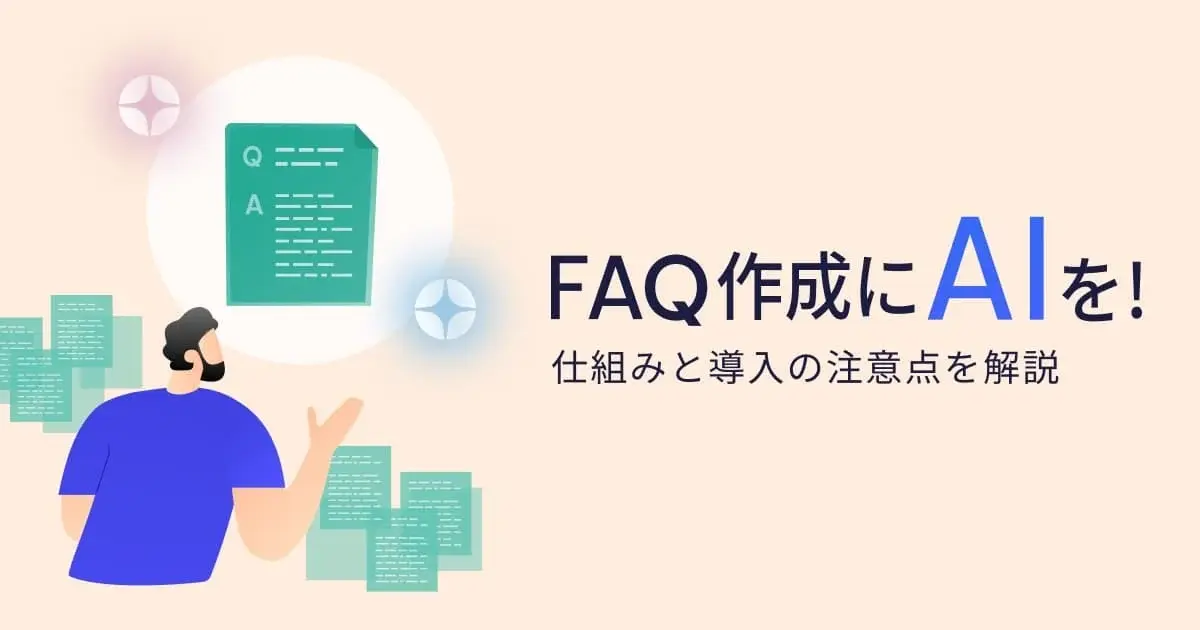▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

コールセンターの抱える代表的な課題

コールセンターの抱える課題には、主に以下の3つに分けられます。
|
効果的な解決策を導くためにも、個々の課題について詳しく見ていきましょう。
オペレーターの人材に関する課題
コールセンターにおいて、オペレーターの確保や育成、定着率の低下といった問題に頭を抱えている企業は少なくありません。まずは、オペレーターの人材に関する課題について詳しく解説します。
1. オペレーターの人手不足
コールセンターの中には24時間、365日の営業体制を敷いている企業も多く、人手不足は、長年にわたってコールセンター業界を悩ませてきた代表的な課題です。
月刊コールセンター2024年7月号(※1)を見ると、2023年8月〜2024年7月の新規求人倍率(季節調整値)は、全国平均2.22倍と高い数値を記録しています。2024年7月は、東京都は3.56倍、北海道は1.73倍と、地域差が大きい点も読み取れます。
チャットボットやFAQシステムをはじめとするITシステムの活用によって、人手に頼らないコールセンター運営を目指していく必要があるでしょう。
※1 出典:月刊コールセンタージャパン2024年7月号
2. 定着率の低下
コールセンターではオペレーターの定着率の低さが大きな課題となっています。精神的負荷の高いクレーム対応を含むことや、評価制度やキャリアパスが不透明であることが、早期離職率を高める要因となっているケースも珍しくありません。
また、時給制アルバイトや派遣社員としての雇用が多く、長期的な視点で働きづらい環境も定着率低下の要因の一つです。人手不足の中で離職が続くと、現場の負担が増えて悪循環に陥りやすく、サービス品質の低下にもつながります。
3. 人材の育成環境不足
新人オペレーターの育成に十分なリソースを割けないことも、コールセンターにおける深刻な課題です。マニュアルが不十分であったり、OJT(職場内訓練)に頼りきりの現場も多く、指導者のスキルや業務量に左右される不安定な育成体制になりがちです。
人材不足に悩む現場では、丁寧な指導やフォローが難しく、育成の質が低下してしまうケースも少なくありません。結果として、対応品質や定着率の悪化を引き起こす恐れがあります。
▼あわせて読みたい
4. 対応品質の個人差
コールセンターでは、オペレーターごとの対応品質に差が出やすいという課題があります。話し方や傾聴力、トラブル時の判断力などは経験や個人のスキルに大きく依存するため、顧客満足度にばらつきが生じる要因となります。
マニュアルが整備されていても、実践レベルでの再現性が乏しい場合、顧客対応の一貫性を保つのは難しいでしょう。対応品質の差が企業の信頼に直結することもあるため、組織的な品質管理と継続的なスキル研修の実施が不可欠です。
働き方や勤務体制に関する課題
コールセンターでは、働き方の多様化や業務時間の拡大に伴い、勤務体制にもさまざまな課題が生じています。ここでは、働き方や勤務体制に関する課題を詳しく解説します。
1. 在宅勤務の導入
近年では、首都圏企業を中心に在宅勤務の導入が広がっています。一方で、業務内容によっては在宅勤務での対応が難しいものが少なくありません。コールセンター業務もその1つです。
在宅勤務でコールセンターを運用するとなると、それぞれのオペレーターが自宅から安全に顧客情報へアクセスできる仕組みや、電話機やパソコンの貸与などを検討する必要があります。準備に時間がかかる上にかなりのコストを要するため、在宅勤務が実現できていない企業も多数あります。
2024年度コールセンター企業実態調査(※2)によると、在宅テレコミュニケーターの有無に関して、「すでに採用」と回答した企業は35社であり、情報非公開の企業を除くと53.8%の企業が採用していることがわかります。
一方で、採用する予定はないと回答した企業の割合は27%で、環境整備や顧客情報漏えいを防ぐためのセキュリティ対策にコストや時間がかかることから、導入を踏みとどまっている企業も多いのが現状です。
※2 出典:一般社団法人日本コールセンター協会「2024年度コールセンター企業実態調査」
2. 24時間体制の構築
顧客ニーズの多様化やグローバル対応の必要性により、24時間体制の構築を求められるコールセンターが増えています。しかし、深夜帯や早朝シフトに対応できる人材の確保は難しく、人員配置の偏りや業務の属人化が起こりがちです。
また、夜間でも一定の品質を維持するためには、教育体制やサポート体制も整えなくてはなりません。コスト面の負担も大きく、特に中小規模のセンターでは、完全な24時間対応は大きなハードルとなっています。
3. 時期による業務量のばらつき
コールセンターでは、季節や時期によって業務量が大きく変動することが多く、対応体制の維持が課題となります。
例えば、年度末やキャンペーン期間中は、問い合わせ件数が急増し、一時的な人員強化やシフト調整が不可欠です。一方で、閑散期にはスタッフの稼働率が下がり、人件費が無駄になるケースもあるでしょう。
こうした業務量のばらつきに対応するには、データに基づく予測とフレキシブルな勤務体制の導入が必要です。しかし、データ分析や勤務体制の構築には高度な運用スキルと準備が必要になるため、導入に関してハードルが高いと感じている企業も多い傾向にあります。
顧客対応や社内連携の課題
顧客ニーズの多様化や複雑化により、対応の高度化とともに社内の連携体制も重要性を増しています。ここでは、顧客対応や社内連携の課題について詳しく解説します。
1. 顧客行動の多様化への対応
コールセンターでは、顧客行動の多様化に対応するため、電話だけに頼らない柔軟なチャネル設計が求められています。
かつては、製品に関する疑問やトラブルがあれば電話で問い合わせるのが一般的でしたが、現在はインターネットの普及により、顧客はまずオンラインでの自己解決を試みる傾向にあります。
サービスサイトやFAQ、SNS、ユーザーコミュニティなど、情報収集の手段は多様化しており、従来の電話対応だけでは対応が追いつかない場面もあるでしょう。
そのため、メールやチャットなどのチャネルを整備し、顧客が求める方法でスムーズに接触できる環境の構築が不可欠です。多様な顧客接点に対応できなければ、顧客満足度の低下や機会損失を招く可能性もあるため、柔軟な対応体制が求められます。
2. 部署間の連携不足
コールセンターにおける部署間の連携不足は、顧客対応の質を大きく左右する深刻な課題です。
顧客からの問い合わせ内容が商品開発や営業、配送、システム管理など複数の部署にまたがる場合、情報の引き継ぎや共有が不十分だと対応が遅れたり、二重対応が発生したりと、顧客満足度を著しく下げる原因になります。
また、センター内のオペレーターが最新情報を把握できないまま応対すると、誤案内やトラブルにつながるリスクも高まるでしょう。特に、部門ごとに使用しているシステムやデータベースが異なる場合、連携の手間やミスが生じやすく、業務が属人化してしまう懸念もあります。
円滑な社内連携のためには、横断的な情報共有基盤や定期的なコミュニケーションの場を設けることが欠かせません。
▼コールセンターの品質を根本から向上させるお役立ち資料もご用意しております。ぜひ併せてご覧ください。
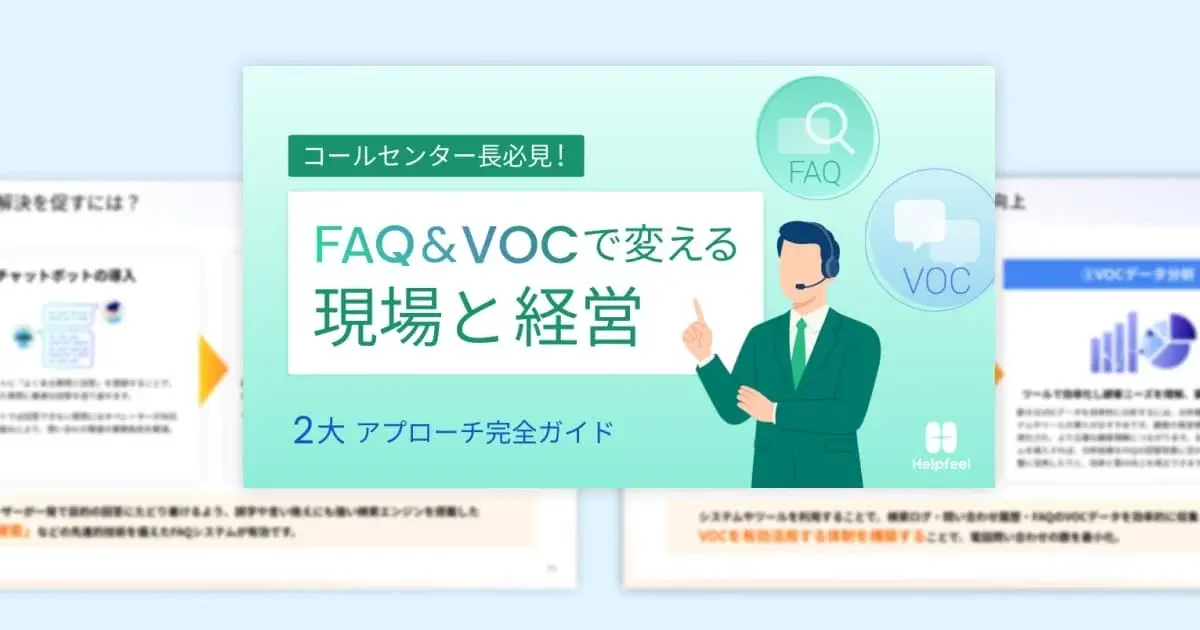
コールセンターが抱える課題の解決方法5つ

多くの課題を抱えるコールセンターですが、具体的な解決策を講じることで業務効率や顧客満足度を大きく改善することが可能です。ここからは、コールセンターが抱える課題への解決策を5つ紹介します。
1. マニュアルを整備する
コールセンター業務においてマニュアルを整備することは、オペレーターの対応品質を標準化し、属人化を防ぐために非常に重要です。
対応フローやFAQ、トークスクリプトが明確であれば、経験の浅いスタッフでも一定のレベルを保った対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
対応内容が複雑化する現代では、更新性の高いデジタルマニュアルの導入が特に効果的です。業務変更や新商品の情報を即時反映できる仕組みがあれば、全員が最新情報に基づいた対応を実現できるでしょう。
また、研修ツールとしても活用できるため、新人育成の効率化にも大きく役立ちます。マニュアルを「作って終わり」にせず、現場の声を反映しながら定期的に見直す運用体制を構築することも大切です。
▼あわせて読みたい
2. アウトソーシングを利用する
コールセンター業務をアウトソーシングすることは、課題解決の有効な手段の1つです。特に、人手不足や定着率の低下に悩む企業にとっては、専門性を持つ外部業者に業務を委託することで、一定の品質と対応力を安定的に確保できます。
業務量が時期によって変動する業態においても、アウトソーシング先なら柔軟な人員体制で繁閑差に対応できる点は大きなメリットです。社内のリソースをコア業務に集中させることで、生産性向上にもつながるでしょう。
注意点は、委託先との情報共有や品質管理体制の構築が不可欠であることです。単なるコスト削減を目的とした外部委託ではなく、戦略的パートナーとしての位置づけることが成果を最大化する鍵となります。
▼あわせて読みたい
3. 柔軟な働き方に対応する
近年、コールセンターにおいても柔軟な働き方への対応が重要な課題となっています。特に在宅勤務や時短勤務、副業人材の活用など、多様な勤務形態を認めることで、これまで採用が難しかった人材層を取り込むチャンスが広がります。
実際、在宅オペレーター制度を導入することで、子育て中の方や地方在住者など、従来の就労条件では働きにくかった人材が活躍できる環境を整えることができます。さらに、柔軟なシフト制を導入することで、突発的な業務量の変動にも迅速に対応できる体制が構築できるでしょう。
ただし、勤務場所や時間が分散することで発生する情報共有の難しさや管理コストの増加には注意が必要です。クラウドツールや定期的なミーティングなど、運用面での工夫も同時に求められます。
4. チャットボットを導入する
コールセンターの業務効率化や人手不足の緩和策として、チャットボットの導入が注目されています。特に、FAQや定型業務に対しては、チャットボットが24時間365日対応可能なため、顧客の利便性が向上するだけでなく、オペレーターの負荷軽減にも大きく貢献します。
さらに、対応ログが自動で記録されることで、顧客の傾向分析やナレッジの蓄積にも効果的です。最近では、自然言語処理の精度向上により、より複雑な質問にも柔軟に対応できるAIチャットボットも増えています。
ただし、全ての問い合わせを自動化するのではなく、有人対応と組み合わせたハイブリッド運用が理想的です。顧客体験を損なわずに効率化を図るためには、導入目的を明確にし、定期的なチューニングをする必要があるでしょう。
▼あわせて読みたい
5. FAQを改善する
FAQの改善は、コールセンターにおける問い合わせ対応の負担を減らし、顧客満足度を高めるための有効な施策です。
顧客が自己解決できる環境を整えることで、オペレーターの対応件数を削減し、業務の効率化が図れます。特に近年では、FAQをウェブサイト上で検索しやすくする「ナレッジベース型FAQ」や、ユーザーの質問に応じて回答候補を提示するインタラクティブなFAQシステムも登場しています。
FAQは、顧客の行動変化やサービス内容の更新に応じて、常に見直す運用体制を整えることが不可欠です。実際のコールログやチャットログを活用し、、現場のリアルな質問に基づいた改善を行うことで、より実用的なFAQを構築することができます。
▼コールセンターでのFAQ活用ノウハウをまとめたお役立ち資料をご用意しています。ぜひ日々の業務にご活用ください。

コールセンターの課題解決にはFAQの改善がおすすめ
コールセンターが抱える課題を根本から改善するには、FAQの見直しと強化が効果的です。中でも注目されているのが、検索に特化したAI-FAQシステム「Helpfeel」です。
Helpfeelは、ユーザーが入力する曖昧な表現や話し言葉にまで対応する独自技術を採用しており、「探せない」「見つからない」といったFAQの限界を突破します。これにより、顧客の自己解決率が大幅に向上し、コール数の削減とオペレーターの負担軽減を同時に実現できます。
また、検索ログを分析することで、ユーザーが本当に求めている情報に基づいたPDCAサイクル型のFAQ改善が可能です。コールセンターが抱える課題に同時にアプローチできる、現場実装性の高いソリューションといえるでしょう。
まとめ:コールセンターの課題解決を図りましょう

コールセンター業界は、人材不足や定着率の低下、対応品質のばらつき、働き方の多様化、顧客ニーズの変化など、複数の課題に直面しています。
これらの課題はそれぞれが独立しているわけではなく、互いに連動しながら、現場の業務負荷や顧客体験に大きな影響を与えています。部分的な対処では限界があるため、組織全体での構造的な見直しと、適切なツールの導入は欠かせません。
たとえば、FAQの充実やチャットボットの導入は、比較的短期間で効果を実感しやすい施策です。顧客の自己解決を促す仕組みを整えることで、オペレーターの対応負荷を軽減し、教育コストや応対品質のばらつきといった課題の改善にもつながります。
まずは自社の課題を整理し、それに合った解決策を導入し、将来を見据えた持続的な改善へとつなげていきましょう。