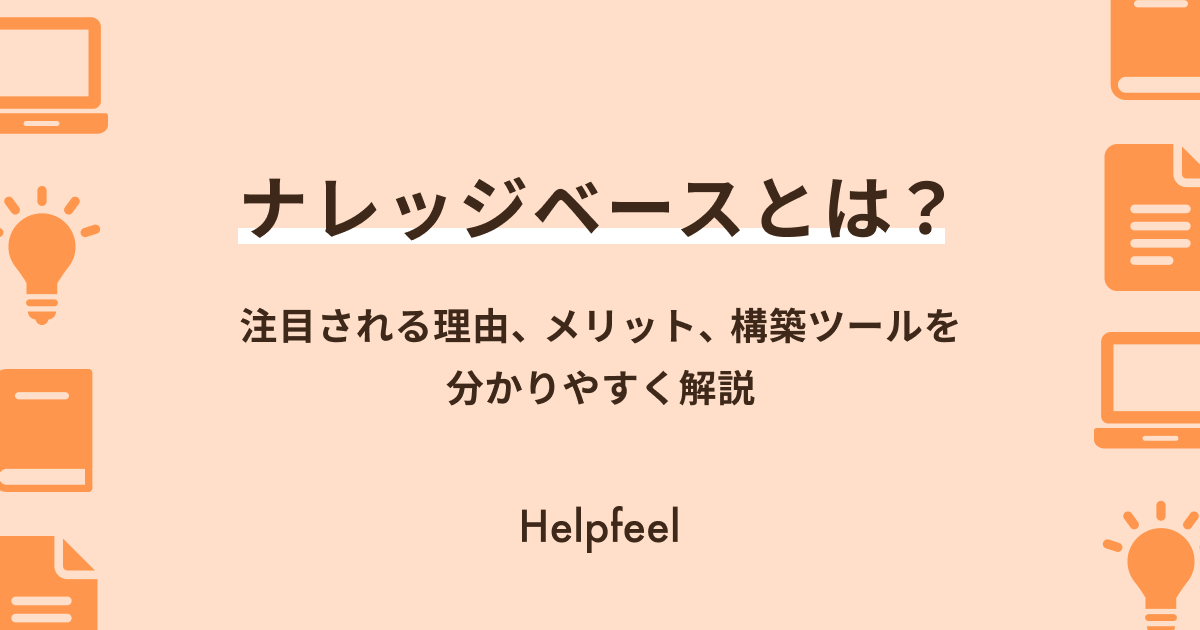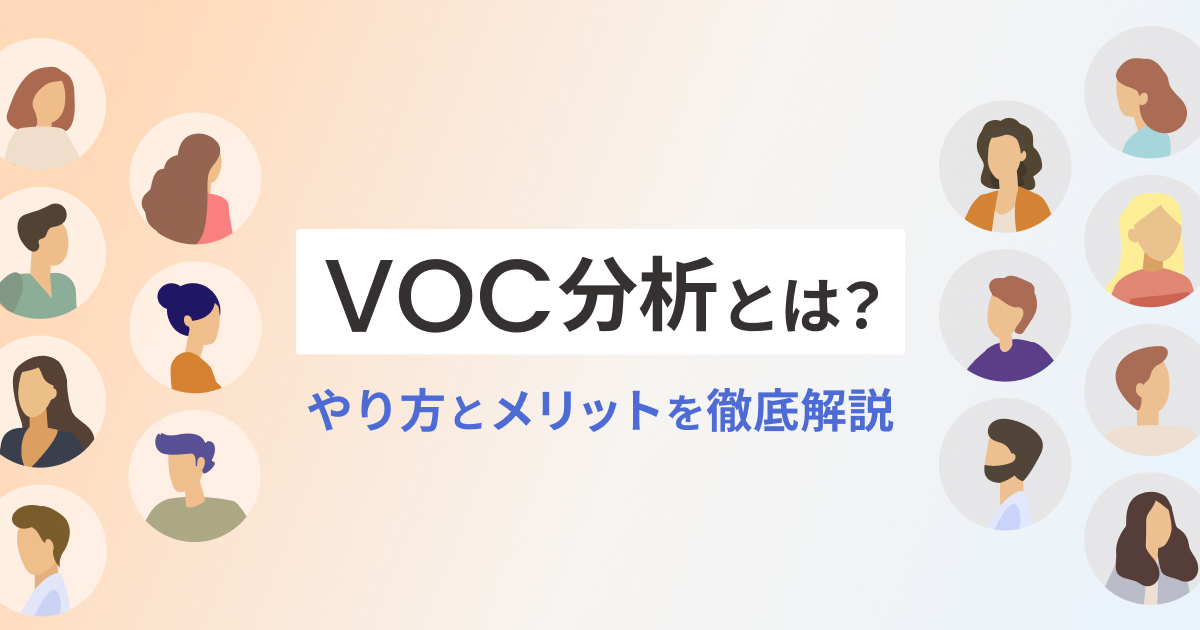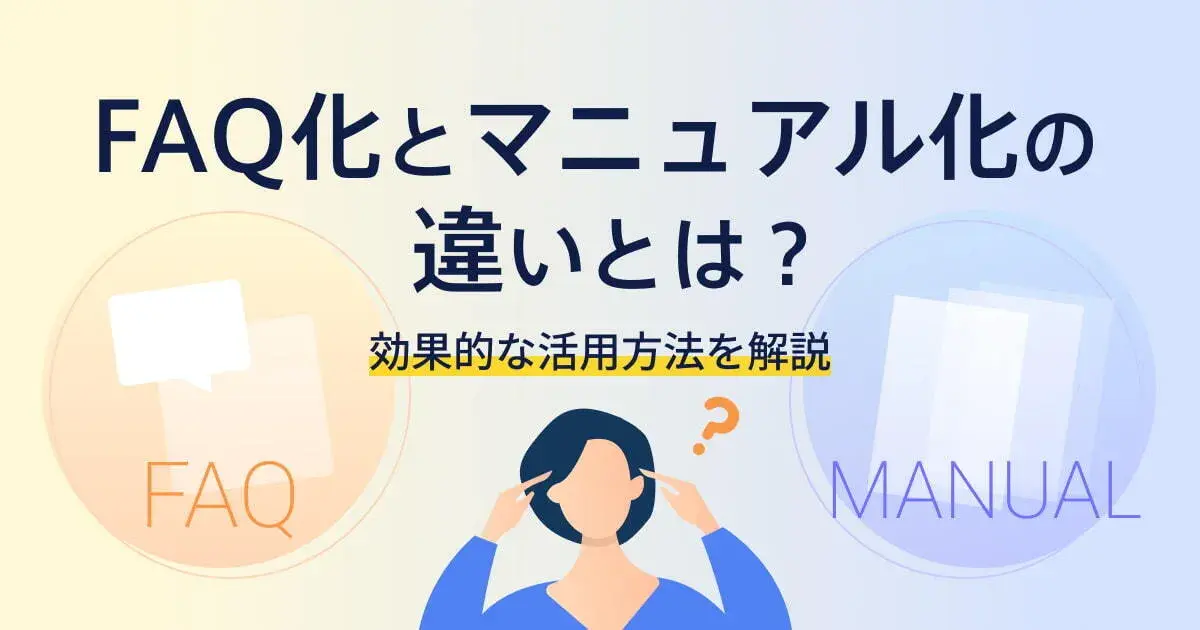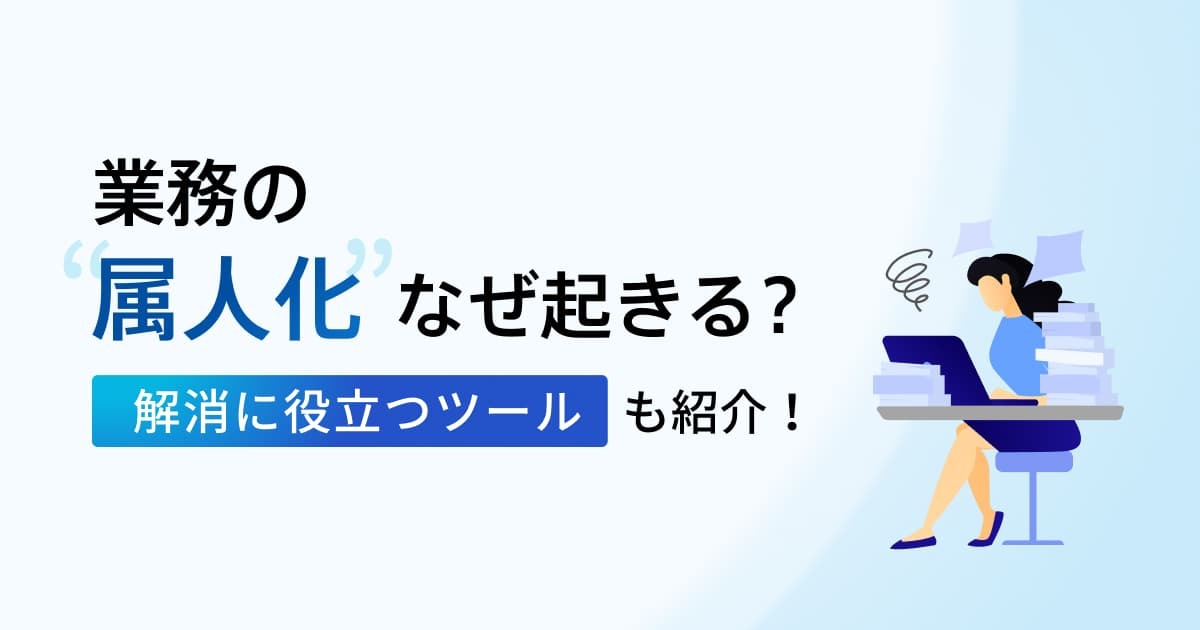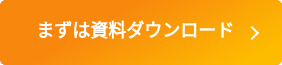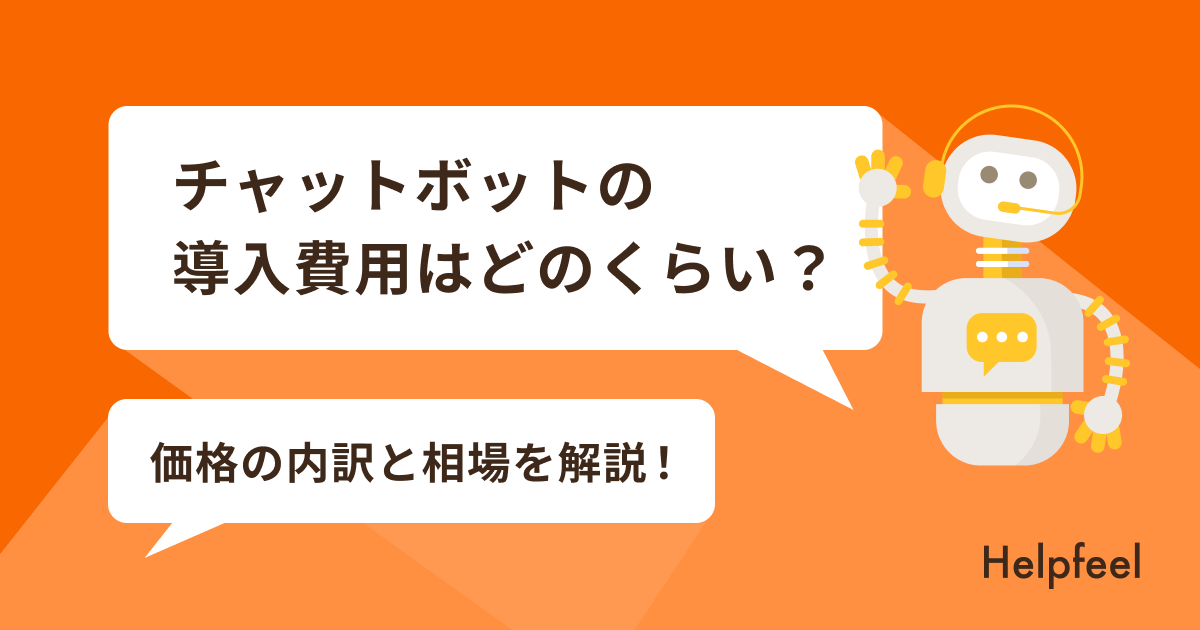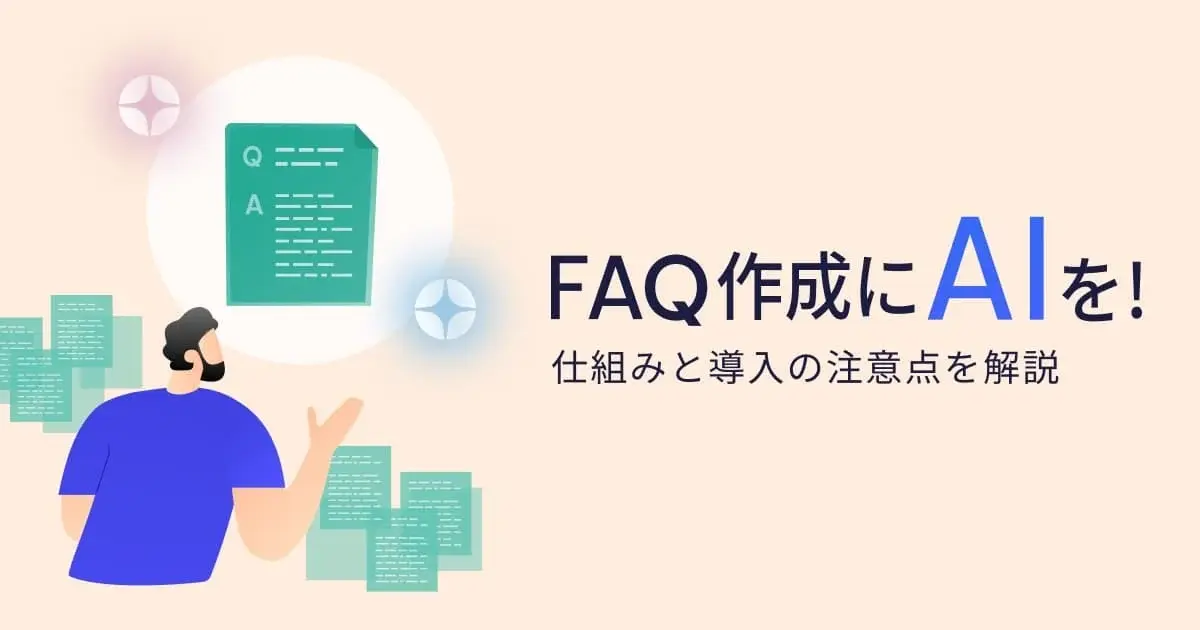ナレッジマネジメントの基礎知識
ナレッジマネジメントとは、従業員一人ひとりが持つ業務の知識やノウハウを集めて可視化し、社内で共有・活用することで、組織全体の生産性や競争力を高める手法です。
ここではナレッジマネジメントに関して、下記の3点を解説します。
|
ナレッジマネジメントを理解するために、まずは知識がどのように生まれ、共有されていくかを示した代表的なフレームワーク「SECI(セキ)モデル」を見ていきましょう。
SECI(セキ)モデル
SECIモデルを理解するには、まず「暗黙知」と「形式知」について知る必要があります。
|
経験に基づく、言語化されていない知識やノウハウ |
|
言語や図表などで共有できる知識 |
形式知は組織内で容易に共有できますが、暗黙知は個人が持つ知識やノウハウであることから、簡単に共有できません。
ナレッジマネジメントでは、暗黙知と形式知をどのように循環させ、組織として活用していくかが重要であり、そのプロセスを示した代表的なモデルが「SECIモデル」です。
SECIモデルは、暗黙知を形式知へ変換して共有したり、形式知同士を組み合わせて新たな知識やイノベーションを生み出したりする流れを整理したモデルです。
このSECIモデルは、暗黙知を形式知へ変換する4つのプロセスの頭文字から名付けられました。
|
ここからは、それぞれのプロセスについて解説します。
▪️共同化(Socialization)
共同化は、個人が持つ暗黙知を共有するプロセスです。OJT(On-the-Job Training)や会議などを通じて、暗黙知を組織内で伝達します。
例えば、先輩と一緒に作業する、上長と一緒に営業先を回るなどが共同化にあたります。共同化の段階では、形式知として伝える必要はなく、体験を共有することで、勘や感覚などの暗黙知として相手と共有します。
▪️表出化(Externalization)
表出化は、共同化で獲得した暗黙知を、共有しやすい形式知へと変換するプロセスです。わかりやすい例を示すと、マニュアルの作成や業務報告が表出化にあたります。
共同化で獲得したのはあくまでも暗黙知であり、そのまま共有することは容易ではありません。そのため、ナレッジベースに言語化・図表化して形式知にします。
▼あわせて読みたい
▪️連結化(Combination)
連結化は、2つの形式知を組み合わせて新たな形式知を作り上げるプロセスです。既存の形式知に別の形式知を組み合わせることで、より体系化することを目指します。
例えば、先輩が作成した営業マニュアルを参考にして、トーク術を自分の営業方法に取り入れる、業務ナレッジにあるテンプレートを自分なりにアレンジして使用するなどが、連結化にあたります。
連結化によって新たな形式知となった段階でようやく組織の財産となります。そのため、連結化はSECIモデルにおいて重要なプロセスです。
▪️内面化(Internalization)
内面化は、連結化によって新たに創出された形式知を暗黙知化するプロセスです。何度も繰り返し作業をし、マニュアルを見たり、先輩にアドバイスをもらわなくても、自分で完結できる状態になるのが内面化です。
実践や行動によって、個人はその形式知に関する経験やノウハウを得て、暗黙知化していきます。ここで生まれた新たな暗黙知を再び共同化するといったサイクルを繰り返すことで、組織の知的財産が育ち、生産性が向上します。
▼あわせて読みたい
ナレッジマネジメントが重視される理由
ナレッジマネジメントが重視される背景には、働き方の多様化があります。終身雇用が当たり前であった従来の働き方では、組織のなかに多くの経験や知識、ノウハウを持った人材が存在していました。
多くの企業ではこれまで、長年働き続ける社員が経験から身につけた知識やスキル、ノウハウを後任へと継承してきました。しかし、団塊世代の定年や終身雇用の崩壊、リモートワークの普及など、労働環境はめまぐるしく変化し、高度なスキルや知識の伝達が難しくなっています。
こうした状況を補うために暗黙知を形式知化してナレッジとして蓄積する「ナレッジマネジメント」への注目が集まっています。ナレッジを蓄積しておけば、人材が入れ替わっても業務の品質や効率を落とすことなく、事業を継続できます。
企業での取り組み
働き方が大きく変化した現在、多くの企業がナレッジマネジメントに取り組んでいます。
|
このように、知識を「残す・共有する」仕組みをつくることで、暗黙知を形式知へ変換し、組織全体の生産性を高めています。
「直感的に使える」からこそ、ナレッジが自然とたまり、活用されていく。Helpfeelは、検索性と使いやすさを兼ね備えた社内FAQシステムで、ナレッジの定着をサポートします。
>> Helpfeelのナレッジシステムを詳しく見る
ナレッジマネジメントの4つの手法

ナレッジマネジメントには、目的や対象に応じた以下4つの代表的な手法があります。
|
以下、それぞれの特徴と活用シーンを見ていきましょう。
顧客知識共有型
顧客知識共有型は、顧客から得られる知識や声を組織内で共有し、製品やサービスの改善、カスタマーサポートの質向上に活用する手法です。
問い合わせ内容、アンケート結果、SNSでの投稿内容などを収集・分析し、部門間でナレッジとして共有することで、対応のばらつきを減らし、顧客満足度の向上を図ります。
この手法は、特にBtoC企業におけるカスタマーサポート部門や商品開発部門で有効です。また、VOC(Voice of Customer)活動と連携することで、ナレッジの質が高まり、改善サイクルの精度とスピードも加速します。
収集した情報をFAQやマニュアルに反映する仕組みを整えることで、ナレッジの継続的な蓄積と活用ができるでしょう。
▼あわせて読みたい
ヘルプデスク型
ヘルプデスク型は、社員からの問い合わせ対応を効率化するためにナレッジを蓄積・共有する手法です。社内ヘルプデスクに寄せられる質問と回答をFAQとして整理・共有し、同じ問い合わせの繰り返し対応を減らすことで、業務効率の向上を図ります。
特に、ITサポートや人事・総務など、全社対応が求められる部門で有効です。チャットボットやナレッジベースツールと組み合わせることで、24時間365日自己解決できる体制の構築も可能となり、属人化防止や対応品質の標準化も期待できます。
結果として、ナレッジの蓄積・活用により、ヘルプデスクの負担軽減だけでなく、社内全体の生産性向上にもつながるでしょう。
▼あわせて読みたい
業務プロセス型
業務プロセス型は、日々の業務の中で生まれるノウハウや暗黙知を体系的に整理し、再現できる知識として共有する手法です。営業活動、製造工程、プロジェクト管理など、あらゆる業務の中にある成功事例・失敗事例をナレッジ化し、マニュアルや社内FAQ、事例集として蓄積します。
この手法は、特に属人化しやすい業務において有効で、ベテラン社員の退職によるノウハウ喪失のリスクを防ぐことが可能です。また、オンボーディングや人材育成にも活用しやすく、新入社員や異動者がスムーズに業務に適応できる環境を整える効果もあります。
定期的なナレッジの更新や、業務改善サイクルと組み合わせることで、継続的なプロセス改善が期待できるでしょう。
▼あわせて読みたい
経営資産・戦略策定型
経営資産・戦略策定型は、企業の中長期的な成長や競争優位性の確立を目的に、ナレッジを経営資源として捉える手法です。市場動向、競合分析、社内の成功モデル、技術資産などをナレッジとして集約し、経営層が戦略立案に活用します。
この手法は特に、経営企画部門や研究開発部門など、戦略的判断を求められる部門で活用されます。過去の施策とその成果を可視化し、意思決定の精度を高めると同時に、新たなビジネスチャンスの発掘にもつながるでしょう。
ナレッジを「資産」として管理し、社内外の知識と結びつけて活用することで、組織全体の知的競争力を高められるようになります。
ナレッジマネジメントを活用する5つのメリット

ナレッジマネジメントの導入は、業務効率や組織力の向上に大きく貢献します。主なメリットは次の5つです。
|
それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
ナレッジの収集が効率化する
ナレッジマネジメントを導入することで、社内に散在する情報やノウハウを体系的に収集・蓄積できるようになります。
属人的な記憶やメール・チャット履歴の中に埋もれていた情報を「見える化」し、誰もがアクセス可能な状態にすることで、情報収集にかかる時間の大幅に短縮できます。
FAQや業務マニュアルなどの共有コンテンツを構築すれば、繰り返し発生する問い合わせにも即時対応でき、日常業務の効率化につながります。さらに、ナレッジを自動的に蓄積・整理する仕組みと組み合わせることで、継続的な改善も実現できるでしょう。
▼あわせて読みたい
業務の属人化を防ぐ
特定の業務が一部の社員に依存する「属人化」は、業務効率の低下やリスク管理の観点から大きな課題です。ナレッジマネジメントにより、ベテラン社員のノウハウや手順を明文化・共有することで、誰でも同じ水準で対応できる体制を構築できます。
業務の標準化やマニュアル化が進めば、異動や退職による業務停滞を防げるだけでなく、チーム間の業務引き継ぎもスムーズになるでしょう。特にプロジェクト型の業務や専門性の高い分野においては、属人性の排除が成果の安定性につながります。
▼あわせて読みたい
人材育成の効率化が図れる
ナレッジマネジメントは、新人教育や中途社員の即戦力化にも有効です。業務マニュアルや事例集などをナレッジとして整備しておくことで、OJTや個別指導に頼らずとも、必要な知識を自ら学べる仕組みが整います。
社員ごとの習熟度やペースに合わせた学習ができるため、教育コストの削減と早期戦力化が同時に実現可能です。さらに、ナレッジの蓄積があることで指導する側の負担も軽減され、組織全体として継続的な学習文化の形成にもつながります。
顧客対応の品質を保てる
ナレッジマネジメントにより、顧客対応に関する情報や過去事例を社内で一元管理・共有することで、誰が対応しても一定の品質を保てる体制が整います。対応のばらつきを防ぎ、迅速かつ的確な対応ができ、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
特にカスタマーサポート部門では、問い合わせ内容や回答履歴を蓄積することで、対応の再現性が高まり、クレームやトラブルを未然に防げます。さらに、対応履歴を分析することで、サービス改善へのフィードバックにもつなげられます。
離職率の改善につながる
ナレッジマネジメントは、働きやすい職場環境づくりにも貢献します。業務の透明性が高まり、情報が共有されることで、不安や孤立感を感じにくくなり、新人や中途社員の定着率向上につながるでしょう。
特定の人に業務が集中することも減り、過重労働や心理的負担の軽減にも効果的です。さらに、組織全体で知見を共有・活用する文化が根づけば、「自分の知識や経験が役立っている」という実感が生まれ、社員のエンゲージメント向上や離職防止が期待できます。
▼社内の対応負荷を減らすには、“聞かなくても分かる”ナレッジの仕組みが不可欠です。Helpfeelは、検索性に優れたFAQで、社内ナレッジ活用を強力にサポートします。
ナレッジマネジメントの導入手順
ナレッジマネジメントの流れを、4つの手順で解説します。
|
1.ナレッジマネジメントの目的を共有する
ナレッジマネジメントには、社内の協力が欠かせません。暗黙知の共有には業務時間を使うため、理解と納得がなければ取り組みが進まないからです。
形式知化されたナレッジを蓄積するには、ナレッジマネジメントを行うメリットや重要性をしっかりと伝え、共感を得ることが重要です。例えば、以下のようなことが挙げられます。
|
2.共有する情報を選定する
誰が持つどのようなナレッジを形式知化するのか、という情報の選定も必要です。共有する情報の選定が事前にできていないと、価値の低い情報の蓄積に時間を割かなければなりません。
「ナレッジとして残すべき情報」を明確にし、的確に選別することで、有益な知識を効率的に蓄積できます。
3.ナレッジを管理するツールを選定する
蓄積したナレッジを利用するには、ナレッジを管理するツールが必要です。ナレッジをデータベース化するツールには、FAQや社内Wiki、社内SNS、Excelなどさまざまな選択肢があります。
ツールを選定する際は、実際に活用するシーンを想定して、スピーディーに必要な情報を見つけられる「検索性」を重視する必要があります。必要な情報が見つけにくいツールを導入してしまうと、かえって使う側の負担を増やしかねません。
▼あわせて読みたい
4.ナレッジを蓄積する
ナレッジを管理するツールを選定したら、実際にナレッジを蓄積していきます。ここでの注意点は、社員の自主性に任せきりにしないことです。
通常業務を優先するあまり、ナレッジ整理が後回しになるケースは少なくありません。そうならないためには、通常業務のなかにナレッジをまとめる時間を組み込み、確実にナレッジの蓄積が行われる仕組みを作ることが重要です。
ナレッジマネジメントツールの活用実例

ナレッジマネジメントは、理論だけでなく実践が重要です。ここでは、実際にナレッジマネジメントツールを導入し、業務改善や組織力向上に成功した企業の事例を紹介します。
▼社内ナレッジシステムを活用した事例をまとめたお役立ち資料もご用意しております。1分でダウンロードできるので、ぜひ併せてご覧下さい。

パーソルテンプスタッフ株式会社|知識共有の文化を醸成
人材派遣・アウトソーシング事業を手がけるパーソルテンプスタッフ株式会社では、BPO事業の拡大やプロジェクト数の増加にともない、これまで蓄積されてきたナレッジを事業部全体で体系的にマネジメントする必要性が生じました。
BPO運用のナレッジ(正解)はひとつではなく、クライアントの数だけナレッジ(正解)が存在しています。そのため、各人の知見を集めながら蓄積・更新していくものだと理解してもらうと同時に、ナレッジ共有に対するハードルを下げる必要がありました。
そこで、ナレッジは正解を積み上げていくものではなく、現場で活躍する各人の知見を持ち寄り磨いていくものというメッセージを、複数回のオンライン説明会で発信していきました。
現在はナレッジを「みんなで使い、育てる」という文化に醸成すべく、専用フォームからナレッジを投稿してくれた人にポイントを還元する制度を運用しています。このような取り組みによって、社内では「今まで探せなかった情報が見つかる」といった声が挙がるようになっています。
▼事例詳細はこちら
株式会社北陸銀行|ヘルプデスク業務を効率化
株式会社北陸銀行では、営業店や本部への問い合わせ対応に多くの時間が割かれ、対応業務が属人化していました。特に、FAQの情報が分散していることや検索性の低さが課題であり、行員の知見がスムーズに共有されていない状況でした。
このため、AI検索機能を備えた「Helpfeel」を導入することで、電子会議室などに蓄積されたナレッジ約1,800件を社内ヘルプデスクで活用できるよう整備しました。
その結果、行員は必要な情報を自ら検索して解決できるようになり、属人化の解消と応答の迅速化が実現しています。FAQ記事の精選やログ分析による改善のPDCAサイクルも構築され、業務効率が飛躍的に向上した好事例といえるでしょう。
▼事例詳細はこちら
DAC|社内FAQの利用率を改善
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(DAC)は、2,000人以上が利用する社内ヘルプデスクへ、Helpfeelによるナレッジ検索システムを導入しました。従来のFAQは検索性能が低く、更新も遅れがちで「直接問い合わせたほうが早い」悪循環に陥っていました。
Helpfeelの優れた検索精度と直感的なUIが導入の決め手となり、リプレイス後、月々の問い合わせ件数が最大100件以上削減され、利用者数も100人以上増加しました。また「曖昧なワードでもヒット」「検索途中でのサジェスト機能」が高評価を得ており、利用者の約7割が「使いやすい」と回答しています。
ナレッジ共有のしやすさとFAQの使い勝手向上の両立により、DACは社内問い合わせの効率化と知識活用の定着に成功しています。
▼事例詳細はこちら
ナレッジマネジメントには検索ヒット率の高いFAQツールを
ナレッジマネジメントをおこなううえで、ナレッジを管理・活用するためのツール選択は非常に重要です。どれだけ多くのナレッジをデータベース化できても、活用する側がスムーズに必要な情報へたどり着けなければ意味がありません。
Helpfeelは、圧倒的な検索力を誇るFAQシステムです。独自技術「意図予測検索」が、人によって異なる曖昧な言葉や感情的な表現、スペルミスなど予測パターンを汲み取り、検索ヒット率98%を実現します。蓄積したナレッジから必要な情報へスピーディーにアクセスできます。
また、Helpfeelには標準で手厚い伴走支援が付帯しています。ナレッジ共有サイトの構築、既存のマニュアルやFAQからのコンテンツ移行、分析、改善提案などを専任チームが担当します。
- ナレッジマネジメントの必要性を感じている
- 検索性の高いナレッジ管理ツールを利用したい
- 運用サポートが手厚いツールを利用したい